羊たち
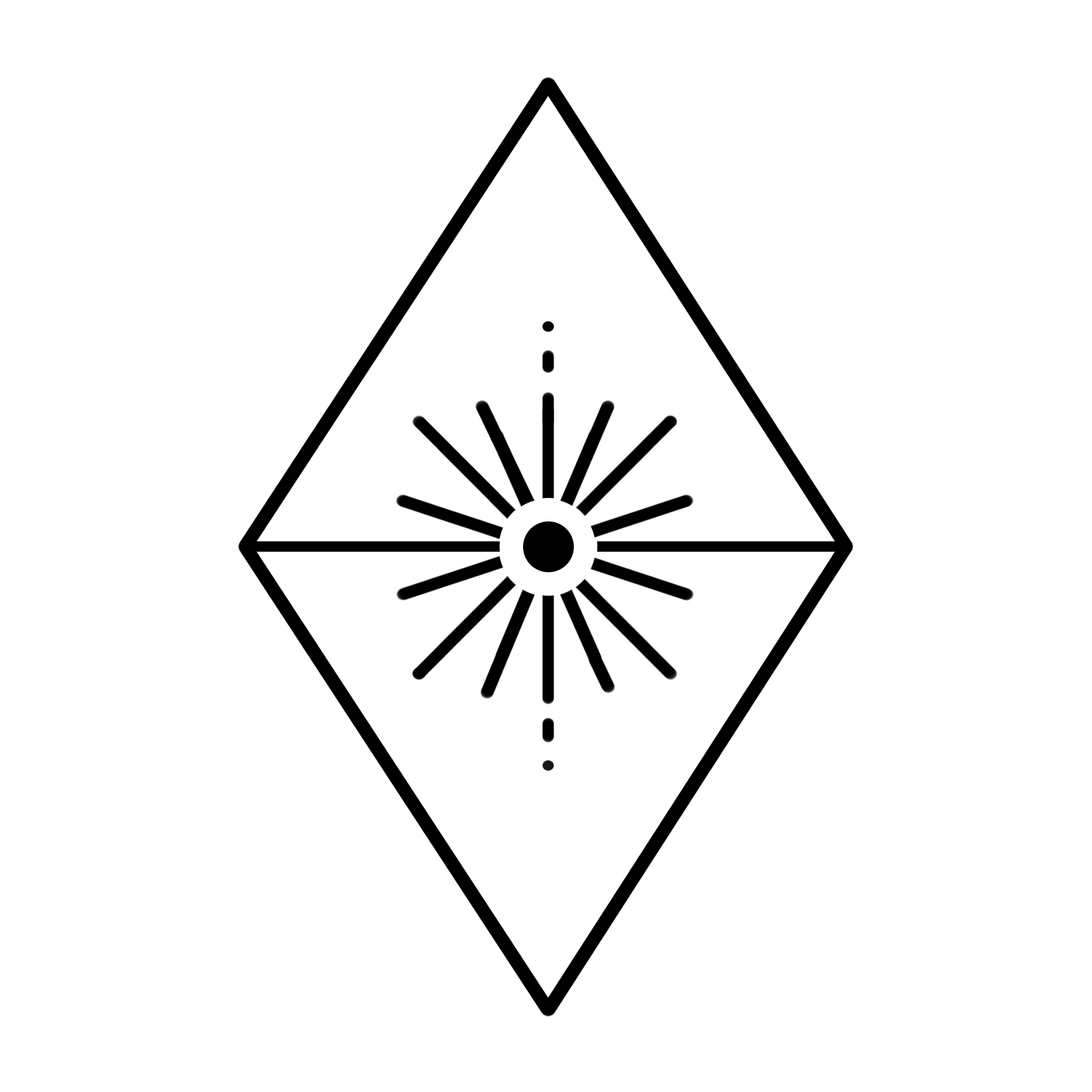
羊たち
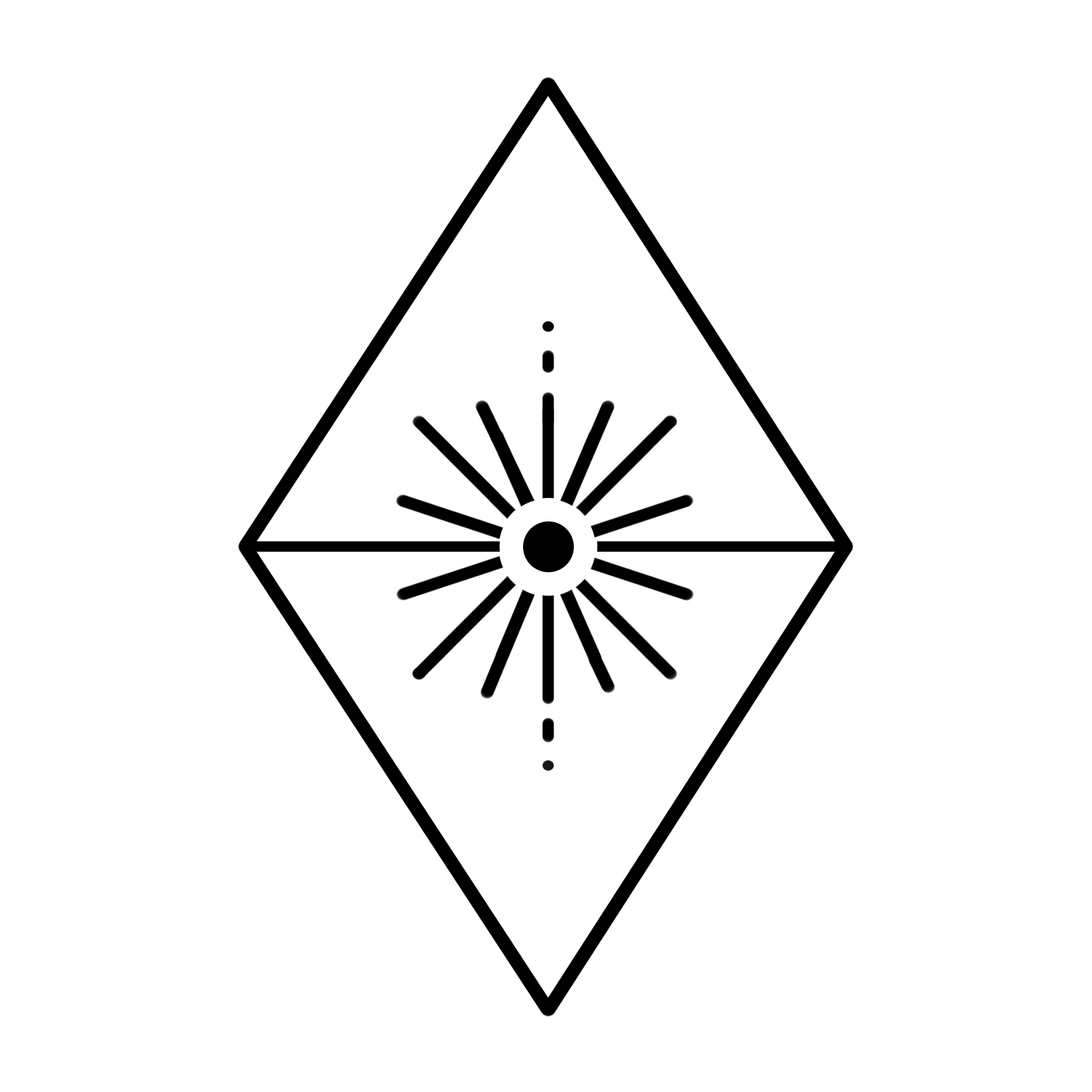
|
第四幕 某企業一般社員
前置きはいいからさっさと本題に入りましょう。携帯の電源は切らないわ、それがゆるされないならわたしは帰る。構わないかしら。 ありがとう。 あなた、おかしな神父ね。 知った仲でもないのに急にごめんなさい。でも安心したの。わたしのこの行動のわけをあなたは問わないでしょう、それで十分伝わってきた。あなたの興味の矛先はあくまであの子に向いているのであって、あの子をだしにわたしを呼んだのではないのだと。 確かにわたしはあのマンションに住んでいます。一時期はあの子も一緒だった。なぜあなたがそれを知っているのか、いえ、あの子は目立つ見た目をしていたし、そう、知られてもおかしくないのね。人の口に戸は立てられないから。 あの子はもともと芸能人だったというのはご存知かしら。 引退したのか、ただの休止状態だったのか厳密なところはわたしにもわかりません。わたしは確かにあの子のファンだったけど、あの子は贔屓目に見てもあまり万人受けのするほうではなくて、知りたくても満足に情報が入ってこなかったから。 歌手、たまにモデルじみた仕事もしていたわ。グラビアといえばいいのかしら。いえ、全年齢。雑誌ならまだ捨ててないから、もしもご所望なら見せることも可能です。 最初に気になったのは、やっぱり目つきだった。 まっさおなリップでいろどられた唇、奇抜な髪型や服装、そういう特徴を売りにしていたようだったけど、わたしがいちばん惹かれたのはそれらではなかった。あの子はどこでどんなふうにしていてもどこか不満げで孤独で、それなのに不敵で、自棄を起こしているような顔つきをしていた。とがった鼻も小さな顎もすがめられた目も歪んだ姿勢もわざと傷めたような声もぜんぶぜんぶ「どこにも居場所がない」と言っているみたいで、 わたしよりもずっと輝いた場所にいるくせにしあわせそうではなくて、 どうしてと訊かれてもこれ以上かみくだいて説明できそうにないわ。惹かれるってそういうことでしょう。 とにかくあの子を知ってからずっと、寝ても覚めてもあの子の顔や声があたまから離れなかった。あんなにのめりこんだのは、生活に色がなかったから尚のことという理由もあるのかもしれません。わたしの人生はよくも悪くも平凡で、わたし自身、何の取り柄もない。突出した才能もなければ夢もないし、努力も苦手なふつうすぎる若者だった。高校の頃は恋人も友人もいたわ。でもだからといって特別ドラマティックな事件もなく、可もなく不可もない大学に進んで、面白みのない職場に就いて、日々あじけない時間だけ咀嚼していたの、 そんななかで知ったあの子の存在は花より華々しい光だった。ほんとうに、そう思っていた。たいせつにしなくてはと感じたの。できる応援はぜんぶしたかった。ブラウン管の奥であの子が笑うだけで、いいえただこの世にいると知れるだけで毎日嬉しかった。 でも、そんな日々も長続きはしませんでした。あの子は目立った活躍をする前に芸能界からだんだんフェードアウトしていって、わたしは陽が落ちる予感にいつも怯えることになった。藁に縋る思いでファンレターを出したりもしたけど、届いたかはわからない。焼け石に水だったかもしれない。意欲がそがれてそのうちわたしは、落ちていくあの子の影をただ見ているだけになった。 それから世界はまた砂に逆戻り。 わたし、何も長続きしない女なの。新しく趣味を始める元気も時間もお金もない、日々の楽しみなんてスーパーのタイムセールくらいのもの。田舎の弱小企業の雑用なんてこんなものよ、つつましやかでいいでしょう、ね、神父様。 そんな或る日のことだった、道ばたであの子を見つけたのは。 うそだと思うでしょう。わたしも思ったわ、何度も他人のそら似だと自分自身に言い聞かせた、でもどこからどう見てもほんものだった。何年もポスターにテレビに雑誌にあの子の姿を追い求めたわたしの記憶が「間違いない」と告げたのよ。板ほど細い猫背、わたしにはわかった。わかってしまった、本人なのだと。 神父様はここからちょっと南にある公園、わかるかしら。あそこの自販機の付近だった。あの子、この寒々しい町でもとから〝異質という役割〟を持った背景の構成物みたいにしてそこに佇んでいた。 気づいた以上無視なんてできなかったから通行人を装って話しかけたの。そうしたら思った通りの声と表情で名前を教えてくれた。ファンだと告げると気まずそうにしていたけど、どこか得意そうにもしていたわね。いわく身体を壊してから仕事がうまくできなくなって、故郷に療養に戻ってきたはいいけど身寄りがなく、この町でしばらくホテル暮らしをしていたのだと教えてくれたわ、そして今はお金が尽きて、どうすべきか考えあぐねていたのだと。 実を言うとお金に困っているのは説明されなくても見当はついていたの、あの子、わたしと話す間にも落ちつきなく視線が地面をうろついていたから。 わたしは指摘しなかった。ただ見ているだけだった。手伝いを申し出ても恐らく断られると見たから、それならゆるされるあいだそばにいようと思った。どのくらい時間が経ったのかはよく覚えていない。何千年も経ったみたいな感覚だった。まだわたしがいるのに気づいて戻ってきたあの子の足音を今でも覚えている。握りこぶしを掲げて、まるで昔からのともだちにそうするみたいに駆け寄ってきたあの子の顔を。 ゆっくり、蜘蛛の脚みたいな指があまく動いて、手のひらの中の土にまみれた古くさい指輪を、見せてくれたの、そして自慢だったはずの青が剥がれたはだかの唇が動いて、 ――いいもん見つけた、 翳りを含んでやさしい声がそう言った。わたしも一字一句違わず、同じ思いだった。 よほど参っていたんでしょう、わたしを不審がる様子も見せないで、あの子はわたしの提案にのってついてきてくれた。いくら行く宛てがないと言ったってふつうは警戒するのが当然でしょうにね、とても用心深く見えたのに、意外。 家に行く道中の無言はいつまでも続く真夏の高速道路みたいに伸びていた。それをよく覚えている。 あの子は誰も近寄らせないような壁を醸し出しながら、同時に無邪気に笑うのが得意だった。営業用だったのかもしれない、どっちも素かもしれない、でもとにかく心の底までは誰にも触らせないという雰囲気をいつも纏っていて、わたしは一緒に暮らすうちにそれがほどけてくるのじゃないかと期待していたの。 帰宅するとあの子がいる。毎日終業までの時間が待ち遠しくなったわ。それが嬉しくて、これまで生きてきたぶんのごほうびはなんて後ろ暗いんだろうと喜んだ、わかるかしらこの気持ちが。 おしえてあげる、しあわせとは表に出せない色とかたちをしているものよ。 借りてきた猫みたいにおずおずソファに座っていた体が日を追うごとに伸びていくのがはがゆくておかしかった。シャワータイムになると水音に混じって細い歌声が聞こえてきて、わたし、その時間だけは持ち帰った仕事も家事も手につかないで廊下に座ってた。わたしの仕事場から電話がくると、あの子、いつもベランダに出ていた、別に強制したわけでもないのに。そっと窓に寄るとあの子が黒を背景に手すりにもたれているのがわかる、わたしに気がつかないで手遊びをして、ときどき知らない国の迷子みたいに頼りない瞳を空に向けるさまが闇に浮かんでくるの。 あの子の洗った服を着て、あの子の出した皿を使って、あの子の拭いた廊下を歩いた、わたしの稼いだお金でふたりぶんの食材をわたしが買ってわたしの料理をふたりで食べた、わたしのただいまにあの子のおかえりがにじむ毎日、 あのときのあの場所がらくえんだった。それ以外に言い表しようがない。 テレビもCDももうぜんぶいらなかった。あの子が隣にいるのだから他に望むものはないし、飾っていたポスターも捨てたわ、あの子が目にしてもしも傷つくといけないから。 終わりはあっけなく来るものね。 散歩の時間がどんどん長くなって、やがて帰ってこなくなったあの子をわたしは引き留められなかった。バイト先から連絡が来たのを取ったことがあって、それであの子が働いていたのを知ったのだけど、あの子、わたしに与えられるものだけでは満足ができなかったんでしょう、きっと。田舎の薄給生活に耐えられなかったのかも。相談もなくうちの電話番号を使われたことなんかどうでもよかった、そんな理由で怒るはずなかった、誤解しないであなたが想像するようなことなんか一度たりともしていないわ。言い合いすら満足にさせてもらえなかった。遠慮が抜けきらなかったのか、いつもあの子は聞き分けがよかったからわたしも言いたいことができたって外には出さずに呑み込んでばかりだった。 なぜ出て行ったの。のぞみならなるべく叶えてあげたのに。何が足りなかったの。いずれ離れるならどうして一度この手を取ったりしたの。ただの戯れ? わたしはあの子に何も求めなかった。歌ってほしいとせがんだわけでもない、浜辺でするデートだって想像だけで済ませたわ、あの子毎日笑ってわたしを出迎えていたくせに、 どう説明したらいいのかまるでわからない。とにかく、やっとのぼったはずだった陽にまた沈まれてわたしは人生何度目かの荒野をひとりで歩く羽目になった。 高校時代の恋人と再会したのはその時期です。まさか彼が隣町で小児科医をしていたなんて夢にも思わなかったわ、喧嘩別れしたわけじゃないけど、大学に進学してから疎遠になっていたの。思いがけず話が弾んで、忙しいあいまを縫って会うようになって。 いいひとよ。 あの子と、 もう一度会ったのは、 わたしのマンションの前だった、あの子は今度は道なんか見ていなかった、思い詰めた瞳で空を、わからない、どうせ曇天よ、わたしに気づくとすぐ立ち上がって「待ってた」とそう、わらって、 どう言えば伝わるの。 わたしは笑わなかった。どうでもよかったわけじゃないの、でも、もう会わない、一緒には住まないし部屋に二度と上げないから帰ってと、そう告げたのはあの子ではなく、 もうあなたとわたしには何の関係もないって。こういうのはやめようって。 だって先に出ていったのはあの子よ。わたしがどういう気分で毎日すごしたか、わたしが何と言おうとあの子に異論なんかあるはずなかった、そんなのわかってた、だってわたしが何か言う前に先にいなくなったのは向こうなのだから。何一つ変わらない。あの子はわたしの家の人間なんかじゃなかった、それだけよ。あるべき状態に戻っただけ。違う違うわ報復したかったんじゃないわ、そうじゃない。そんなこと。 自由になりたかったんでしょう。のぞみどおりにしたのよ。 やっぱりあの子は何も言い返してこなかった、予定調和の沈黙はあやまたずわたしを貫いた、そうしてあの子はいつも通り、いつも通りに上がった口の端、それなのに落ちた視線。 どうして笑ってくれないの。あんなのあの子の笑顔なんかじゃない。この町の空や浜辺と同じくらい薄汚れたあの子、あの子を不完全にしたのは青いリップがない唇なんかじゃなくて、だったらいったいなんだったの。何がだめだったの。 それきりよ。それから二度と会ってない。 さあ、よそに友人がいたらそもそもわたしについて来たかしら。誰かと会ってるそぶりなんて見せなかったからよくわからない――巧妙に隠していた可能性もあるけど――バイト先以外だったらそうね、この町そのものに詳しそうな人、たとえば駐在さんなんかどう。あの子の存在も把握していた可能性はあるわ。わたし、あの人には昔だいぶ助けられたからわかる、たぶんあなたの期待も裏切ることはないでしょう。勤勉で物腰がやわらかなのになんとなく他者に有無を言わせない不思議な貫禄のある人よ。駐在所に行けばすぐにわかるわ、一人でやっているらしいから。 わからない。説明できない気持ちが多いのはきっとわたしがわたしの心を知らないからでしょう。でも知る必要性も感じないからこのままでわたしはまったく構わない。 あなたのこともそう。わたしが知る必要はないわ。 他にわたしに何ができたと言うの。わたしはただ自分のやるべきことをしたまで。からっぽのわたしでも考えつくいちばんを選び取っただけ。 ほんとうに奇妙なひとね。石像みたい。神父ってみんなこうなの。 責める気はないわ、あなたの無言はわたしに都合がいいから。わたしはどんな歴史ある教えにもわたしを裁いてほしくはない。あなたにわざわざ咎められなくてもわかってるつもり。もう何もかもわたしの手からは離れたはずよ。 はなしたはずよ。 問いなんかじゃない。ぜんぶただの独り言よ。わたしをここから出して。 わたし結婚するの、さっき話した恋人と。すぐ引っ越してこの町を出るからもうこれきり会うことはないでしょう、あなたにも、あの子にも。 あなたとあの子の関係を訊かないわたしがそんなにおかしいかしら。 言ったじゃない。これがあの子が望んだ事態だとしても、いいえいい話さなくていい、何も詮索しないわ。わたしとあの子はもう終わったの、あの別れのあとあの子に何が起きていたってわたしとあの子は「もう何の関係もない」。説明は一切不要よ。わたしが知ってもどうしようもない。もういいの。 でも、もしできるなら、あの子には今日のことは内緒にしてほしい。告解室での会話とはすべて秘されるものという認識であってるかしら。ねえ、わたしは今日、ここにいなかった。わたしたちは何も話してなどいない。 さよならのつもりのない行動ばかりがいつもほんとうのさよならね。とどめしかさせないから、もう、会わないわ。 |