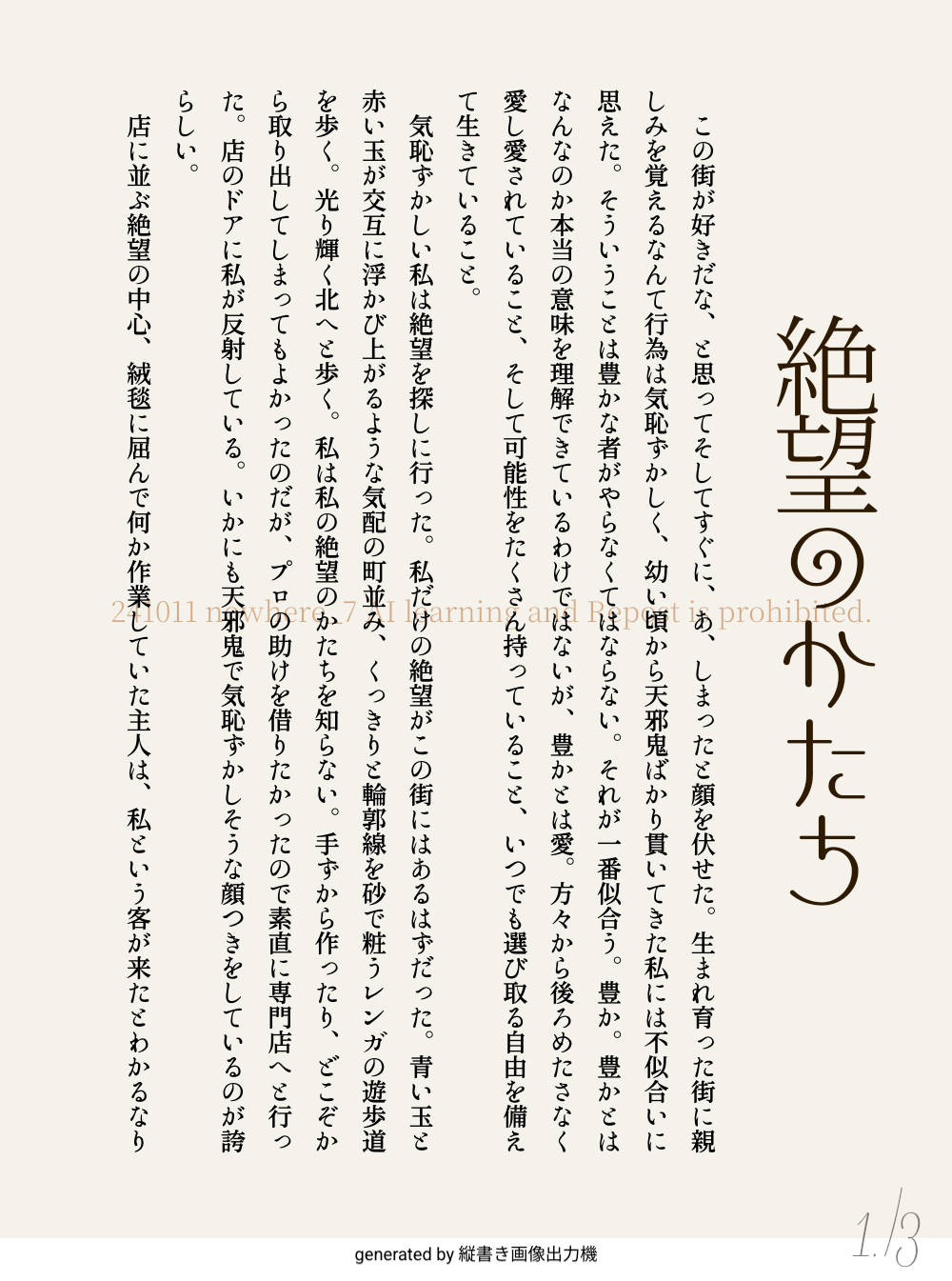
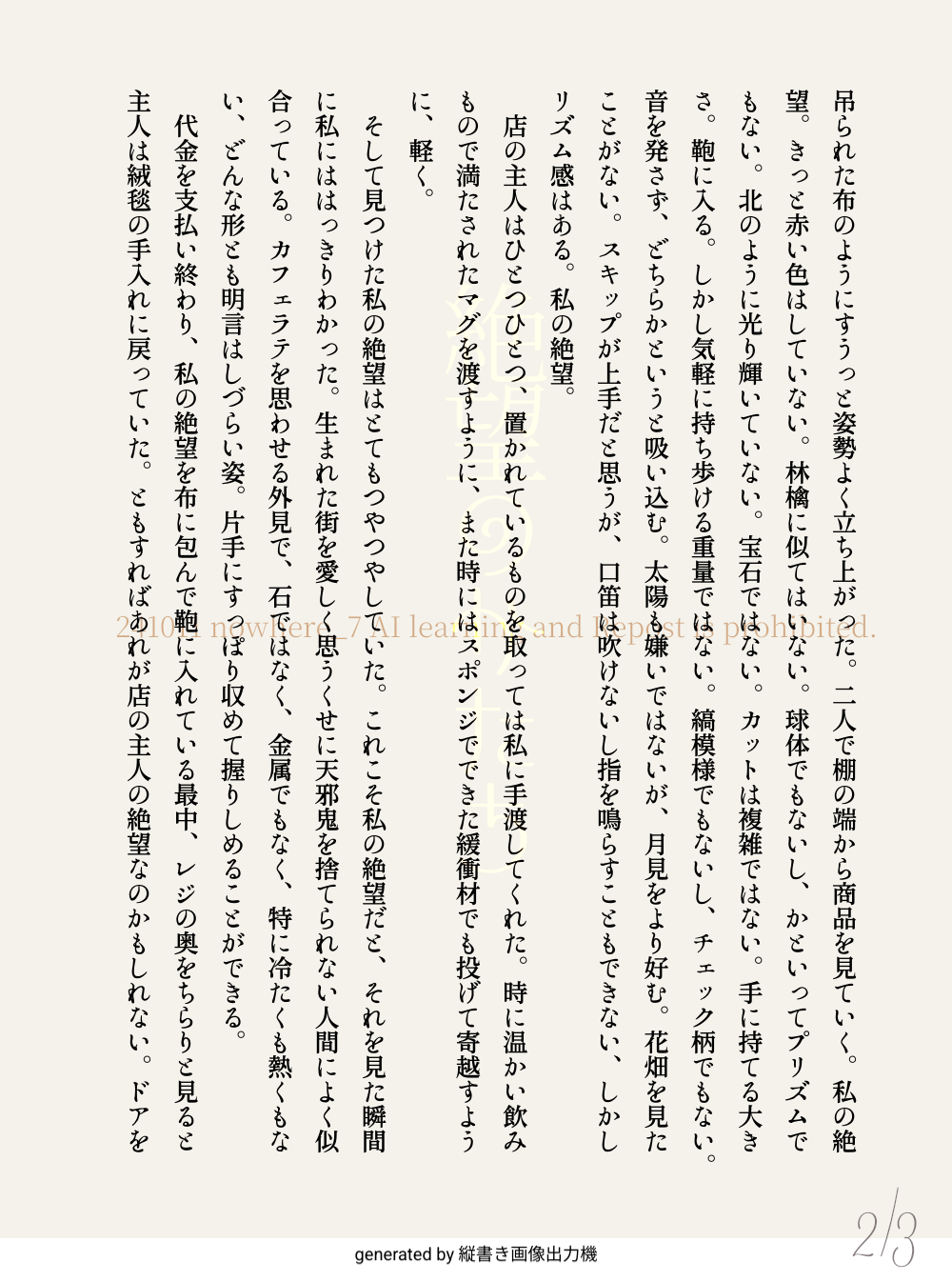
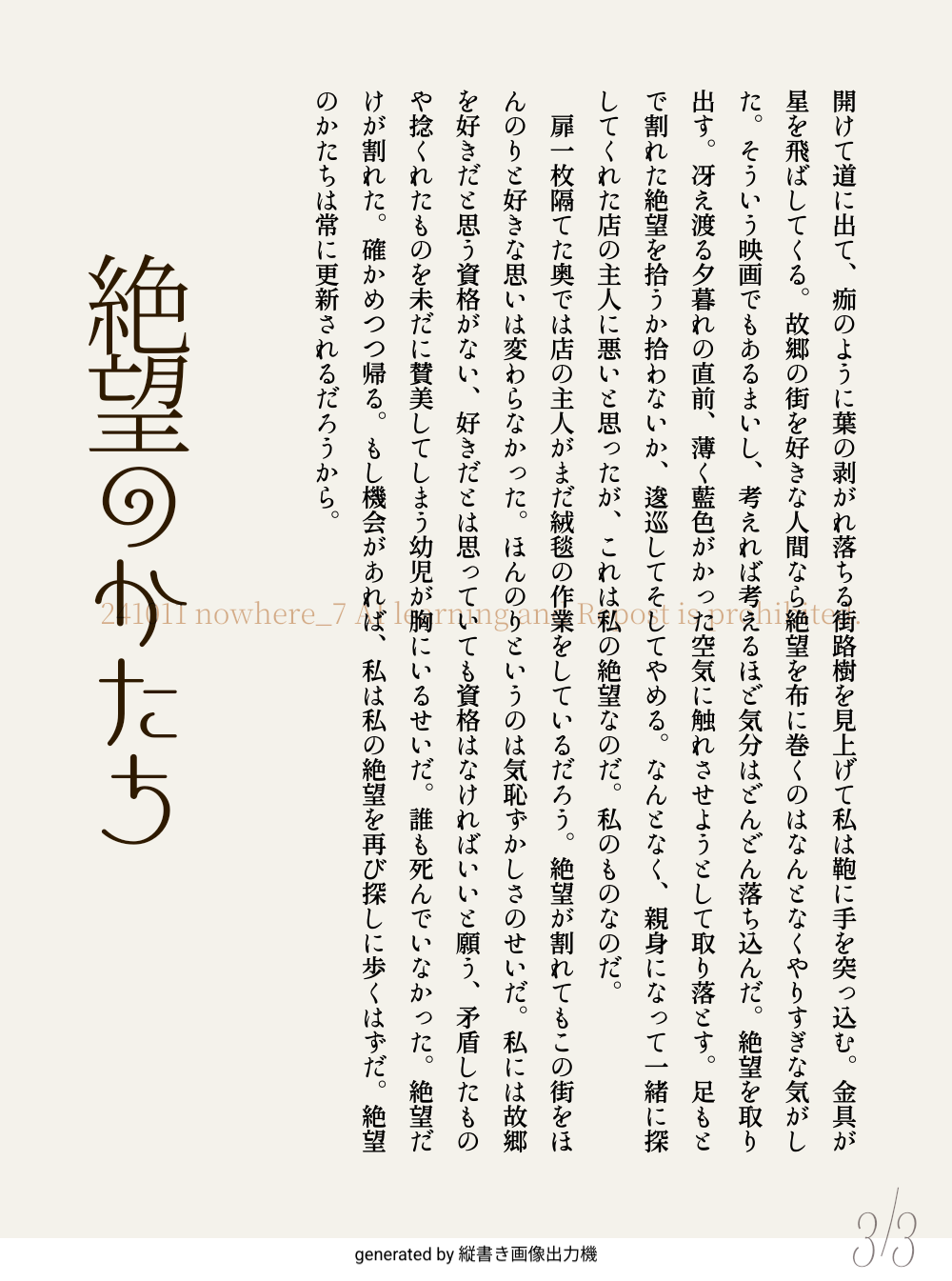
この街が好きだな、と思ってそしてすぐに、あ、しまったと顔を伏せた。生まれ育った街に親しみを覚えるなんて行為は気恥ずかしく、幼い頃から天邪鬼ばかり貫いてきた私には不似合いに思えた。そういうことは豊かな者がやらなくてはならない。それが一番似合う。豊か。豊かとはなんなのか本当の意味を理解できているわけではないが、豊かとは愛。方々から後ろめたさなく愛し愛されていること、そして可能性をたくさん持っていること、いつでも選び取る自由を備えて生きていること。
気恥ずかしい私は絶望を探しに行った。私だけの絶望がこの街にはあるはずだった。青い玉と赤い玉が交互に浮かび上がるような気配の町並み、くっきりと輪郭線を砂で粧うレンガの遊歩道を歩く。光り輝く北へと歩く。私は私の絶望のかたちを知らない。手ずから作ったり、どこぞから取り出してしまってもよかったのだが、プロの助けを借りたかったので素直に専門店へと行った。店のドアに私が反射している。いかにも天邪鬼で気恥ずかしそうな顔つきをしているのが誇らしい。
店に並ぶ絶望の中心、絨毯に屈んで何か作業していた主人は、私という客が来たとわかるなり吊られた布のようにすうっと姿勢よく立ち上がった。二人で棚の端から商品を見ていく。私の絶望。きっと赤い色はしていない。林檎に似てはいない。球体でもないし、かといってプリズムでもない。北のように光り輝いていない。宝石ではない。カットは複雑ではない。手に持てる大きさ。鞄に入る。しかし気軽に持ち歩ける重量ではない。縞模様でもないし、チェック柄でもない。音を発さず、どちらかというと吸い込む。太陽も嫌いではないが、月見をより好む。花畑を見たことがない。スキップが上手だと思うが、口笛は吹けないし指を鳴らすこともできない、しかしリズム感はある。私の絶望。
店の主人はひとつひとつ、置かれているものを取っては私に手渡してくれた。時に温かい飲みもので満たされたマグを渡すように、また時にはスポンジでできた緩衝材でも投げて寄越すように、軽く。
そして見つけた私の絶望はとてもつやつやしていた。これこそ私の絶望だと、それを見た瞬間に私にははっきりわかった。生まれた街を愛しく思うくせに天邪鬼を捨てられない人間によく似合っている。カフェラテを思わせる外見で、石ではなく、金属でもなく、特に冷たくも熱くもない、どんな形とも明言はしづらい姿。片手にすっぽり収めて握りしめることができる。
代金を支払い終わり、私の絶望を布に包んで鞄に入れている最中、レジの奥をちらりと見ると主人は絨毯の手入れに戻っていた。ともすればあれが店の主人の絶望なのかもしれない。ドアを開けて道に出て、痂のように葉の剥がれ落ちる街路樹を見上げて私は鞄に手を突っ込む。金具が星を飛ばしてくる。故郷の街を好きな人間なら絶望を布に巻くのはなんとなくやりすぎな気がした。そういう映画でもあるまいし、考えれば考えるほど気分はどんどん落ち込んだ。絶望を取り出す。冴え渡る夕暮れの直前、薄く藍色がかった空気に触れさせようとして取り落とす。足もとで割れた絶望を拾うか拾わないか、逡巡してそしてやめる。なんとなく、親身になって一緒に探してくれた店の主人に悪いと思ったが、これは私の絶望なのだ。私のものなのだ。
扉一枚隔てた奥では店の主人がまだ絨毯の作業をしているだろう。絶望が割れてもこの街をほんのりと好きな思いは変わらなかった。ほんのりというのは気恥ずかしさのせいだ。私には故郷を好きだと思う資格がない、好きだとは思っていても資格はなければいいと願う、矛盾したものや捻くれたものを未だに賛美してしまう幼児が胸にいるせいだ。誰も死んでいなかった。絶望だけが割れた。確かめつつ帰る。もし機会があれば、私は私の絶望を再び探しに歩くはずだ。絶望のかたちは常に更新されるだろうから。
絶望のかたち/不可村/241011/AI learning and Repost is prohibited.