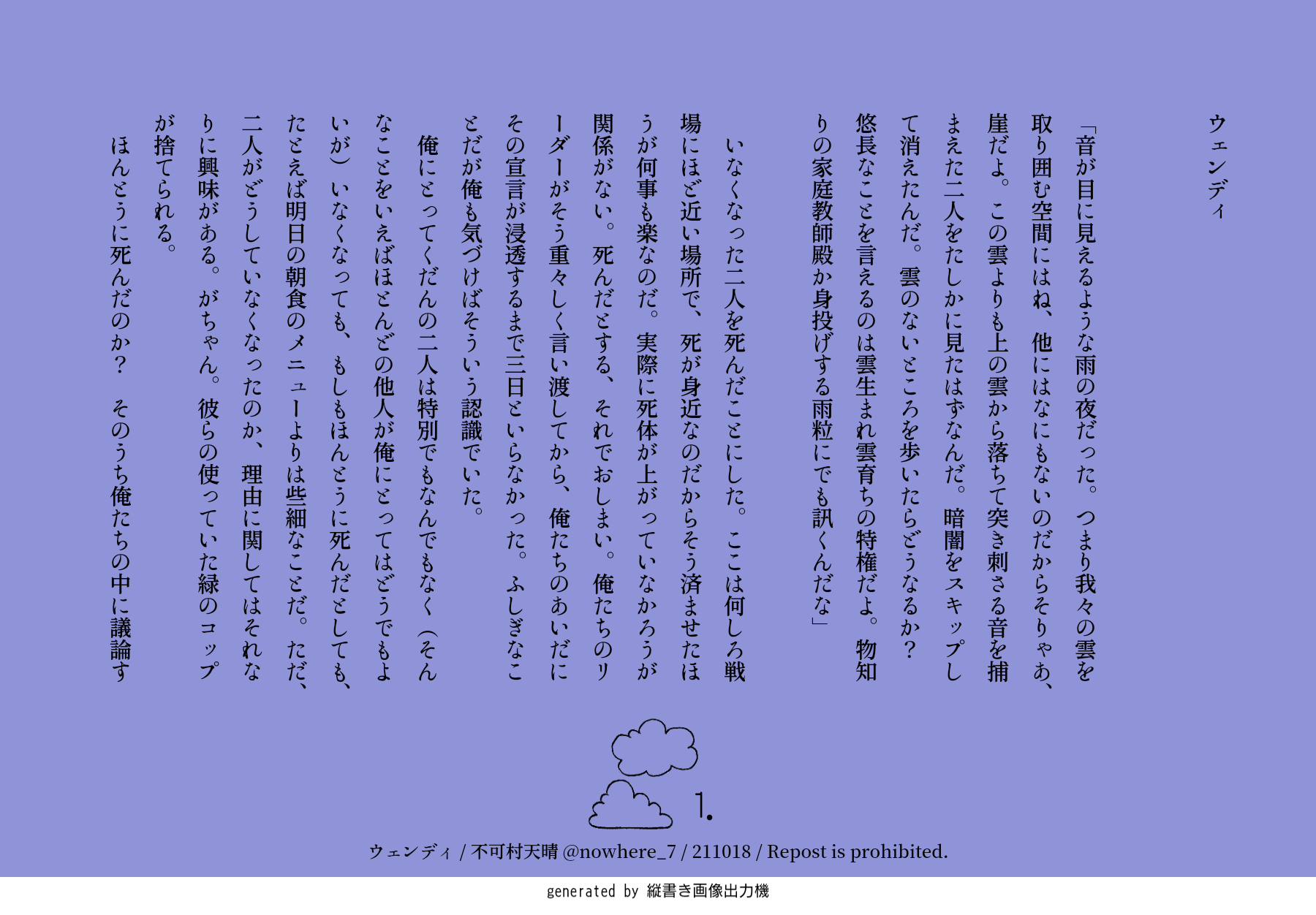
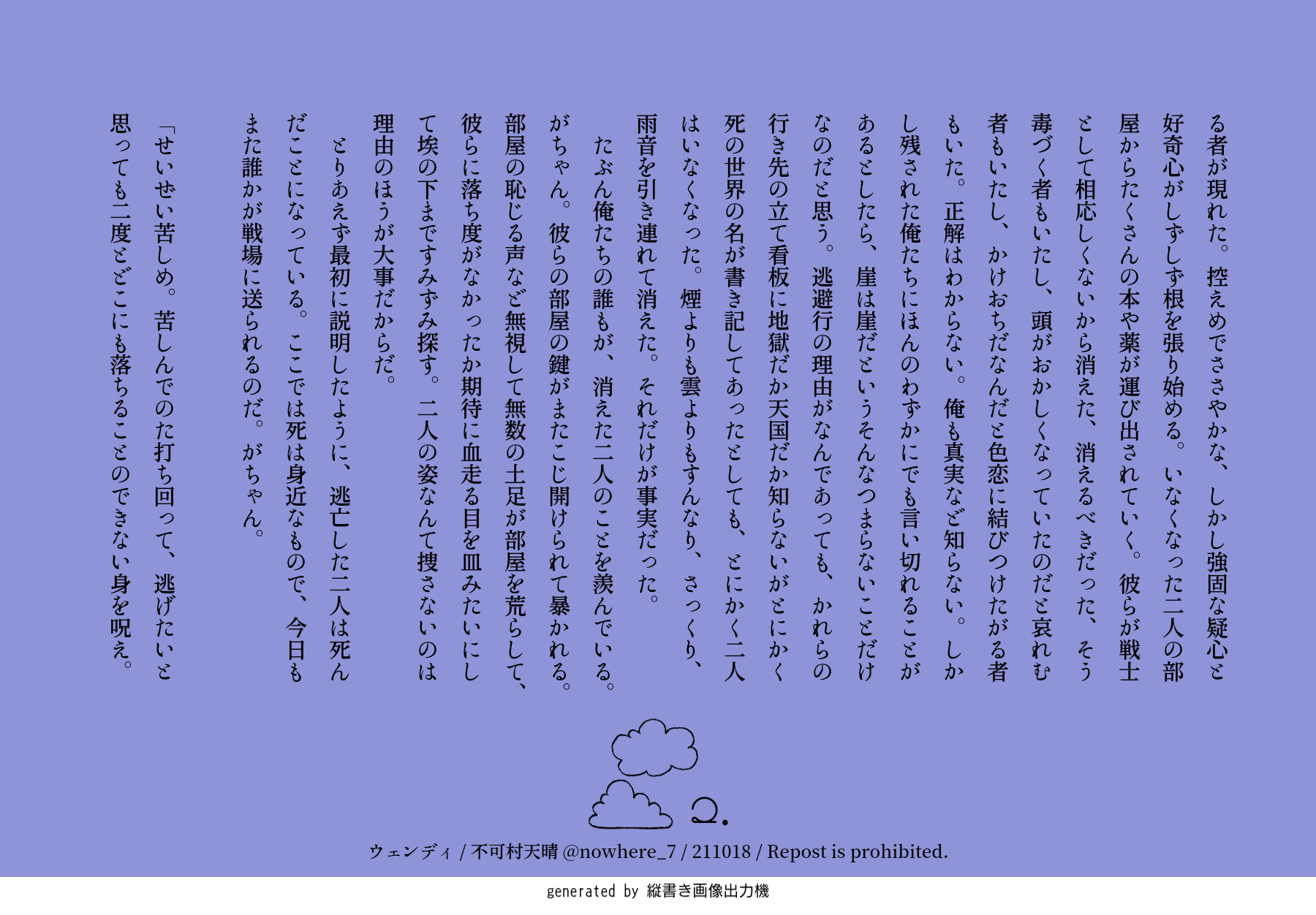

「音が目に見えるような雨の夜だった。つまり我々の雲を取り囲む空間にはね、他にはなにもないのだからそりゃあ、崖だよ。この雲よりも上の雲から落ちて突き刺さる音を捕まえた二人をたしかに見たはずなんだ。暗闇をスキップして消えたんだ。雲のないところを歩いたらどうなるか? 悠長なことを言えるのは雲生まれ雲育ちの特権だよ。物知りの家庭教師殿か身投げする雨粒にでも訊くんだな」
いなくなった二人を死んだことにした。ここは何しろ戦場にほど近い場所で、死が身近なのだからそう済ませたほうが何事も楽なのだ。実際に死体が上がっていなかろうが関係がない。死んだとする、それでおしまい。俺たちのリーダーがそう重々しく言い渡してから、俺たちのあいだにその宣言が浸透するまで三日といらなかった。ふしぎなことだが俺も気づけばそういう認識でいた。
俺にとってくだんの二人は特別でもなんでもなく(そんなことをいえばほとんどの他人が俺にとってはどうでもよいが)いなくなっても、もしもほんとうに死んだとしても、たとえば明日の朝食のメニューよりは些細なことだ。ただ、二人がどうしていなくなったのか、理由に関してはそれなりに興味がある。がちゃん。彼らの使っていた緑のコップが捨てられる。
ほんとうに死んだのか? そのうち俺たちの中に議論する者が現れた。控えめでささやかな、しかし強固な疑心と好奇心がしずしず根を張り始める。いなくなった二人の部屋からたくさんの本や薬が運び出されていく。彼らが戦士として相応しくないから消えた、消えるべきだった、そう毒づく者もいたし、頭がおかしくなっていたのだと哀れむ者もいたし、かけおちだなんだと色恋に結びつけたがる者もいた。正解はわからない。俺も真実など知らない。しかし残された俺たちにほんのわずかにでも言い切れることがあるとしたら、崖は崖だというそんなつまらないことだけなのだと思う。逃避行の理由がなんであっても、かれらの行き先の立て看板に地獄だか天国だか知らないがとにかく死の世界の名が書き記してあったとしても、とにかく二人はいなくなった。煙よりも雲よりもすんなり、さっくり、雨音を引き連れて消えた。それだけが事実だった。
たぶん俺たちの誰もが、消えた二人のことを羨んでいる。がちゃん。彼らの部屋の鍵がまたこじ開けられて暴かれる。部屋の恥じる声など無視して無数の土足が部屋を荒らして、彼らに落ち度がなかったか期待に血走る目を皿みたいにして埃の下まですみずみ探す。二人の姿なんて捜さないのは理由のほうが大事だからだ。
とりあえず最初に説明したように、逃亡した二人は死んだことになっている。ここでは死は身近なもので、今日もまた誰かが戦場に送られるのだ。がちゃん。
「せいぜい苦しめ。苦しんでのた打ち回って、逃げたいと思っても二度とどこにも落ちることのできない身を呪え。最後の雲から落ちたらもう、その下には何もないのだから」
ウェンディ / 不可村天晴 @nowhere_7 / 211018 / Repost is prohibited.