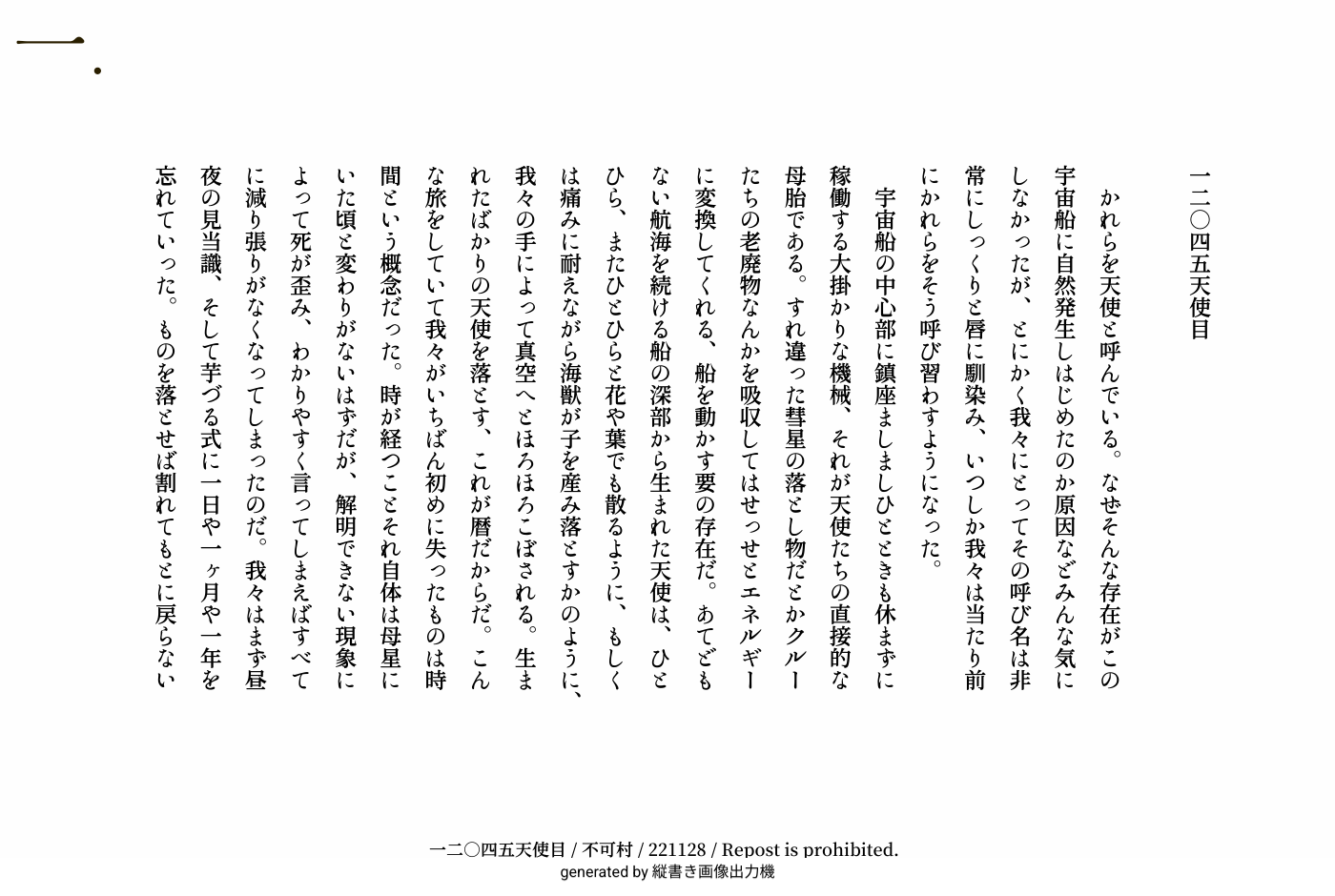
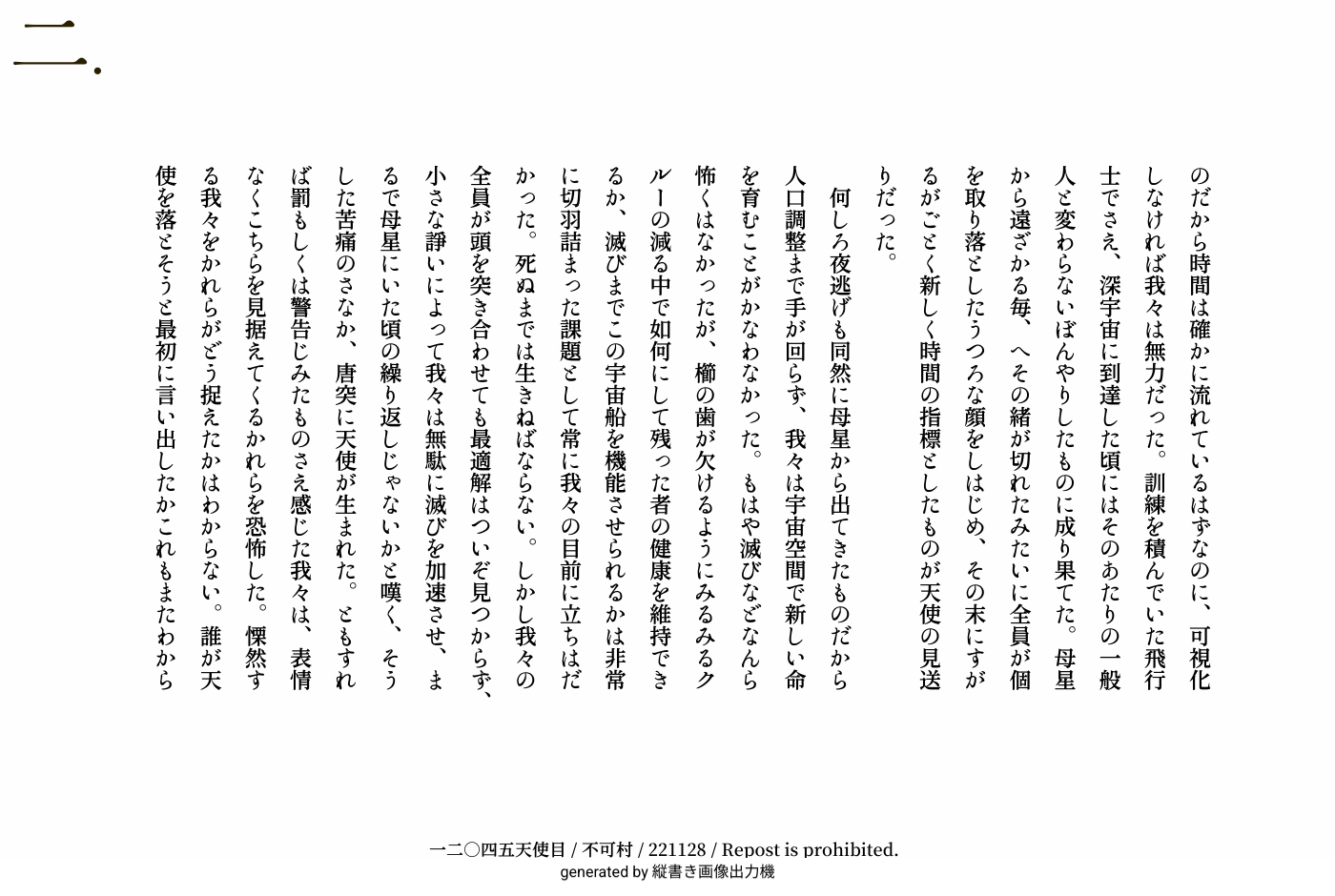
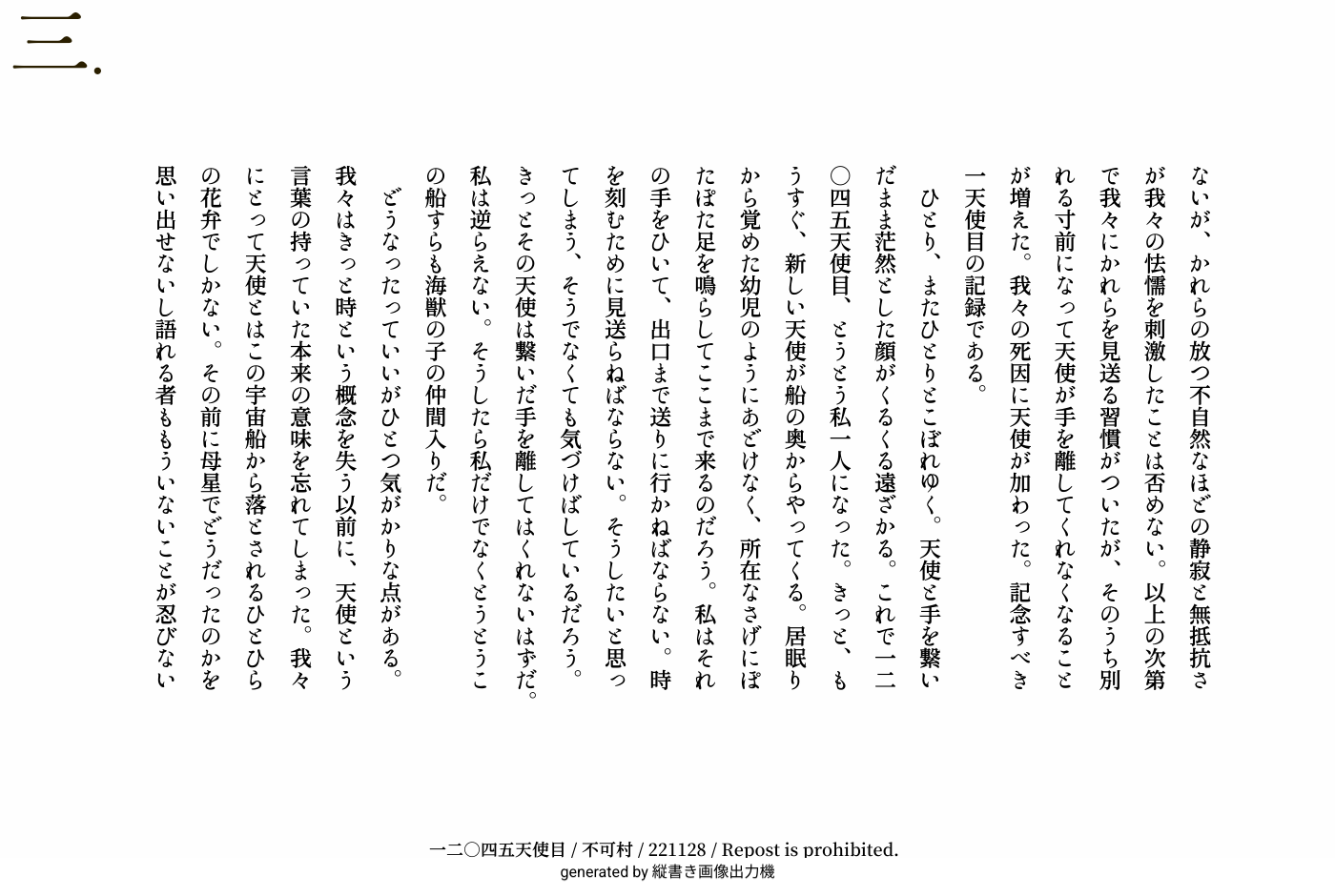
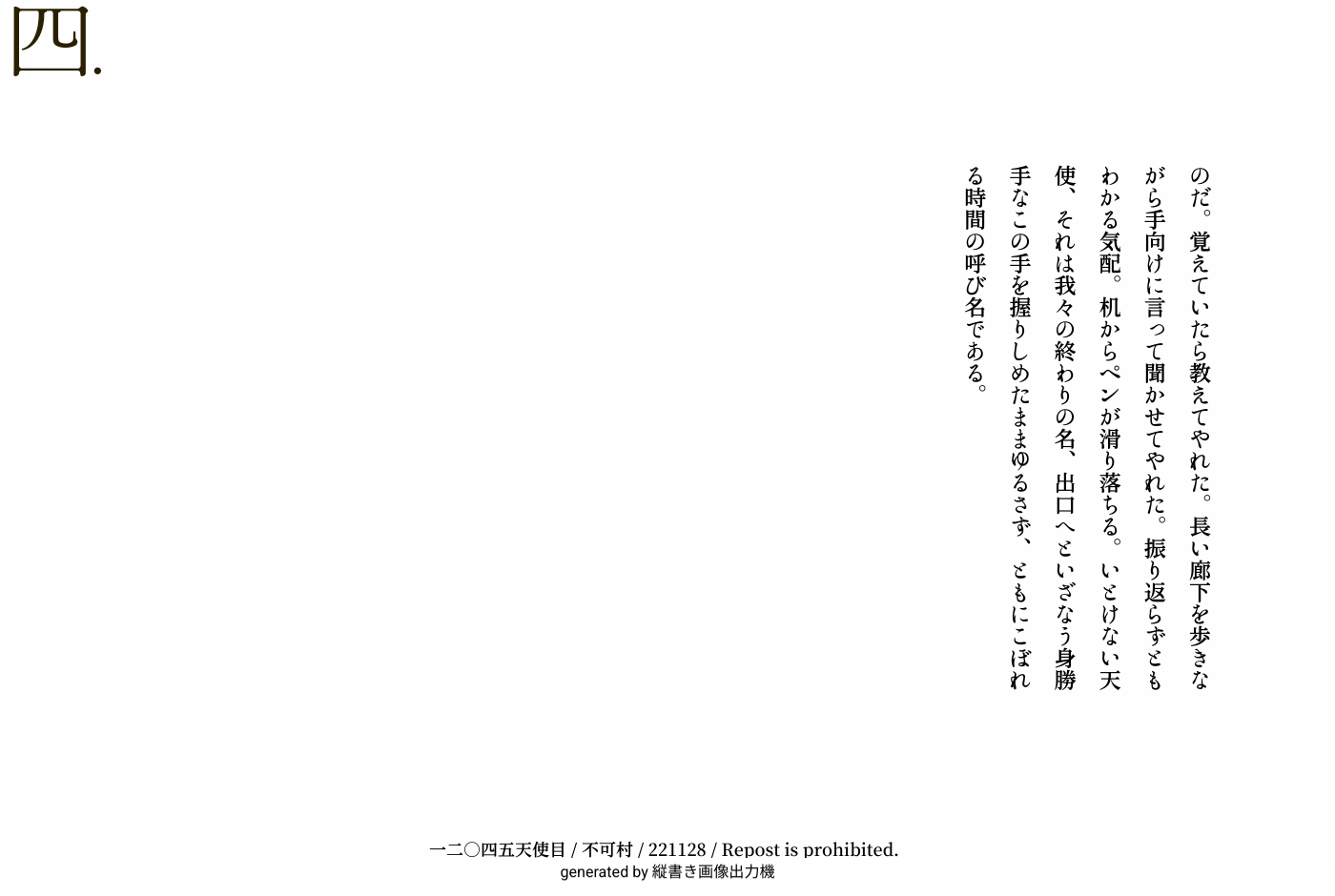
かれらを天使と呼んでいる。なぜそんな存在がこの宇宙船に自然発生しはじめたのか原因などみんな気にしなかったが、とにかく我々にとってその呼び名は非常にしっくりと唇に馴染み、いつしか我々は当たり前にかれらをそう呼び習わすようになった。
宇宙船の中心部に鎮座ましましひとときも休まずに稼働する大掛かりな機械、それが天使たちの直接的な母胎である。すれ違った彗星の落とし物だとかクルーたちの老廃物なんかを吸収してはせっせとエネルギーに変換してくれる、船を動かす要の存在だ。あてどもない航海を続ける船の深部から生まれた天使は、ひとひら、またひとひらと花や葉でも散るように、もしくは痛みに耐えながら海獣が子を産み落とすかのように、我々の手によって真空へとほろほろこぼされる。生まれたばかりの天使を落とす、これが暦だからだ。こんな旅をしていて我々がいちばん初めに失ったものは時間という概念だった。時が経つことそれ自体は母星にいた頃と変わりがないはずだが、解明できない現象によって死が歪み、わかりやすく言ってしまえばすべてに減り張りがなくなってしまったのだ。我々はまず昼夜の見当識、そして芋づる式に一日や一ヶ月や一年を忘れていった。ものを落とせば割れてもとに戻らないのだから時間は確かに流れているはずなのに、可視化しなければ我々は無力だった。訓練を積んでいた飛行士でさえ、深宇宙に到達した頃にはそのあたりの一般人と変わらないぼんやりしたものに成り果てた。母星から遠ざかる毎、へその緒が切れたみたいに全員が個を取り落としたうつろな顔をしはじめ、その末にすがるがごとく新しく時間の指標としたものが天使の見送りだった。
何しろ夜逃げも同然に母星から出てきたものだから人口調整まで手が回らず、我々は宇宙空間で新しい命を育むことがかなわなかった。もはや滅びなどなんら怖くはなかったが、櫛の歯が欠けるようにみるみるクルーの減る中で如何にして残った者の健康を維持できるか、滅びまでこの宇宙船を機能させられるかは非常に切羽詰まった課題として常に我々の目前に立ちはだかった。死ぬまでは生きねばならない。しかし我々の全員が頭を突き合わせても最適解はついぞ見つからず、小さな諍いによって我々は無駄に滅びを加速させ、まるで母星にいた頃の繰り返しじゃないかと嘆く、そうした苦痛のさなか、唐突に天使が生まれた。ともすれば罰もしくは警告じみたものさえ感じた我々は、表情なくこちらを見据えてくるかれらを恐怖した。慄然する我々をかれらがどう捉えたかはわからない。誰が天使を落とそうと最初に言い出したかこれもまたわからないが、かれらの放つ不自然なほどの静寂と無抵抗さが我々の怯懦を刺激したことは否めない。以上の次第で我々にかれらを見送る習慣がついたが、そのうち別れる寸前になって天使が手を離してくれなくなることが増えた。我々の死因に天使が加わった。記念すべき一天使目の記録である。
ひとり、またひとりとこぼれゆく。天使と手を繋いだまま茫然とした顔がくるくる遠ざかる。これで一二○四五天使目、とうとう私一人になった。きっと、もうすぐ、新しい天使が船の奥からやってくる。居眠りから覚めた幼児のようにあどけなく、所在なさげにぽたぽた足を鳴らしてここまで来るのだろう。私はそれの手をひいて、出口まで送りに行かねばならない。時を刻むために見送らねばならない。そうしたいと思ってしまう、そうでなくても気づけばしているだろう。きっとその天使は繋いだ手を離してはくれないはずだ。私は逆らえない。そうしたら私だけでなくとうとうこの船すらも海獣の子の仲間入りだ。
どうなったっていいがひとつ気がかりな点がある。我々はきっと時という概念を失う以前に、天使という言葉の持っていた本来の意味を忘れてしまった。我々にとって天使とはこの宇宙船から落とされるひとひらの花弁でしかない。その前に母星でどうだったのかを思い出せないし語れる者ももういないことが忍びないのだ。覚えていたら教えてやれた。長い廊下を歩きながら手向けに言って聞かせてやれた。振り返らずともわかる気配。机からペンが滑り落ちる。いとけない天使、それは我々の終わりの名、出口へといざなう身勝手なこの手を握りしめたままゆるさず、ともにこぼれる時間の呼び名である。
一二○四五天使目 / 不可村 / 211123~221128 / Repost is prohibited.