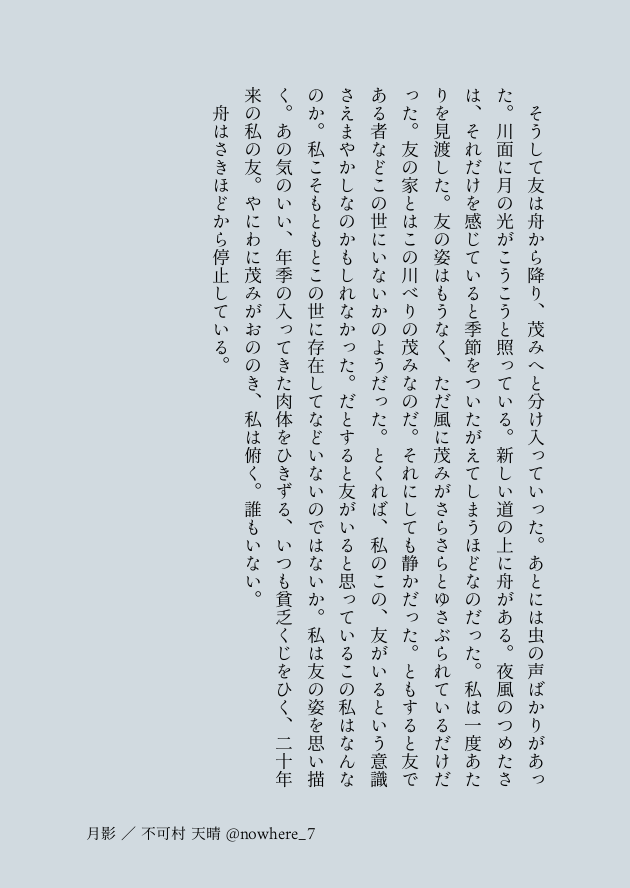
そうして友は舟から降り、茂みへと分け入っていった。あとには虫の声ばかりがあった。川面に月の光がこうこうと照っている。新しい道の上に舟がある。夜風のつめたさは、それだけを感じていると季節をついたがえてしまうほどなのだった。私は一度あたりを見渡した。友の姿はもうなく、ただ風に茂みがさらさらとゆさぶられているだけだった。友の家とはこの川べりの茂みなのだ。それにしても静かだった。ともすると友である者などこの世にいないかのようだった。とくれば、私のこの、友がいるという意識さえまやかしなのかもしれなかった。だとすると友がいると思っているこの私はなんなのか。私こそもともとこの世に存在してなどいないのではないか。私は友の姿を思い描く。あの気のいい、年季の入ってきた肉体をひきずる、いつも貧乏くじをひく、二十年来の私の友。やにわに茂みがおののき、私は俯く。誰もいない。
舟はさきほどから停止している。
月影 190609