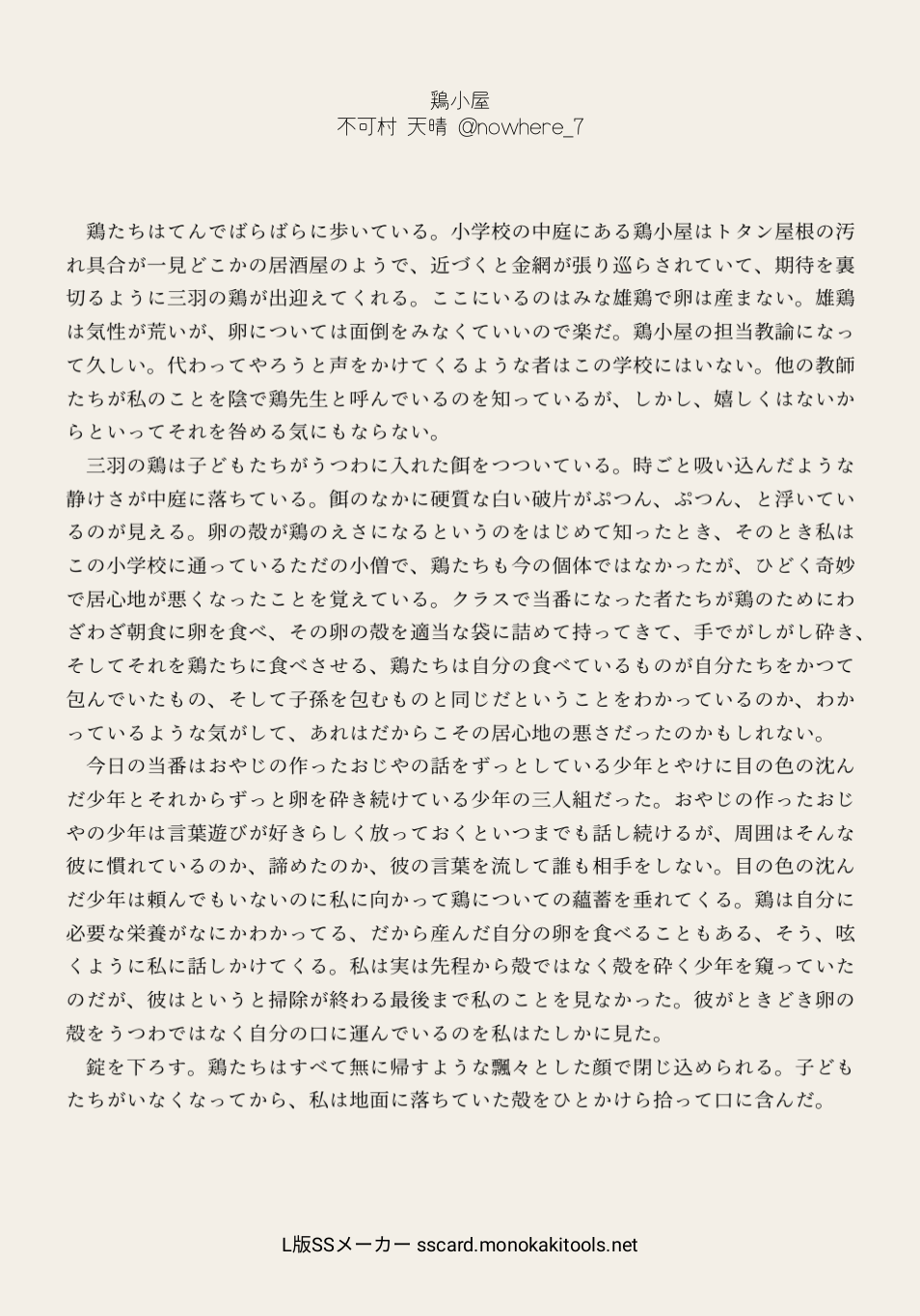
鶏たちはてんでばらばらに歩いている。小学校の中庭にある鶏小屋はトタン屋根の汚れ具合が一見どこかの居酒屋のようで、近づくと金網が張り巡らされていて、期待を裏切るように三羽の鶏が出迎えてくれる。ここにいるのはみな雄鶏で卵は産まない。雄鶏は気性が荒いが、卵については面倒をみなくていいので楽だ。鶏小屋の担当になって久しい。代わってやろうと声をかけてくるような人間はこの職場にはいない。他の教師たちが私のことを陰で鶏先生と呼んでいるのを知っているが、しかし、嬉しくはないからといってそれを咎める気にもならない。
三羽の鶏は子どもたちがうつわに入れた餌をつついている。時ごと吸い込んだような静けさが中庭に落ちている。餌のなかに硬質な白い破片がぷつん、ぷつん、と浮いているのが見える。卵の殻が鶏のえさになるというのをはじめて知ったとき、そのとき私はこの小学校に通っているただの小僧で、鶏たちも今の個体ではなかったが、ひどく奇妙で居心地が悪くなったことを覚えている。クラスで当番になった者たちが鶏のためにわざわざ朝食に卵を食べ、その卵の殻を適当な袋に詰めて持ってきて、手でがしがし砕き、そしてそれを鶏たちに食べさせる、鶏たちは自分の食べているものが自分たちをかつて包んでいたもの、そして子孫を包むものと同じだということをわかっているのか、わかっているような気がして、あれはだからこその居心地の悪さだったのかもしれない。
今日の当番はおやじの作ったおじやの話をずっとしている少年とやけに目の色の沈んだ少年とそれからずっと卵を砕き続けている少年の三人組だった。おやじの作ったおじやの少年は言葉遊びが好きらしく放っておくといつまでも話し続けるが、周囲はそんな彼に慣れているのか、諦めたのか、彼の言葉を流して誰も相手をしない。目の色の沈んだ少年は頼んでもいないのに私に向かって鶏についての蘊蓄を垂れてくる。鶏は自分に必要な栄養がなにかわかってる、だから産んだ自分の卵を食べることもある、そう、呟くように私に話しかけてくる。私は実は先程から殻ではなく殻を砕く少年を窺っていたのだが、彼はというと掃除が終わる最後まで私のことを見なかった。彼がときどき卵の殻をうつわではなく自分の口に運んでいるのを私はたしかに見た。
錠を下ろす。鶏たちはすべて無に帰すような飄々とした顔で閉じ込められる。子どもたちがいなくなってから、私は地面に落ちていた殻をひとかけら拾って口に含んだ。
鶏小屋 200120