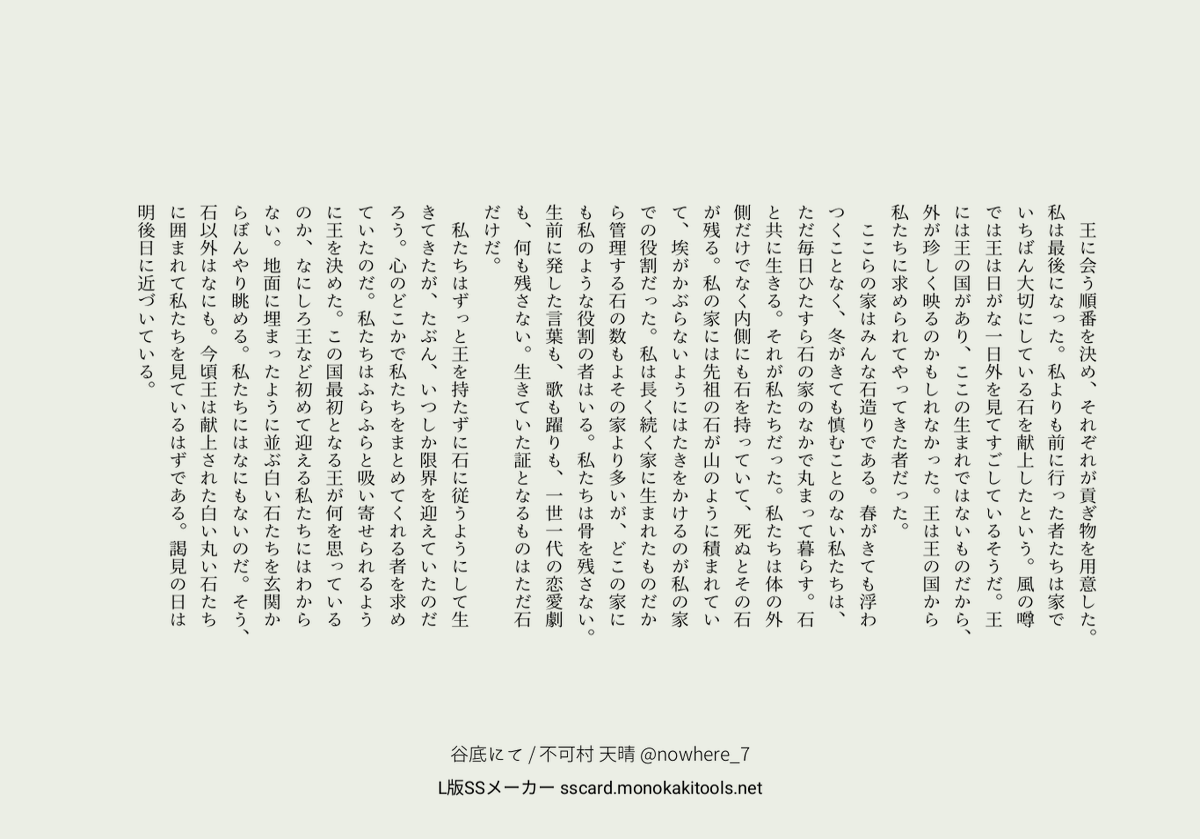
王に会う順番を決め、それぞれが貢ぎ物を用意した。私は最後になった。私よりも前に行った者たちは家でいちばん大切にしている石を献上したという。風の噂では王は日がな一日外を見てすごしているそうだ。王には王の国があり、ここの生まれではないものだから、外が珍しく映るのかもしれなかった。王は王の国から私たちに求められてやってきた者だった。
ここらの家はみんな石造りである。春がきても浮わつくことなく、冬がきても慎むことのない私たちは、ただ毎日ひたすら石の家のなかで丸まって暮らす。石と共に生きる。それが私たちだった。私たちは体の外側だけでなく内側にも石を持っていて、死ぬとその石が残る。私の家には先祖の石が山のように積まれていて、埃がかぶらないようにはたきをかけるのが私の家での役割だった。私は長く続く家に生まれたものだから管理する石の数もよその家より多いが、どこの家にも私のような役割の者はいる。私たちは骨を残さない。生前に発した言葉も、歌も躍りも、一世一代の恋愛劇も、何も残さない。生きていた証となるものはただ石だけだ。
私たちはずっと王を持たずに石に従うようにして生きてきたが、たぶん、いつしか限界を迎えていたのだろう。心のどこかで私たちをまとめてくれる者を求めていたのだ。私たちはふらふらと吸い寄せられるように王を決めた。この国最初となる王が何を思っているのか、なにしろ王など初めて迎える私たちにはわからない。地面に埋まったように並ぶ白い石たちを、玄関からぼんやり眺める。私たちにはなにもないのだ。そう、石以外はなにも。今頃王は献上された白い丸い石たちに囲まれて私たちを見ているはずである。謁見の日は明後日に近づいている。
谷底にて 191215