
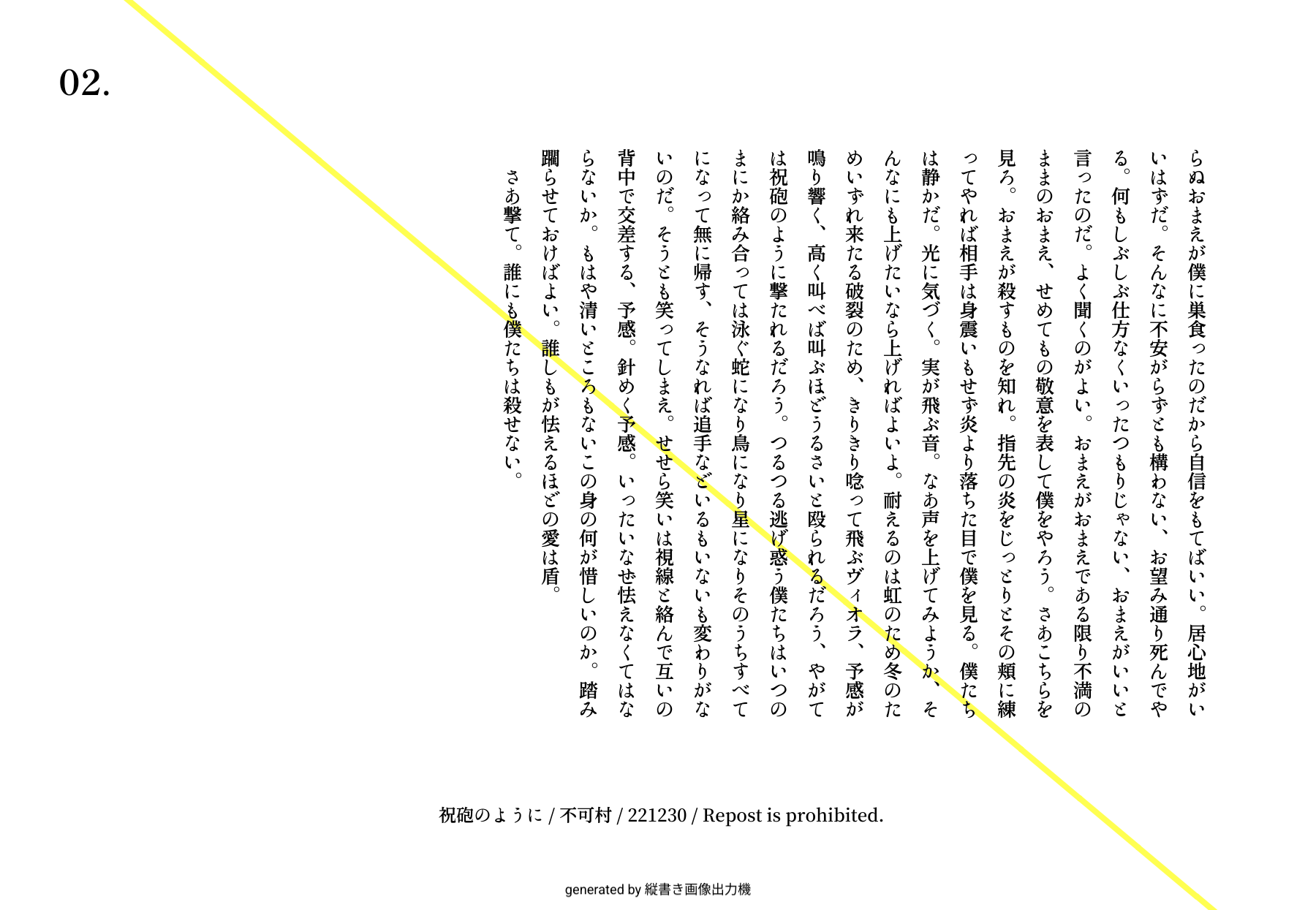
夕暮れに愛はいつもひとしく、宵にまばらになる。本来僕たちは愛について語るには少々もどかしい。すべてが足りないからだ。さらまた僕たちは、不足こそ僕たちが愛の隣人たる証明である事実に気づかない。足ろう足ろうとしては縺れて転び、転んでは左見右見そわそわ蟻でも吐いたみたいに立ち上がる。得ようとして失いたがっているおのれを実感しない。
もうすぐ撃たれるかもしれない、予感は春を待たずに芽吹いて雨を待つ。愛がないと信じ込んでいるせいである。目には見えないものをいつかいつか手に取れると錯覚しているためである。ないものはない。ないという事実含めて確かにある、それを信じられない僕。気づいてもすぐに忘れる。真実は、たぶん、違和感じみたもので、取り払おうと咳き込んだとたんに消えてゆく。それだからやはりぜったいに足ることがない。うつくしい僕。しかし自信がないという手枷を振り回して僕が耕した大地から生えるのは往々にしてこういう苦しみだった。やがて撃たれる予感であった。僕は、べつだん、そいつのことはきらいではない、それどころかかえって好んでいるかもしれないと最近はとみに思い始めている。腹からしたたる血のためにすっかり陰影のなくなった、傷まみれの体を引きずってそいつに笑い囁やきかけるのだ。やあずいぶん待たせた。面白いだろう。この身の傷がいつのものかおまえはわかるか、深さはわかるか、いくつあるのか知っているか。体が鉄砲、赤一輪。目の前に座っていた予感がにわかにさんざめいて風を起こせば、手に取るように伝わるおそれと喜びは期待にはち切れそうになる。そうだ、おまえがいなくては成り立たないのだ。おまえと一緒にひとつ死んでやろう。僕はそいつへ音もなく距離を詰めその胸ぐらを掴んでやる。近づいた顔の蒼白加減につい漏れ出た笑いを浴びせかける。いったいどうして目を白黒させているのか、おまえといえばおまえなのだ。他ならぬおまえが僕に巣食ったのだから自信をもてばいい。居心地がいいはずだ。そんなに不安がらずとも構わない、お望み通り死んでやる。何もしぶしぶ仕方なくいったつもりじゃない、おまえがいいと言ったのだ。よく聞くのがよい。おまえがおまえである限り不満のままのおまえ、せめてもの敬意を表して僕をやろう。さあこちらを見ろ。おまえが殺すものを知れ。指先の炎をじっとりとその頬に練ってやれば相手は身震いもせず炎より落ちた目で僕を見る。僕たちは静かだ。光に気づく。実が飛ぶ音。なあ声を上げてみようか、そんなにも上げたいなら上げればよいよ。耐えるのは虹のため冬のためいずれ来たる破裂のため、きりきり唸って飛ぶヴィオラ、予感が鳴り響く、高く叫べば叫ぶほどうるさいと殴られるだろう、やがては祝砲のように撃たれるだろう。つるつる逃げ惑う僕たちはいつのまにか絡み合っては泳ぐ蛇になり鳥になり星になりそのうちすべてになって無に帰す、そうなれば追手などいるもいないも変わりがないのだ。そうとも笑ってしまえ。せせら笑いは視線と絡んで互いの背中で交差する、予感。針めく予感。いったいなぜ怯えなくてはならないか。もはや清いところもないこの身の何が惜しいのか。踏み躙らせておけばよい。誰しもが怯えるほどの愛は盾。
さあ撃て。誰にも僕たちは殺せない。
祝砲のように / 不可村 / 221230 / Repost is prohibited.