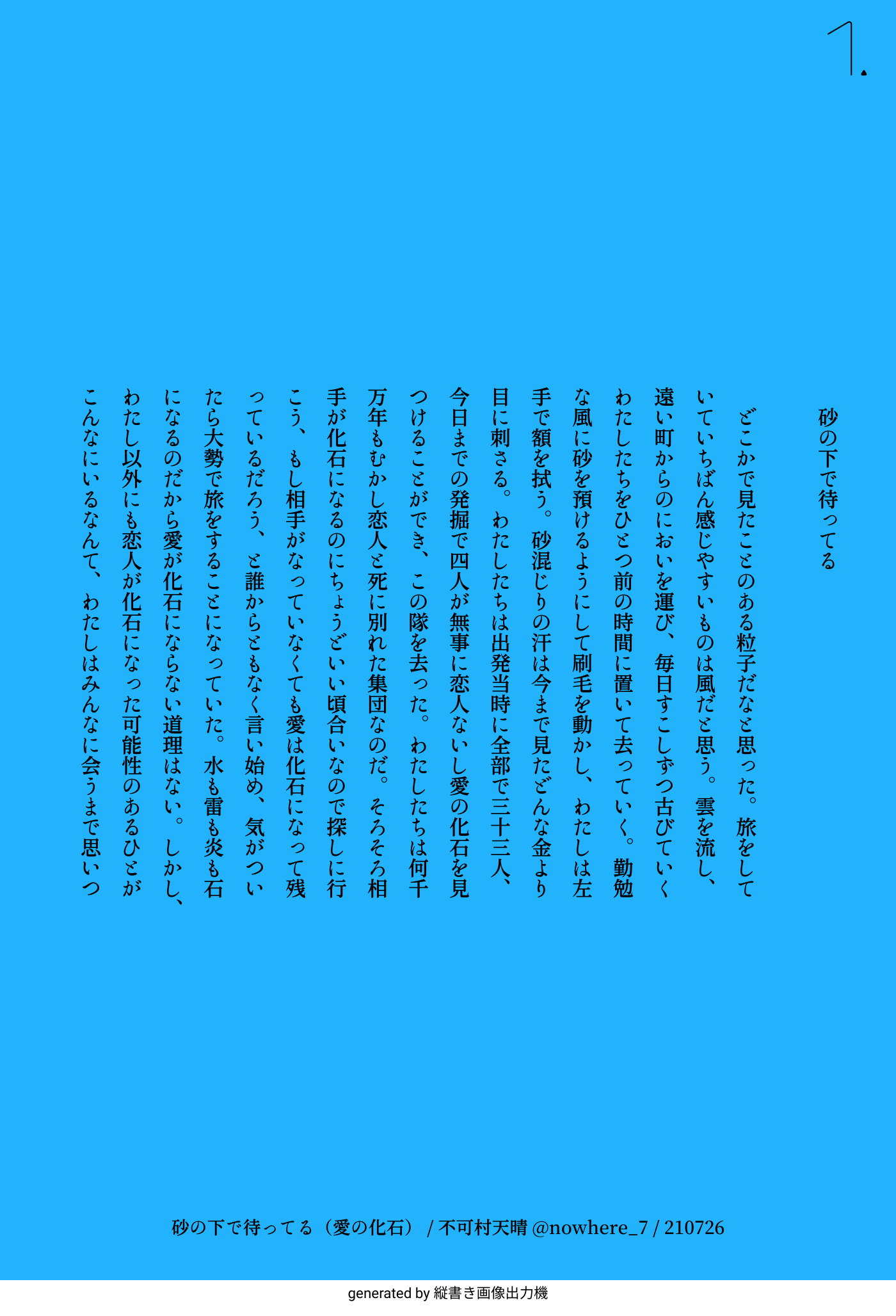
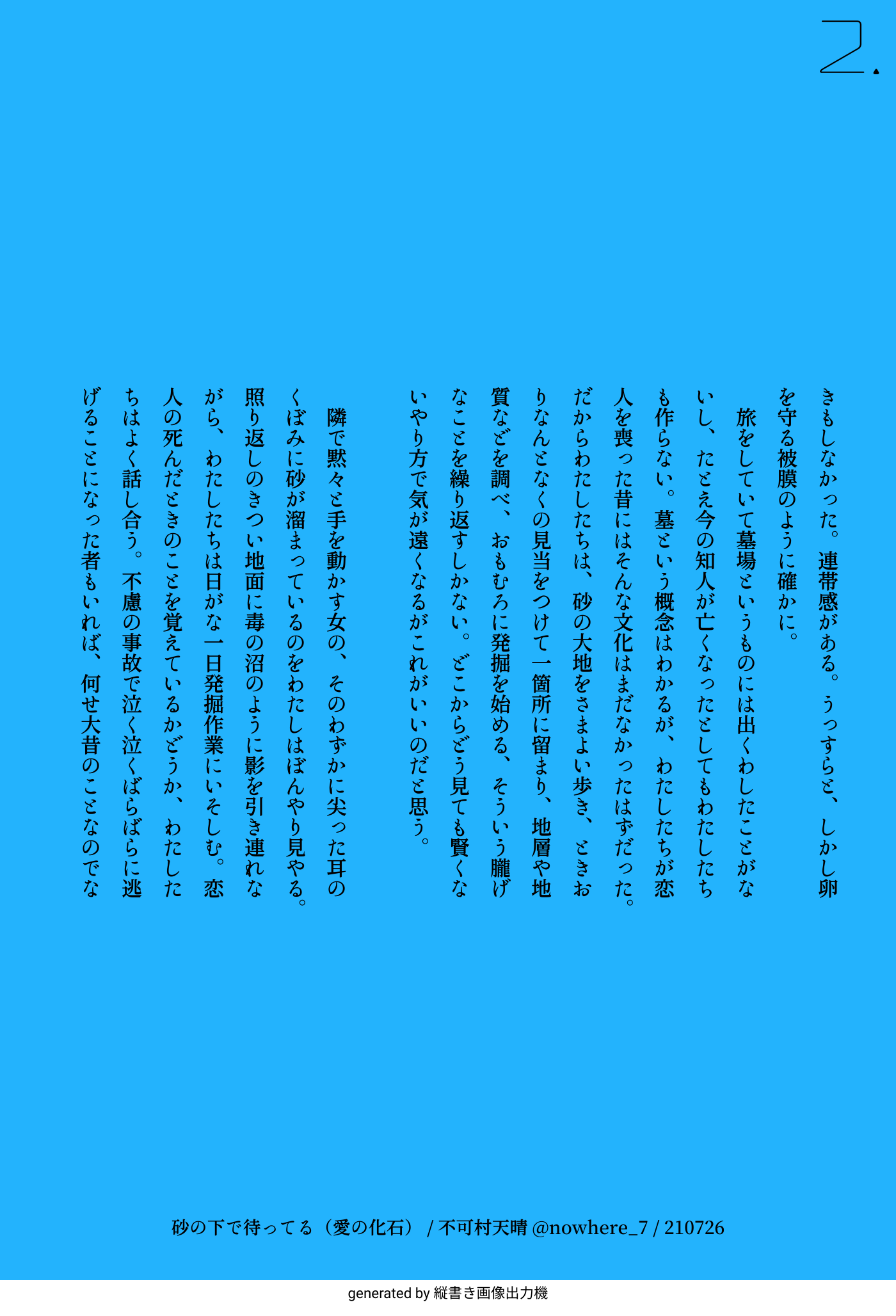
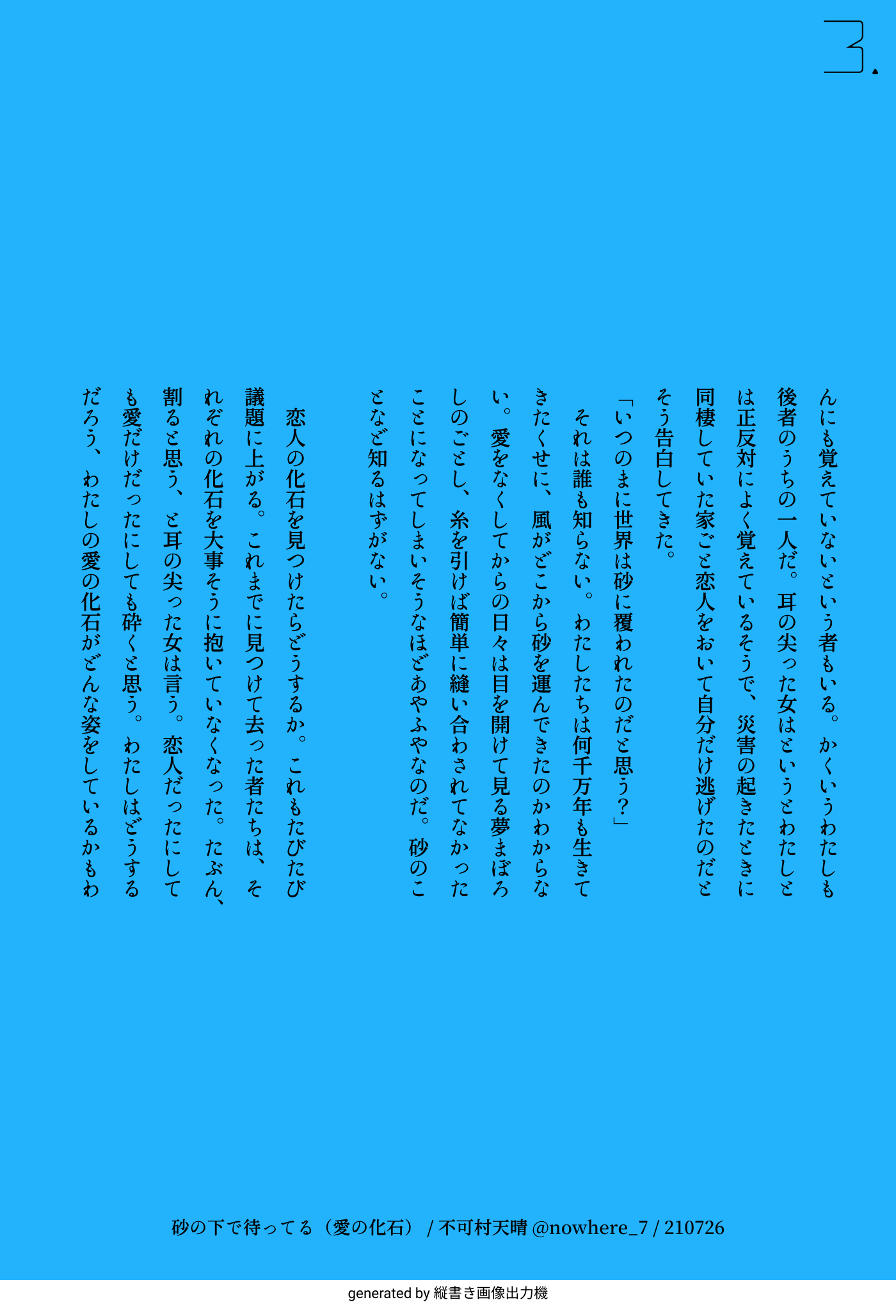
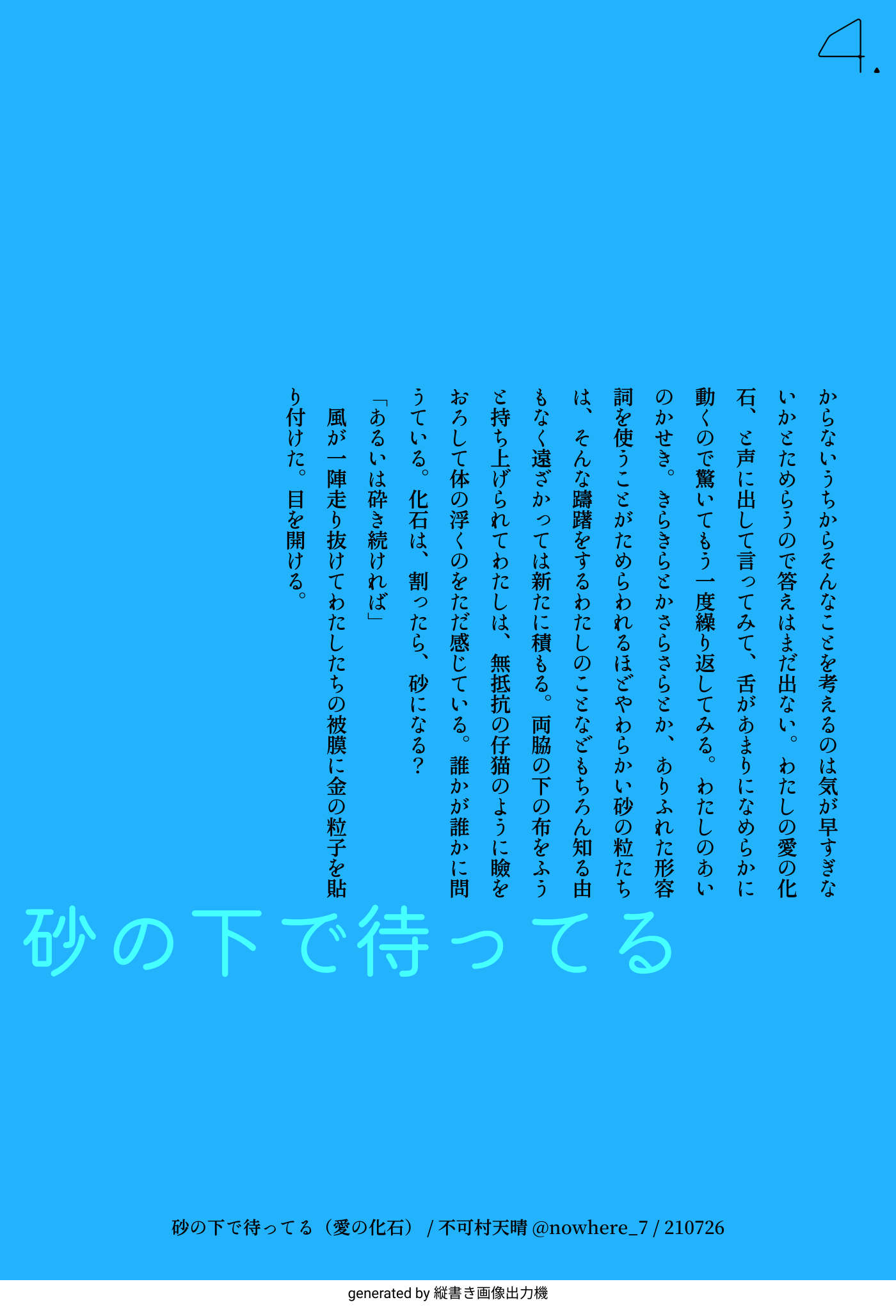
どこかで見たことのある粒子だなと思った。旅をしていていちばん感じやすいものは風だと思う。雲を流し、遠い町からのにおいを運び、毎日すこしずつ古びていくわたしたちをひとつ前の時間に置いて去っていく。勤勉な風に砂を預けるようにして刷毛を動かし、わたしは左手で額を拭う。砂混じりの汗は今まで見たどんな金より目に刺さる。わたしたちは出発当時に全部で三十三人、今日までの発掘で四人が無事に恋人ないし愛の化石を見つけることができ、この隊を去った。わたしたちは何千万年もむかし恋人と死に別れた集団なのだ。そろそろ相手が化石になるのにちょうどいい頃合いなので探しに行こう、もし相手がなっていなくても愛は化石になって残っているだろう、と誰からともなく言い始め、気がついたら大勢で旅をすることになっていた。水も雷も炎も石になるのだから愛が化石にならない道理はない。しかし、わたし以外にも恋人が化石になった可能性のあるひとがこんなにいるなんて、わたしはみんなに会うまで思いつきもしなかった。連帯感がある。うっすらと、しかし卵を守る被膜のように確かに。
旅をしていて墓場というものには出くわしたことがないし、たとえ今の知人が亡くなったとしてもわたしたちも作らない。墓という概念はわかるが、わたしたちが恋人を喪った昔にはそんな文化はまだなかったはずだった。だからわたしたちは、砂の大地をさまよい歩き、ときおりなんとなくの見当をつけて一箇所に留まり、地層や地質などを調べ、おもむろに発掘を始める、そういう朧げなことを繰り返すしかない。どこからどう見ても賢くないやり方で気が遠くなるがこれがいいのだと思う。
隣で黙々と手を動かす女の、そのわずかに尖った耳のくぼみに砂が溜まっているのをわたしはぼんやり見やる。照り返しのきつい地面に毒の沼のように影を引き連れながら、わたしたちは日がな一日発掘作業にいそしむ。恋人の死んだときのことを覚えているかどうか、わたしたちはよく話し合う。不慮の事故で泣く泣くばらばらに逃げることになった者もいれば、何せ大昔のことなのでなんにも覚えていないという者もいる。かくいうわたしも後者のうちの一人だ。耳の尖った女はというとわたしとは正反対によく覚えているそうで、災害の起きたときに同棲していた家ごと恋人をおいて自分だけ逃げたのだとそう告白してきた。
「いつのまに世界は砂に覆われたのだと思う?」
それは誰も知らない。わたしたちは何千万年も生きてきたくせに、風がどこから砂を運んできたのかわからない。愛をなくしてからの日々は目を開けて見る夢まぼろしのごとし、糸を引けば簡単に縫い合わされてなかったことになってしまいそうなほどあやふやなのだ。砂のことなど知るはずがない。
恋人の化石を見つけたらどうするか。これもたびたび議題に上がる。これまでに見つけて去った者たちは、それぞれの化石を大事そうに抱いていなくなった。たぶん、割ると思う、と耳の尖った女は言う。恋人だったにしても愛だけだったにしても砕くと思う。わたしはどうするだろう、わたしの愛の化石がどんな姿をしているかもわからないうちからそんなことを考えるのは気が早すぎないかとためらうので答えはまだ出ない。わたしの愛の化石、と声に出して言ってみて、舌があまりになめらかに動くので驚いてもう一度繰り返してみる。わたしのあいのかせき。きらきらとかさらさらとか、ありふれた形容詞を使うことがためらわれるほどやわらかい砂の粒たちは、そんな躊躇をするわたしのことなどもちろん知る由もなく遠ざかっては新たに積もる。両脇の下の布をふうと持ち上げられてわたしは、無抵抗の仔猫のように瞼をおろして体の浮くのをただ感じている。誰かが誰かに問うている。化石は、割ったら、砂になる?
「あるいは砕き続ければ」
風が一陣走り抜けてわたしたちの被膜に金の粒子を貼り付けた。目を開ける。
砂の下で待ってる(愛の化石) 210726