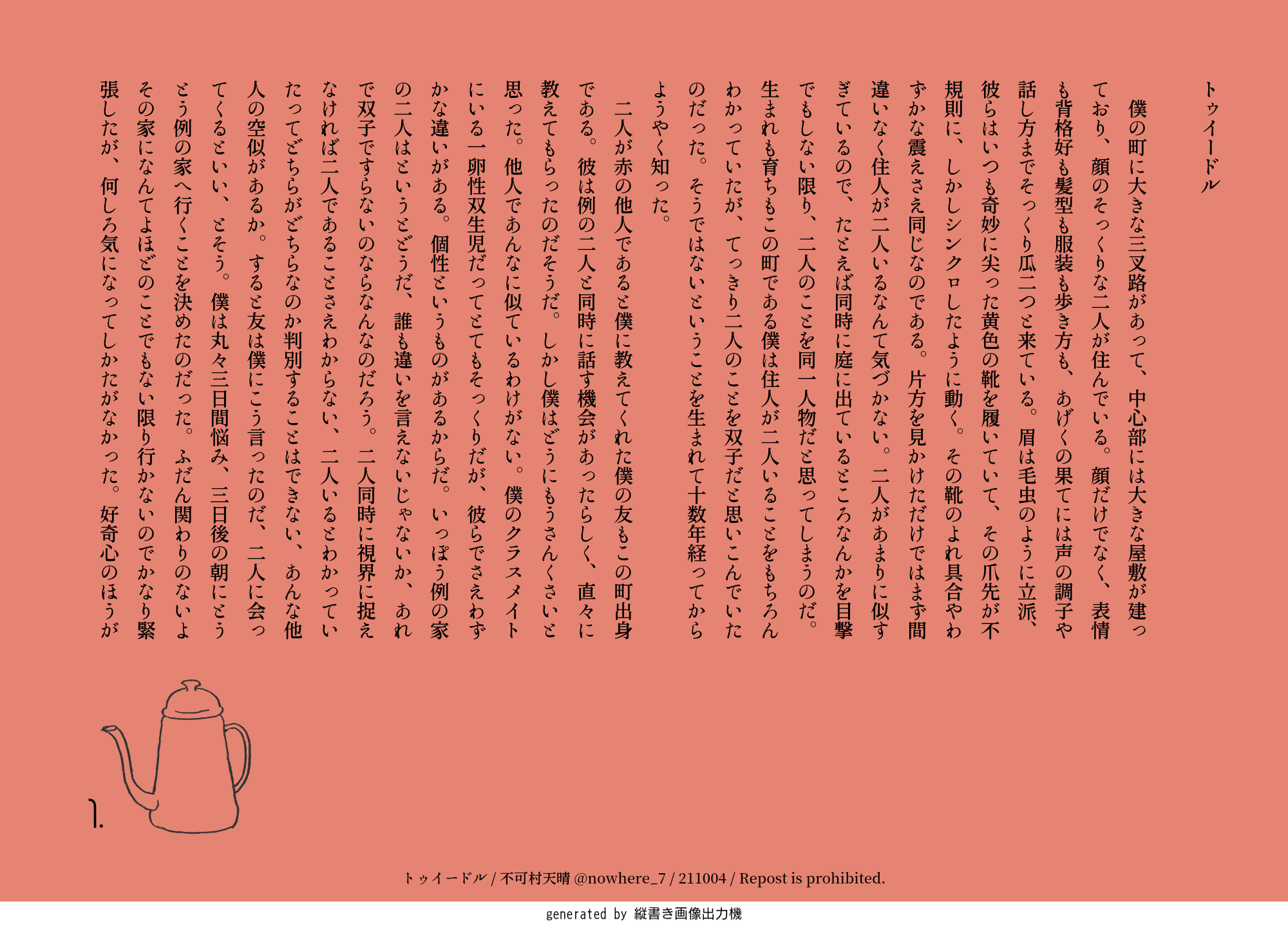
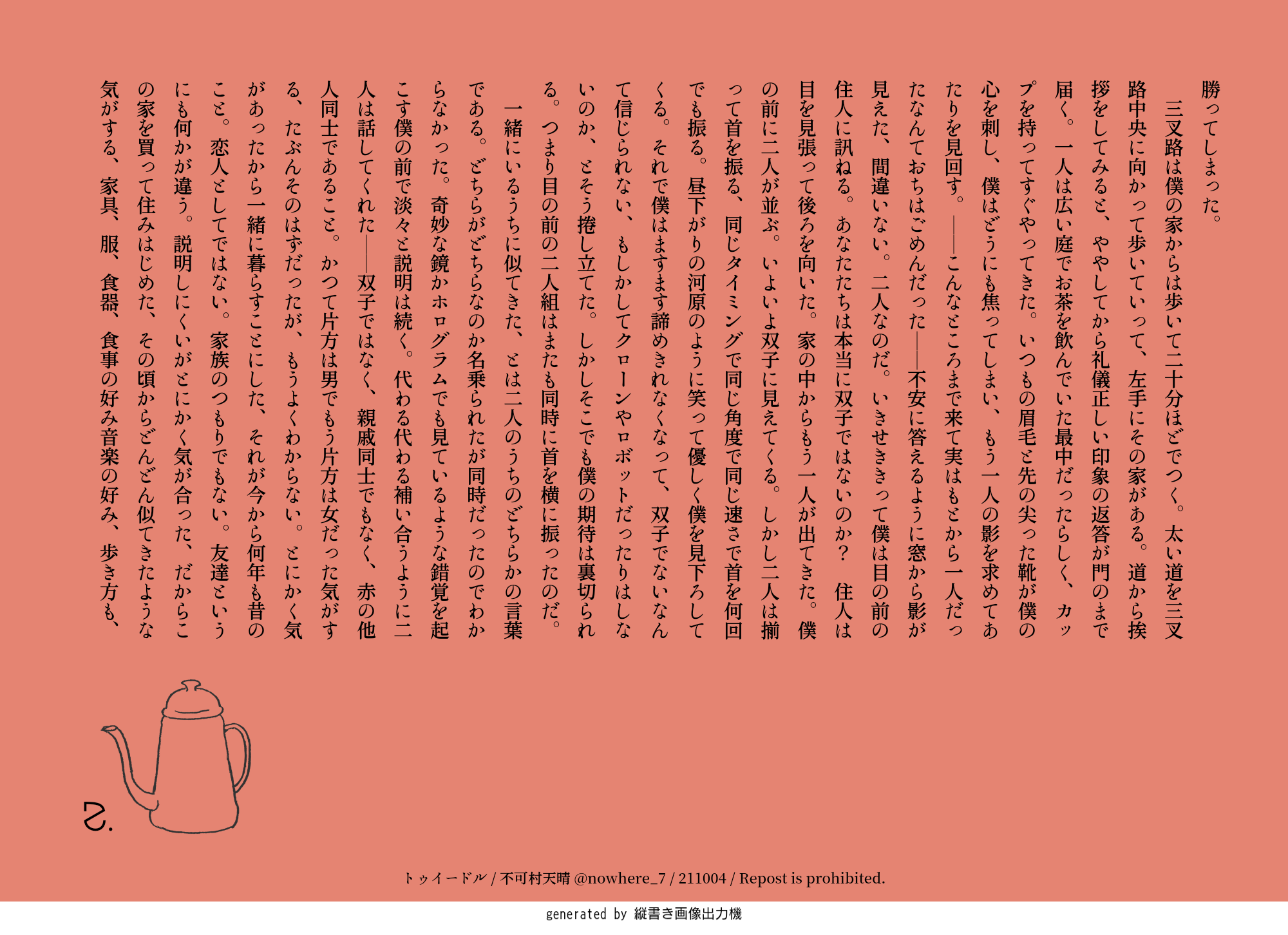
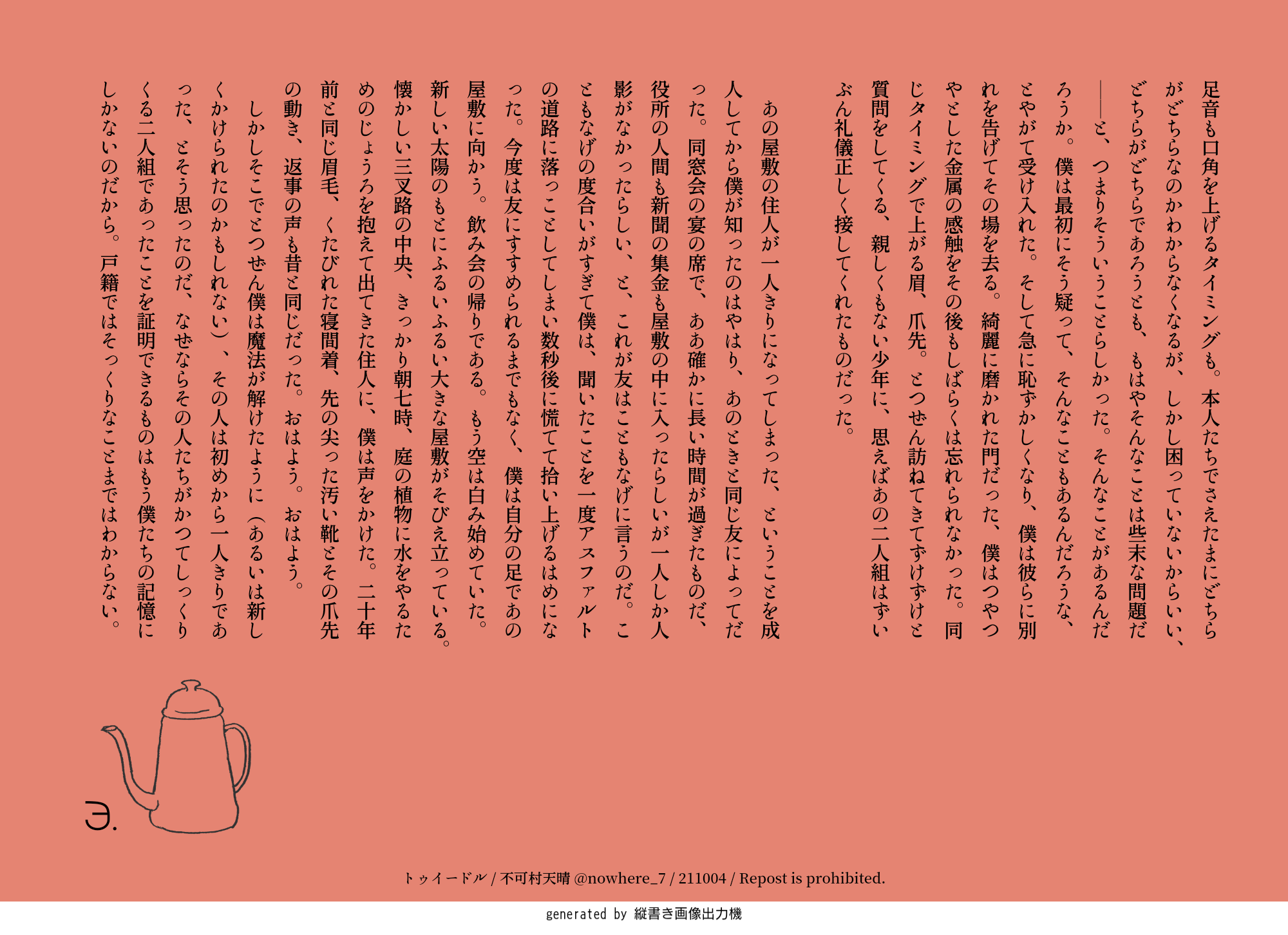

僕の町に大きな三叉路があって、中心部には大きな屋敷が建っており、顔のそっくりな二人が住んでいる。顔だけでなく、表情も背格好も髪型も服装も歩き方も、あげくの果てには声の調子や話し方までそっくり瓜二つと来ている。眉は毛虫のように立派、彼らはいつも奇妙に尖った黄色の靴を履いていて、その爪先が不規則に、しかしシンクロしたように動く。その靴のよれ具合やわずかな震えさえ同じなのである。片方を見かけただけではまず間違いなく住人が二人いるなんて気づかない。二人があまりに似すぎているので、たとえば同時に庭に出ているところなんかを目撃でもしない限り、二人のことを同一人物だと思ってしまうのだ。生まれも育ちもこの町である僕は住人が二人いることをもちろんわかっていたが、てっきり二人のことを双子だと思いこんでいたのだった。そうではないということを生まれて十数年経ってからようやく知った。
二人が赤の他人であると僕に教えてくれた僕の友もこの町出身である。彼は例の二人と同時に話す機会があったらしく、直々に教えてもらったのだそうだ。しかし僕はどうにもうさんくさいと思った。他人であんなに似ているわけがない。僕のクラスメイトにいる一卵性双生児だってとてもそっくりだが、彼らでさえわずかな違いがある。個性というものがあるからだ。いっぽう例の家の二人はというとどうだ、誰も違いを言えないじゃないか、あれで双子ですらないのならなんなのだろう。二人同時に視界に捉えなければ二人であることさえわからない、二人いるとわかっていたってどちらがどちらなのか判別することはできない、あんな他人の空似があるか。すると友は僕にこう言ったのだ、二人に会ってくるといい、とそう。僕は丸々三日間悩み、三日後の朝にとうとう例の家へ行くことを決めたのだった。ふだん関わりのないよその家になんてよほどのことでもない限り行かないのでかなり緊張したが、何しろ気になってしかたがなかった。好奇心のほうが勝ってしまった。
三叉路は僕の家からは歩いて二十分ほどでつく。太い道を三叉路中央に向かって歩いていって、左手にその家がある。道から挨拶をしてみると、ややしてから礼儀正しい印象の返答が門のまで届く。一人は広い庭でお茶を飲んでいた最中だったらしく、カップを持ってすぐやってきた。いつもの眉毛と先の尖った靴が僕の心を刺し、僕はどうにも焦ってしまい、もう一人の影を求めてあたりを見回す。――こんなところまで来て実はもとから一人だったなんておちはごめんだった――不安に答えるように窓から影が見えた、間違いない。二人なのだ。いきせききって僕は目の前の住人に訊ねる。あなたたちは本当に双子ではないのか? 住人は目を見張って後ろを向いた。家の中からもう一人が出てきた。僕の前に二人が並ぶ。いよいよ双子に見えてくる。しかし二人は揃って首を振る、同じタイミングで同じ角度で同じ速さで首を何回でも振る。昼下がりの河原のように笑って優しく僕を見下ろしてくる。それで僕はますます諦めきれなくなって、双子でないなんて信じられない、もしかしてクローンやロボットだったりはしないのか、とそう捲し立てた。しかしそこでも僕の期待は裏切られる。つまり目の前の二人組はまたも同時に首を横に振ったのだ。
一緒にいるうちに似てきた、とは二人のうちのどちらかの言葉である。どちらがどちらなのか名乗られたが同時だったのでわからなかった。奇妙な鏡かホログラムでも見ているような錯覚を起こす僕の前で淡々と説明は続く。代わる代わる補い合うように二人は話してくれた――双子ではなく、親戚同士でもなく、赤の他人同士であること。かつて片方は男でもう片方は女だった気がする、たぶんそのはずだったが、もうよくわからない。とにかく気があったから一緒に暮らすことにした、それが今から何年も昔のこと。恋人としてではない。家族のつもりでもない。友達というにも何かが違う。説明しにくいがとにかく気が合った、だからこの家を買って住みはじめた、その頃からどんどん似てきたような気がする、家具、服、食器、食事の好み音楽の好み、歩き方も、足音も口角を上げるタイミングも。本人たちでさえたまにどちらがどちらなのかわからなくなるが、しかし困っていないからいい、どちらがどちらであろうとも、もはやそんなことは些末な問題だ――と、つまりそういうことらしかった。そんなことがあるんだろうか。僕は最初にそう疑って、そんなこともあるんだろうな、とやがて受け入れた。そして急に恥ずかしくなり、僕は彼らに別れを告げてその場を去る。綺麗に磨かれた門だった、僕はつやつやとした金属の感触をその後もしばらくは忘れられなかった。同じタイミングで上がる眉、爪先。とつぜん訪ねてきてずけずけと質問をしてくる、親しくもない少年に、思えばあの二人組はずいぶん礼儀正しく接してくれたものだった。
あの屋敷の住人が一人きりになってしまった、ということを成人してから僕が知ったのはやはり、あのときと同じ友によってだった。同窓会の宴の席で、ああ確かに長い時間が過ぎたものだ、役所の人間も新聞の集金も屋敷の中に入ったらしいが一人しか人影がなかったらしい、と、これが友はこともなげに言うのだ。こともなげの度合いがすぎて僕は、聞いたことを一度アスファルトの道路に落っことしてしまい数秒後に慌てて拾い上げるはめになった。今度は友にすすめられるまでもなく、僕は自分の足であの屋敷に向かう。飲み会の帰りである。もう空は白み始めていた。新しい太陽のもとにふるいふるい大きな屋敷がそびえ立っている。懐かしい三叉路の中央、きっかり朝七時、庭の植物に水をやるためのじょうろを抱えて出てきた住人に、僕は声をかけた。二十年前と同じ眉毛、くたびれた寝間着、先の尖った汚い靴とその爪先の動き、返事の声も昔と同じだった。おはよう。おはよう。
しかしそこでとつぜん僕は魔法が解けたように(あるいは新しくかけられたのかもしれない)、その人は初めから一人きりであった、とそう思ったのだ、なぜならその人たちがかつてしっくりくる二人組であったことを証明できるものはもう僕たちの記憶にしかないのだから。戸籍ではそっくりなことまではわからない。そして片方が消えてしまったのなら「そっくりな二人」を維持することはできない。残された者はただの一人になる。それを思ったまま残された一人に告げてしまうと、相手は朝日のように、うすくほほえんだまま軽く俯いた。薄い茶色の瞳は一度も僕を向かなかった。相手の眉の中にいくつか白いものがまじっているのに僕は気づく。よくよく見れば、毛虫のような眉は、二十年前とまったく同じではなかった。しばらくのあいだ無言で向き合っていたが、そのうち、僕はそっと門から手を離す。錆びが指の表面に移る。僕の背後をバイクに乗った誰かが通りすぎる、その振動が前髪まで伝わった。さようなら。そう言うと、向こうも返事をくれた。さようなら。ここは三叉路の中央、町でも評判の大きな屋敷、広い庭は昔よりも荒廃しており、壁にも好き勝手に蔦が這っている。ここにはそっくりな二人組だったはずの片割れのどちらか一人が住んでいる。どちらなのかわからないが、どちらか一人、残されたひとりが。
トゥイードル / 不可村天晴 @nowhere_7 / 211004 / Repost is prohibited.
20年11月に書いていたもの