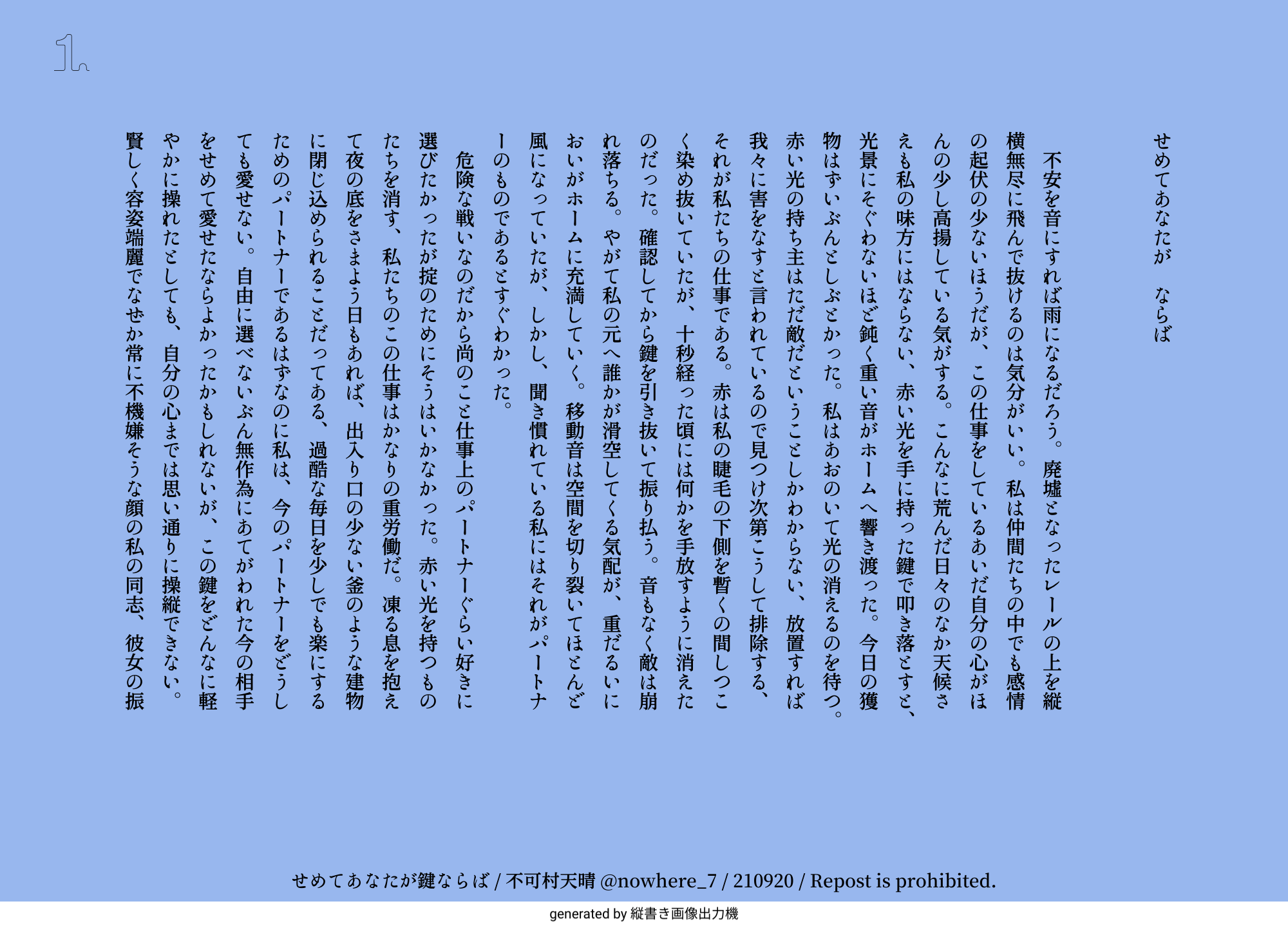
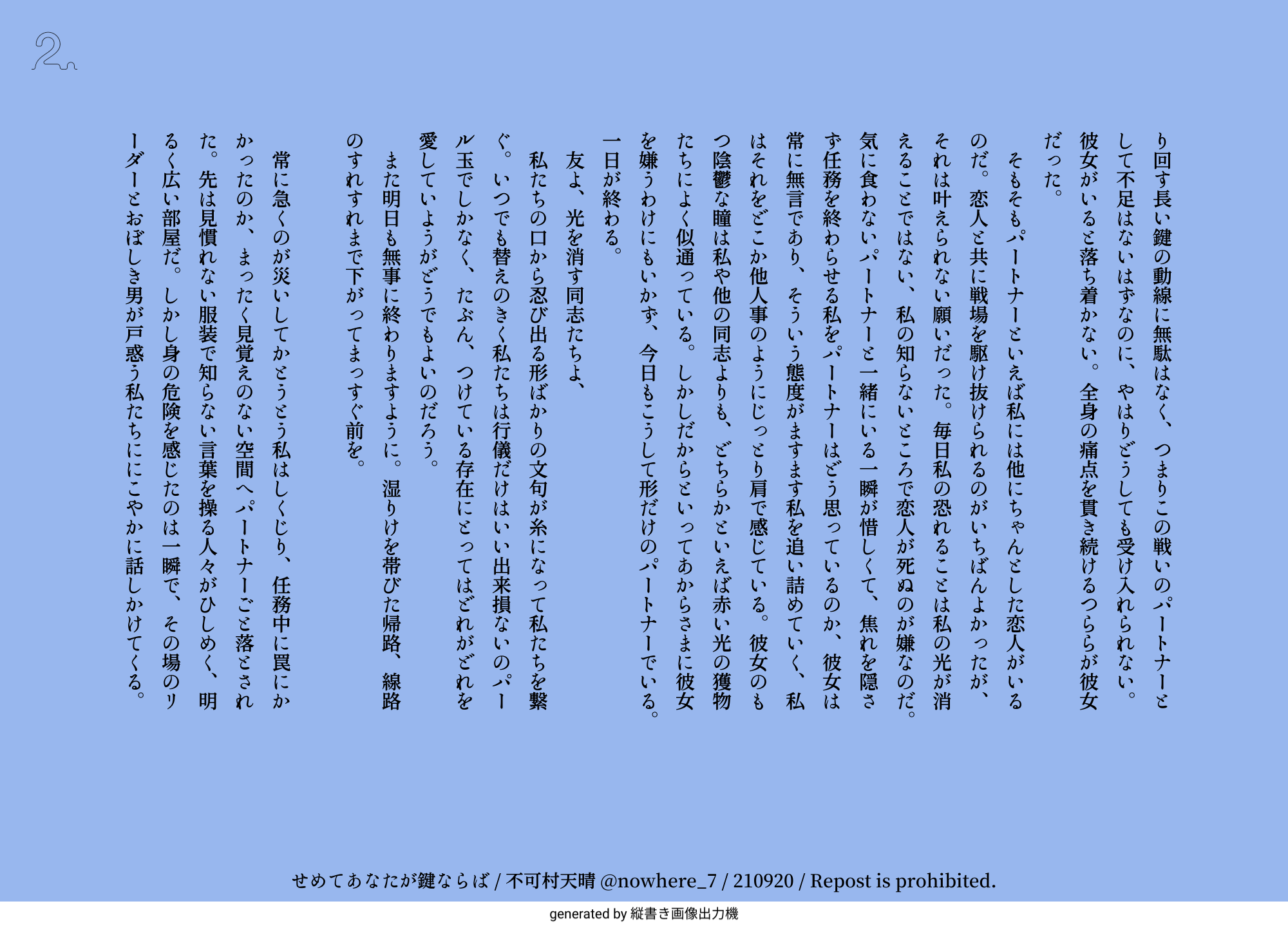
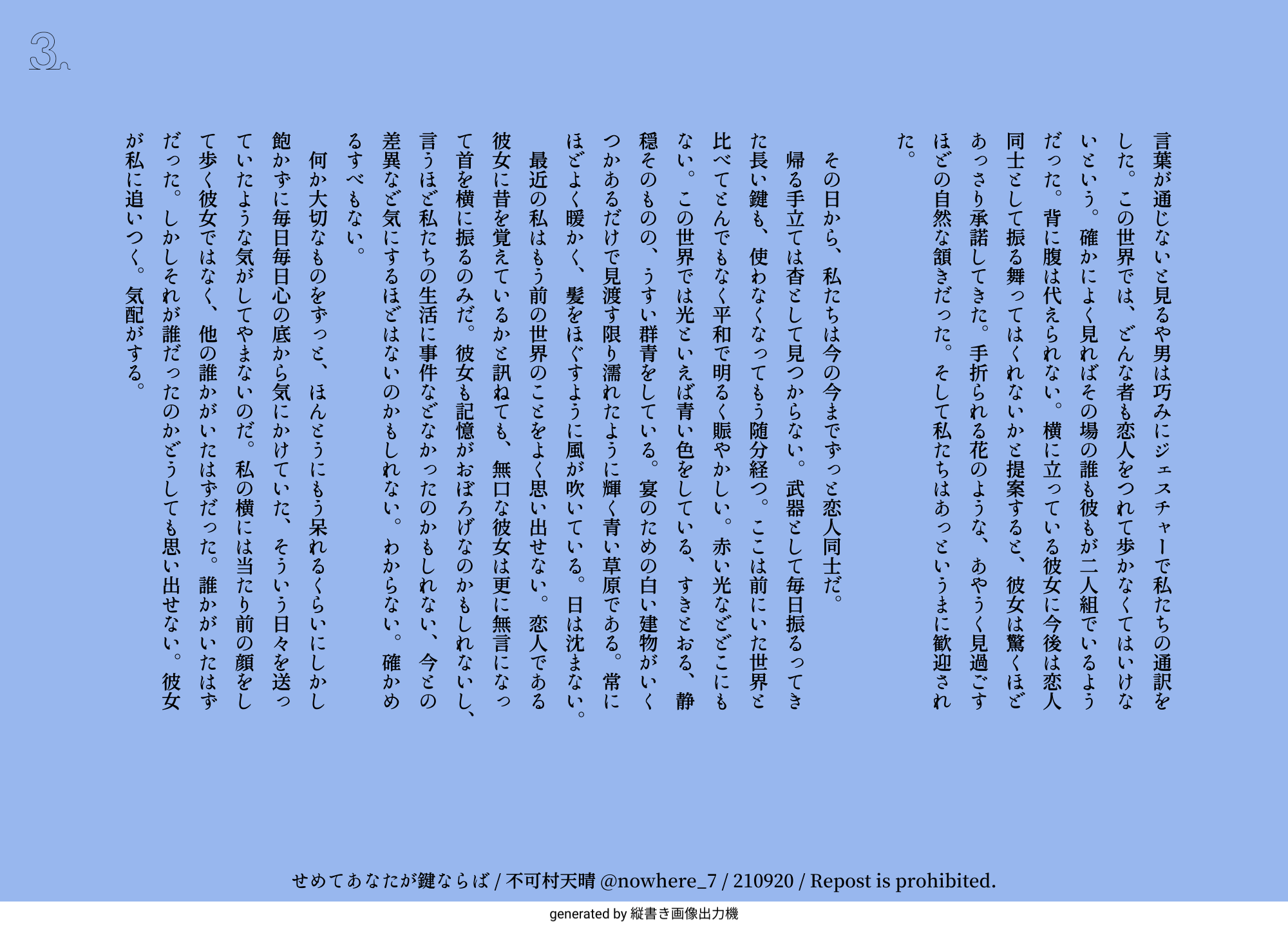
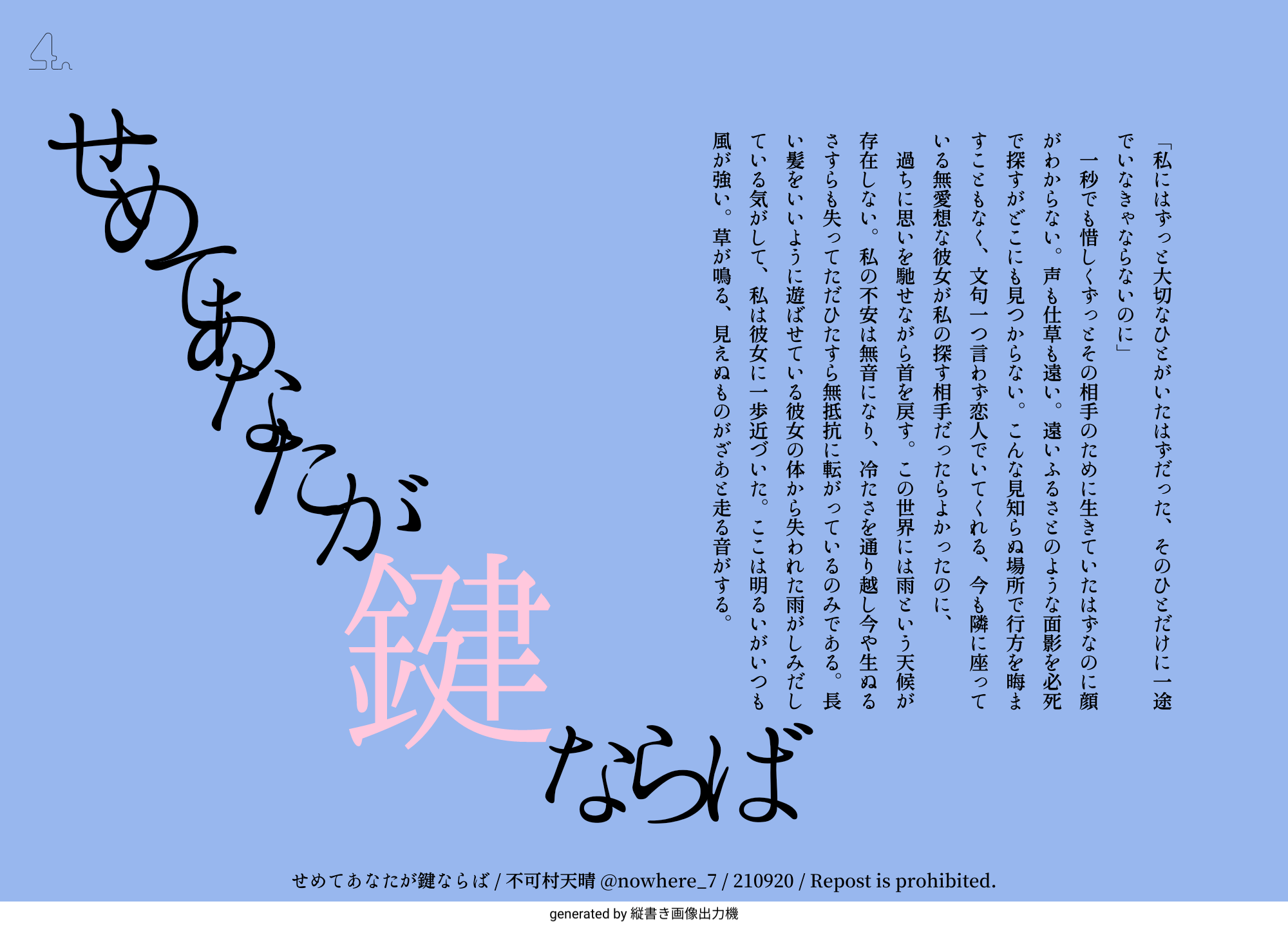
不安を音にすれば雨になるだろう。廃墟となったレールの上を縦横無尽に飛んで抜けるのは気分がいい。私は仲間たちの中でも感情の起伏の少ないほうだが、この仕事をしているあいだ自分の心がほんの少し高揚している気がする。こんなに荒んだ日々のなか天候さえも私の味方にはならない、赤い光を手に持った鍵で叩き落とすと、光景にそぐわないほど鈍く重い音がホームへ響き渡った。今日の獲物はずいぶんとしぶとかった。私はあおのいて光の消えるのを待つ。赤い光の持ち主はただ敵だということしかわからない、放置すれば我々に害をなすと言われているので見つけ次第こうして排除する、それが私たちの仕事である。赤は私の睫毛の下側を暫くの間しつこく染め抜いていたが、十秒経った頃には何かを手放すように消えたのだった。確認してから鍵を引き抜いて振り払う。音もなく敵は崩れ落ちる。やがて私の元へ誰かが滑空してくる気配が、重だるいにおいがホームに充満していく。移動音は空間を切り裂いてほとんど風になっていたが、しかし、聞き慣れている私にはそれがパートナーのものであるとすぐわかった。
危険な戦いなのだから尚のこと仕事上のパートナーぐらい好きに選びたかったが掟のためにそうはいかなかった。赤い光を持つものたちを消す、私たちのこの仕事はかなりの重労働だ。凍る息を抱えて夜の底をさまよう日もあれば、出入り口の少ない釜のような建物に閉じ込められることだってある、過酷な毎日を少しでも楽にするためのパートナーであるはずなのに私は、今のパートナーをどうしても愛せない。自由に選べないぶん無作為にあてがわれた今の相手をせめて愛せたならよかったかもしれないが、この鍵をどんなに軽やかに操れたとしても、自分の心までは思い通りに操縦できない。賢しく容姿端麗でなぜか常に不機嫌そうな顔の私の同志、彼女の振り回す長い鍵の動線に無駄はなく、つまりこの戦いのパートナーとして不足はないはずなのに、やはりどうしても受け入れられない。彼女がいると落ち着かない。全身の痛点を貫き続けるつららが彼女だった。
そもそもパートナーといえば私には他にちゃんとした恋人がいるのだ。恋人と共に戦場を駆け抜けられるのがいちばんよかったが、それは叶えられない願いだった。毎日私の恐れることは私の光が消えることではない、私の知らないところで恋人が死ぬのが嫌なのだ。気に食わないパートナーと一緒にいる一瞬が惜しくて、焦れを隠さず任務を終わらせる私をパートナーはどう思っているのか、彼女は常に無言であり、そういう態度がますます私を追い詰めていく、私はそれをどこか他人事のようにじっとり肩で感じている。彼女のもつ陰鬱な瞳は私や他の同志よりも、どちらかといえば赤い光の獲物たちによく似通っている。しかしだからといってあからさまに彼女を嫌うわけにもいかず、今日もこうして形だけのパートナーでいる。一日が終わる。
友よ、光を消す同志たちよ、
私たちの口から忍び出る形ばかりの文句が糸になって私たちを繋ぐ。いつでも替えのきく私たちは行儀だけはいい出来損ないのパール玉でしかなく、たぶん、つけている存在にとってはどれがどれを愛していようがどうでもよいのだろう。
また明日も無事に終わりますように。湿りけを帯びた帰路、線路のすれすれまで下がってまっすぐ前を。
常に急くのが災いしてかとうとう私はしくじり、任務中に罠にかかったのか、まったく見覚えのない空間へパートナーごと落とされた。先は見慣れない服装で知らない言葉を操る人々がひしめく、明るく広い部屋だ。しかし身の危険を感じたのは一瞬で、その場のリーダーとおぼしき男が戸惑う私たちににこやかに話しかけてくる。言葉が通じないと見るや男は巧みにジェスチャーで私たちの通訳をした。この世界では、どんな者も恋人をつれて歩かなくてはいけないという。確かによく見ればその場の誰も彼もが二人組でいるようだった。背に腹は代えられない。横に立っている彼女に今後は恋人同士として振る舞ってはくれないかと提案すると、彼女は驚くほどあっさり承諾してきた。手折られる花のような、あやうく見過ごすほどの自然な頷きだった。そして私たちはあっというまに歓迎された。
その日から、私たちは今の今までずっと恋人同士だ。
帰る手立ては杳として見つからない。武器として毎日振るってきた長い鍵も、使わなくなってもう随分経つ。ここは前にいた世界と比べてとんでもなく平和で明るく賑やかしい。赤い光などどこにもない。この世界では光といえば青い色をしている、すきとおる、静穏そのものの、うすい群青をしている。宴のための白い建物がいくつかあるだけで見渡す限り濡れたように輝く青い草原である。常にほどよく暖かく、髪をほぐすように風が吹いている。日は沈まない。
最近の私はもう前の世界のことをよく思い出せない。恋人である彼女に昔を覚えているかと訊ねても、無口な彼女は更に無言になって首を横に振るのみだ。彼女も記憶がおぼろげなのかもしれないし、言うほど私たちの生活に事件などなかったのかもしれない、今との差異など気にするほどはないのかもしれない。わからない。確かめるすべもない。
何か大切なものをずっと、ほんとうにもう呆れるくらいにしかし飽かずに毎日毎日心の底から気にかけていた、そういう日々を送っていたような気がしてやまないのだ。私の横には当たり前の顔をして歩く彼女ではなく、他の誰かがいたはずだった。誰かがいたはずだった。しかしそれが誰だったのかどうしても思い出せない。彼女が私に追いつく。気配がする。
「私にはずっと大切なひとがいたはずだった、そのひとだけに一途でいなきゃならないのに」
一秒でも惜しくずっとその相手のために生きていたはずなのに顔がわからない。声も仕草も遠い。遠いふるさとのような面影を必死で探すがどこにも見つからない。こんな見知らぬ場所で行方を晦ますこともなく、文句一つ言わず恋人でいてくれる、今も隣に座っている無愛想な彼女が私の探す相手だったらよかったのに、
過ちに思いを馳せながら首を戻す。この世界には雨という天候が存在しない。私の不安は無音になり、冷たさを通り越し今や生ぬるさすらも失ってただひたすら無抵抗に転がっているのみである。長い髪をいいように遊ばせている彼女の体から失われた雨がしみだしている気がして、私は彼女に一歩近づいた。ここは明るいがいつも風が強い。草が鳴る、見えぬものがざあと走る音がする。
せめてあなたが鍵ならば / 不可村天晴 @nowhere_7 / 210920(190620) / Repost is prohibited.