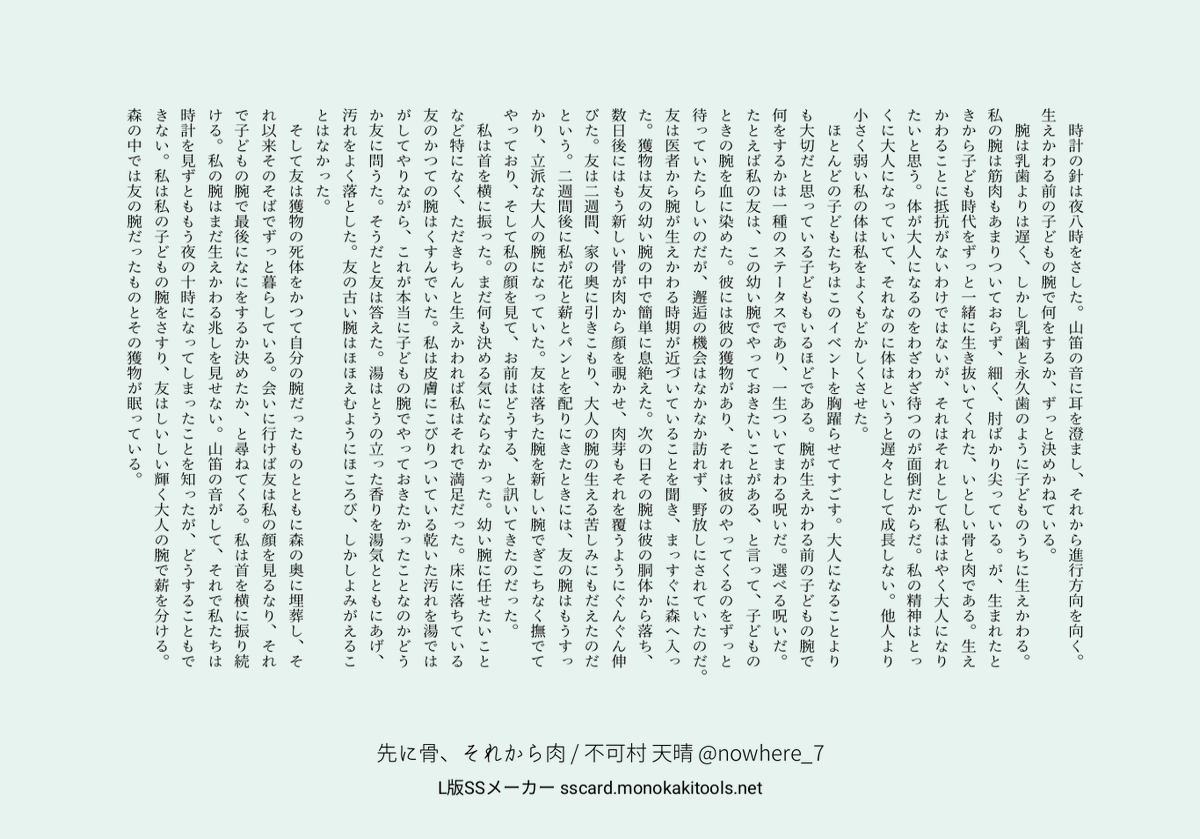
時計の針は夜八時をさした。山笛の音に耳を澄まし、それから進行方向を向く。生えかわる前の子どもの腕で何をするか、ずっと決めかねている。
腕は乳歯よりは遅く、しかし乳歯と永久歯のように子どものうちに生えかわる。私の腕は筋肉もあまりついておらず、細く、肘ばかり尖っている。が、生まれたときから子ども時代をずっと一緒に生き抜いてくれた、いとしい骨と肉である。生えかわることに抵抗がないわけではないが、それはそれとして私ははやく大人になりたいと思う。体が大人になるのをわざわざ待つのが面倒だからだ。私の精神はとっくに大人になっていて、それなのに体はというと遅々として成長しない。他人より小さく弱い私の体は私をよくもどかしくさせた。
ほとんどの子どもたちはこのイベントを胸躍らせてすごす。大人になることよりも大切だと思っている子どももいるほどである。腕が生えかわる前の子どもの腕で何をするかは一種のステータスであり、一生ついてまわる呪いだ。選べる呪いだ。たとえば私の友は、この幼い腕でやっておきたいことがある、と言って、子どものときの腕を血に染めた。彼には彼の獲物があり、それは彼のやってくるのをずっと待っていたらしいのだが、邂逅の機会はなかなか訪れず、野放しにされていたのだ。友は医者から腕が生えかわる時期が近づいていることを聞き、まっすぐに森へ入った。獲物は友の幼い腕の中で簡単に息絶えた。次の日その腕は彼の胴体から落ち、数日後にはもう新しい骨が肉から顔を覗かせ、肉芽もそれを覆うようにぐんぐん伸びた。友は二週間、家の奥に引きこもり、大人の腕の生える苦しみにもだえたのだという。二週間後に私が花と薪とパンとを配りにきたときには、友の腕はもうすっかり、立派な大人の腕になっていた。友は落ちた腕を新しい腕でぎこちなく撫でてやっており、そして私の顔を見て、お前はどうする、と訊いてきたのだった。
私は首を横に振った。まだ何も決める気にならなかった。幼い腕に任せたいことなど特になく、ただきちんと生えかわれば私はそれで満足だった。床に落ちている友のかつての腕はくすんでいた。私は皮膚にこびりついている乾いた汚れを湯ではがしてやりながら、これが本当に子どもの腕でやっておきたかったことなのかどうか友に問うた。そうだと友は答えた。湯はとうの立った香りを湯気とともにあげ、汚れをよく落とした。友の古い腕はほほえむようにほころび、しかしよみがえることはなかった。
そして友は獲物の死体をかつて自分の腕だったものとともに森の奥に埋葬し、それ以来そのそばでずっと暮らしている。会いに行けば友は私の顔を見るなり、それで子どもの腕で最後になにをするか決めたか、と尋ねてくる。私は首を横に振り続ける。私の腕はまだ生えかわる兆しを見せない。山笛の音がして、それで私たちは時計を見ずとももう夜の十時になってしまったことを知ったが、どうすることもできない。私は私の子どもの腕をさすり、友はしいしい輝く大人の腕で薪を分ける。森の中では友の腕だったものとその獲物が眠っている。
先に骨、それから肉 191125