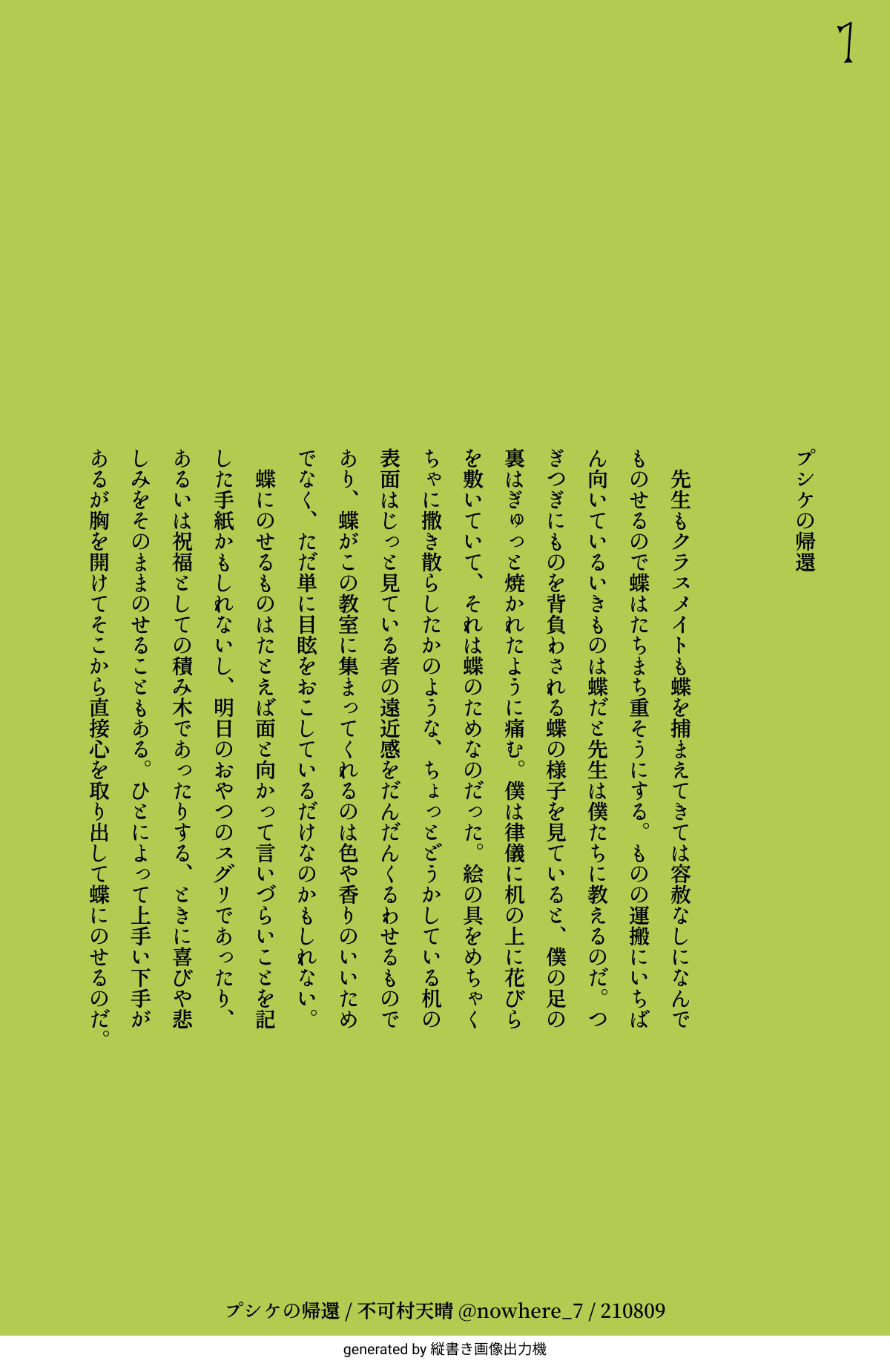
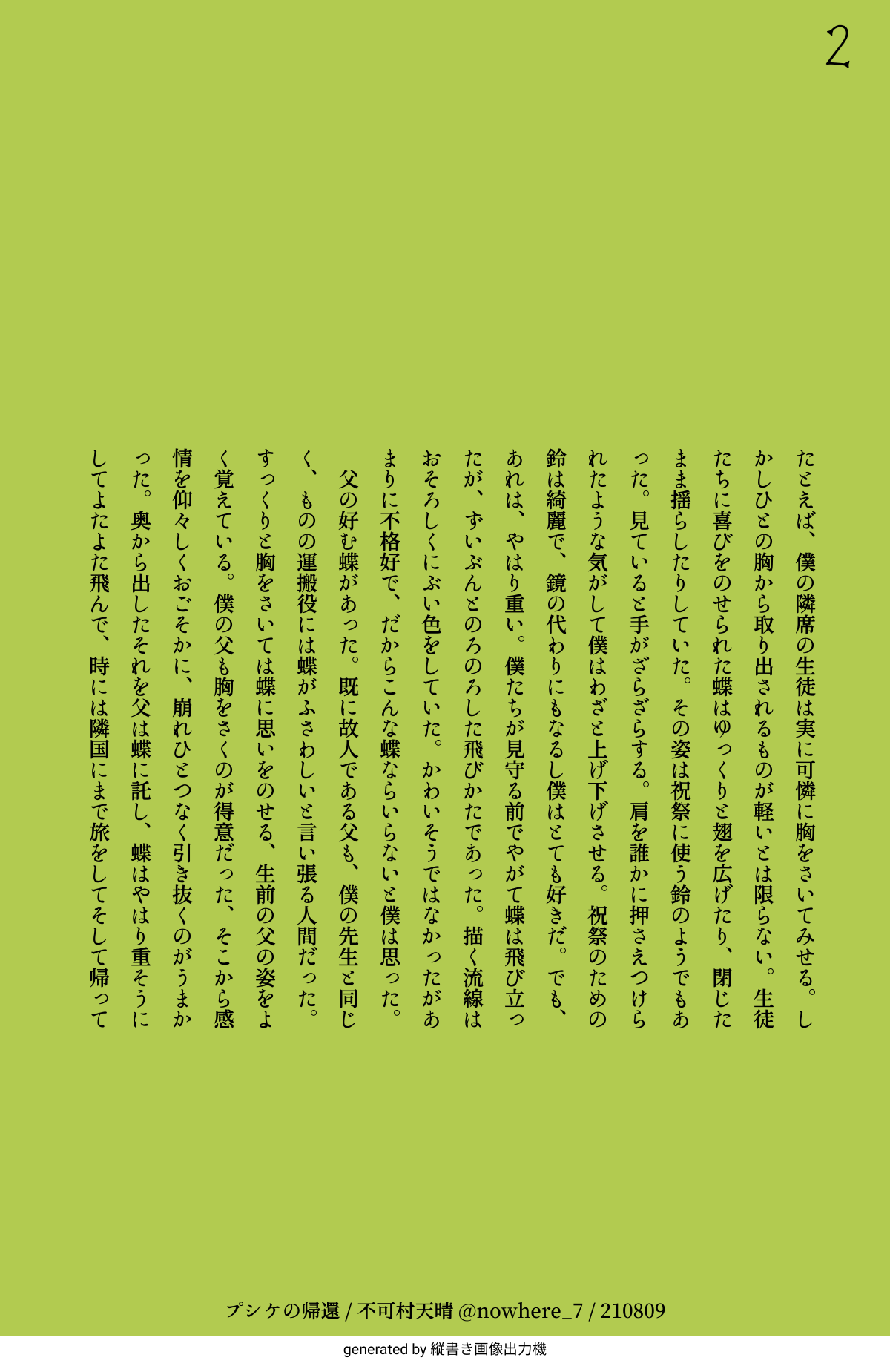
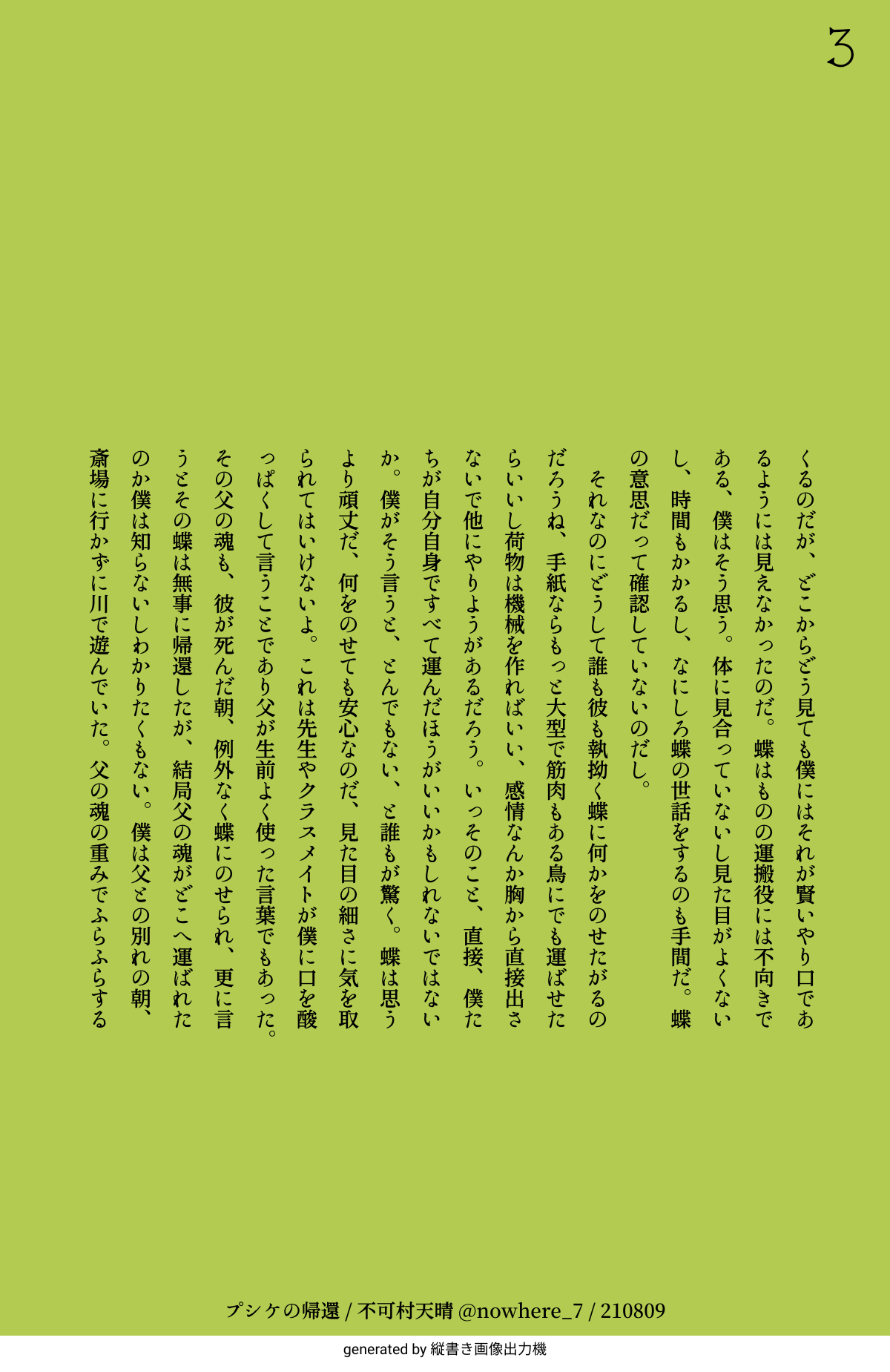

先生もクラスメイトも蝶を捕まえてきては容赦なしになんでものせるので蝶はたちまち重そうにする。ものの運搬にいちばん向いているいきものは蝶だと先生は僕たちに教えるのだ。つぎつぎにものを背負わされる蝶の様子を見ていると、僕の足の裏はぎゅっと焼かれたように痛む。僕は律儀に机の上に花びらを敷いていて、それは蝶のためなのだった。絵の具をめちゃくちゃに撒き散らしたかのような、ちょっとどうかしている机の表面はじっと見ている者の遠近感をだんだんくるわせるものであり、蝶がこの教室に集まってくれるのは色や香りのいいためでなく、ただ単に目眩をおこしているだけなのかもしれない。
蝶にのせるものはたとえば面と向かって言いづらいことを記した手紙かもしれないし、明日のおやつのスグリであったり、あるいは祝福としての積み木であったりする、ときに喜びや悲しみをそのままのせることもある。ひとによって上手い下手があるが胸を開けてそこから直接心を取り出して蝶にのせるのだ。たとえば、僕の隣席の生徒は実に可憐に胸をさいてみせる。しかしひとの胸から取り出されるものが軽いとは限らない。生徒たちに喜びをのせられた蝶はゆっくりと翅を広げたり、閉じたまま揺らしたりしていた。その姿は祝祭に使う鈴のようでもあった。見ていると手がざらざらする。肩を誰かに押さえつけられたような気がして僕はわざと上げ下げさせる。祝祭のための鈴は綺麗で、鏡の代わりにもなるし僕はとても好きだ。でも、あれは、やはり重い。僕たちが見守る前でやがて蝶は飛び立ったが、ずいぶんとのろのろした飛びかたであった。描く流線はおそろしくにぶい色をしていた。かわいそうではなかったがあまりに不格好で、だからこんな蝶ならいらないと僕は思った。
父の好む蝶があった。既に故人である父も、僕の先生と同じく、ものの運搬役には蝶がふさわしいと言い張る人間だった。すっくりと胸をさいては蝶に思いをのせる、生前の父の姿をよく覚えている。僕の父も胸をさくのが得意だった、そこから感情を仰々しくおごそかに、崩れひとつなく引き抜くのがうまかった。奥から出したそれを父は蝶に託し、蝶はやはり重そうにしてよたよた飛んで、時には隣国にまで旅をしてそして帰ってくるのだが、どこからどう見ても僕にはそれが賢いやり口であるようには見えなかったのだ。蝶はものの運搬役には不向きである、僕はそう思う。体に見合っていないし見た目がよくないし、時間もかかるし、なにしろ蝶の世話をするのも手間だ。蝶の意思だって確認していないのだし。
それなのにどうして誰も彼も執拗く蝶に何かをのせたがるのだろうね、手紙ならもっと大型で筋肉もある鳥にでも運ばせたらいいし荷物は機械を作ればいい、感情なんか胸から直接出さないで他にやりようがあるだろう。いっそのこと、直接、僕たちが自分自身ですべて運んだほうがいいかもしれないではないか。僕がそう言うと、とんでもない、と誰もが驚く。蝶は思うより頑丈だ、何をのせても安心なのだ、見た目の細さに気を取られてはいけないよ。これは先生やクラスメイトが僕に口を酸っぱくして言うことであり父が生前よく使った言葉でもあった。その父の魂も、彼が死んだ朝、例外なく蝶にのせられ、更に言うとその蝶は無事に帰還したが、結局父の魂がどこへ運ばれたのか僕は知らないしわかりたくもない。僕は父との別れの朝、斎場に行かずに川で遊んでいた。父の魂の重みでふらふらする蝶なんて見たくなかった。父の愛した蝶などもともと好きではなかった。
先生はどうしても僕にも蝶に何かのせてほしくてたまらないらしい。教室中から僕に視線が集まっているのを感じる。うんと言わなくては居残りでは済まないようだ。しかたなく、すっくり胸を開いて、それを蝶の背中にのせる。すぐに後悔した僕が直してやろうとしても蝶はするりと逃げてしまう。もういい、そのままどこへでも運んでいけばいい、と思ったが、蝶はというとそのあたりをゆっくり歩き回ったあとは、翅を傾けて静止しただけだった。昼下がり、授業の終わりはまだ遠い。
プシケの帰還 210809