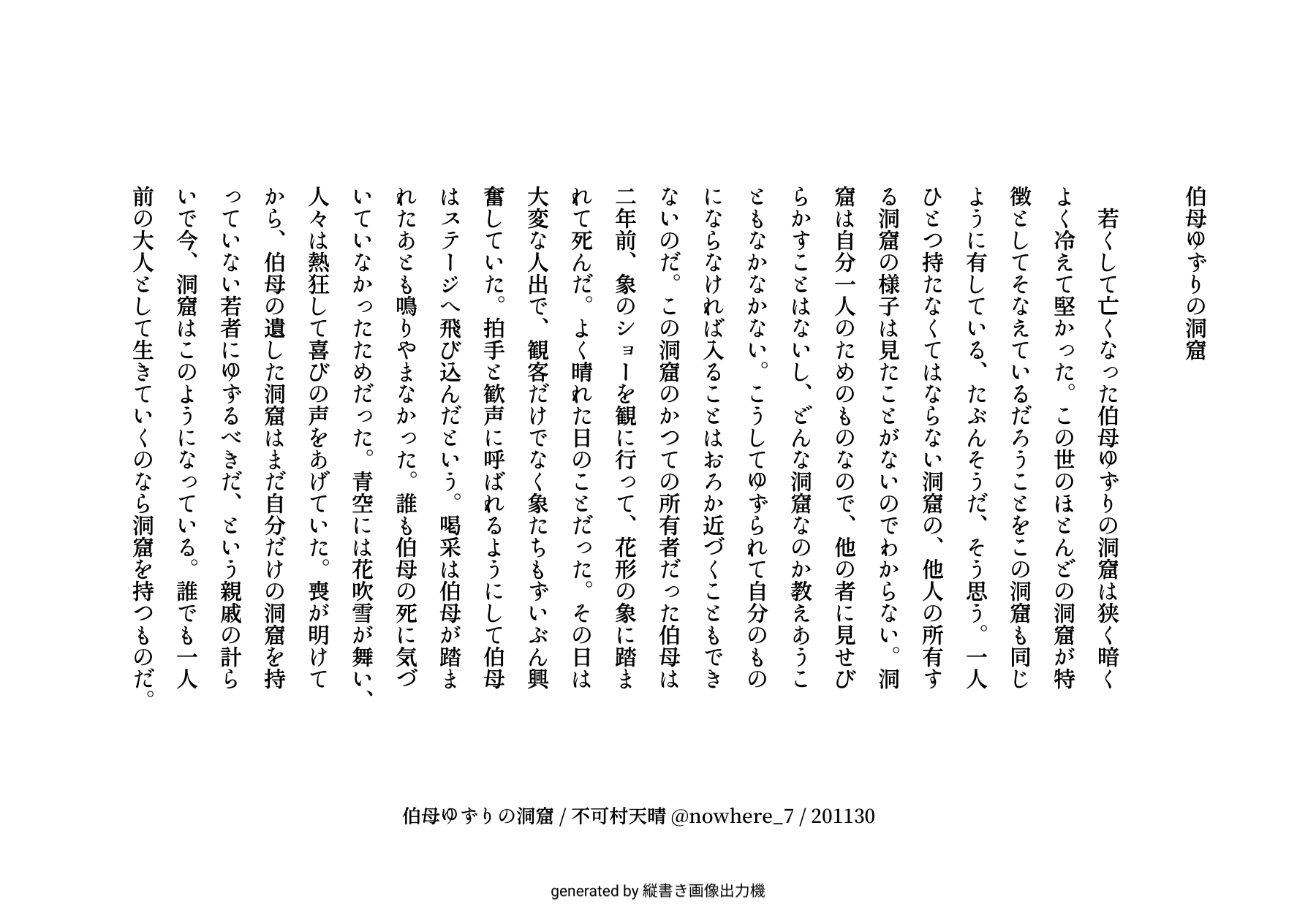
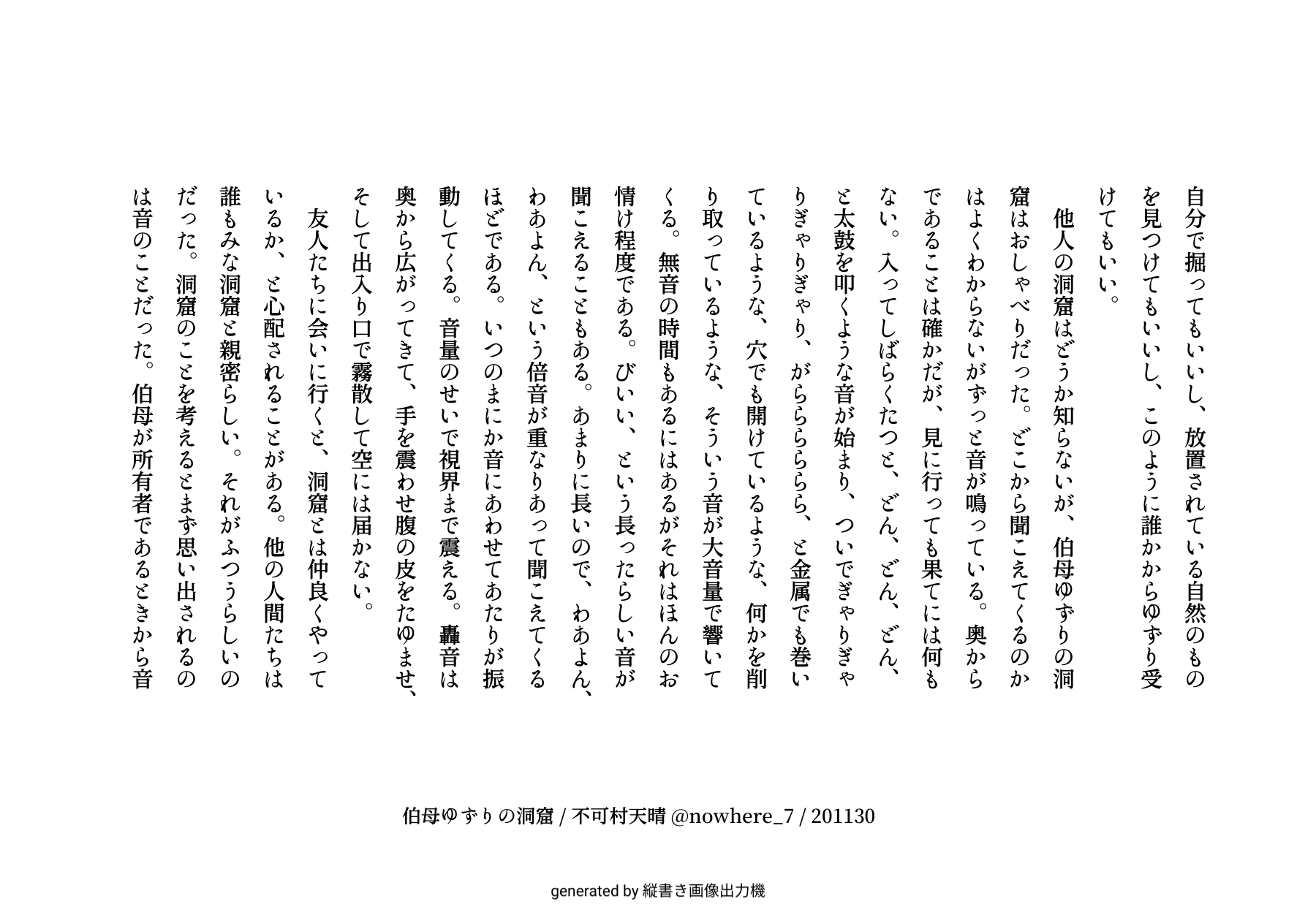
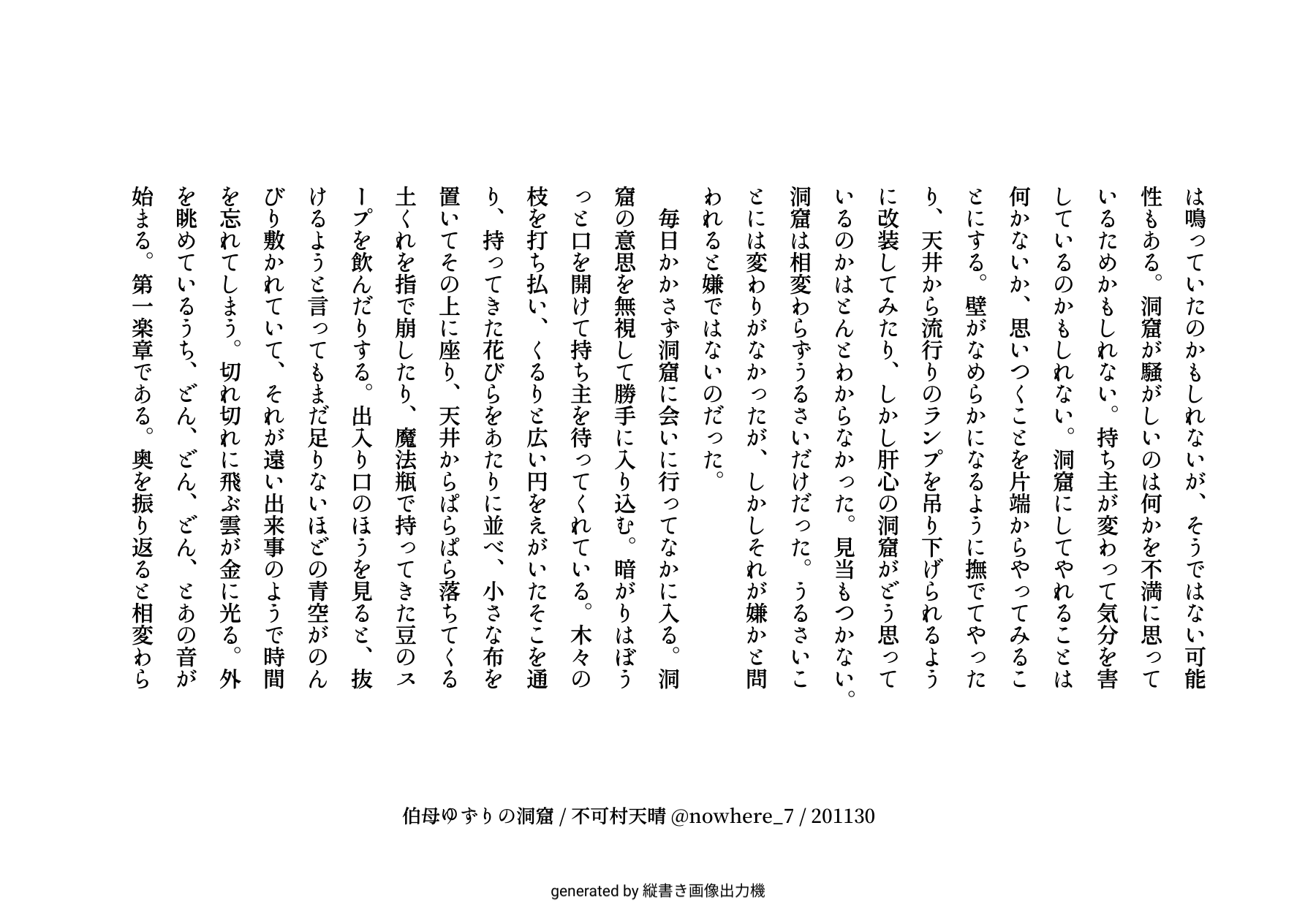
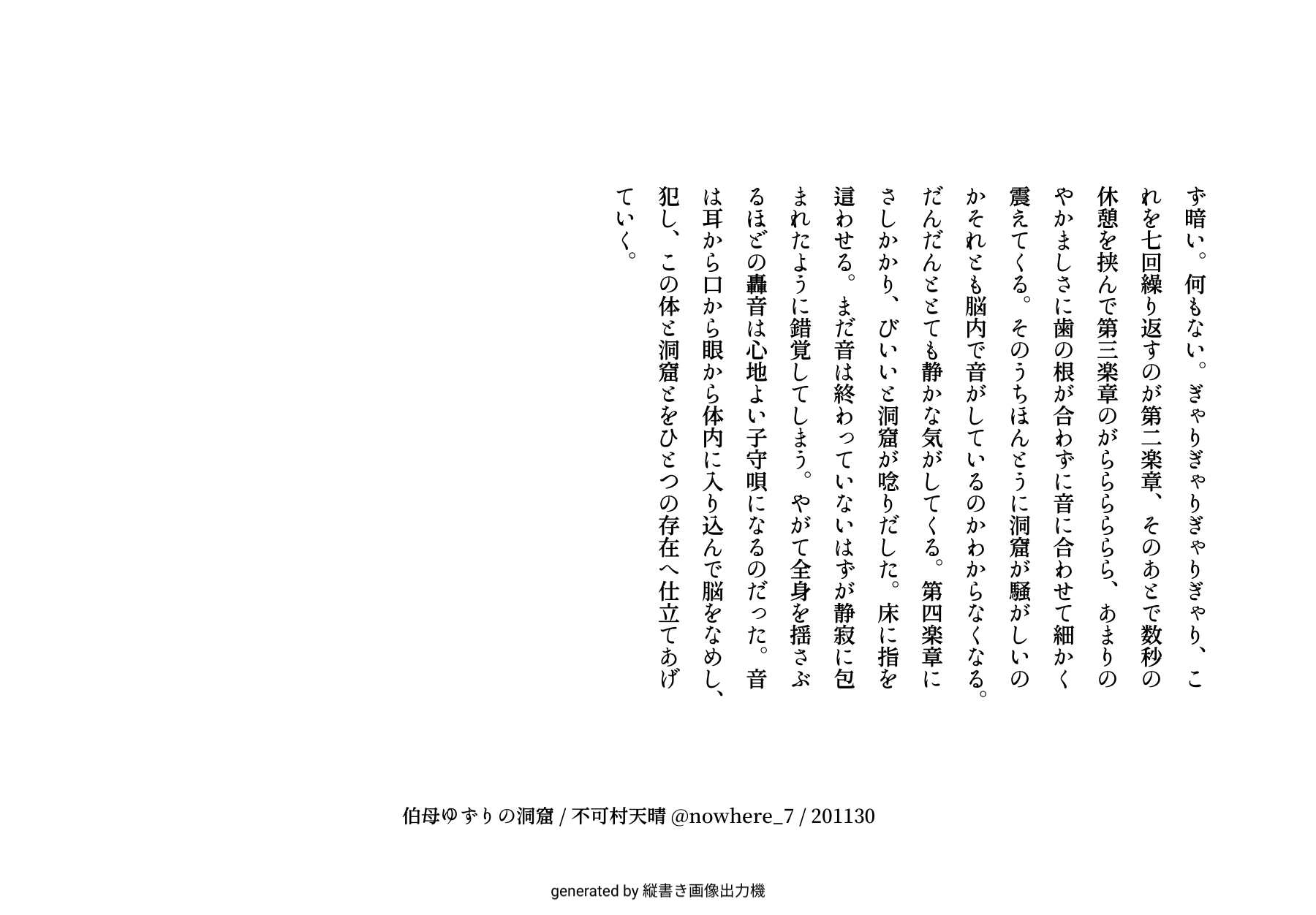
若くして亡くなった伯母ゆずりの洞窟は狭く暗くよく冷えて堅かった。この世のほとんどの洞窟が特徴としてそなえているだろうことをこの洞窟も同じように有している、たぶんそうだ、そう思う。一人ひとつ持たなくてはならない洞窟の、他人の所有する洞窟の様子は見たことがないのでわからない。洞窟は自分一人のためのものなので、他の者に見せびらかすことはないし、どんな洞窟なのか教えあうこともなかなかない。こうしてゆずられて自分のものにならなければ入ることはおろか近づくこともできないのだ。この洞窟のかつての所有者だった伯母は二年前、象のショーを観に行って、花形の象に踏まれて死んだ。よく晴れた日のことだった。その日は大変な人出で、観客だけでなく象たちもずいぶん興奮していた。拍手と歓声に呼ばれるようにして伯母はステージへ飛び込んだという。喝采は伯母が踏まれたあとも鳴りやまなかった。誰も伯母の死に気づいていなかったためだった。青空には花吹雪が舞い、人々は熱狂して喜びの声をあげていた。喪が明けてから、伯母の遺した洞窟はまだ自分だけの洞窟を持っていない若者にゆずるべきだ、という親戚の計らいで今、洞窟はこのようになっている。誰でも一人前の大人として生きていくのなら洞窟を持つものだ。自分で掘ってもいいし、放置されている自然のものを見つけてもいいし、このように誰かからゆずり受けてもいい。
他人の洞窟はどうか知らないが、伯母ゆずりの洞窟はおしゃべりだった。どこから聞こえてくるのかはよくわからないがずっと音が鳴っている。奥からであることは確かだが、見に行っても果てには何もない。入ってしばらくたつと、どん、どん、どん、と太鼓を叩くような音が始まり、ついでぎゃりぎゃりぎゃりぎゃり、がらららららら、と金属でも巻いているような、穴でも開けているような、何かを削り取っているような、そういう音が大音量で響いてくる。無音の時間もあるにはあるがそれはほんのお情け程度である。びいい、という長ったらしい音が聞こえることもある。あまりに長いので、わあよん、わあよん、という倍音が重なりあって聞こえてくるほどである。いつのまにか音にあわせてあたりが振動してくる。音量のせいで視界まで震える。轟音は奥から広がってきて、手を震わせ腹の皮をたゆませ、そして出入り口で霧散して空には届かない。
友人たちに会いに行くと、洞窟とは仲良くやっているか、と心配されることがある。他の人間たちは誰もみな洞窟と親密らしい。それがふつうらしいのだった。洞窟のことを考えるとまず思い出されるのは音のことだった。伯母が所有者であるときから音は鳴っていたのかもしれないが、そうではない可能性もある。洞窟が騒がしいのは何かを不満に思っているためかもしれない。持ち主が変わって気分を害しているのかもしれない。洞窟にしてやれることは何かないか、思いつくことを片端からやってみることにする。壁がなめらかになるように撫でてやったり、天井から流行りのランプを吊り下げられるように改装してみたり、しかし肝心の洞窟がどう思っているのかはとんとわからなかった。見当もつかない。洞窟は相変わらずうるさいだけだった。うるさいことには変わりがなかったが、しかしそれが嫌かと問われると嫌ではないのだった。
毎日かかさず洞窟に会いに行ってなかに入る。洞窟の意思を無視して勝手に入り込む。暗がりはぼうっと口を開けて持ち主を待ってくれている。木々の枝を打ち払い、くるりと広い円をえがいたそこを通り、持ってきた花びらをあたりに並べ、小さな布を置いてその上に座り、天井からぱらぱら落ちてくる土くれを指で崩したり、魔法瓶で持ってきた豆のスープを飲んだりする。出入り口のほうを見ると、抜けるようと言ってもまだ足りないほどの青空がのんびり敷かれていて、それが遠い出来事のようで時間を忘れてしまう。切れ切れに飛ぶ雲が金に光る。外を眺めているうち、どん、どん、どん、とあの音が始まる。第一楽章である。奥を振り返ると相変わらず暗い。何もない。ぎゃりぎゃりぎゃりぎゃり、これを七回繰り返すのが第二楽章、そのあとで数秒の休憩を挟んで第三楽章のがらららららら、あまりのやかましさに歯の根が合わずに音に合わせて細かく震えてくる。そのうちほんとうに洞窟が騒がしいのかそれとも脳内で音がしているのかわからなくなる。だんだんととても静かな気がしてくる。第四楽章にさしかかり、びいいと洞窟が唸りだした。床に指を這わせる。まだ音は終わっていないはずが静寂に包まれたように錯覚してしまう。やがて全身を揺さぶるほどの轟音は心地よい子守唄になるのだった。音は耳から口から眼から体内に入り込んで脳をなめし、犯し、この体と洞窟とをひとつの存在へ仕立てあげていく。
伯母ゆずりの洞窟 201130