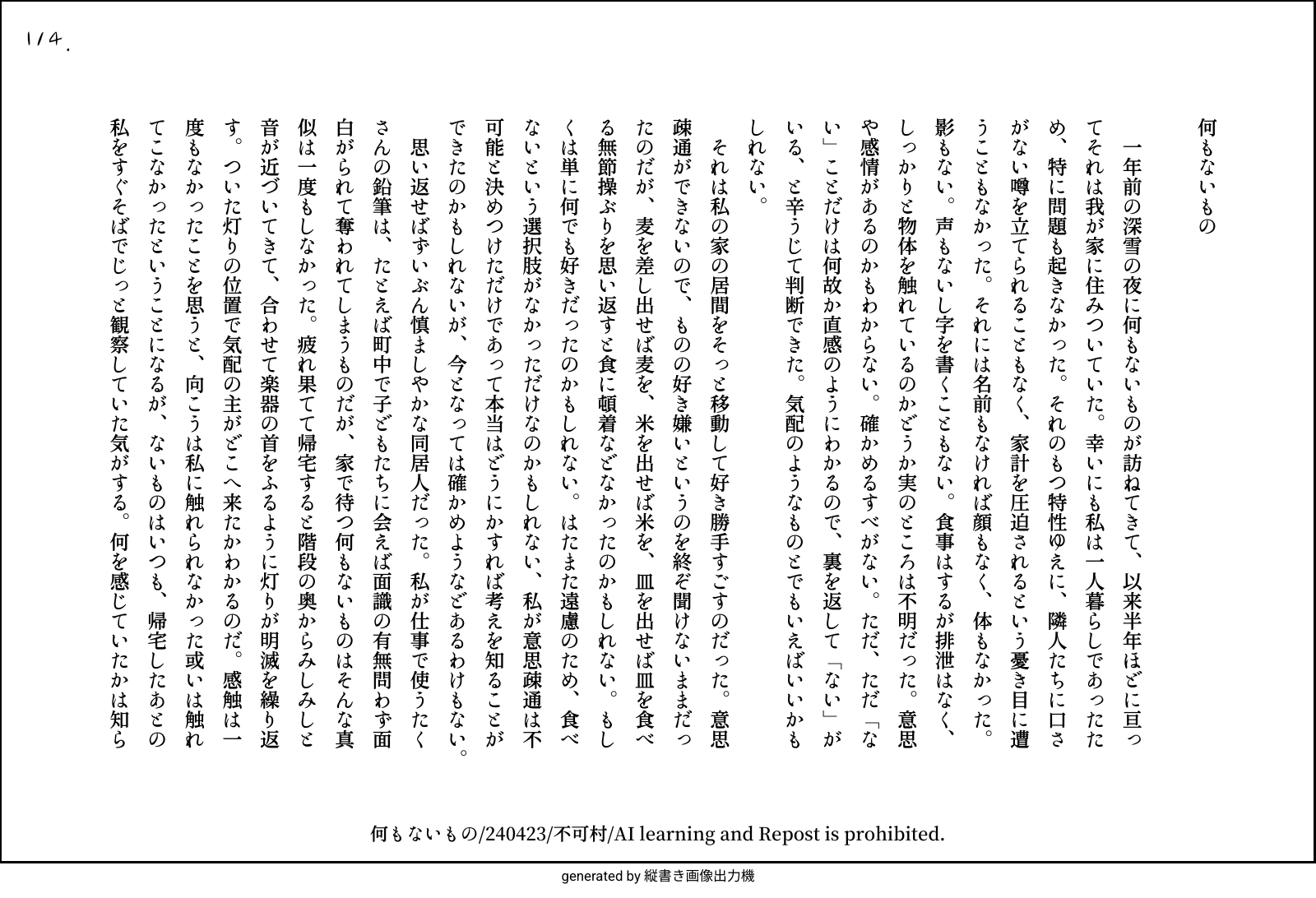
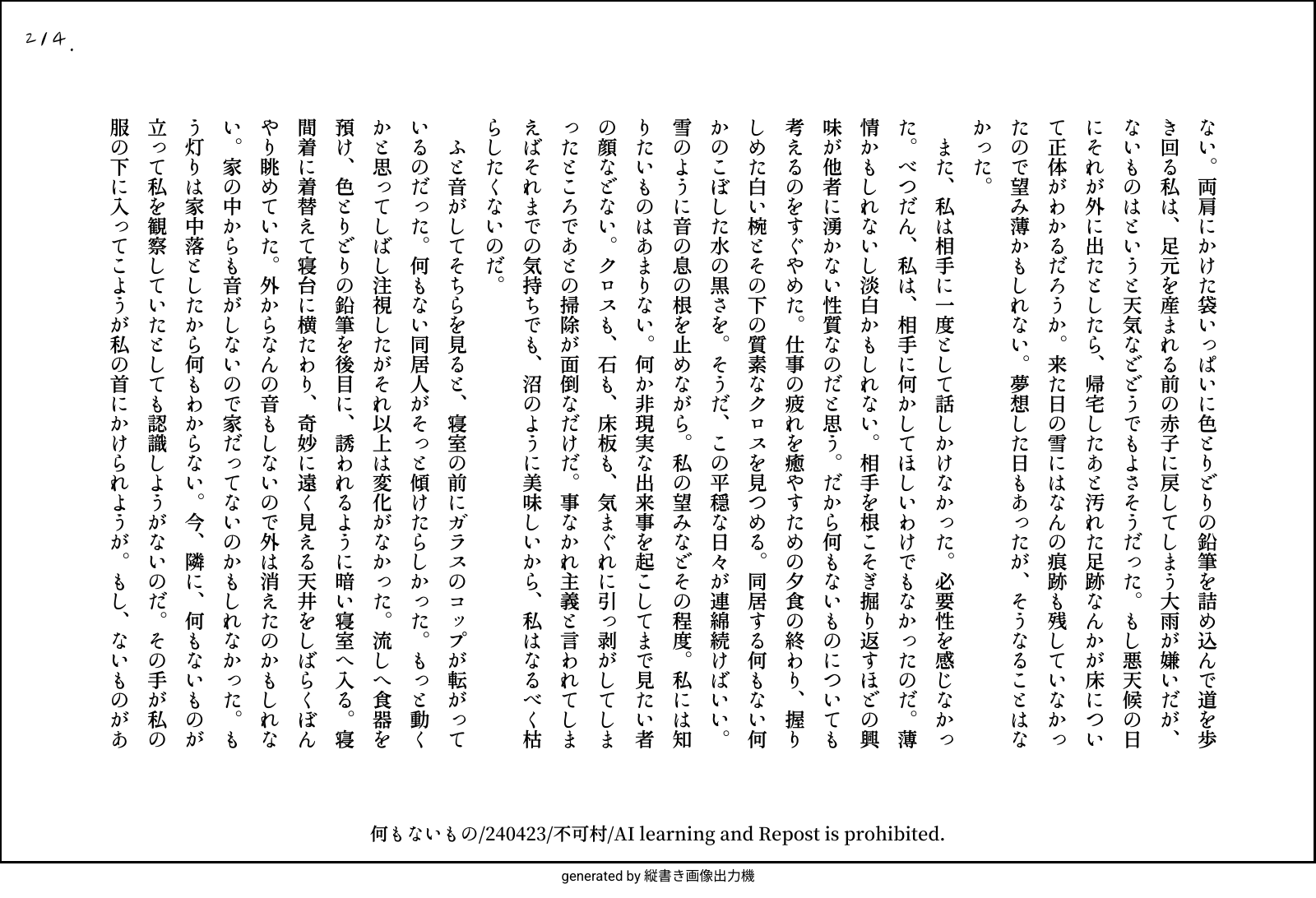
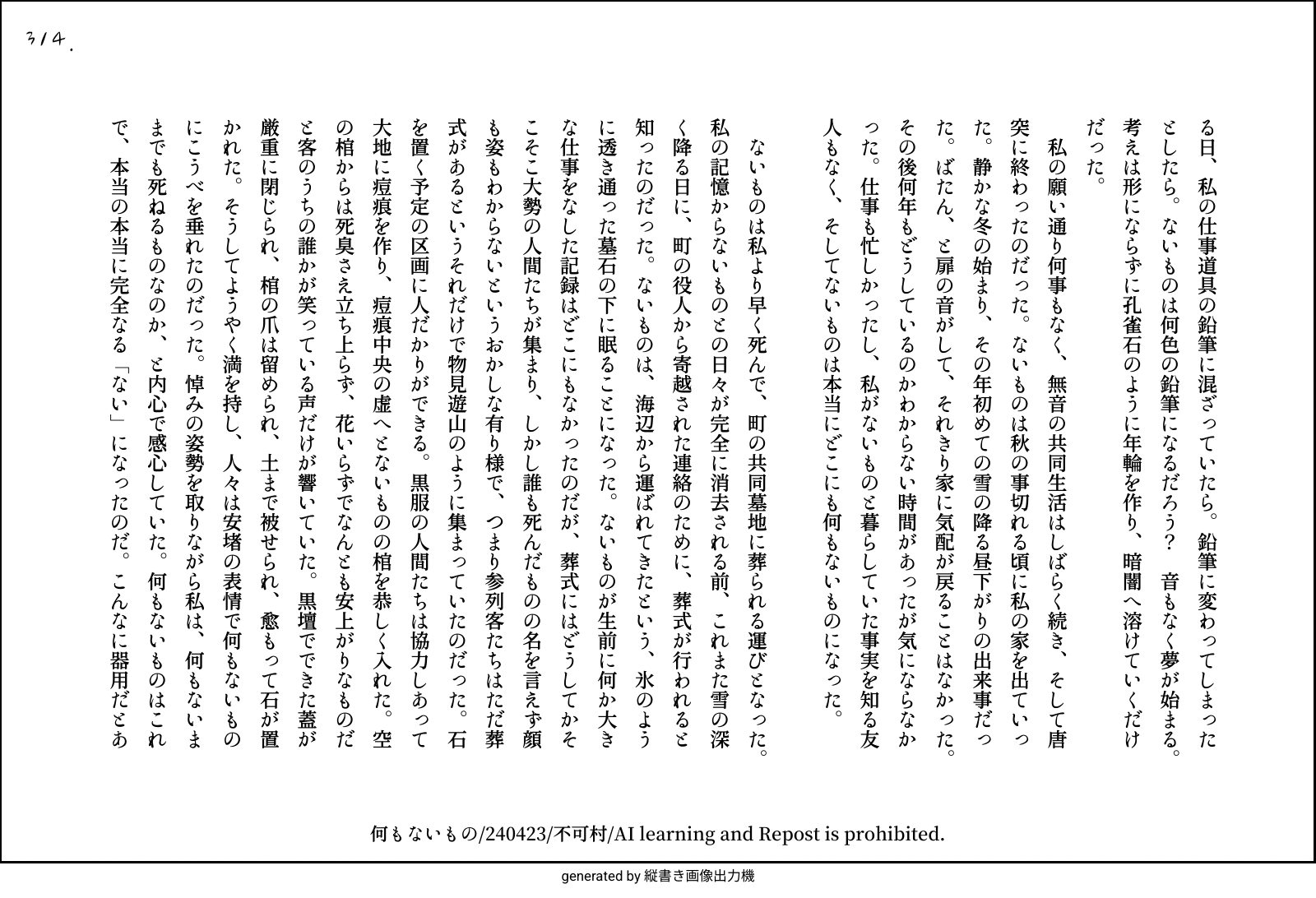
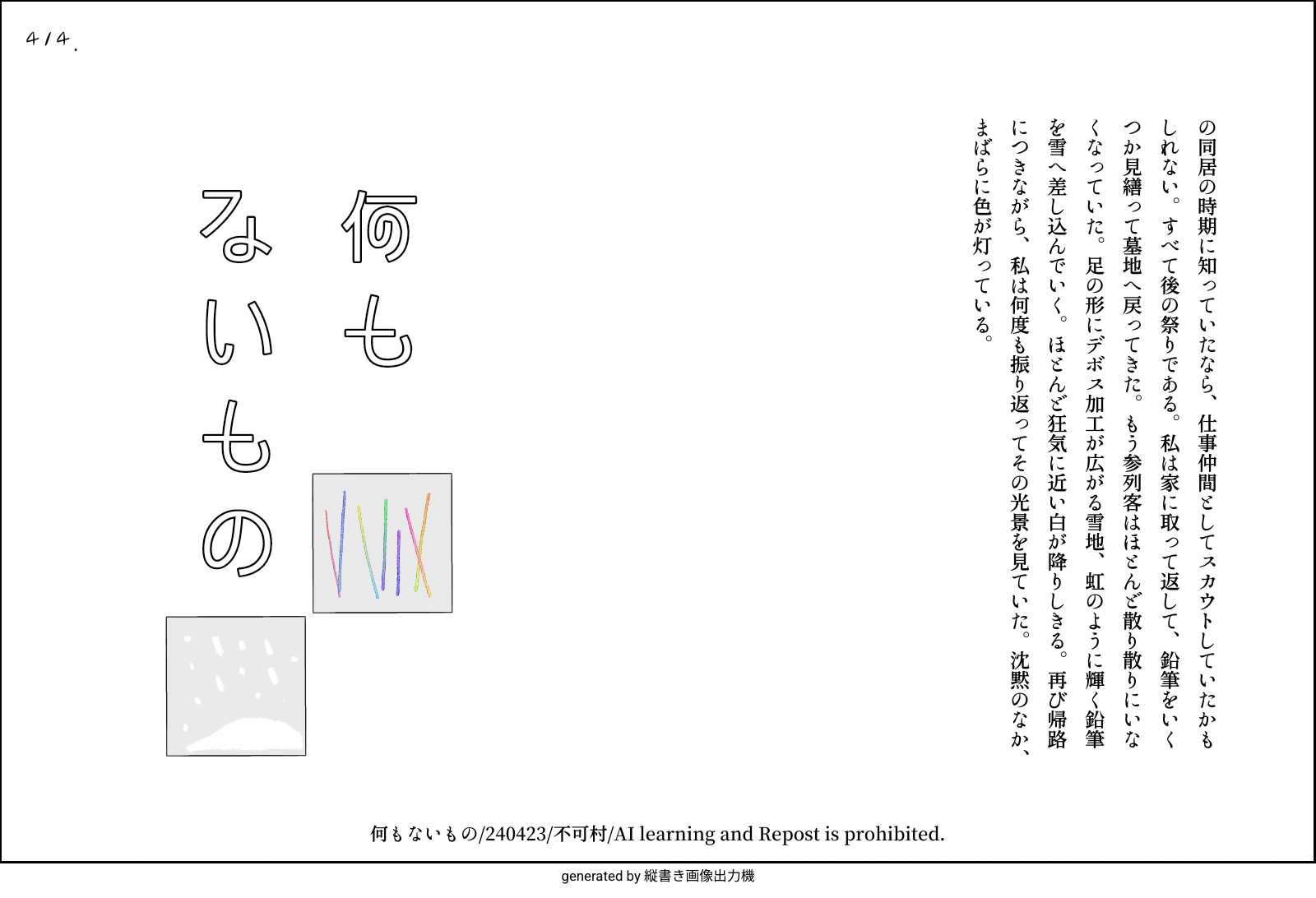
一年前の深雪の夜に何もないものが訪ねてきて、以来半年ほどに亘ってそれは我が家に住みついていた。幸いにも私は一人暮らしであったため、特に問題も起きなかった。それのもつ特性ゆえに、隣人たちに口さがない噂を立てられることもなく、家計を圧迫されるという憂き目に遭うこともなかった。それには名前もなければ顔もなく、体もなかった。影もない。声もないし字を書くこともない。食事はするが排泄はなく、しっかりと物体を触れているのかどうか実のところは不明だった。意思や感情があるのかもわからない。確かめるすべがない。ただ、ただ「ない」ことだけは何故か直感のようにわかるので、裏を返して「ない」がいる、と辛うじて判断できた。気配のようなものとでもいえばいいかもしれない。
それは私の家の居間をそっと移動して好き勝手すごすのだった。意思疎通ができないので、ものの好き嫌いというのを終ぞ聞けないままだったのだが、麦を差し出せば麦を、米を出せば米を、皿を出せば皿を食べる無節操ぶりを思い返すと食に頓着などなかったのかもしれない。もしくは単に何でも好きだったのかもしれない。はたまた遠慮のため、食べないという選択肢がなかっただけなのかもしれない、私が意思疎通は不可能と決めつけただけであって本当はどうにかすれば考えを知ることができたのかもしれないが、今となっては確かめようなどあるわけもない。
思い返せばずいぶん慎ましやかな同居人だった。私が仕事で使うたくさんの鉛筆は、たとえば町中で子どもたちに会えば面識の有無問わず面白がられて奪われてしまうものだが、家で待つ何もないものはそんな真似は一度もしなかった。疲れ果てて帰宅すると階段の奥からみしみしと音が近づいてきて、合わせて楽器の首をふるように灯りが明滅を繰り返す。ついた灯りの位置で気配の主がどこへ来たかわかるのだ。感触は一度もなかったことを思うと、向こうは私に触れられなかった或いは触れてこなかったということになるが、ないものはいつも、帰宅したあとの私をすぐそばでじっと観察していた気がする。何を感じていたかは知らない。両肩にかけた袋いっぱいに色とりどりの鉛筆を詰め込んで道を歩き回る私は、足元を産まれる前の赤子に戻してしまう大雨が嫌いだが、ないものはというと天気などどうでもよさそうだった。もし悪天候の日にそれが外に出たとしたら、帰宅したあと汚れた足跡なんかが床について正体がわかるだろうか。来た日の雪にはなんの痕跡も残していなかったので望み薄かもしれない。夢想した日もあったが、そうなることはなかった。
また、私は相手に一度として話しかけなかった。必要性を感じなかった。べつだん、私は、相手に何かしてほしいわけでもなかったのだ。薄情かもしれないし淡白かもしれない。相手を根こそぎ掘り返すほどの興味が他者に湧かない性質なのだと思う。だから何もないものについても考えるのをすぐやめた。仕事の疲れを癒やすための夕食の終わり、握りしめた白い椀とその下の質素なクロスを見つめる。同居する何もない何かのこぼした水の黒さを。そうだ、この平穏な日々が連綿続けばいい。雪のように音の息の根を止めながら。私の望みなどその程度。私には知りたいものはあまりない。何か非現実な出来事を起こしてまで見たい者の顔などない。クロスも、石も、床板も、気まぐれに引っ剥がしてしまったところであとの掃除が面倒なだけだ。事なかれ主義と言われてしまえばそれまでの気持ちでも、沼のように美味しいから、私はなるべく枯らしたくないのだ。
ふと音がしてそちらを見ると、寝室の前にガラスのコップが転がっているのだった。何もない同居人がそっと傾けたらしかった。もっと動くかと思ってしばし注視したがそれ以上は変化がなかった。流しへ食器を預け、色とりどりの鉛筆を後目に、誘われるように暗い寝室へ入る。寝間着に着替えて寝台に横たわり、奇妙に遠く見える天井をしばらくぼんやり眺めていた。外からなんの音もしないので外は消えたのかもしれない。家の中からも音がしないので家だってないのかもしれなかった。もう灯りは家中落としたから何もわからない。今、隣に、何もないものが立って私を観察していたとしても認識しようがないのだ。その手が私の服の下に入ってこようが私の首にかけられようが。もし、ないものがある日、私の仕事道具の鉛筆に混ざっていたら。鉛筆に変わってしまったとしたら。ないものは何色の鉛筆になるだろう? 音もなく夢が始まる。考えは形にならずに孔雀石のように年輪を作り、暗闇へ溶けていくだけだった。
私の願い通り何事もなく、無音の共同生活はしばらく続き、そして唐突に終わったのだった。ないものは秋の事切れる頃に私の家を出ていった。静かな冬の始まり、その年初めての雪の降る昼下がりの出来事だった。ばたん、と扉の音がして、それきり家に気配が戻ることはなかった。その後何年もどうしているのかわからない時間があったが気にならなかった。仕事も忙しかったし、私がないものと暮らしていた事実を知る友人もなく、そしてないものは本当にどこにも何もないものになった。
ないものは私より早く死んで、町の共同墓地に葬られる運びとなった。私の記憶からないものとの日々が完全に消去される前、これまた雪の深く降る日に、町の役人から寄越された連絡のために、葬式が行われると知ったのだった。ないものは、海辺から運ばれてきたという、氷のように透き通った墓石の下に眠ることになった。ないものが生前に何か大きな仕事をなした記録はどこにもなかったのだが、葬式にはどうしてかそこそこ大勢の人間たちが集まり、しかし誰も死んだものの名を言えず顔も姿もわからないというおかしな有り様で、つまり参列客たちはただ葬式があるというそれだけで物見遊山のように集まっていたのだった。石を置く予定の区画に人だかりができる。黒服の人間たちは協力しあって大地に痘痕を作り、痘痕中央の虚へとないものの棺を恭しく入れた。空の棺からは死臭さえ立ち上らず、花いらずでなんとも安上がりなものだと客のうちの誰かが笑っている声だけが響いていた。黒壇でできた蓋が厳重に閉じられ、棺の爪は留められ、土まで被せられ、愈もって石が置かれた。そうしてようやく満を持し、人々は安堵の表情で何もないものにこうべを垂れたのだった。悼みの姿勢を取りながら私は、何もないままでも死ねるものなのか、と内心で感心していた。何もないものはこれで、本当の本当に完全なる「ない」になったのだ。こんなに器用だとあの同居の時期に知っていたなら、仕事仲間としてスカウトしていたかもしれない。すべて後の祭りである。私は家に取って返して、鉛筆をいくつか見繕って墓地へ戻ってきた。もう参列客はほとんど散り散りにいなくなっていた。足の形にデボス加工が広がる雪地、虹のように輝く鉛筆を雪へ差し込んでいく。ほとんど狂気に近い白が降りしきる。再び帰路につきながら、私は何度も振り返ってその光景を見ていた。沈黙のなか、まばらに色が灯っている。
何もないもの/240423/不可村/Repost is prohibited.