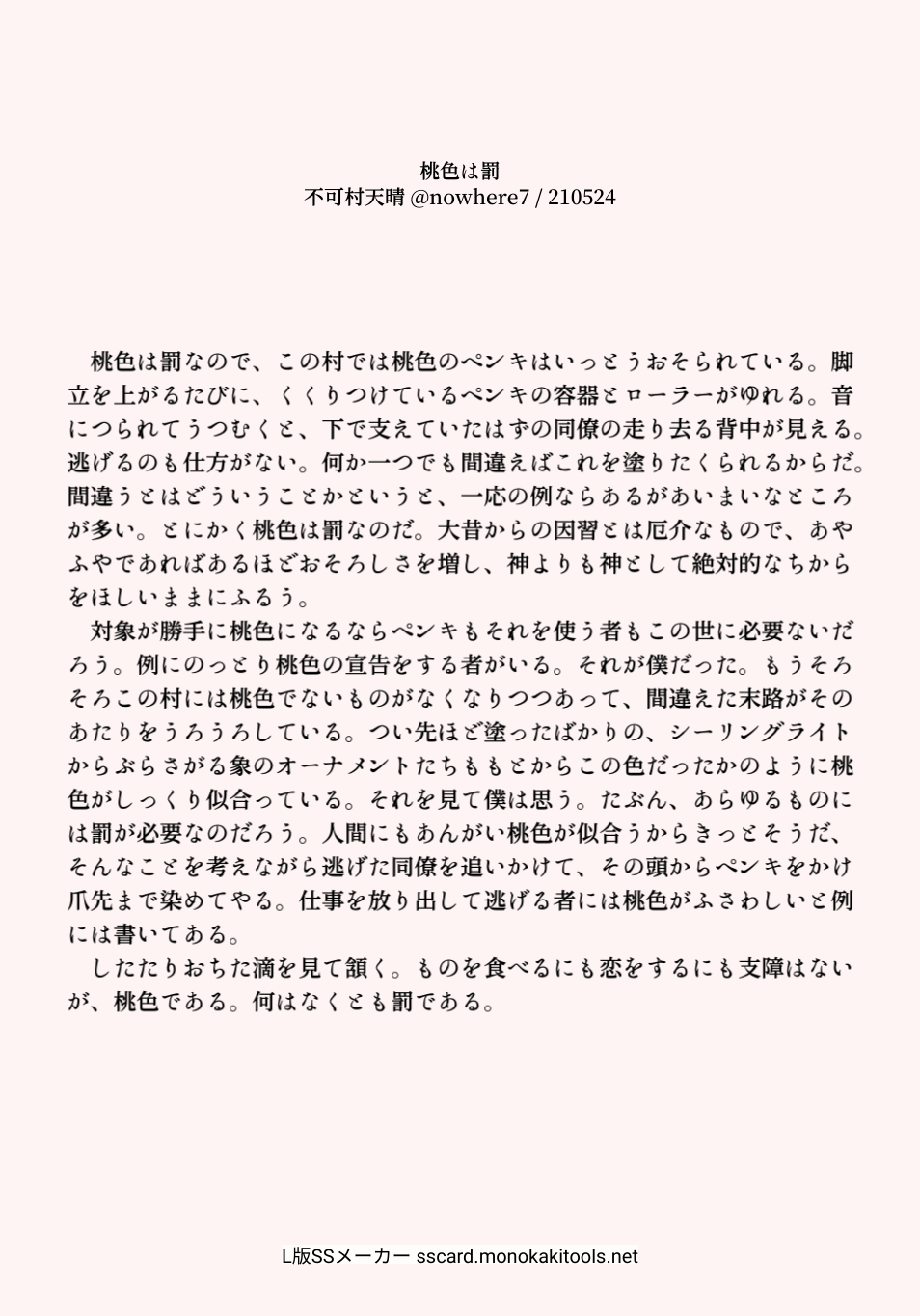
桃色は罰なので、この村では桃色のペンキはいっとうおそられている。脚立を上がるたびに、くくりつけているペンキの容器とローラーがゆれる。音につられてうつむくと、下で支えていたはずの同僚の走り去る背中が見える。逃げるのも仕方がない。何か一つでも間違えばこれを塗りたくられるからだ。間違うとはどういうことかというと、一応の例ならあるがあいまいなところが多い。とにかく桃色は罰なのだ。大昔からの因習とは厄介なもので、あやふやであればあるほどおそろしさを増し、神よりも神として絶対的なちからをほしいままにふるう。
対象が勝手に桃色になるならペンキもそれを使う者もこの世に必要ないだろう。例にのっとり桃色の宣告をする者がいる。それが僕だった。もうそろそろこの村には桃色でないものがなくなりつつあって、間違えた末路がそのあたりをうろうろしている。つい先ほど塗ったばかりの、シーリングライトからぶらさがる象のオーナメントたちももとからこの色だったかのように桃色がしっくり似合っている。それを見て僕は思う。たぶん、あらゆるものには罰が必要なのだろう。人間にもあんがい桃色が似合うからきっとそうだ、そんなことを考えながら逃げた同僚を追いかけて、その頭からペンキをかけ爪先まで染めてやる。仕事を放り出して逃げる者には桃色がふさわしいと例には書いてある。
したたりおちた滴を見て頷く。ものを食べるにも恋をするにも支障はないが、桃色である。何はなくとも罰である。
桃色は罰 210524