

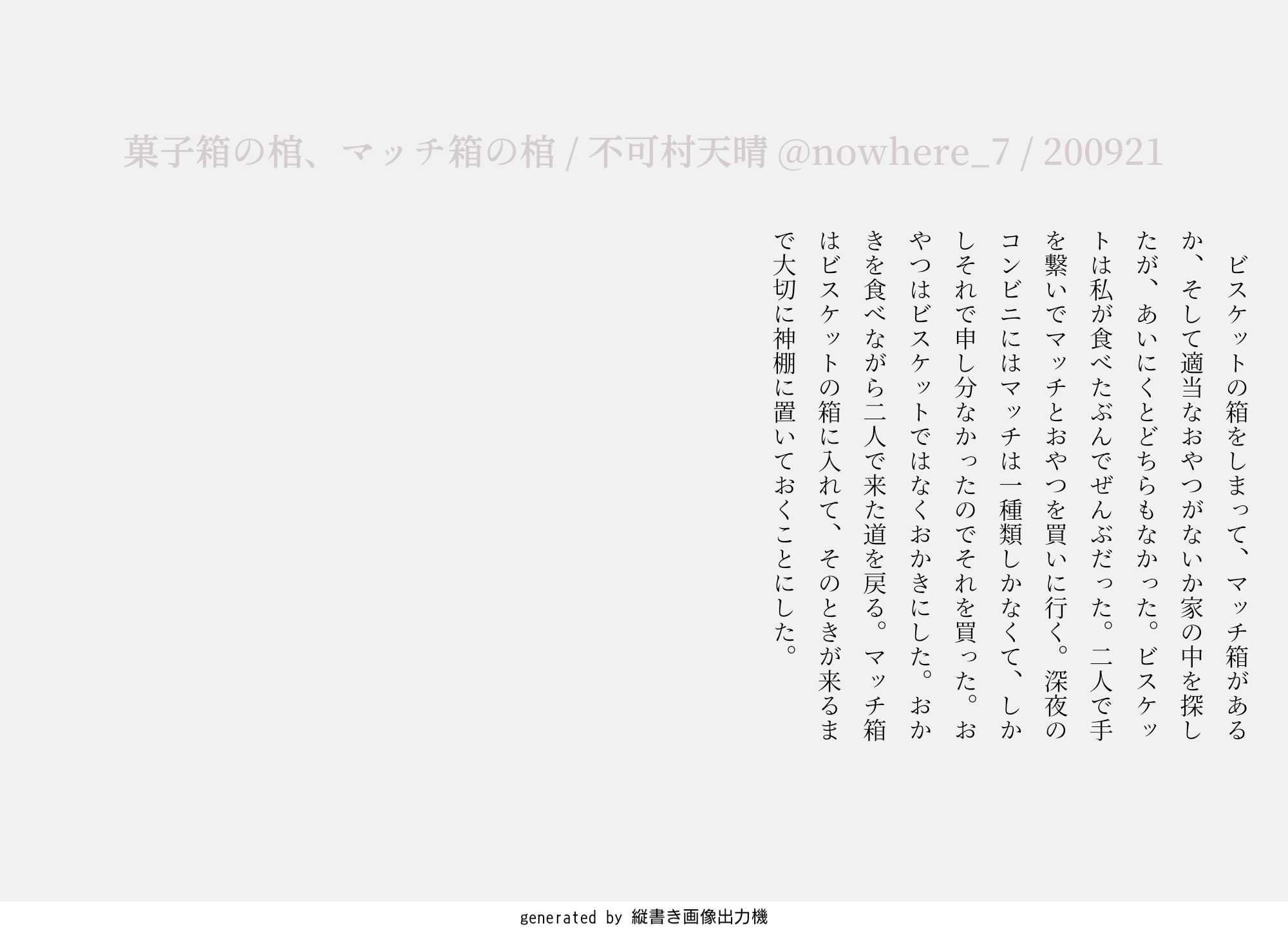
ちょうど食べ終わったばかりのビスケットの空き箱を捨てずにとっておくことにした。その箱が自分の棺にちょうどよさそうだったからだ。神棚にでも置いておけば間違って捨てることもないはずだろう。そのビスケットは近所のコンビニエンスストアで五日前に買ったものだった。老若男女問わず人気の、ビスケットといえば誰だって思い浮かべるだろう、有名な会社のロングセラー商品だ。見慣れたロゴマークのついている空き箱は手のひらほどの大きさで、長方形をしていて、厚紙でできていて、内側は地面の中のようなグレーで、蓋は扉のように開閉できて、ちょっとした宝箱のようでもあった。鼻先を突っ込んでみるとかすかにいいにおいがする。ここで眠ったら具合がよさそうだった。やっぱり、死んだあとは体を小さくしてもらってここに入れてもらおうとそう思った。クッションでも詰めればきっともっとよくなる。箱のなかを好きにコーディネートすることを夢想しながら、私は箱を逆さまにしてビスケットの残りかすをぜんぶ出す。覗いてみるとまだかすがついていたので、それを爪で取って舐めた。かすはちゃんと甘かった。その下に現れた油染みは見て見ぬふりをして、そこそこきれいになったことを確認し、そして恋人に紹介してやることにする。親に引き合わせるように、昔の写真を見せるように。手のひらに箱をのせて、これが私の棺になるよとそう教える。それを見た恋人はいい棺だねとほめてくれた。私の手の上にのったままの箱の蓋を何回か開閉させる。そのあとで、あたしはマッチ箱がいい、とそう言った。私の脳裡に小さな茶色の箱がぽんと浮かび、恋人は人差し指をくるくる回してそれを動かす。マッチ箱はトンネルをくぐる列車みたいにスリーブ箱になっている。そのスリーブがいいのだと恋人は歌うように説明してくれた。スライドさせて出し入れできるのがいい、きっちりしまわれると、四方八方全面、何も見えないのがいい、守られているかんじがするから。それを使って火をつけられるところもいいよね。わきについているあの茶色のところは側薬といって、赤リンなんかでできているんだよ。そこで恋人はおもむろに手を打って顔を輝かせた。そうだ、あたしが死んでマッチ箱に入ったらあなたはマッチ棒になってよ。そして泣くときはあたしの入ったマッチ箱に頭をすりつけて泣いてね。あたしを送り出すときはあたしにすがって、頭で火をつけて。そしてあなたも一緒に燃えてしまってよ。
それはいい提案だと私は思った。すばらしい安心の約束だった。でも私はビスケットの空き箱でいいにおいに包まれる予定だからと答えると、恋人は、なんだかおなかが減ってきた、とそう神妙に答えたのだった。
ビスケットの箱をしまって、マッチ箱があるか、そして適当なおやつがないか家の中を探したが、あいにくとどちらもなかった。ビスケットは私が食べたぶんでぜんぶだった。二人で手を繋いでマッチとおやつを買いに行く。深夜のコンビニにはマッチは一種類しかなくて、しかしそれで申し分なかったのでそれを買った。おやつはビスケットではなくおかきにした。おかきを食べながら二人で来た道を戻る。マッチ箱はビスケットの箱に入れて、そのときが来るまで大切に神棚に置いておくことにした。
菓子箱の棺、マッチ箱の棺 200921