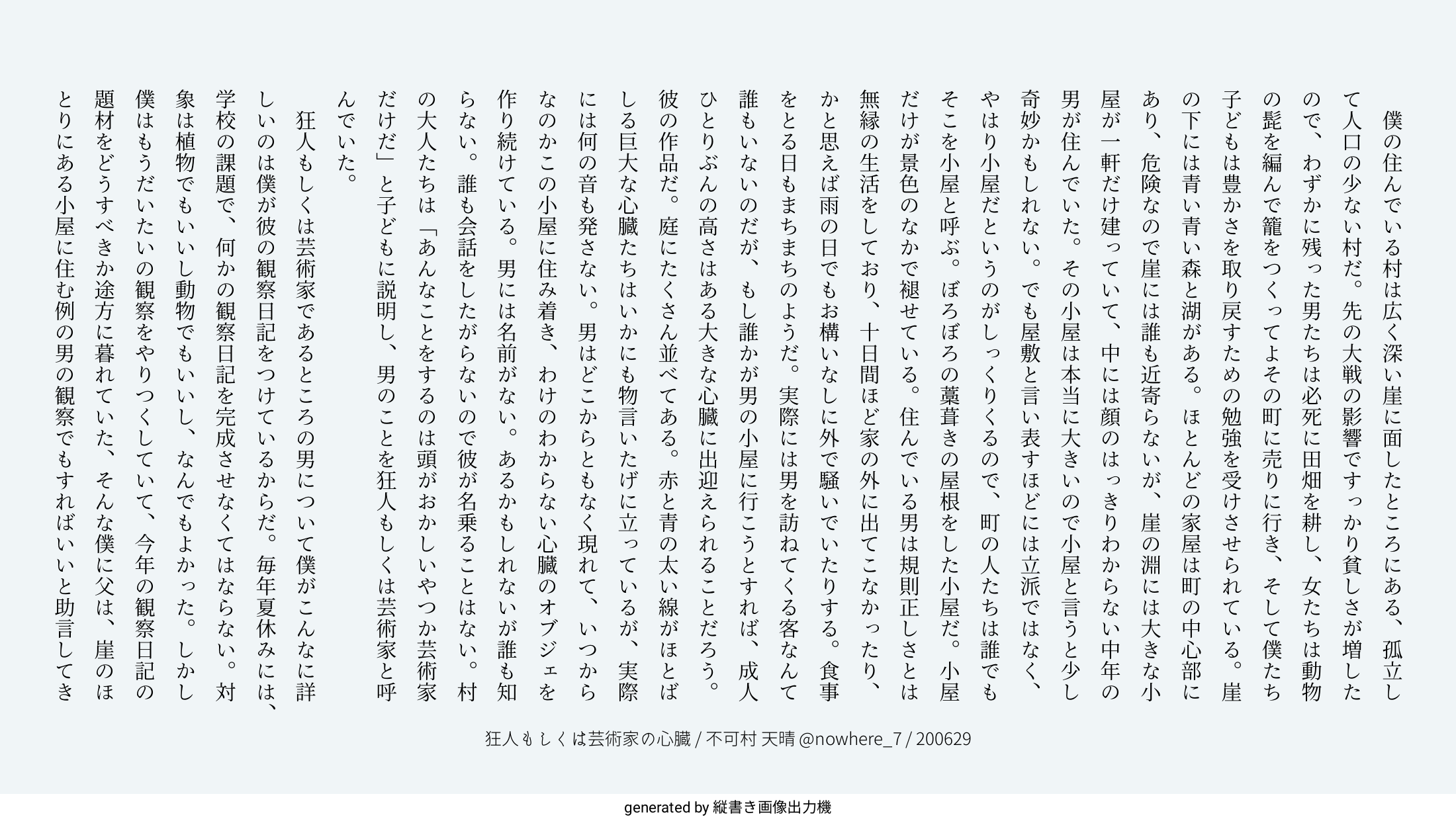
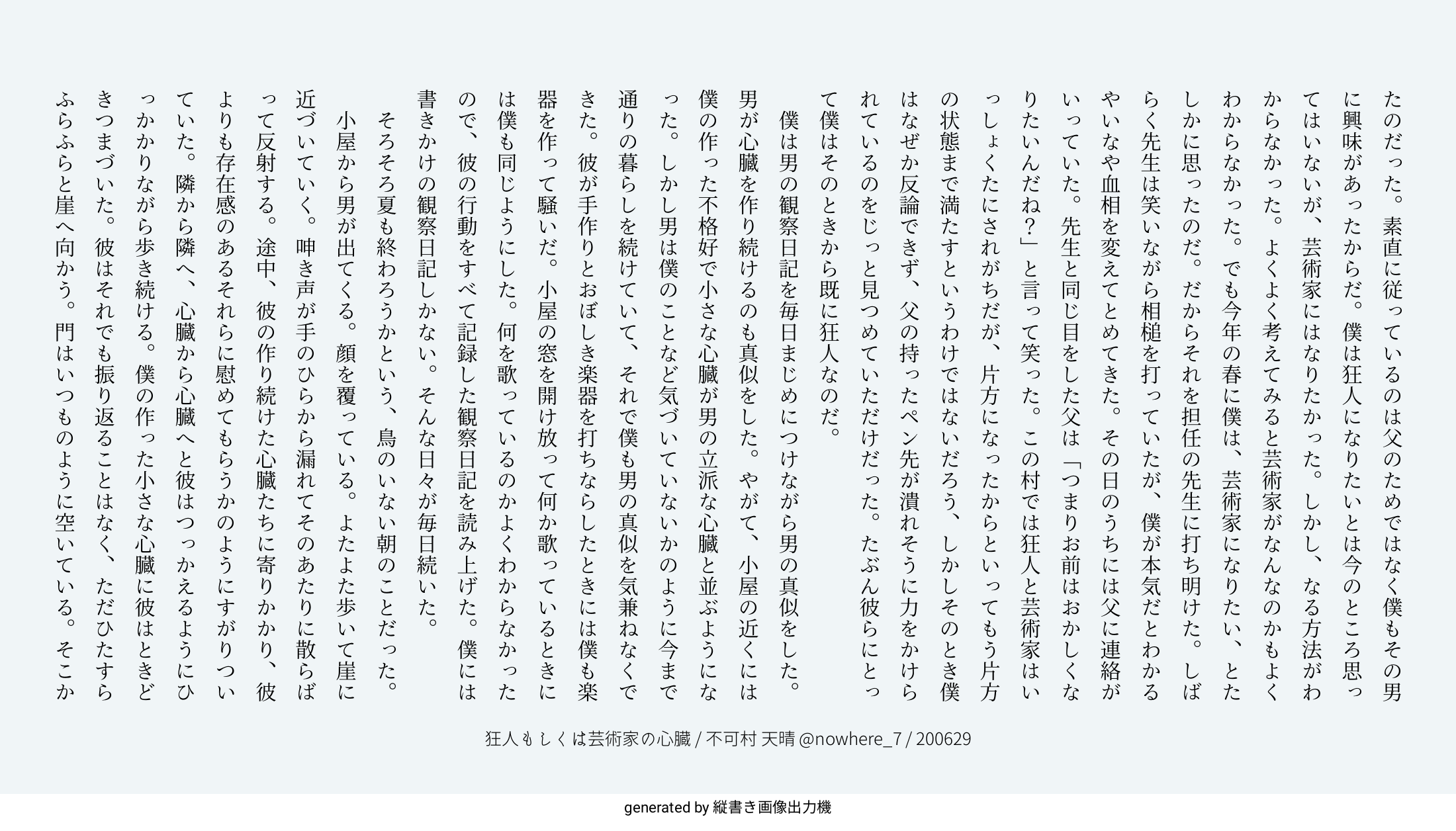

僕の住んでいる村は広く深い崖に面したところにある、孤立して人口の少ない村だ。先の大戦の影響ですっかり貧しさが増したので、わずかに残った男たちは必死に田畑を耕し、女たちは動物の髭を編んで籠をつくってよその町に売りに行き、そして僕たち子どもは豊かさを取り戻すための勉強を受けさせられている。崖の下には青い青い森と湖がある。ほとんどの家屋は町の中心部にあり、危険なので崖には誰も近寄らないが、崖の淵には大きな小屋が一軒だけ建っていて、中には顔のはっきりわからない中年の男が住んでいた。その小屋は本当に大きいので小屋と言うと少し奇妙かもしれない。でも屋敷と言い表すほどには立派ではなく、やはり小屋だというのがしっくりくるので、町の人たちは誰でもそこを小屋と呼ぶ。ぼろぼろの藁葺きの屋根をした小屋だ。小屋だけが景色のなかで褪せている。住んでいる男は規則正しさとは無縁の生活をしており、十日間ほど家の外に出てこなかったり、かと思えば雨の日でもお構いなしに外で騒いでいたりする。食事をとる日もまちまちのようだ。実際には男を訪ねてくる客なんて誰もいないのだが、もし誰かが男の小屋に行こうとすれば、成人ひとりぶんの高さはある大きな心臓に出迎えられることだろう。彼の作品だ。庭にたくさん並べてある。赤と青の太い線がほとばしる巨大な心臓たちはいかにも物言いたげに立っているが、実際には何の音も発さない。男はどこからともなく現れて、いつからなのかこの小屋に住み着き、わけのわからない心臓のオブジェを作り続けている。男には名前がない。あるかもしれないが誰も知らない。誰も会話をしたがらないので彼が名乗ることはない。村の大人たちは「あんなことをするのは頭がおかしいやつか芸術家だけだ」と子どもに説明し、男のことを狂人もしくは芸術家と呼んでいた。
狂人もしくは芸術家であるところの男について僕がこんなに詳しいのは僕が彼の観察日記をつけているからだ。毎年夏休みには、学校の課題で、何かの観察日記を完成させなくてはならない。対象は植物でもいいし動物でもいいし、なんでもよかった。しかし僕はもうだいたいの観察をやりつくしていて、今年の観察日記の題材をどうすべきか途方に暮れていた、そんな僕に父は、崖のほとりにある小屋に住む例の男の観察でもすればいいと助言してきたのだった。素直に従っているのは父のためではなく僕もその男に興味があったからだ。僕は狂人になりたいとは今のところ思ってはいないが、芸術家にはなりたかった。しかし、なる方法がわからなかった。よくよく考えてみると芸術家がなんなのかもよくわからなかった。でも今年の春に僕は、芸術家になりたい、とたしかに思ったのだ。だからそれを担任の先生に打ち明けた。しばらく先生は笑いながら相槌を打っていたが、僕が本気だとわかるやいなや血相を変えてとめてきた。その日のうちには父に連絡がいっていた。先生と同じ目をした父は「つまりお前はおかしくなりたいんだね?」と言って笑った。この村では狂人と芸術家はいっしょくたにされがちだが、片方になったからといってもう片方の状態まで満たすというわけではないだろう、しかしそのとき僕はなぜか反論できず、父の持ったペン先が潰れそうに力をかけられているのをじっと見つめていただけだった。たぶん彼らにとって僕はそのときから既に狂人なのだ。
僕は男の観察日記を毎日まじめにつけながら男の真似をした。男が心臓を作り続けるのも真似をした。やがて、小屋の近くには僕の作った不格好で小さな心臓が男の立派な心臓と並ぶようになった。しかし男は僕のことなど気づいていないかのように今まで通りの暮らしを続けていて、それで僕も男の真似を気兼ねなくできた。彼が手作りとおぼしき楽器を打ちならしたときには僕も楽器を作って騒いだ。小屋の窓を開け放って何か歌っているときには僕も同じようにした。何を歌っているのかよくわからなかったので、彼の行動をすべて記録した観察日記を読み上げた。僕には書きかけの観察日記しかない。そんな日々が毎日続いた。
そろそろ夏も終わろうかという、鳥のいない朝のことだった。
小屋から男が出てくる。顔を覆っている。よたよた歩いて崖に近づいていく。呻き声が手のひらから漏れてそのあたりに散らばって反射する。途中、彼の作り続けた心臓たちに寄りかかり、彼よりも存在感のあるそれらに慰めてもらうかのようにすがりついていた。隣から隣へ、心臓から心臓へと彼はつっかえるようにひっかかりながら歩き続ける。僕の作った小さな心臓に彼はときどきつまづいた。彼はそれでも振り返ることはなく、ただひたすらふらふらと崖へ向かう。門はいつものように空いている。そこから外に出たところで、もうだめだ、うわーっ、と男は叫び、そして倒れこむように崖下へ落ちていった。僕も顔を覆う。男のいなくなった小屋の前、草の上に倒れこむ。もうだめだ、うわーっ。ばさんと草の悲鳴が聞こえてそれっきりだった。崖の下から何か聞こえないか耳を澄ませてみたが何もない。脈打つことを知らない心臓たちはただ黙って僕たちを見ていただけだった。
狂人もしくは芸術家の心臓 200629