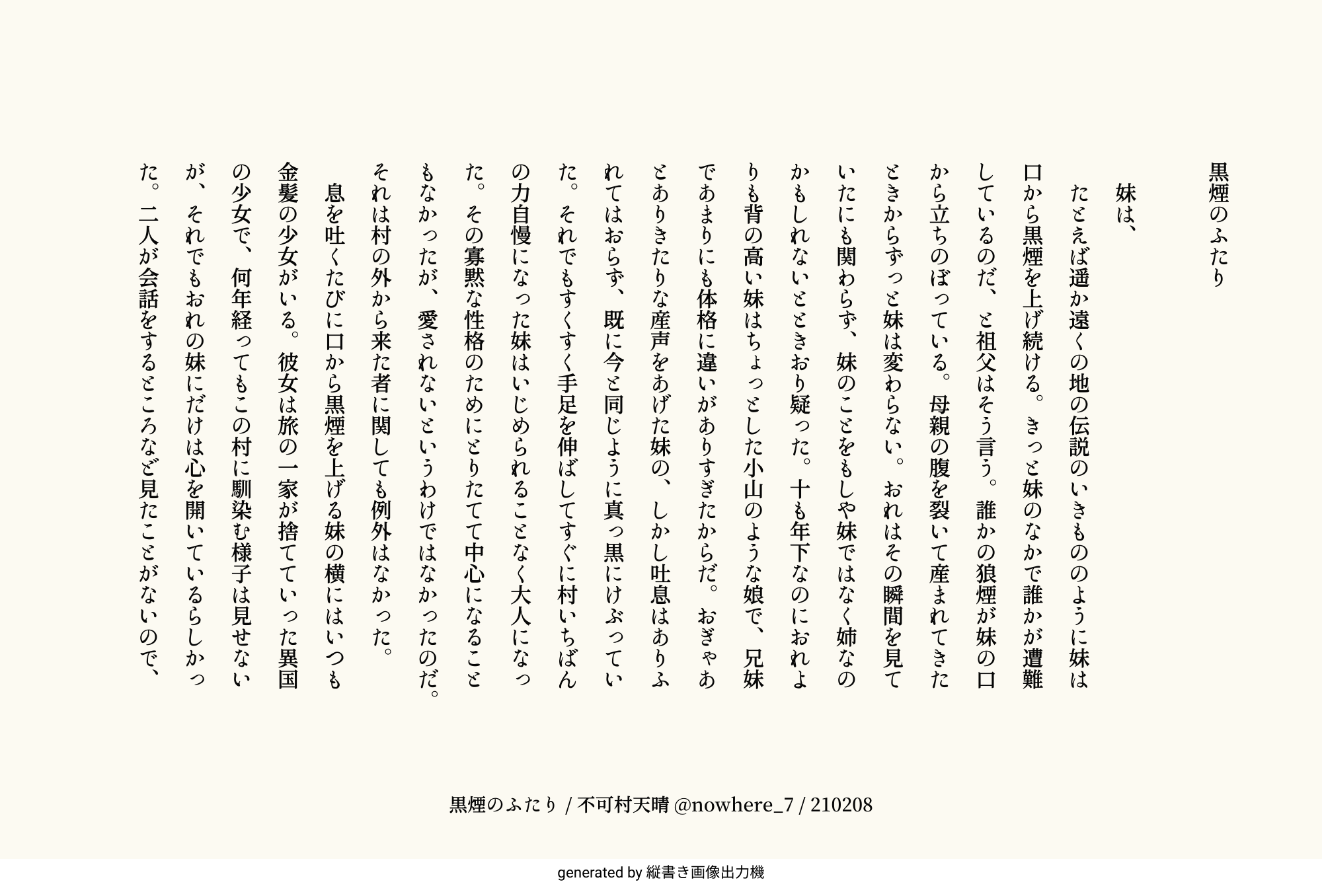
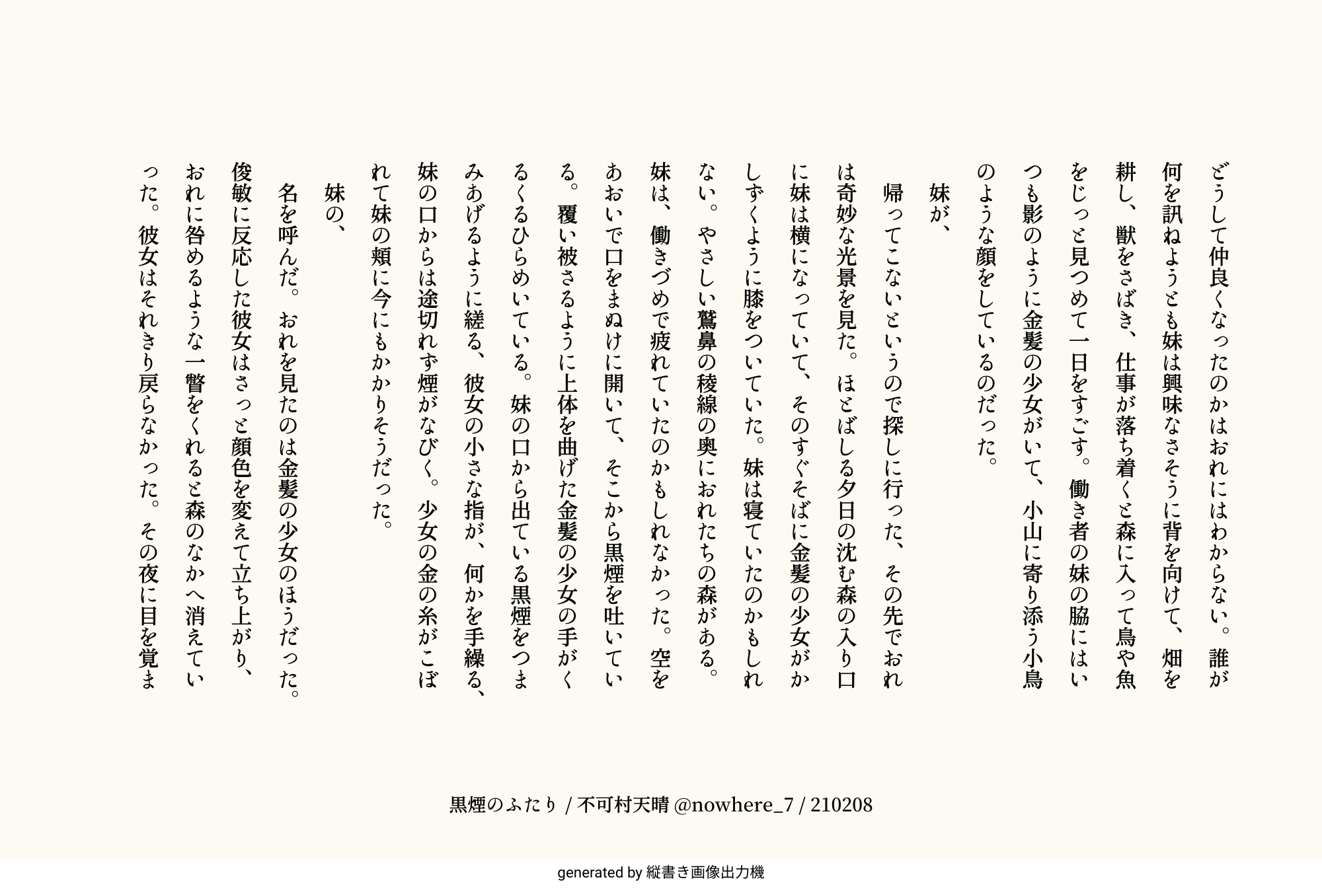
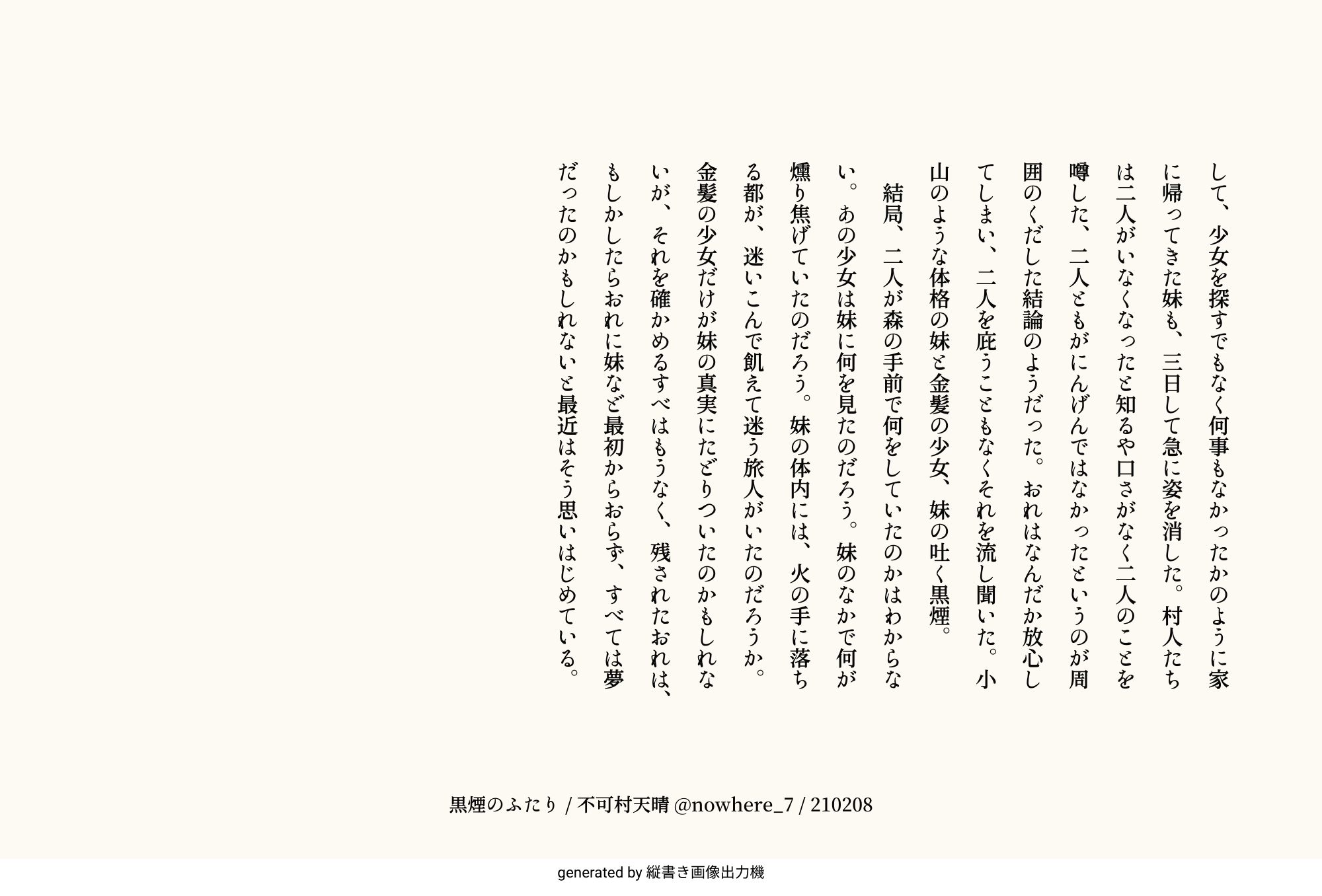
妹は、
たとえば遥か遠くの地の伝説のいきもののように口から黒煙を上げ続ける。きっと妹のなかで誰かが遭難しているのだ、と祖父はそう言う。誰かの狼煙が妹の口から立ちのぼっている。母親の腹を裂いて産まれてきたときからずっと妹は変わらない。おれはその瞬間を見ていたにも関わらず、妹のことをもしや妹ではなく姉なのかもしれないとときおり疑った。十も年下なのにおれよりも背の高い妹はちょっとした小山のような娘で、兄妹であまりにも体格に違いがありすぎたからだ。おぎゃあとありきたりな産声をあげた妹の、しかし吐息はありふれてはおらず、既に今と同じように真っ黒にけぶっていた。それでもすくすく手足を伸ばしてすぐに村いちばんの力自慢になった妹はいじめられることなく大人になった。その寡黙な性格のためにとりたてて中心になることもなかったが、愛されないというわけではなかったのだ。それは村の外から来た者に関しても例外はなかった。
息を吐くたびに口から黒煙を上げる妹の横にはいつも金髪の少女がいる。彼女は旅の一家が捨てていった異国の少女で、何年経ってもこの村に馴染む様子は見せないが、それでもおれの妹にだけは心を開いているらしかった。二人が会話をするところなど見たことがないので、どうして仲良くなったのかはおれにはわからない。誰が何を訊ねようとも妹は興味なさそうに背を向けて、畑を耕し、獣をさばき、仕事が落ち着くと森に入って鳥や魚をじっと見つめて一日をすごす。働き者の妹の脇にはいつも影のように金髪の少女がいて、小山に寄り添う小鳥のような顔をしているのだった。
妹が、
帰ってこないというので探しに行った、その先でおれは奇妙な光景を見た。ほとばしる夕日の沈む森の入り口に妹は横になっていて、そのすぐそばに金髪の少女がかしずくように膝をついていた。妹は寝ていたのかもしれない。やさしい鷲鼻の稜線の奥におれたちの森がある。妹は、働きづめで疲れていたのかもしれなかった。空をあおいで口をまぬけに開いて、そこから黒煙を吐いている。覆い被さるように上体を曲げた金髪の少女の手がくるくるひらめいている。妹の口から出ている黒煙をつまみあげるように縒る、彼女の小さな指が、何かを手繰る、妹の口からは途切れず煙がなびく。少女の金の糸がこぼれて妹の頬に今にもかかりそうだった。
妹の、
名を呼んだ。おれを見たのは金髪の少女のほうだった。俊敏に反応した彼女はさっと顔色を変えて立ち上がり、おれに咎めるような一瞥をくれると森のなかへ消えていった。彼女はそれきり戻らなかった。その夜に目を覚まして、少女を探すでもなく何事もなかったかのように家に帰ってきた妹も、三日して急に姿を消した。村人たちは二人がいなくなったと知るや口さがなく二人のことを噂した、二人ともがにんげんではなかったというのが周囲のくだした結論のようだった。おれはなんだか放心してしまい、二人を庇うこともなくそれを流し聞いた。小山のような体格の妹と金髪の少女、妹の吐く黒煙。
結局、二人が森の手前で何をしていたのかはわからない。あの少女は妹に何を見たのだろう。妹のなかで何が燻り焦げていたのだろう。妹の体内には、火の手に落ちる都が、迷いこんで飢えて迷う旅人がいたのだろうか。金髪の少女だけが妹の真実にたどりついたのかもしれないが、それを確かめるすべはもうなく、残されたおれは、もしかしたらおれに妹など最初からおらず、すべては夢だったのかもしれないと最近はそう思いはじめている。
黒煙のふたり 210208