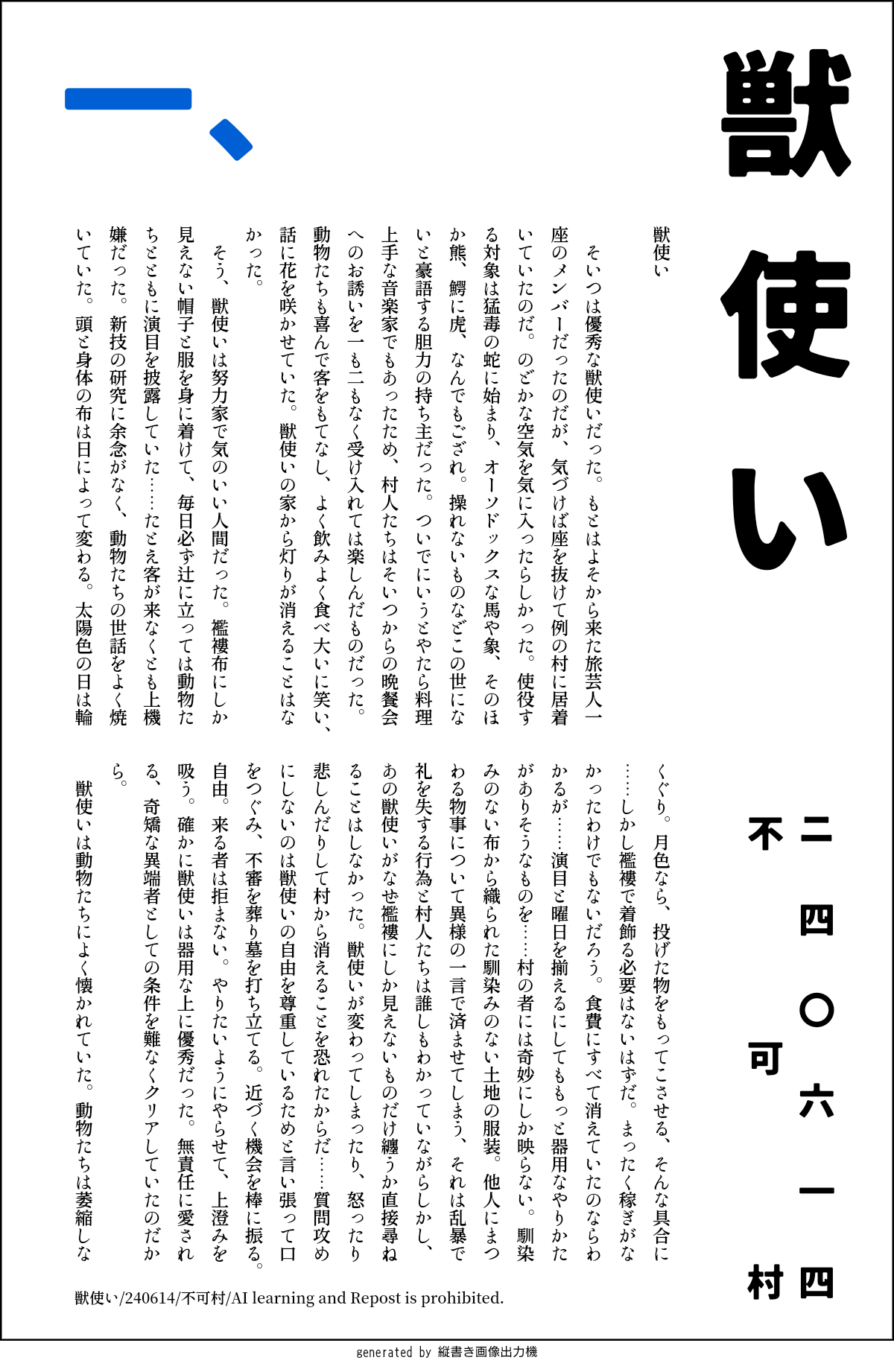
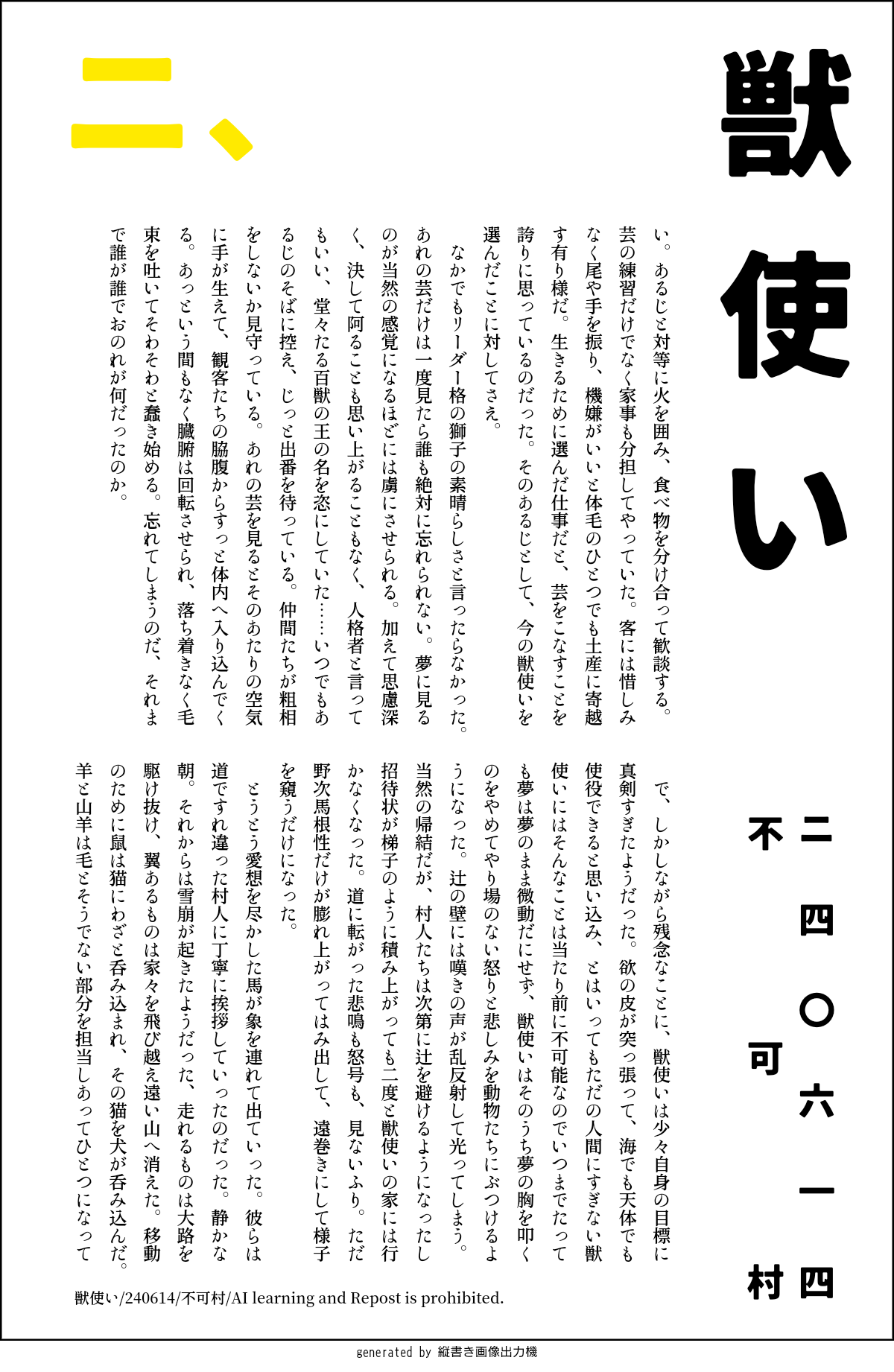
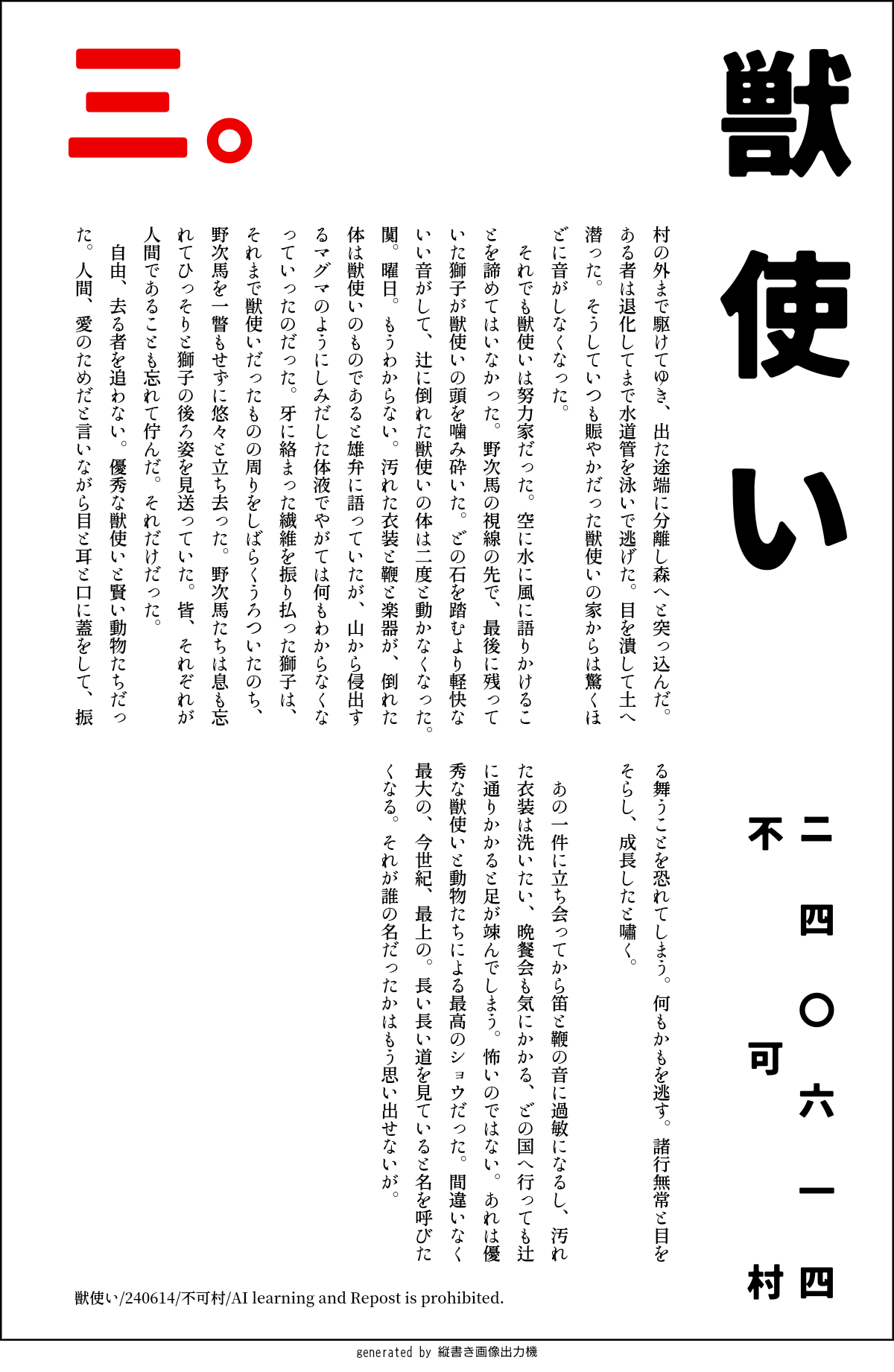
そいつは優秀な獣使いだった。もとはよそから来た旅芸人一座のメンバーだったのだが、気づけば座を抜けて例の村に居着いていたのだ。のどかな空気を気に入ったらしかった。使役する対象は猛毒の蛇に始まり、オーソドックスな馬や象、そのほか熊、鰐に虎、なんでもござれ。操れないものなどこの世にないと豪語する胆力の持ち主だった。ついでにいうとやたら料理上手な音楽家でもあったため、村人たちはそいつからの晩餐会へのお誘いを一も二もなく受け入れては楽しんだものだった。動物たちも喜んで客をもてなし、よく飲みよく食べ大いに笑い、話に花を咲かせていた。獣使いの家から灯りが消えることはなかった。
そう、獣使いは努力家で気のいい人間だった。襤褸布にしか見えない帽子と服を身に着けて、毎日必ず辻に立っては動物たちとともに演目を披露していた……たとえ客が来なくとも上機嫌だった。新技の研究に余念がなく、動物たちの世話をよく焼いていた。頭と身体の布は日によって変わる。太陽色の日は輪くぐり。月色なら、投げた物をもってこさせる、そんな具合に……しかし襤褸で着飾る必要はないはずだ。まったく稼ぎがなかったわけでもないだろう。食費にすべて消えていたのならわかるが……演目と曜日を揃えるにしてももっと器用なやりかたがありそうなものを……村の者には奇妙にしか映らない。馴染みのない布から織られた馴染みのない土地の服装。他人にまつわる物事について異様の一言で済ませてしまう、それは乱暴で礼を失する行為と村人たちは誰しもわかっていながらしかし、あの獣使いがなぜ襤褸にしか見えないものだけ纏うか直接尋ねることはしなかった。獣使いが変わってしまったり、怒ったり悲しんだりして村から消えることを恐れたからだ……質問攻めにしないのは獣使いの自由を尊重しているためと言い張って口をつぐみ、不審を葬り墓を打ち立てる。近づく機会を棒に振る。自由。来る者は拒まない。やりたいようにやらせて、上澄みを吸う。確かに獣使いは器用な上に優秀だった。無責任に愛される、奇矯な異端者としての条件を難なくクリアしていたのだから。
獣使いは動物たちによく懐かれていた。動物たちは萎縮しない。あるじと対等に火を囲み、食べ物を分け合って歓談する。芸の練習だけでなく家事も分担してやっていた。客には惜しみなく尾や手を振り、機嫌がいいと体毛のひとつでも土産に寄越す有り様だ。生きるために選んだ仕事だと、芸をこなすことを誇りに思っているのだった。そのあるじとして、今の獣使いを選んだことに対してさえ。
なかでもリーダー格の獅子の素晴らしさと言ったらなかった。あれの芸だけは一度見たら誰も絶対に忘れられない。夢に見るのが当然の感覚になるほどには虜にさせられる。加えて思慮深く、決して阿ることも思い上がることもなく、人格者と言ってもいい、堂々たる百獣の王の名を恣にしていた……いつでもあるじのそばに控え、じっと出番を待っている。仲間たちが粗相をしないか見守っている。あれの芸を見るとそのあたりの空気に手が生えて、観客たちの脇腹からすっと体内へ入り込んでくる。あっという間もなく臓腑は回転させられ、落ち着きなく毛束を吐いてそわそわと蠢き始める。忘れてしまうのだ、それまで誰が誰でおのれが何だったのか。
で、しかしながら残念なことに、獣使いは少々自身の目標に真剣すぎたようだった。欲の皮が突っ張って、海でも天体でも使役できると思い込み、とはいってもただの人間にすぎない獣使いにはそんなことは当たり前に不可能なのでいつまでたっても夢は夢のまま微動だにせず、獣使いはそのうち夢の胸を叩くのをやめてやり場のない怒りと悲しみを動物たちにぶつけるようになった。辻の壁には嘆きの声が乱反射して光ってしまう。当然の帰結だが、村人たちは次第に辻を避けるようになったし招待状が梯子のように積み上がっても二度と獣使いの家には行かなくなった。道に転がった悲鳴も怒号も、見ないふり。ただ野次馬根性だけが膨れ上がってはみ出して、遠巻きにして様子を窺うだけになった。
とうとう愛想を尽かした馬が象を連れて出ていった。彼らは道ですれ違った村人に丁寧に挨拶していったのだった。静かな朝。それからは雪崩が起きたようだった、走れるものは大路を駆け抜け、翼あるものは家々を飛び越え遠い山へ消えた。移動のために鼠は猫にわざと呑み込まれ、その猫を犬が呑み込んだ。羊と山羊は毛とそうでない部分を担当しあってひとつになって村の外まで駆けてゆき、出た途端に分離し森へと突っ込んだ。ある者は退化してまで水道管を泳いで逃げた。目を潰して土へ潜った。そうしていつも賑やかだった獣使いの家からは驚くほどに音がしなくなった。
それでも獣使いは努力家だった。空に水に風に語りかけることを諦めてはいなかった。野次馬の視線の先で、最後に残っていた獅子が獣使いの頭を噛み砕いた。どの石を踏むより軽快ないい音がして、辻に倒れた獣使いの体は二度と動かなくなった。闃。曜日。もうわからない。汚れた衣装と鞭と楽器が、倒れた体は獣使いのものであると雄弁に語っていたが、山から侵出するマグマのようにしみだした体液でやがては何もわからなくなっていったのだった。牙に絡まった繊維を振り払った獅子は、それまで獣使いだったものの周りをしばらくうろついたのち、野次馬を一瞥もせずに悠々と立ち去った。野次馬たちは息も忘れてひっそりと獅子の後ろ姿を見送っていた。皆、それぞれが人間であることも忘れて佇んだ。それだけだった。
自由、去る者を追わない。優秀な獣使いと賢い動物たちだった。人間、愛のためだと言いながら目と耳と口に蓋をして、振る舞うことを恐れてしまう。何もかもを逃す。諸行無常と目をそらし、成長したと嘯く。
あの一件に立ち会ってから笛と鞭の音に過敏になるし、汚れた衣装は洗いたい、晩餐会も気にかかる、どの国へ行っても辻に通りかかると足が竦んでしまう。怖いのではない。あれは優秀な獣使いと動物たちによる最高のショウだった。間違いなく最大の、今世紀、最上の。長い長い道を見ていると名を呼びたくなる。それが誰の名だったかはもう思い出せないが。
獣使い/240614/不可村/AI learning and Repost is prohibited.