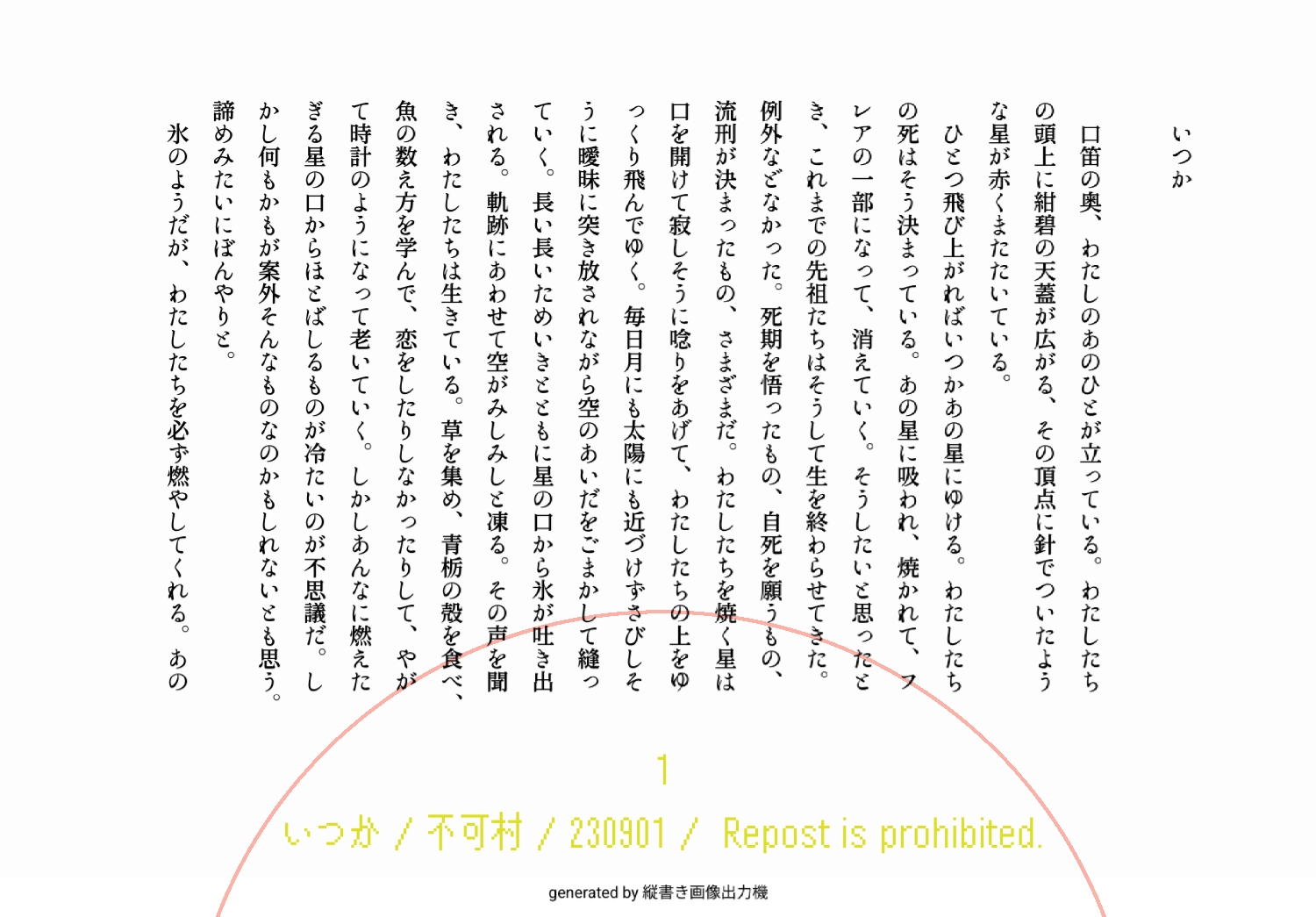
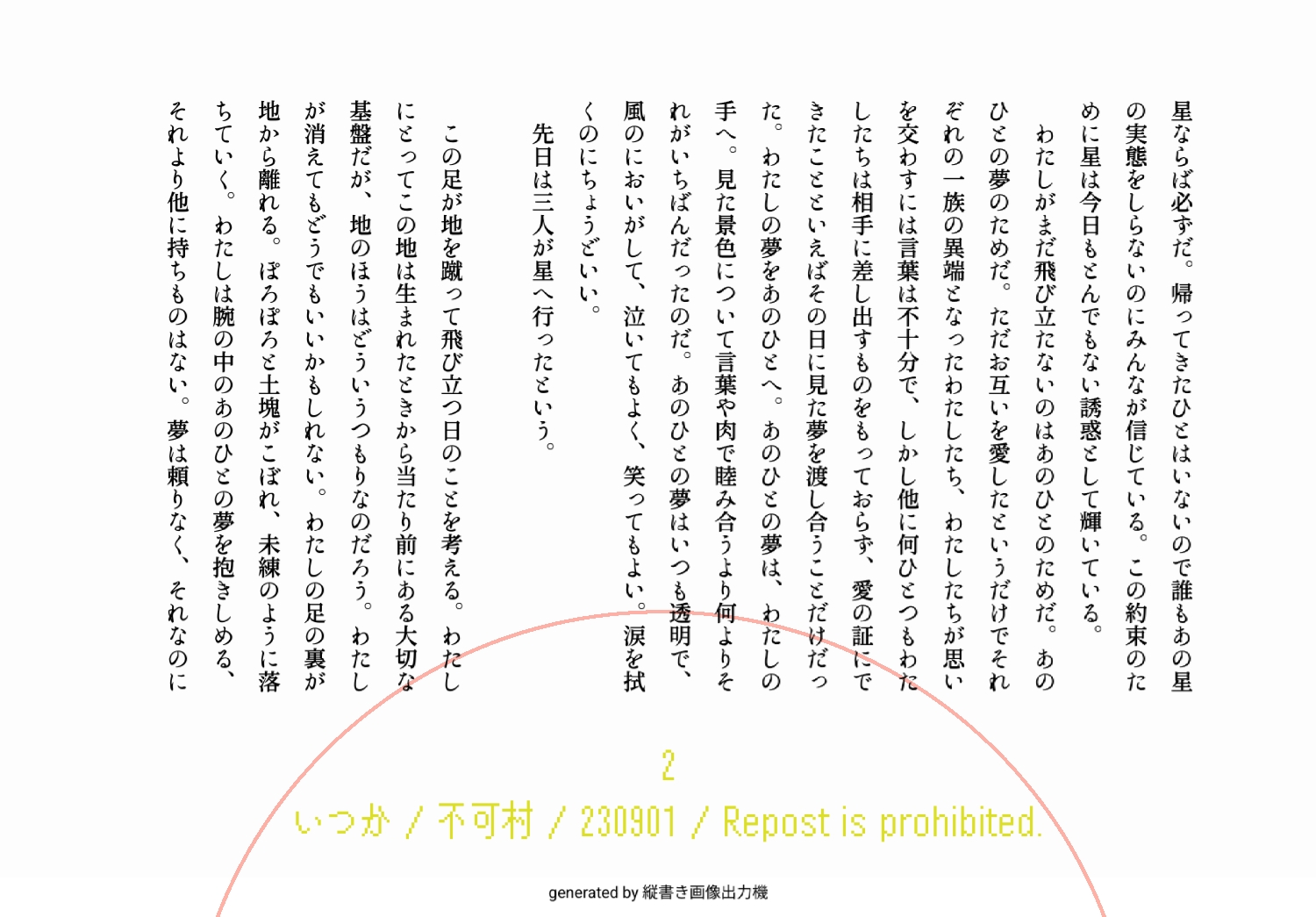
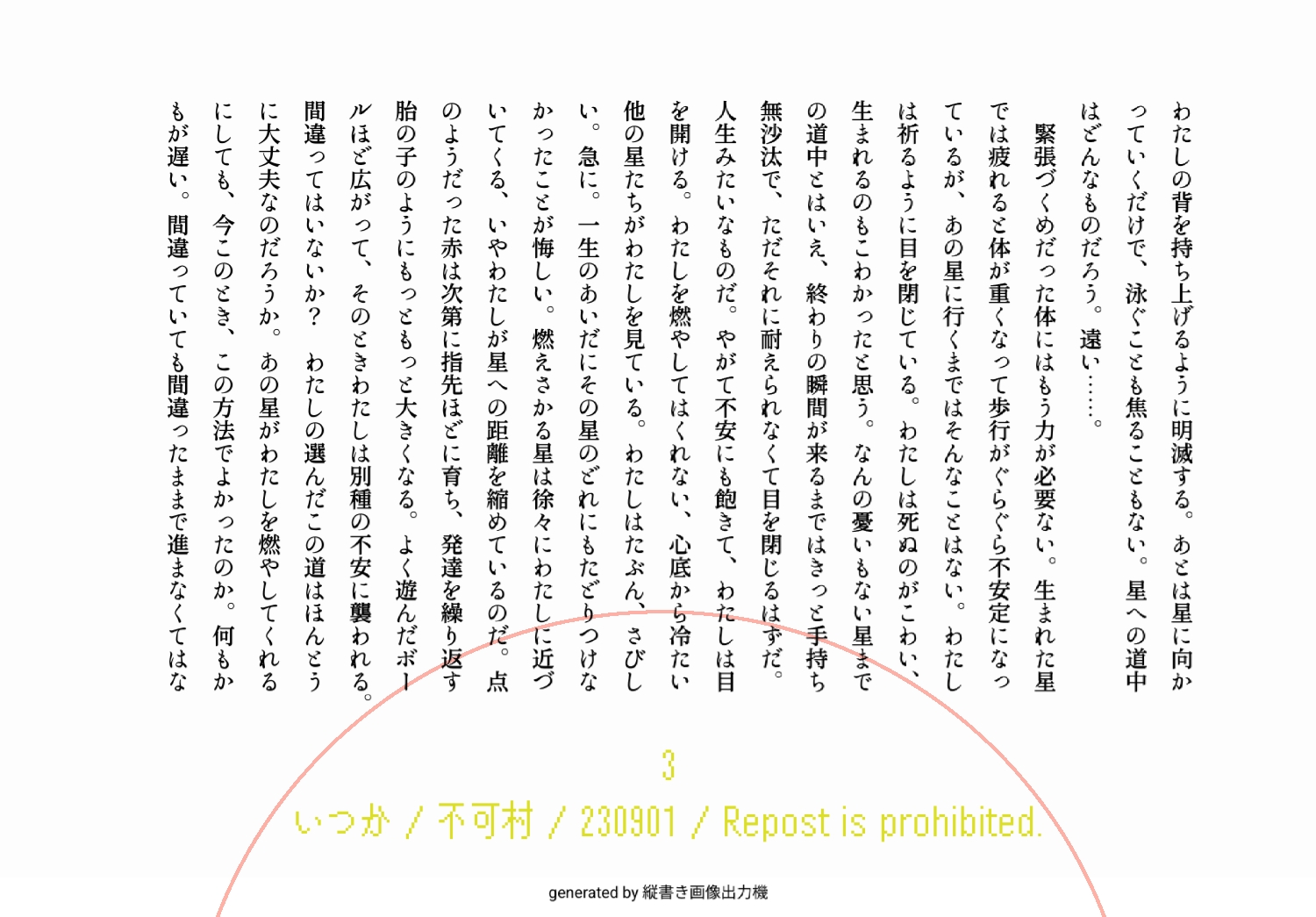
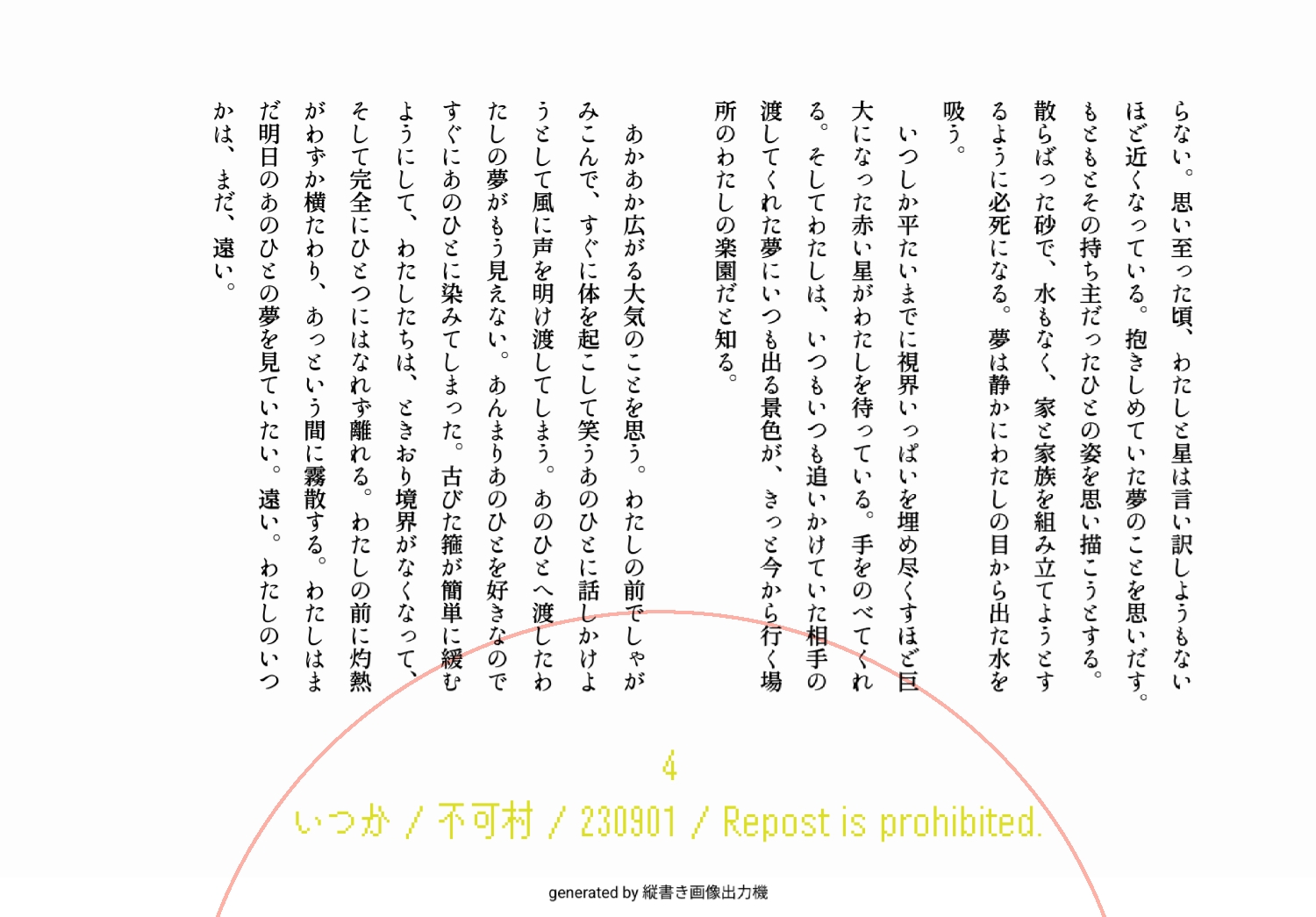
口笛の奥、わたしのあのひとが立っている。わたしたちの頭上に紺碧の天蓋が広がる、その頂点に針でついたような星が赤くまたたいている。
ひとつ飛び上がればいつかあの星にゆける。わたしたちの死はそう決まっている。あの星に吸われ、焼かれて、フレアの一部になって、消えていく。そうしたいと思ったとき、これまでの先祖たちはそうして生を終わらせてきた。例外などなかった。死期を悟ったもの、自死を願うもの、流刑が決まったもの、さまざまだ。わたしたちを焼く星は口を開けて寂しそうに唸りをあげて、わたしたちの上をゆっくり飛んでゆく。毎日月にも太陽にも近づけずさびしそうに曖昧に突き放されながら空のあいだをごまかして縫っていく。長い長いためいきとともに星の口から氷が吐き出される。軌跡にあわせて空がみしみしと凍る。その声を聞き、わたしたちは生きている。草を集め、青栃の殻を食べ、魚の数え方を学んで、恋をしたりしなかったりして、やがて時計のようになって老いていく。しかしあんなに燃えたぎる星の口からほとばしるものが冷たいのが不思議だ。しかし何もかもが案外そんなものなのかもしれないとも思う。諦めみたいにぼんやりと。
氷のようだが、わたしたちを必ず燃やしてくれる。あの星ならば必ずだ。帰ってきたひとはいないので誰もあの星の実態をしらないのにみんなが信じている。この約束のために星は今日もとんでもない誘惑として輝いている。
わたしがまだ飛び立たないのはあのひとのためだ。あのひとの夢のためだ。ただお互いを愛したというだけでそれぞれの一族の異端となったわたしたち、わたしたちが思いを交わすには言葉は不十分で、しかし他に何ひとつもわたしたちは相手に差し出すものをもっておらず、愛の証にできたことといえばその日に見た夢を渡し合うことだけだった。わたしの夢をあのひとへ。あのひとの夢は、わたしの手へ。見た景色について言葉や肉で睦み合うより何よりそれがいちばんだったのだ。あのひとの夢はいつも透明で、風のにおいがして、泣いてもよく、笑ってもよい。涙を拭くのにちょうどいい。
先日は三人が星へ行ったという。
この足が地を蹴って飛び立つ日のことを考える。わたしにとってこの地は生まれたときから当たり前にある大切な基盤だが、地のほうはどういうつもりなのだろう。わたしが消えてもどうでもいいかもしれない。わたしの足の裏が地から離れる。ぽろぽろと土塊がこぼれ、未練のように落ちていく。わたしは腕の中のあのひとの夢を抱きしめる、それより他に持ちものはない。夢は頼りなく、それなのにわたしの背を持ち上げるように明滅する。あとは星に向かっていくだけで、泳ぐことも焦ることもない。星への道中はどんなものだろう。遠い……。
緊張づくめだった体にはもう力が必要ない。生まれた星では疲れると体が重くなって歩行がぐらぐら不安定になっているが、あの星に行くまではそんなことはない。わたしは祈るように目を閉じている。わたしは死ぬのがこわい、生まれるのもこわかったと思う。なんの憂いもない星までの道中とはいえ、終わりの瞬間が来るまではきっと手持ち無沙汰で、ただそれに耐えられなくて目を閉じるはずだ。人生みたいなものだ。やがて不安にも飽きて、わたしは目を開ける。わたしを燃やしてはくれない、心底から冷たい他の星たちがわたしを見ている。わたしはたぶん、さびしい。急に。一生のあいだにその星のどれにもたどりつけなかったことが悔しい。燃えさかる星は徐々にわたしに近づいてくる、いやわたしが星への距離を縮めているのだ。点のようだった赤は次第に指先ほどに育ち、発達を繰り返す胎の子のようにもっともっと大きくなる。よく遊んだボールほど広がって、そのときわたしは別種の不安に襲われる。間違ってはいないか? わたしの選んだこの道はほんとうに大丈夫なのだろうか。あの星がわたしを燃やしてくれるにしても、今このとき、この方法でよかったのか。何もかもが遅い。間違っていても間違ったままで進まなくてはならない。思い至った頃、わたしと星は言い訳しようもないほど近くなっている。抱きしめていた夢のことを思いだす。もともとその持ち主だったひとの姿を思い描こうとする。散らばった砂で、水もなく、家と家族を組み立てようとするように必死になる。夢は静かにわたしの目から出た水を吸う。
いつしか平たいまでに視界いっぱいを埋め尽くすほど巨大になった赤い星がわたしを待っている。手をのべてくれる。そしてわたしは、いつもいつも追いかけていた相手の渡してくれた夢にいつも出る景色が、きっと今から行く場所のわたしの楽園だと知る。
あかあか広がる大気のことを思う。わたしの前でしゃがみこんで、すぐに体を起こして笑うあのひとに話しかけようとして風に声を明け渡してしまう。あのひとへ渡したわたしの夢がもう見えない。あんまりあのひとを好きなのですぐにあのひとに染みてしまった。古びた箍が簡単に緩むようにして、わたしたちは、ときおり境界がなくなって、そして完全にひとつにはなれず離れる。わたしの前に灼熱がわずか横たわり、あっという間に霧散する。わたしはまだ明日のあのひとの夢を見ていたい。遠い。わたしのいつかは、まだ、遠い。
いつか / 不可村 / 230901 / Repost is prohibited.