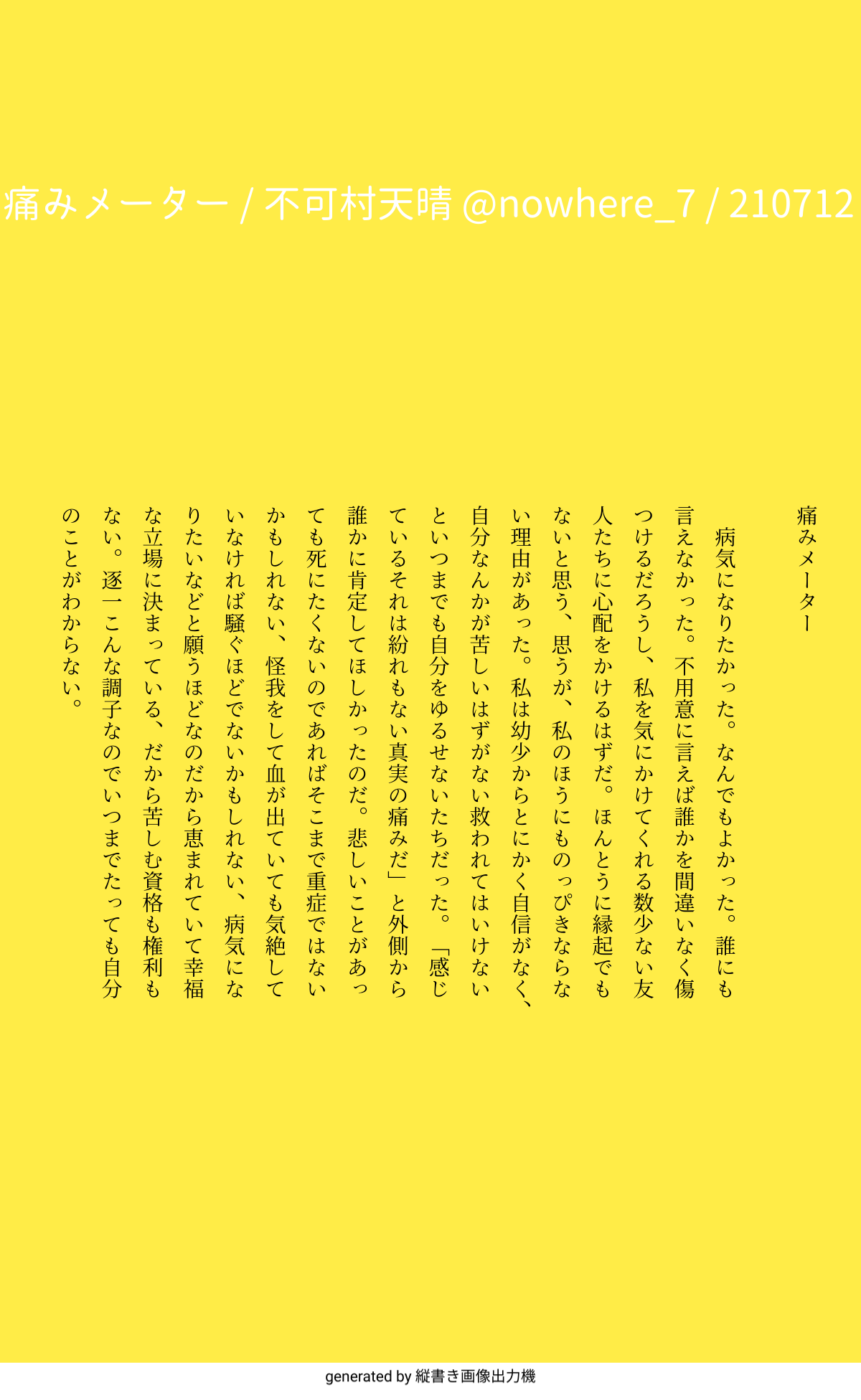
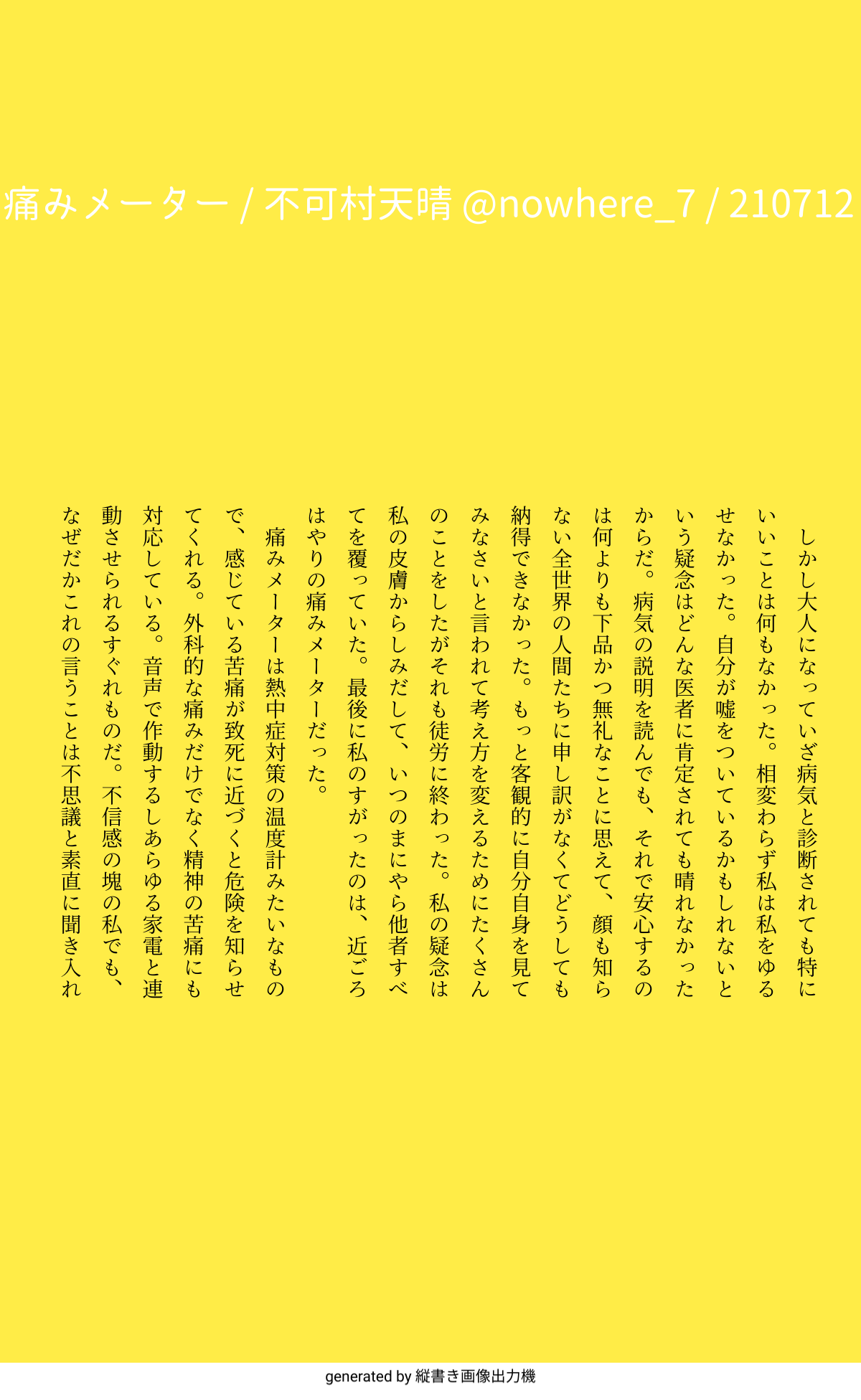
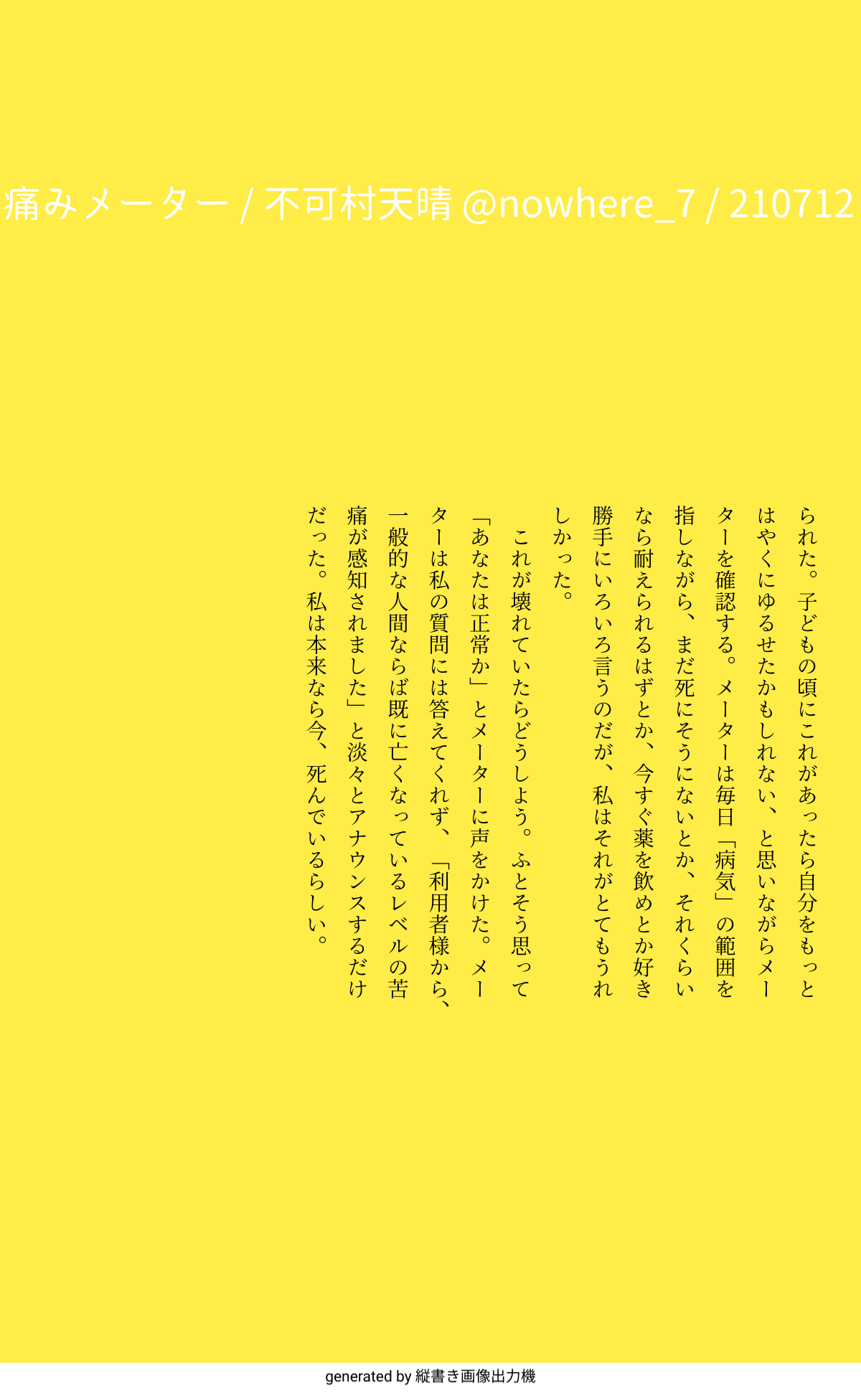
病気になりたかった。なんでもよかった。誰にも言えなかった。不用意に言えば誰かを間違いなく傷つけるだろうし、私を気にかけてくれる数少ない友人たちに心配をかけるはずだ。ほんとうに縁起でもないと思う、思うが、私のほうにものっぴきならない理由がある。私は幼少からとにかく自信がなく、自分なんかが苦しいはずがない救われてはいけないといつまでも自分をゆるせないたちだった。「感じているそれは紛れもない真実の痛みだ」と外側から誰かに肯定してほしかったのだ。悲しいことがあっても死にたくないのであればそこまで重症ではないかもしれない、怪我をして血が出ていても気絶していなければ騒ぐほどでないかもしれない、病気になりたいなどと願うほどなのだから恵まれていて幸福な立場に決まっている、だから苦しむ資格も権利もない。逐一こんな調子なのでいつまでたっても自分のことがわからない。
しかし大人になっていざ病気と診断されても特にいいことは何もなかった。相変わらず私は私をゆるせなかった。自分が嘘をついているかもしれないという疑念はどんな医者に肯定されても晴れなかったからだ。病気の説明を読んでも、それで安心するのは何よりも下品かつ無礼なことに思えて、顔も知らない全世界の人間たちに申し訳がなくてどうしても納得できなかった。もっと客観的に自分自身を見てみなさいと言われて考え方を変えるためにたくさんのことをしたがそれも徒労に終わった。私の疑念は私の皮膚からしみだして、いつのまにやら他者すべてを覆っていた。最後に私のすがったのは、近頃はやりの痛みメーターだった。
痛みメーターは熱中症対策の温度計みたいなもので、感じている苦痛が致死に近づくと危険を知らせてくれる。外科的な痛みだけでなく精神の苦痛にも対応している。音声で作動するしあらゆる家電と連動させられるすぐれものだ。不信感の塊の私でも、なぜだかこれの言うことは不思議と素直に聞き入れられた。子どもの頃にこれがあったら自分をもっとはやくにゆるせたかもしれない、と思いながらメーターを確認する。メーターは毎日「病気」の範囲を指しながら、まだ死にそうにないとか、それくらいなら耐えられるはずとか、今すぐ薬を飲めとか好き勝手にいろいろ言うのだが、私はそれがとてもうれしかった。
これが壊れていたらどうしよう。ふとそう思って「あなたは正常か」とメーターに声をかけた。メーターは私の質問には答えてくれず、「利用者様から、一般的な人間ならば既に亡くなっているレベルの苦痛が感知されました」と淡々とアナウンスするだけだった。私は本来なら今、死んでいるらしい。
痛みメーター 210712