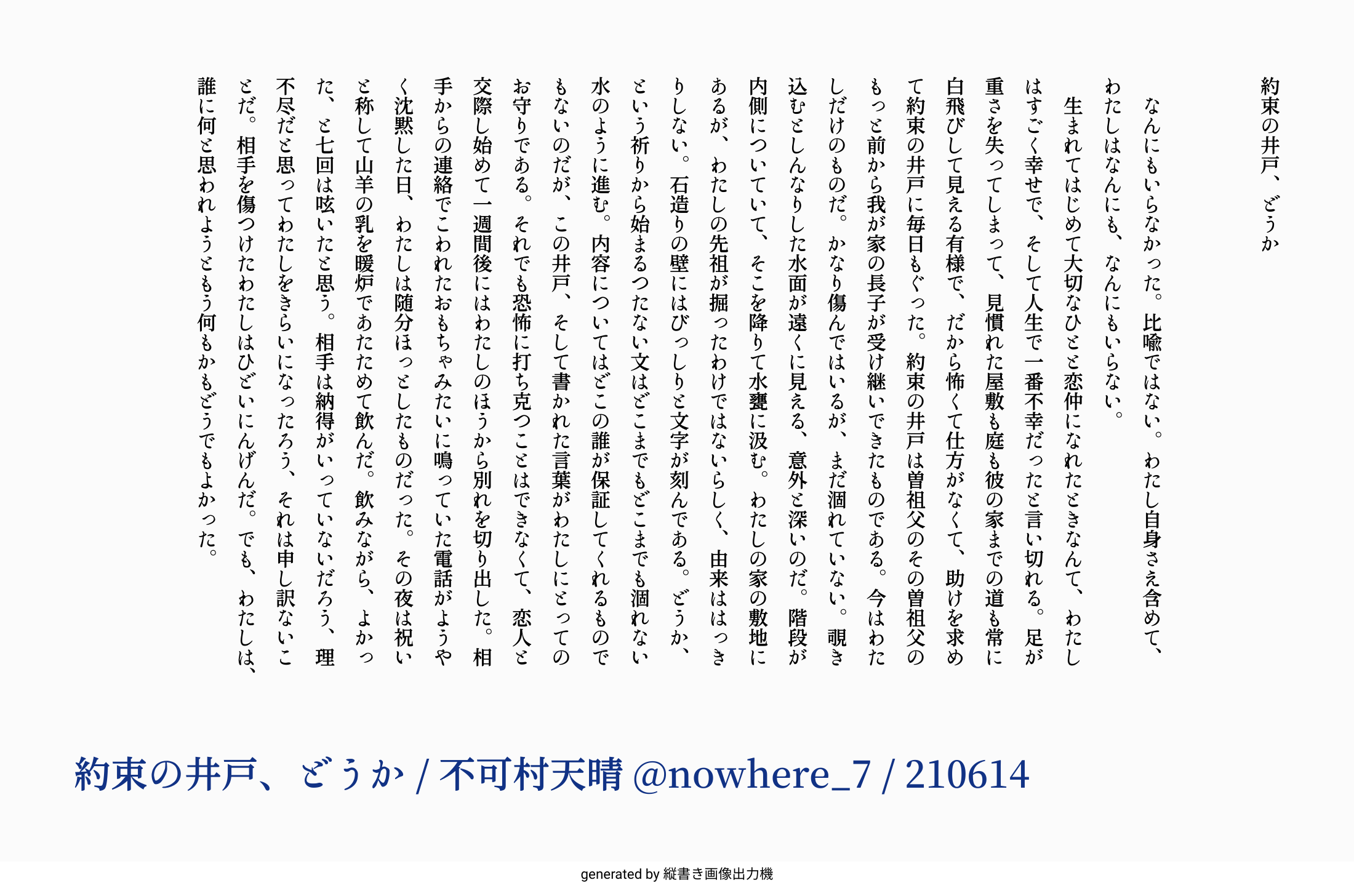
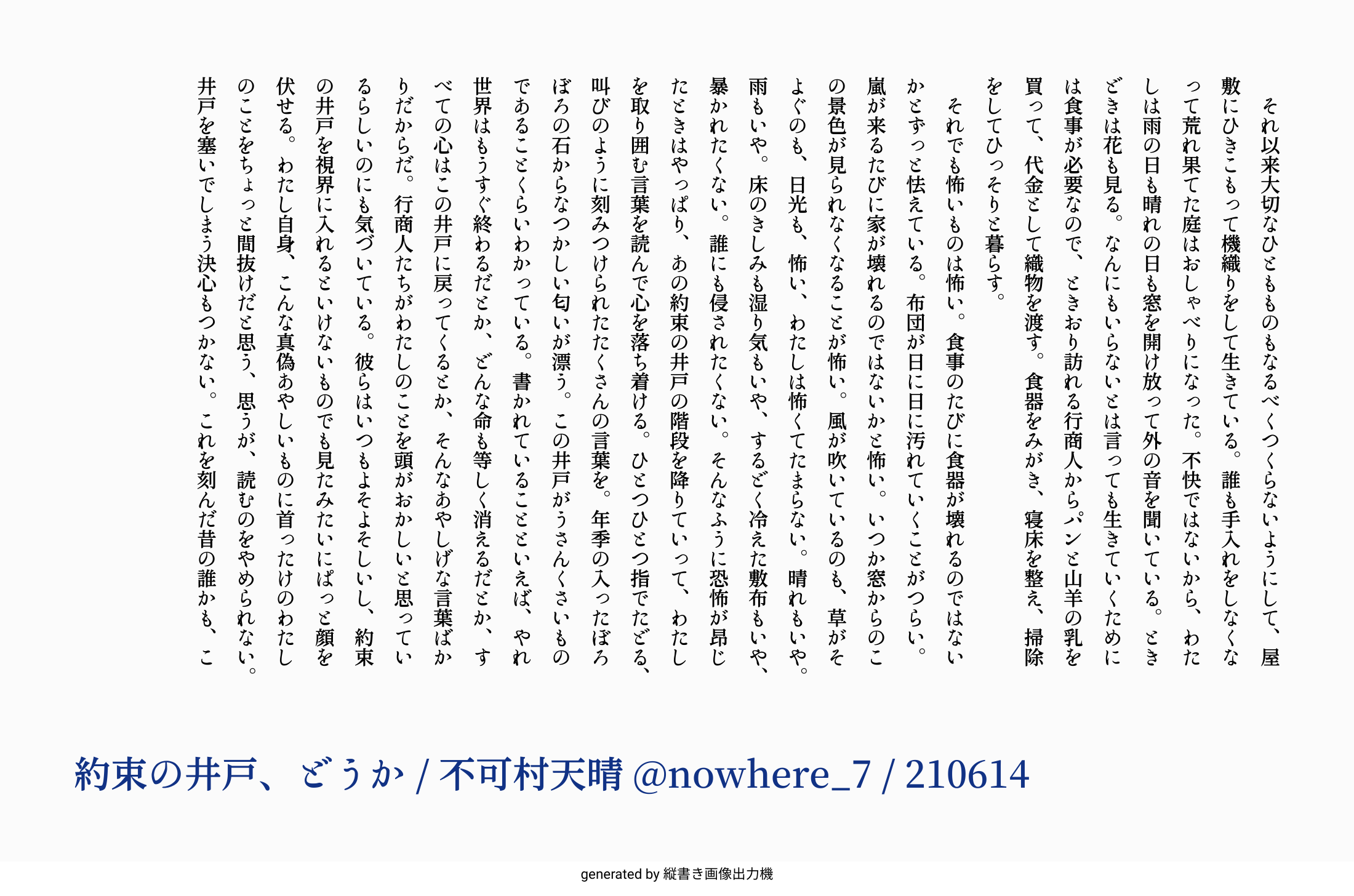
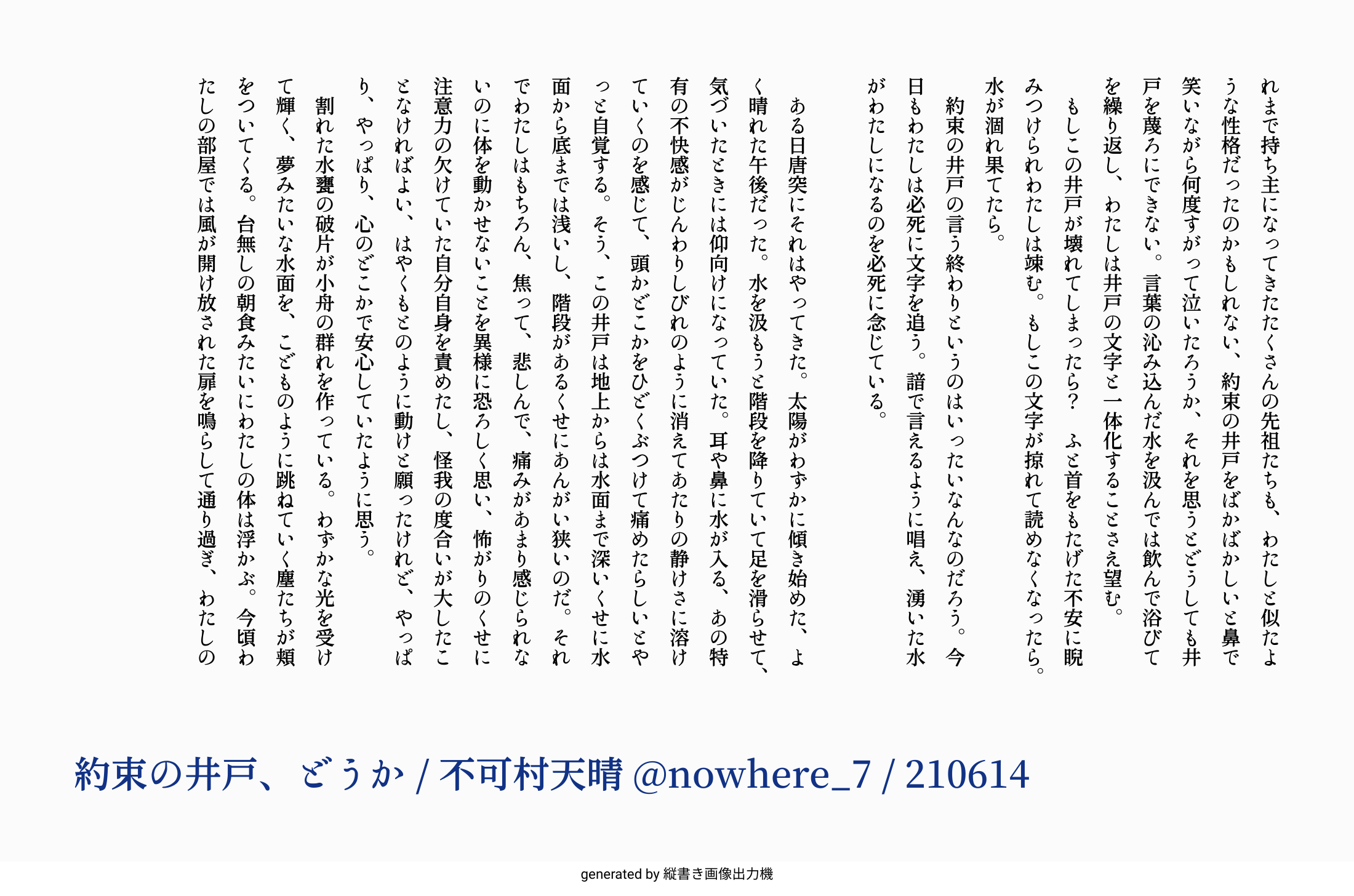
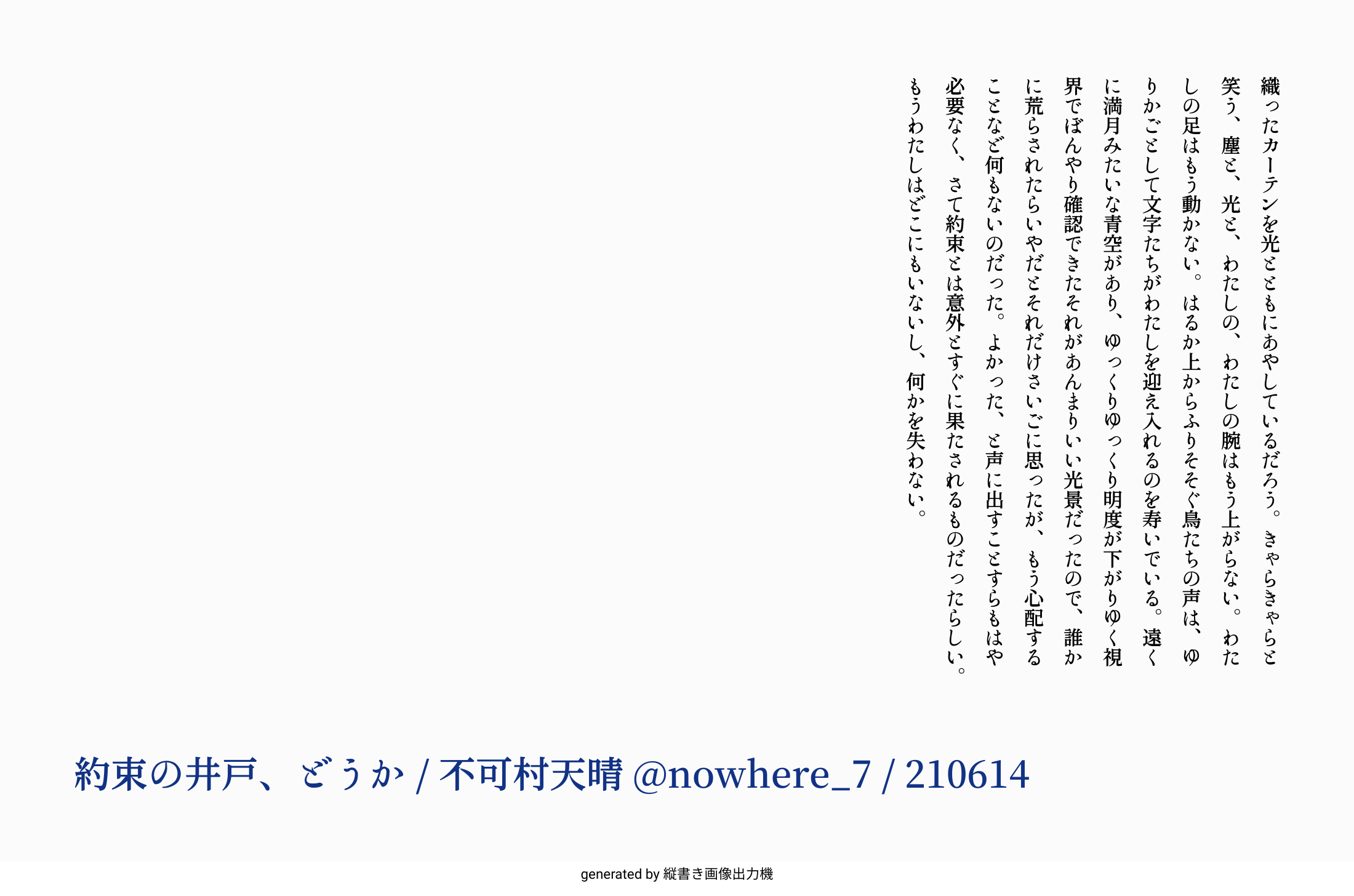
なんにもいらなかった。比喩ではない。わたし自身さえ含めて、わたしはなんにも、なんにもいらない。
生まれてはじめて大切なひとと恋仲になれたときなんて、わたしはすごく幸せで、そして人生で一番不幸だったと言い切れる。足が重さを失ってしまって、見慣れた屋敷も庭も彼の家までの道も常に白飛びして見える有様で、だから怖くて仕方がなくて、助けを求めて約束の井戸に毎日もぐった。約束の井戸は曽祖父のその曽祖父のもっと前から我が家の長子が受け継いできたものである。今はわたしだけのものだ。かなり傷んではいるが、まだ涸れていない。覗き込むとしんなりした水面が遠くに見える、意外と深いのだ。階段が内側についていて、そこを降りて水甕に汲む。わたしの家の敷地にあるが、わたしの先祖が掘ったわけではないらしく、由来ははっきりしない。石造りの壁にはびっしりと文字が刻んである。どうか、という祈りから始まるつたない文はどこまでもどこまでも涸れない水のように進む。内容についてはどこの誰が保証してくれるものでもないのだが、この井戸、そして書かれた言葉がわたしにとってのお守りである。それでも恐怖に打ち克つことはできなくて、恋人と交際し始めて一週間後にはわたしのほうから別れを切り出した。相手からの連絡でこわれたおもちゃみたいに鳴っていた電話がようやく沈黙した日、わたしは随分ほっとしたものだった。その夜は祝いと称して山羊の乳を暖炉であたためて飲んだ。飲みながら、よかった、と七回は呟いたと思う。相手は納得がいっていないだろう、理不尽だと思ってわたしをきらいになったろう、それは申し訳ないことだ。相手を傷つけたわたしはひどいにんげんだ。でも、わたしは、誰に何と思われようともう何もかもどうでもよかった。
それ以来大切なひともものもなるべくつくらないようにして、屋敷にひきこもって機織りをして生きている。誰も手入れをしなくなって荒れ果てた庭はおしゃべりになった。不快ではないから、わたしは雨の日も晴れの日も窓を開け放って外の音を聞いている。ときどきは花も見る。なんにもいらないとは言っても生きていくためには食事が必要なので、ときおり訪れる行商人からパンと山羊の乳を買って、代金として織物を渡す。食器をみがき、寝床を整え、掃除をしてひっそりと暮らす。
それでも怖いものは怖い。食事のたびに食器が壊れるのではないかとずっと怯えている。布団が日に日に汚れていくことがつらい。嵐が来るたびに家が壊れるのではないかと怖い。いつか窓からのこの景色が見られなくなることが怖い。風が吹いているのも、草がそよぐのも、日光も、怖い、わたしは怖くてたまらない。晴れもいや。雨もいや。床のきしみも湿り気もいや、するどく冷えた敷布もいや、暴かれたくない。誰にも侵されたくない。そんなふうに恐怖が昂じたときはやっぱり、あの約束の井戸の階段を降りていって、わたしを取り囲む言葉を読んで心を落ち着ける。ひとつひとつ指でたどる、叫びのように刻みつけられたたくさんの言葉を。年季の入ったぼろぼろの石からなつかしい匂いが漂う。この井戸がうさんくさいものであることくらいわかっている。書かれていることといえば、やれ世界はもうすぐ終わるだとか、どんな命も等しく消えるだとか、すべての心はこの井戸に戻ってくるとか、そんなあやしげな言葉ばかりだからだ。行商人たちがわたしのことを頭がおかしいと思っているらしいのにも気づいている。彼らはいつもよそよそしいし、約束の井戸を視界に入れるといけないものでも見たみたいにぱっと顔を伏せる。わたし自身、こんな真偽あやしいものに首ったけのわたしのことをちょっと間抜けだと思う、思うが、読むのをやめられない。井戸を塞いでしまう決心もつかない。これを刻んだ昔の誰かも、これまで持ち主になってきたたくさんの先祖たちも、わたしと似たような性格だったのかもしれない、約束の井戸をばかばかしいと鼻で笑いながら何度すがって泣いたろうか、それを思うとどうしても井戸を蔑ろにできない。言葉の沁み込んだ水を汲んでは飲んで浴びてを繰り返し、わたしは井戸の文字と一体化することさえ望む。
もしこの井戸が壊れてしまったら? ふと首をもたげた不安に睨みつけられわたしは竦む。もしこの文字が掠れて読めなくなったら。水が涸れ果てたら。
約束の井戸の言う終わりというのはいったいなんなのだろう。今日もわたしは必死に文字を追う。諳で言えるように唱え、湧いた水がわたしになるのを必死に念じている。
ある日唐突にそれはやってきた。太陽がわずかに傾き始めた、よく晴れた午後だった。水を汲もうと階段を降りていて足を滑らせて、気づいたときには仰向けになっていた。耳や鼻に水が入る、あの特有の不快感がじんわりしびれのように消えてあたりの静けさに溶けていくのを感じて、頭かどこかをひどくぶつけて痛めたらしいとやっと自覚する。そう、この井戸は地上からは水面まで深いくせに水面から底までは浅いし、階段があるくせにあんがい狭いのだ。それでわたしはもちろん、焦って、悲しんで、痛みがあまり感じられないのに体を動かせないことを異様に恐ろしく思い、怖がりのくせに注意力の欠けていた自分自身を責めたし、怪我の度合いが大したことなければよい、はやくもとのように動けと願ったけれど、やっぱり、やっぱり、心のどこかで安心していたように思う。
割れた水甕の破片が小舟の群れを作っている。わずかな光を受けて輝く、夢みたいな水面を、こどものように跳ねていく塵たちが頬をついてくる。台無しの朝食みたいにわたしの体は浮かぶ。今頃わたしの部屋では風が開け放された扉を鳴らして通り過ぎ、わたしの織ったカーテンを光とともにあやしているだろう。きゃらきゃらと笑う、塵と、光と、わたしの、わたしの腕はもう上がらない。わたしの足はもう動かない。はるか上からふりそそぐ鳥たちの声は、ゆりかごとして文字たちがわたしを迎え入れるのを寿いでいる。遠くに満月みたいな青空があり、ゆっくりゆっくり明度が下がりゆく視界でぼんやり確認できたそれがあんまりいい光景だったので、誰かに荒らされたらいやだとそれだけさいごに思ったが、もう心配することなど何もないのだった。よかった、と声に出すことすらもはや必要なく、さて約束とは意外とすぐに果たされるものだったらしい。もうわたしはどこにもいないし、何かを失わない。
約束の井戸、どうか 210614