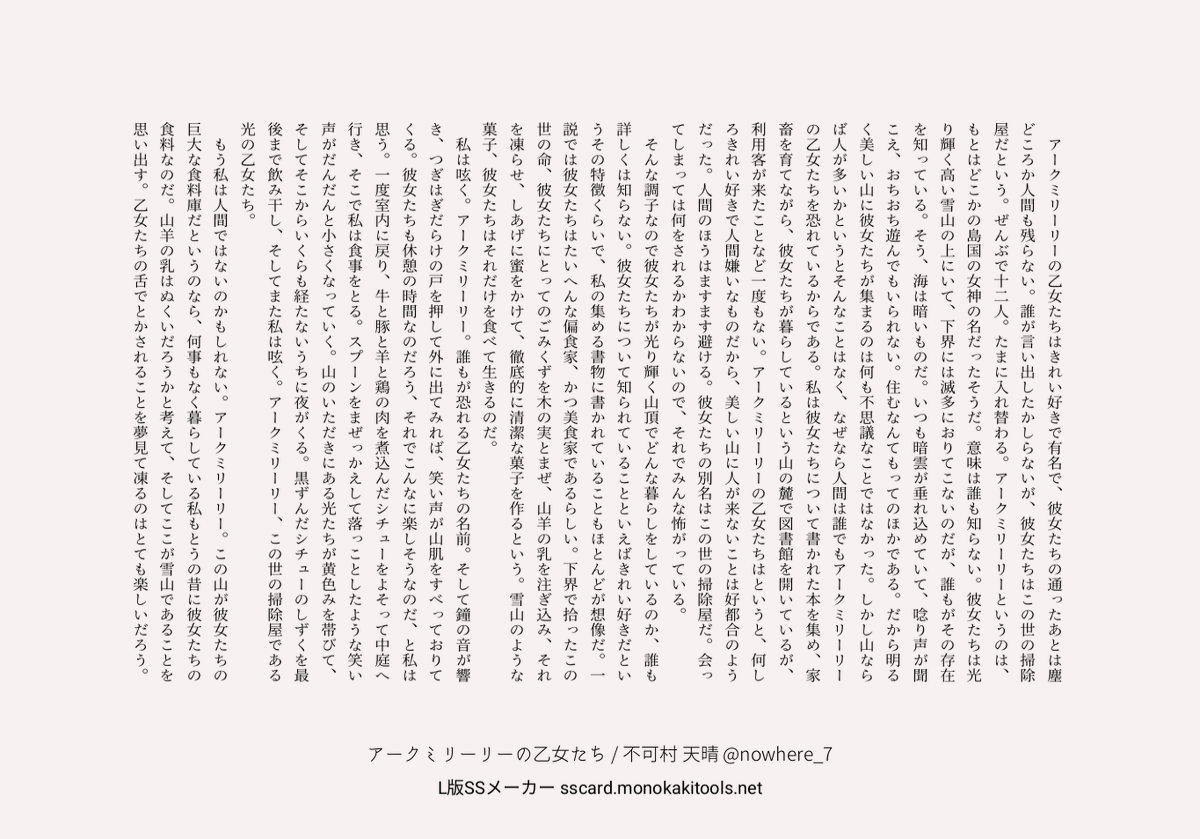
アークミリーリーの乙女たちはきれい好きで有名で、彼女たちの通ったあとは塵どころか人間も残らない。誰が言い出したかしらないが、彼女たちはこの世の掃除屋だという。ぜんぶで十二人。たまに入れ替わる。アークミリーリーというのは、もとはどこかの島国の女神の名だったそうだ。意味は誰も知らない。彼女たちは光り輝く高い雪山の上にいて、下界には滅多におりてこないのだが、誰もがその存在を知っている。そう、海は暗いものだ。いつも暗雲が垂れ込めていて、唸り声が聞こえ、おちおち遊んでもいられない。住むなんてもってのほかである。だから明るく美しい山に彼女たちが集まるのは何も不思議なことではなかった。しかし山ならば人が多いかというとそんなことはなく、なぜなら人間は誰でもアークミリーリーの乙女たちを恐れているからである。私は彼女たちについて書かれた本を集め、家畜を育てながら、彼女たちが暮らしているという山の麓で図書館を開いているが、利用客が来たことなど一度もない。アークミリーリーの乙女たちはというと、何しろきれい好きで人間嫌いなものだから、美しい山に人が来ないことは好都合のようだった。人間のほうはますます避ける。彼女たちの別名はこの世の掃除屋だ。会ってしまっては何をされるかわからないので、それでみんな怖がっている。
そんな調子なので彼女たちが光り輝く山頂でどんな暮らしをしているのか、誰も詳しくは知らない。彼女たちについて知られていることといえばきれい好きだというその特徴くらいで、私の集める書物に書かれていることもほとんどが想像だ。一説では彼女たちはたいへんな偏食家、かつ美食家であるらしい。下界で拾ったこの世の命、彼女たちにとってのごみくずを木の実とまぜ、山羊の乳を注ぎ込み、それを凍らせ、しあげに蜜をかけて、徹底的に清潔な菓子を作るという。雪山のような菓子、彼女たちはそれだけを食べて生きるのだ。
私は呟く。アークミリーリー。誰もが恐れる乙女たちの名前。そして鐘の音が響き、つぎはぎだらけの戸を押して外に出てみれば、笑い声が山肌をすべっておりてくる。彼女たちも休憩の時間なのだろう、それでこんなに楽しそうなのだ、と私は思う。一度室内に戻り、牛と豚と羊と鶏の肉を煮込んだシチューをよそって中庭へ行き、そこで私は食事をとる。スプーンをまぜっかえして落っことしたような笑い声がだんだんと小さくなっていく。山のいただきにある光たちが黄色みを帯びて、そしてそこからいくらも経たないうちに夜がくる。黒ずんだシチューのしずくを最後まで飲み干し、そしてまた私は呟く。アークミリーリー、この世の掃除屋である光の乙女たち。
もう私は人間ではないのかもしれない。アークミリーリー。この山が彼女たちの巨大な食料庫だというのなら、何事もなく暮らしている私もとうの昔に彼女たちの食料なのだ。山羊の乳はぬくいだろうかと考えて、そしてここが雪山であることを思い出す。乙女たちの舌でとかされることを夢見て凍るのはとても楽しいだろう。
アークミリーリーの乙女たち 191202