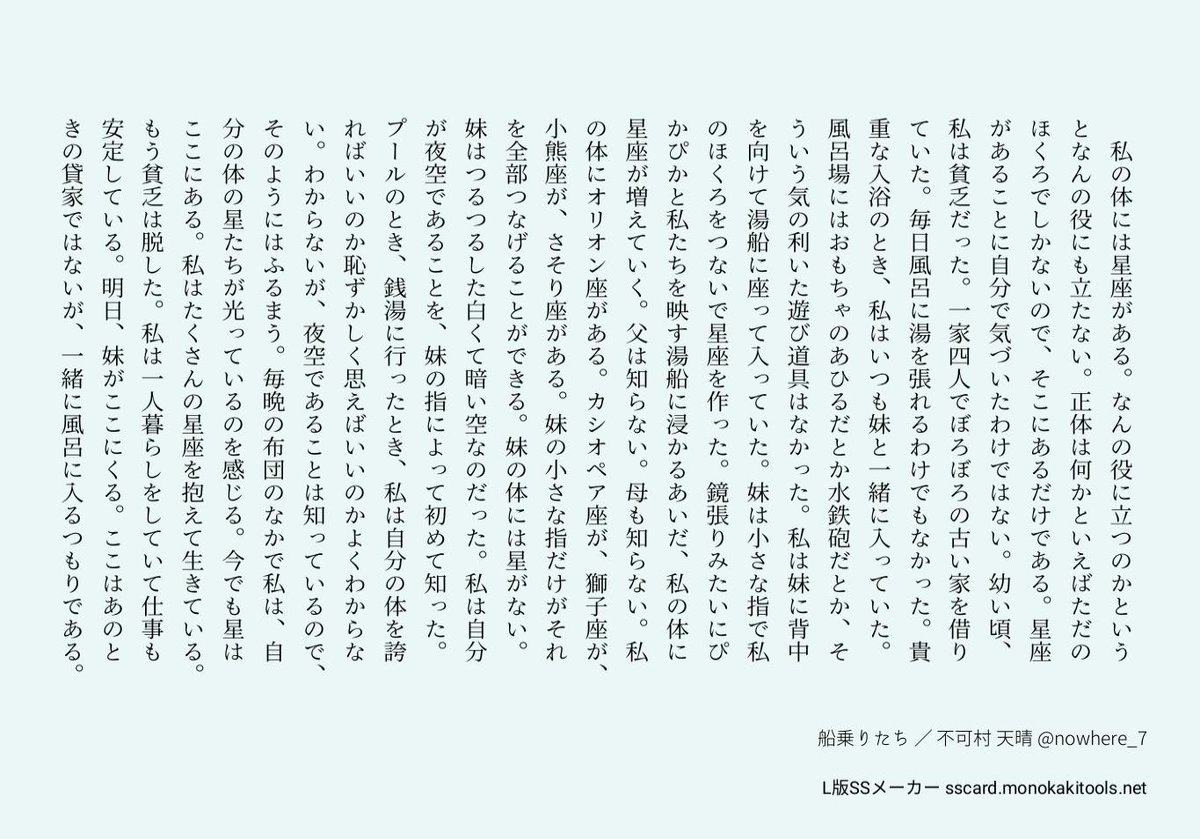
私の体には星座がある。なんの役に立つのかというとなんの役にも立たない。正体は何かといえばただのほくろでしかないので、そこにあるだけである。星座があることに自分で気づいたわけではない。幼い頃、私は貧乏だった。一家四人でぼろぼろの古い家を借りていた。毎日風呂に湯を張れるわけでもなかった。貴重な入浴のとき、私はいつも妹と一緒に入っていた。風呂場にはおもちゃのあひるだとか水鉄砲だとか、そういう気の利いた遊び道具はなかった。私は妹に背中を向けて湯船に座って入っていた。妹は小さな指で私のほくろをつないで星座を作った。鏡張りみたいにぴかぴかと私たちを映す湯船に浸かるあいだ、私の体に星座が増えていく。父は知らない。母も知らない。私の体にオリオン座がある。カシオペア座が、獅子座が、小熊座が、さそり座がある。妹の小さな指だけがそれを全部つなげることができる。妹の体には星がない。妹はつるつるした白くて暗い空なのだった。私は自分が夜空であることを、妹の指によって初めて知った。プールのとき、銭湯に行ったとき、私は自分の体を誇ればいいのか恥ずかしく思えばいいのかよくわからない。わからないが、夜空であることは知っているので、そのようにはふるまう。毎晩の布団のなかで私は、自分の体の星たちが光っているのを感じる。今でも星はここにある。私はたくさんの星座を抱えて生きている。もう貧乏は脱した。私は一人暮らしをしていて仕事も安定している。明日、妹がここにくる。ここはあのときの貸家ではないが、一緒に風呂に入ろうと思う。
船乗りたち 190804