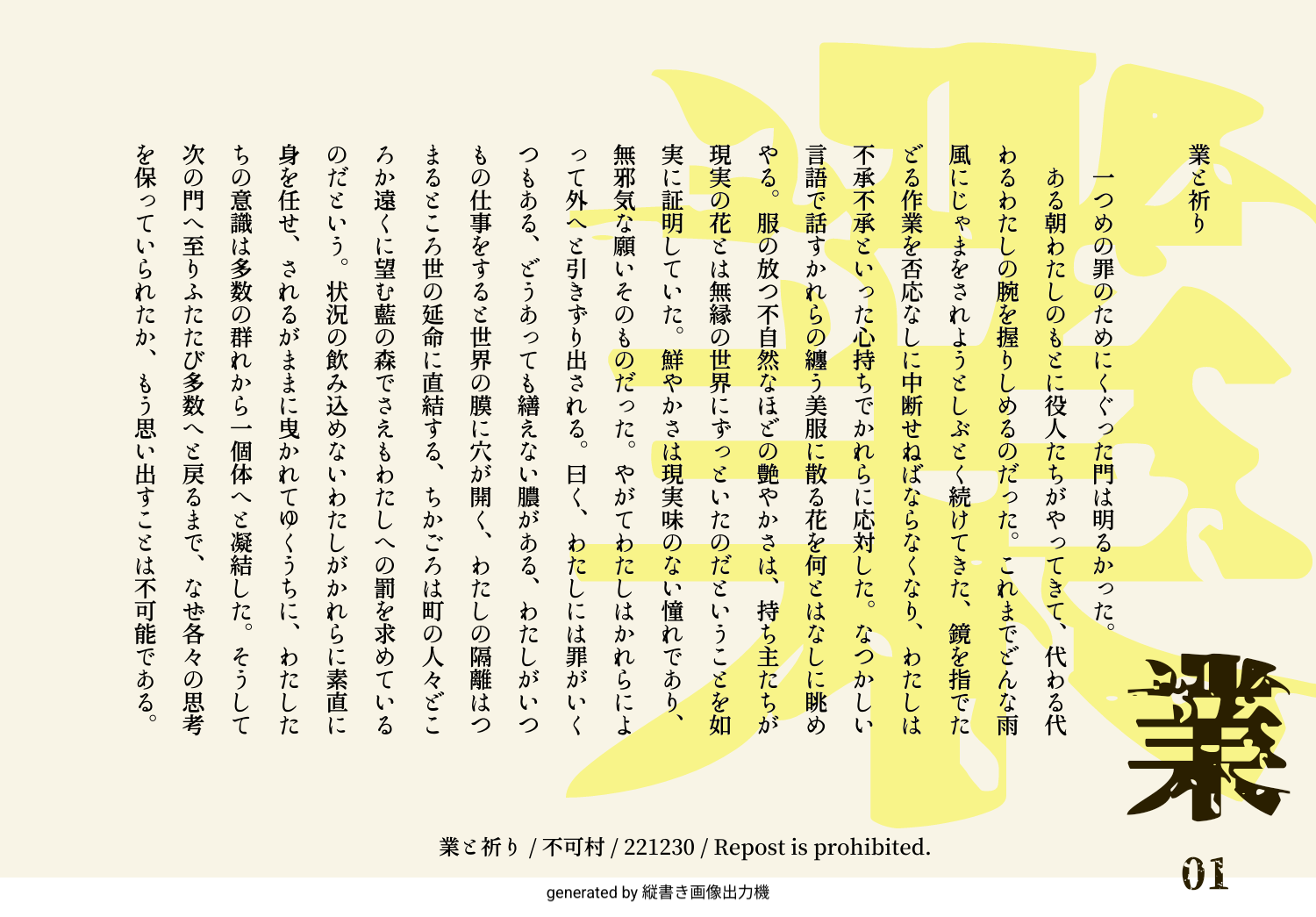
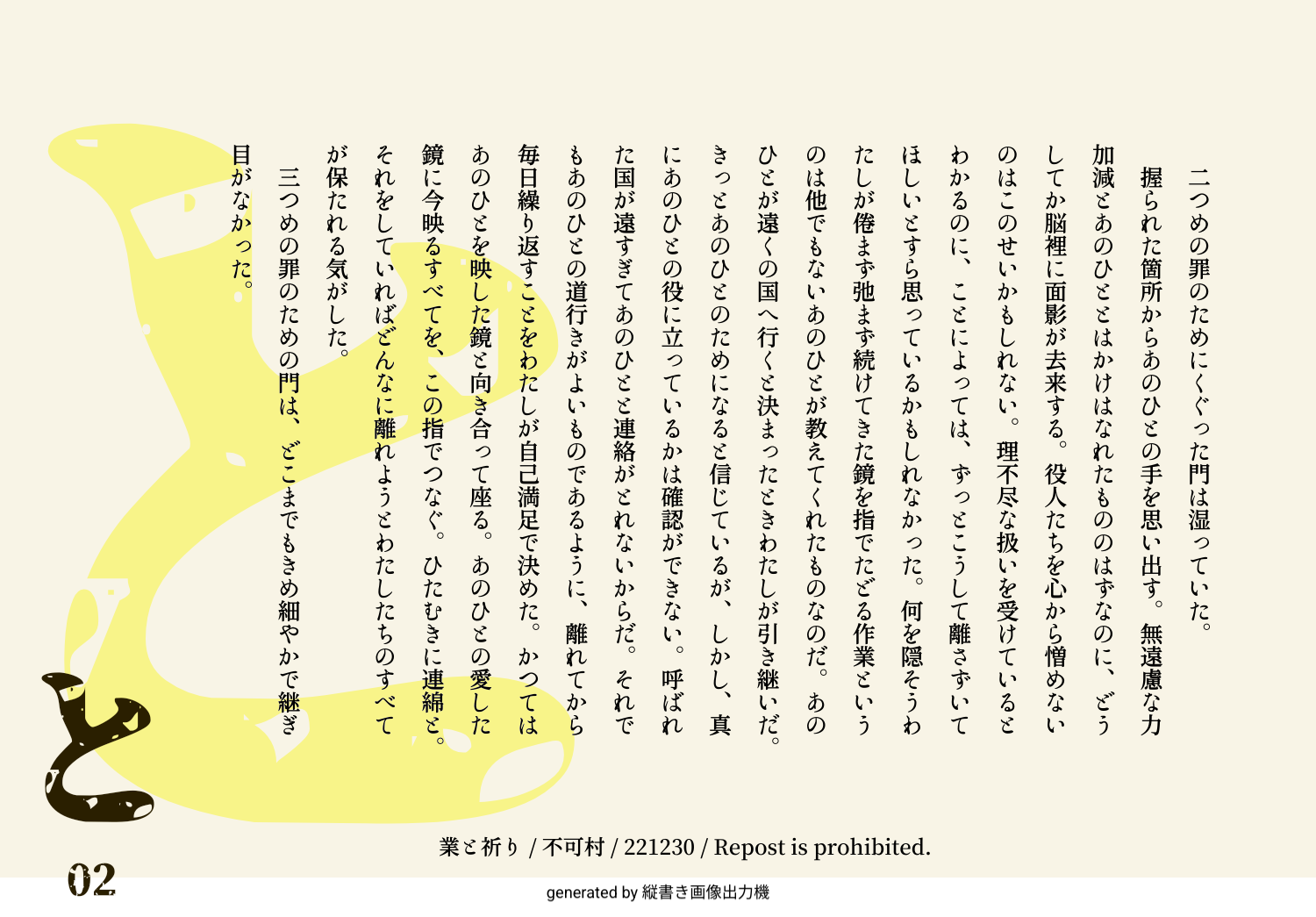
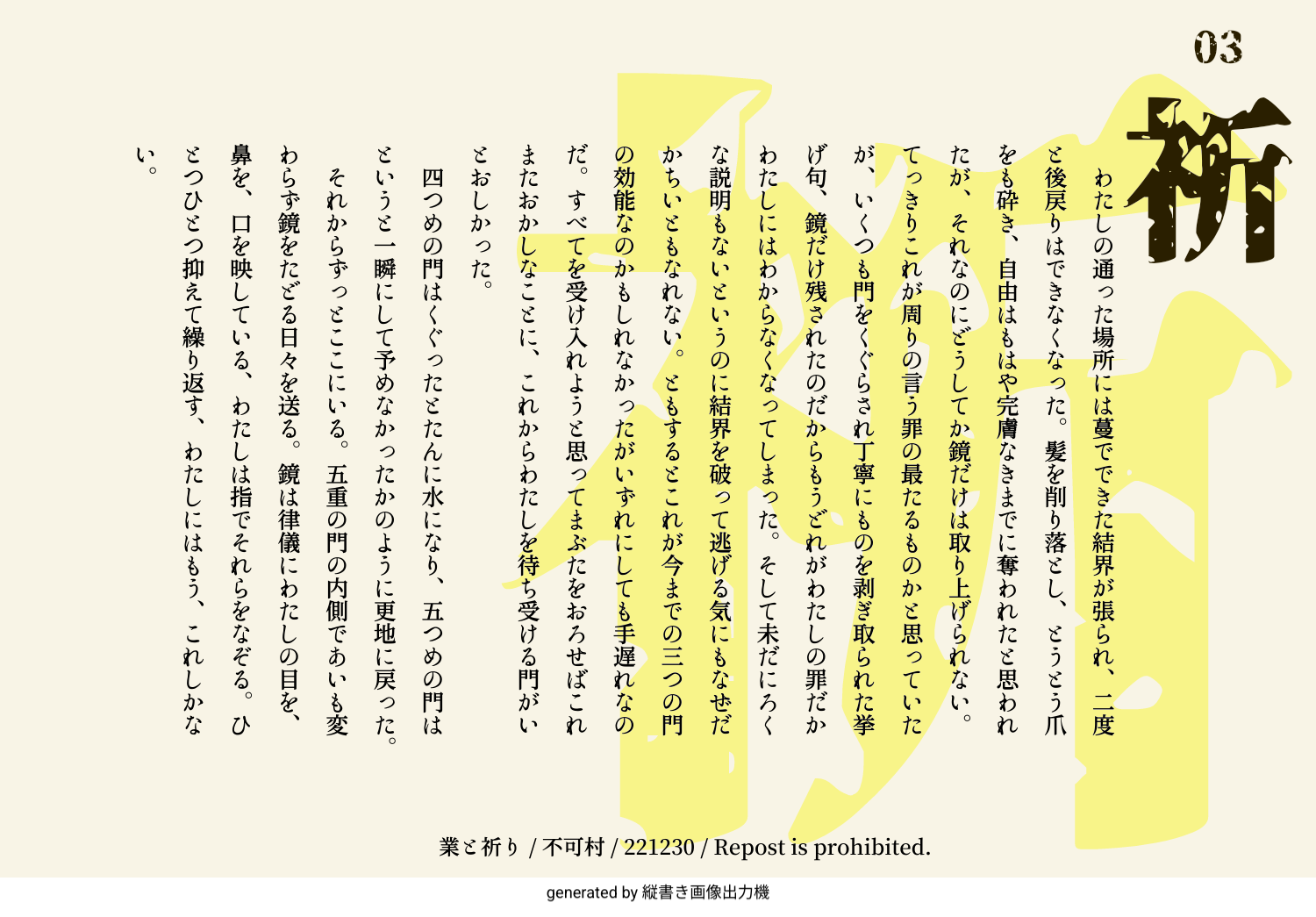
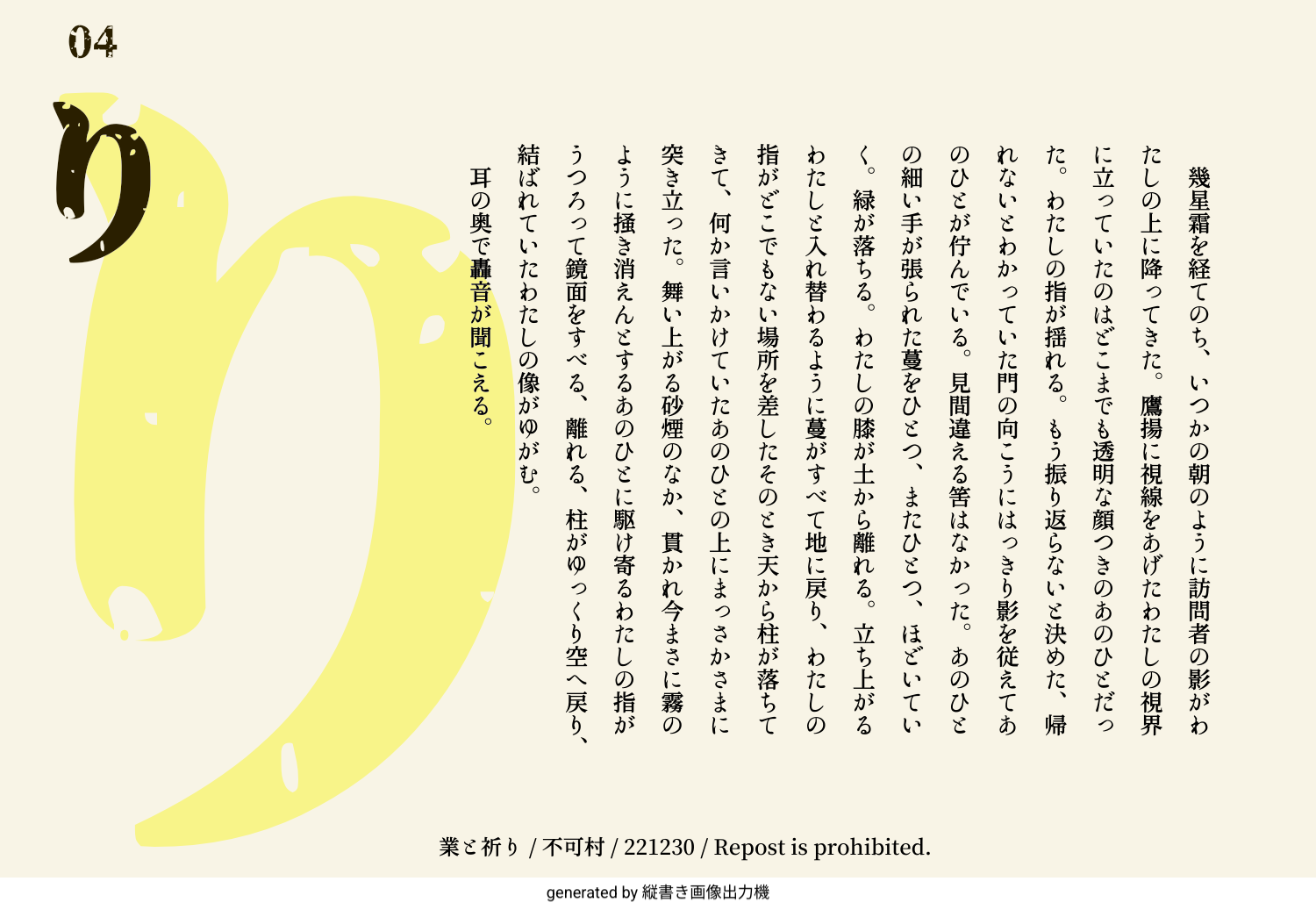
一つめの罪のためにくぐった門は明るかった。
ある朝わたしのもとに役人たちがやってきて、代わる代わるわたしの腕を握りしめるのだった。これまでどんな雨風にじゃまをされようとしぶとく続けてきた、鏡を指でたどる作業を否応なしに中断せねばならなくなり、わたしは不承不承といった心持ちでかれらに応対した。なつかしい言語で話すかれらの纏う美服に散る花を何とはなしに眺めやる。服の放つ不自然なほどの艶やかさは、持ち主たちが現実の花とは無縁の世界にずっといたのだということを如実に証明していた。鮮やかさは現実味のない憧れであり、無邪気な願いそのものだった。やがてわたしはかれらによって外へと引きずり出される。曰く、わたしには罪がいくつもある、どうあっても繕えない膿がある、わたしがいつもの仕事をすると世界の膜に穴が開く、わたしの隔離はつまるところ世の延命に直結する、ちかごろは町の人々どころか遠くに望む藍の森でさえもわたしへの罰を求めているのだという。状況の飲み込めないわたしがかれらに素直に身を任せ、されるがままに曳かれてゆくうちに、わたしたちの意識は多数の群れから一個体へと凝結した。そうして次の門へ至りふたたび多数へと戻るまで、なぜ各々の思考を保っていられたか、もう思い出すことは不可能である。
二つめの罪のためにくぐった門は湿っていた。
握られた箇所からあのひとの手を思い出す。無遠慮な力加減とあのひととはかけはなれたもののはずなのに、どうしてか脳裡に面影が去来する。役人たちを心から憎めないのはこのせいかもしれない。理不尽な扱いを受けているとわかるのに、ことによっては、ずっとこうして離さずいてほしいとすら思っているかもしれなかった。何を隠そうわたしが倦まず弛まず続けてきた鏡を指でたどる作業というのは他でもないあのひとが教えてくれたものなのだ。あのひとが遠くの国へ行くと決まったときわたしが引き継いだ。きっとあのひとのためになると信じているが、しかし、真にあのひとの役に立っているかは確認ができない。呼ばれた国が遠すぎてあのひとと連絡がとれないからだ。それでもあのひとの道行きがよいものであるように、離れてから毎日繰り返すことをわたしが自己満足で決めた。かつてはあのひとを映した鏡と向き合って座る。あのひとの愛した鏡に今映るすべてを、この指でつなぐ。ひたむきに連綿と。それをしていればどんなに離れようとわたしたちのすべてが保たれる気がした。
三つめの罪のための門は、どこまでもきめ細やかで継ぎ目がなかった。
わたしの通った場所には蔓でできた結界が張られ、二度と後戻りはできなくなった。髪を削り落とし、とうとう爪をも砕き、自由はもはや完膚なきまでに奪われたと思われたが、それなのにどうしてか鏡だけは取り上げられない。てっきりこれが周りの言う罪の最たるものかと思っていたが、いくつも門をくぐらされ丁寧にものを剥ぎ取られた挙げ句、鏡だけ残されたのだからもうどれがわたしの罪だかわたしにはわからなくなってしまった。そして未だにろくな説明もないというのに結界を破って逃げる気にもなぜだかちいともなれない。ともするとこれが今までの三つの門の効能なのかもしれなかったがいずれにしても手遅れなのだ。すべてを受け入れようと思ってまぶたをおろせばこれまたおかしなことに、これからわたしを待ち受ける門がいとおしかった。
四つめの門はくぐったとたんに水になり、五つめの門はというと一瞬にして予めなかったかのように更地に戻った。
それからずっとここにいる。五重の門の内側であいも変わらず鏡をたどる日々を送る。鏡は律儀にわたしの目を、鼻を、口を映している、わたしは指でそれらをなぞる。ひとつひとつ抑えて繰り返す、わたしにはもう、これしかない。
幾星霜を経てのち、いつかの朝のように訪問者の影がわたしの上に降ってきた。鷹揚に視線をあげたわたしの視界に立っていたのはどこまでも透明な顔つきのあのひとだった。わたしの指が揺れる。もう振り返らないと決めた、帰れないとわかっていた門の向こうにはっきり影を従えてあのひとが佇んでいる。見間違える筈はなかった。あのひとの細い手が張られた蔓をひとつ、またひとつ、ほどいていく。緑が落ちる。わたしの膝が土から離れる。立ち上がるわたしと入れ替わるように蔓がすべて地に戻り、わたしの指がどこでもない場所を差したそのとき天から柱が落ちてきて、何か言いかけていたあのひとの上にまっさかさまに突き立った。舞い上がる砂煙のなか、貫かれ今まさに霧のように掻き消えんとするあのひとに駆け寄るわたしの指がうつろって鏡面をすべる、離れる、柱がゆっくり空へ戻り、結ばれていたわたしの像がゆがむ。
耳の奥で轟音が聞こえる。
業と祈り / 不可村 / 221230 / Repost is prohibited.