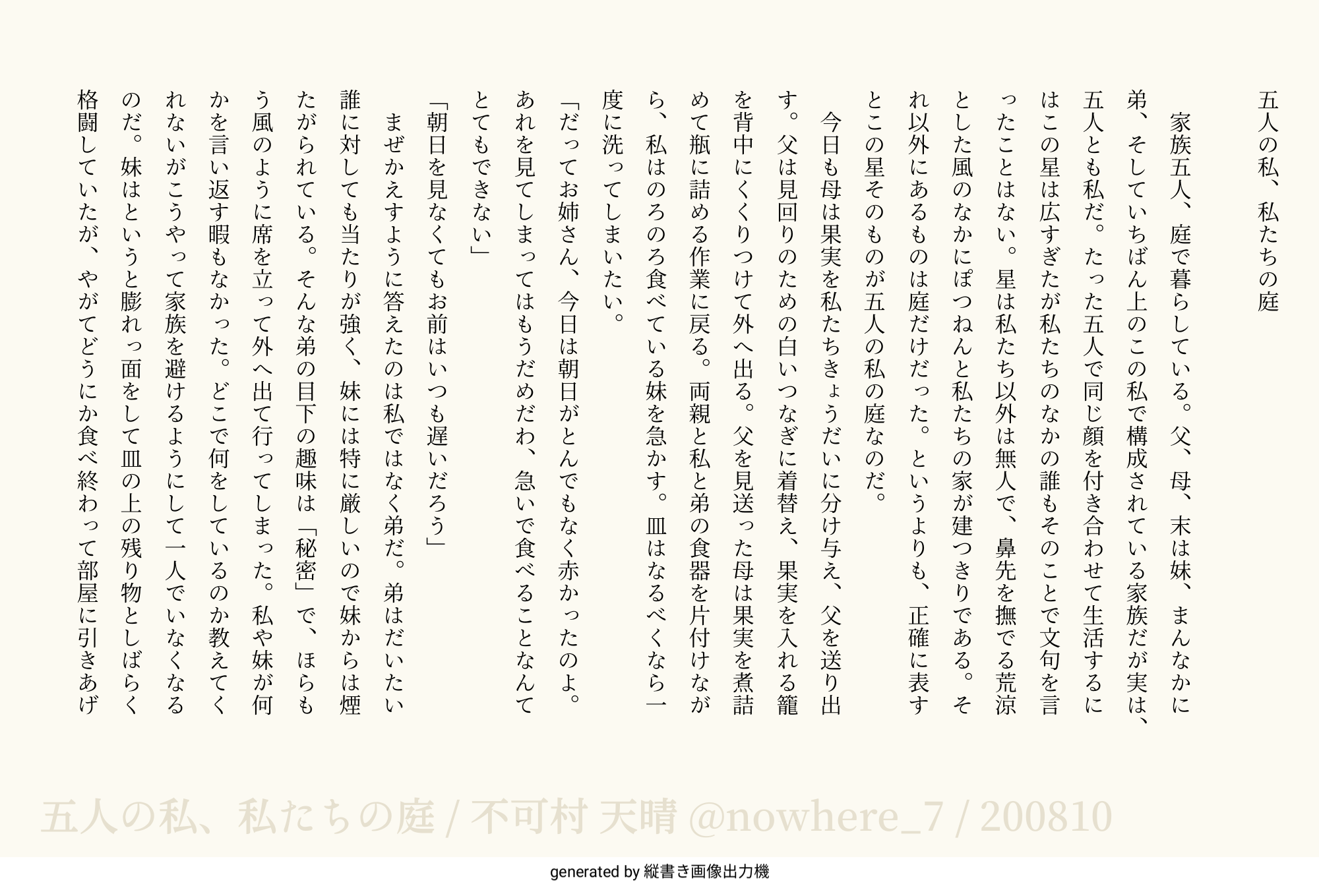
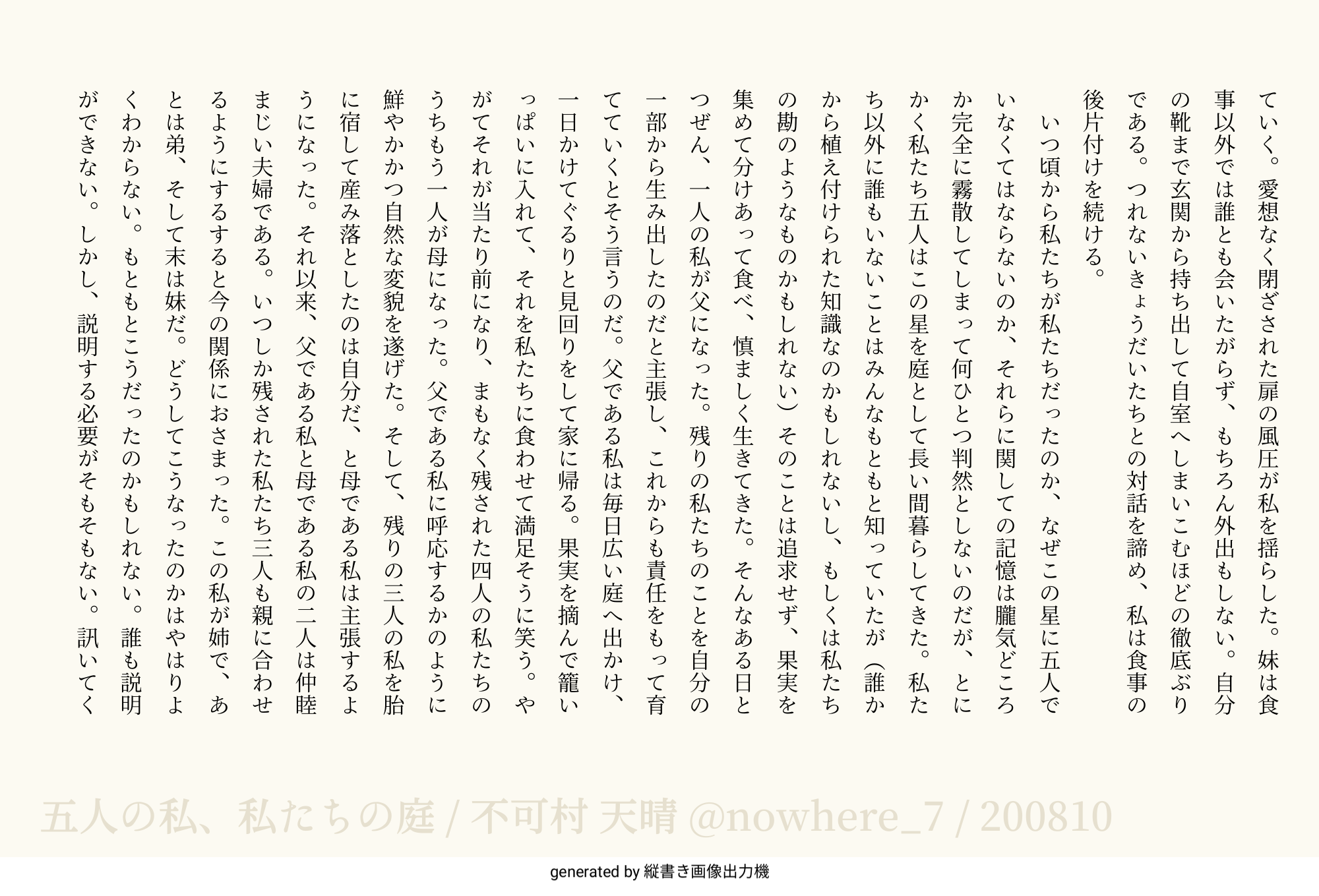
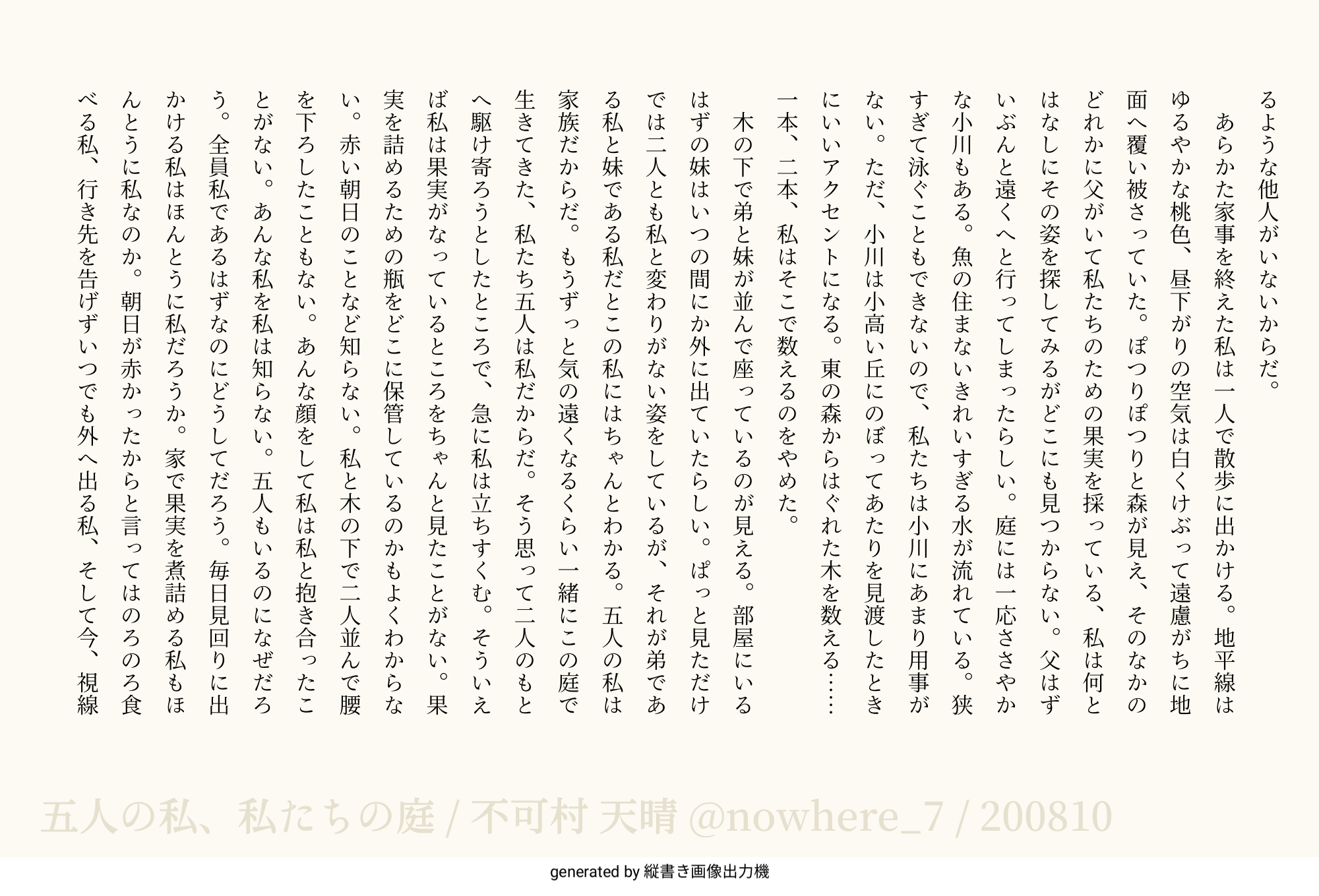
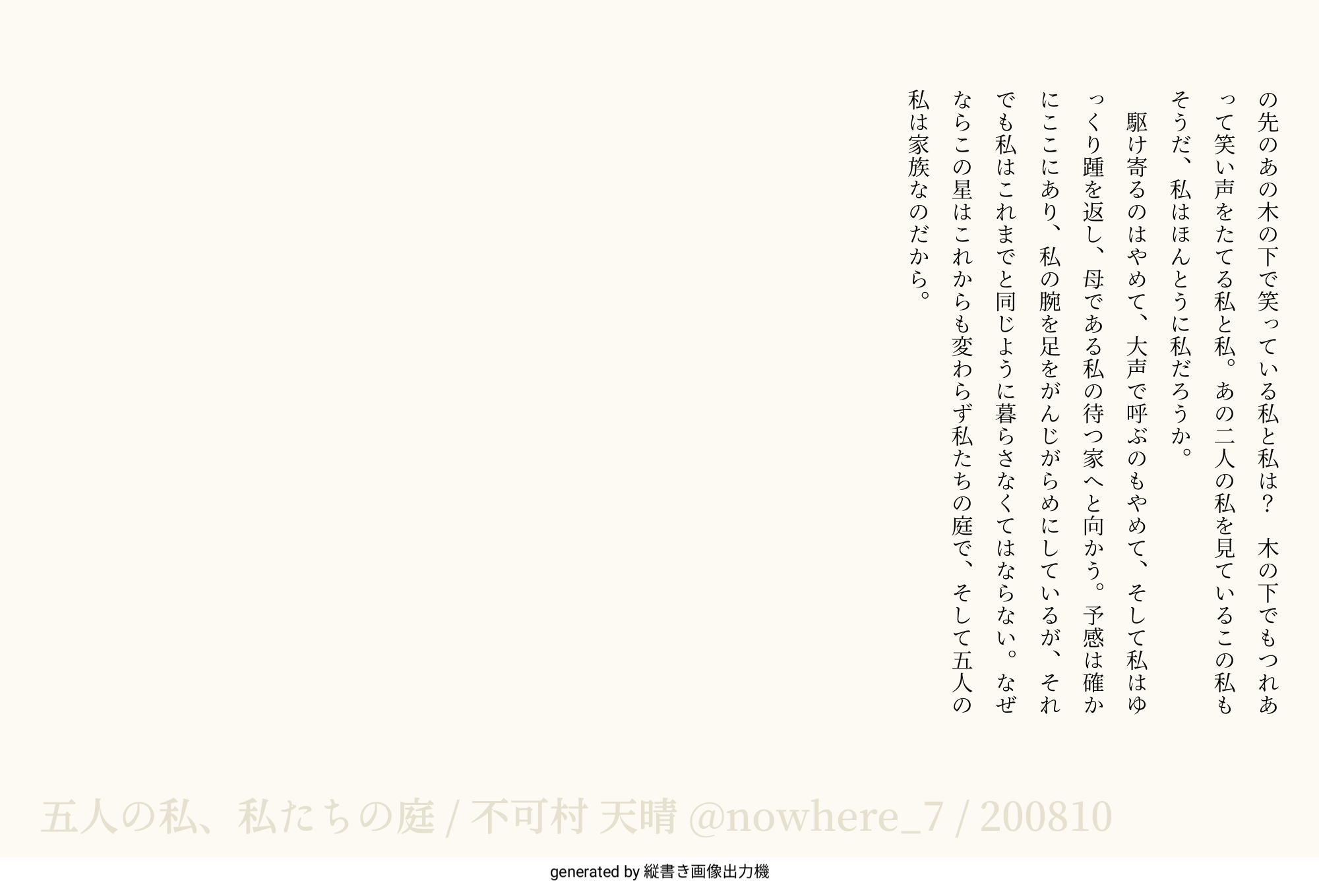
家族五人、庭で暮らしている。父、母、末は妹、まんなかに弟、そしていちばん上のこの私で構成されている家族だが実は、五人とも私だ。たった五人で同じ顔を付き合わせて生活するにはこの星は広すぎたが私たちのなかの誰もそのことで文句を言ったことはない。星は私たち以外は無人で、鼻先を撫でる荒涼とした風のなかにぽつねんと私たちの家が建つきりである。それ以外にあるものは庭だけだった。というよりも、正確に表すとこの星そのものが五人の私の庭なのだ。
今日も母は果実を私たちきょうだいに分け与え、父を送り出す。父は見回りのための白いつなぎに着替え、果実を入れる籠を背中にくくりつけて外へ出る。父を見送った母は果実を煮詰めて瓶に詰める作業に戻る。両親と私と弟の食器を片付けながら、私はのろのろ食べている妹を急かす。皿はなるべくなら一度に洗ってしまいたい。
「だってお姉さん、今日は朝日がとんでもなく赤かったのよ。あれを見てしまってはもうだめだわ、急いで食べることなんてとてもできない」
「朝日を見なくてもお前はいつも遅いだろう」
まぜかえすように答えたのは私ではなく弟だ。弟はだいたい誰に対しても当たりが強く、妹には特に厳しいので妹からは煙たがられている。そんな弟の目下の趣味は「秘密」で、ほらもう風のように席を立って外へ出て行ってしまった。私や妹が何かを言い返す暇もなかった。どこで何をしているのか教えてくれないがこうやって家族を避けるようにして一人でいなくなるのだ。妹はというと膨れっ面をして皿の上の残り物としばらく格闘していたが、やがてどうにか食べ終わって部屋に引きあげていく。愛想なく閉ざされた扉の風圧が私を揺らした。妹は食事以外では誰とも会いたがらず、もちろん外出もしない。自分の靴まで玄関から持ち出して自室へしまいこむほどの徹底ぶりである。つれないきょうだいたちとの対話を諦め、私は食事の後片付けを続ける。
いつ頃から私たちが私たちだったのか、なぜこの星に五人でいなくてはならないのか、それらに関しての記憶は朧気どころか完全に霧散してしまって何ひとつ判然としないのだが、とにかく私たち五人はこの星を庭として長い間暮らしてきた。私たち以外に誰もいないことはみんなもともと知っていたが(誰かから植え付けられた知識なのかもしれないし、もしくは私たちの勘のようなものかもしれない)そのことは追求せず、果実を集めて分けあって食べ、慎ましく生きてきた。そんなある日とつぜん、一人の私が父になった。残りの私たちのことを自分の一部から生み出したのだと主張し、これからも責任をもって育てていくとそう言うのだ。父である私は毎日広い庭へ出かけ、一日かけてぐるりと見回りをして家に帰る。果実を摘んで籠いっぱいに入れて、それを私たちに食わせて満足そうに笑う。やがてそれが当たり前になり、まもなく残された四人の私たちのうちもう一人が母になった。父である私に呼応するかのように鮮やかかつ自然な変貌を遂げた。そして、残りの三人の私を胎に宿して産み落としたのは自分だ、と母である私は主張するようになった。それ以来、父である私と母である私の二人は仲睦まじい夫婦である。いつしか残された私たち三人も親に合わせるようにするすると今の関係におさまった。この私が姉で、あとは弟、そして末は妹だ。どうしてこうなったのかはやはりよくわからない。もともとこうだったのかもしれない。誰も説明ができない。しかし、説明する必要がそもそもない。訊いてくるような他人がいないからだ。
あらかた家事を終えた私は一人で散歩に出かける。地平線はゆるやかな桃色、昼下がりの空気は白くけぶって遠慮がちに地面へ覆い被さっていた。ぽつりぽつりと森が見え、そのなかのどれかに父がいて私たちのための果実を採っている、私は何とはなしにその姿を探してみるがどこにも見つからない。父はずいぶんと遠くへと行ってしまったらしい。庭には一応ささやかな小川もある。魚の住まないきれいすぎる水が流れている。狭すぎて泳ぐこともできないので、私たちは小川にあまり用事がない。ただ、小川は小高い丘にのぼってあたりを見渡したときにいいアクセントになる。東の森からはぐれた木を数える……一本、二本、私はそこで数えるのをやめた。
木の下で弟と妹が並んで座っているのが見える。部屋にいるはずの妹はいつの間にか外に出ていたらしい。ぱっと見ただけでは二人とも私と変わりがない姿をしているが、それが弟である私と妹である私だとこの私にはちゃんとわかる。五人の私は家族だからだ。もうずっと気の遠くなるくらい一緒にこの庭で生きてきた、私たち五人は私だからだ。そう思って二人のもとへ駆け寄ろうとしたところで、急に私は立ちすくむ。そういえば私は果実がなっているところをちゃんと見たことがない。果実を詰めるための瓶をどこに保管しているのかもよくわからない。赤い朝日のことなど知らない。私と木の下で二人並んで腰を下ろしたこともない。あんな顔をして私は私と抱き合ったことがない。あんな私を私は知らない。五人もいるのになぜだろう。全員私であるはずなのにどうしてだろう。毎日見回りに出かける私はほんとうに私だろうか。家で果実を煮詰める私もほんとうに私なのか。朝日が赤かったからと言ってはのろのろ食べる私、行き先を告げずいつでも外へ出る私、そして今、視線の先のあの木の下で笑っている私と私は? 木の下でもつれあって笑い声をたてる私と私。あの二人の私を見ているこの私もそうだ、私はほんとうに私だろうか。
駆け寄るのはやめて、大声で呼ぶのもやめて、そして私はゆっくり踵を返し、母である私の待つ家へと向かう。予感は確かにここにあり、私の腕を足をがんじがらめにしているが、それでも私はこれまでと同じように暮らさなくてはならない。なぜならこの星はこれからも変わらず私たちの庭で、そして五人の私は家族なのだから。
五人の私、私たちの庭 200810