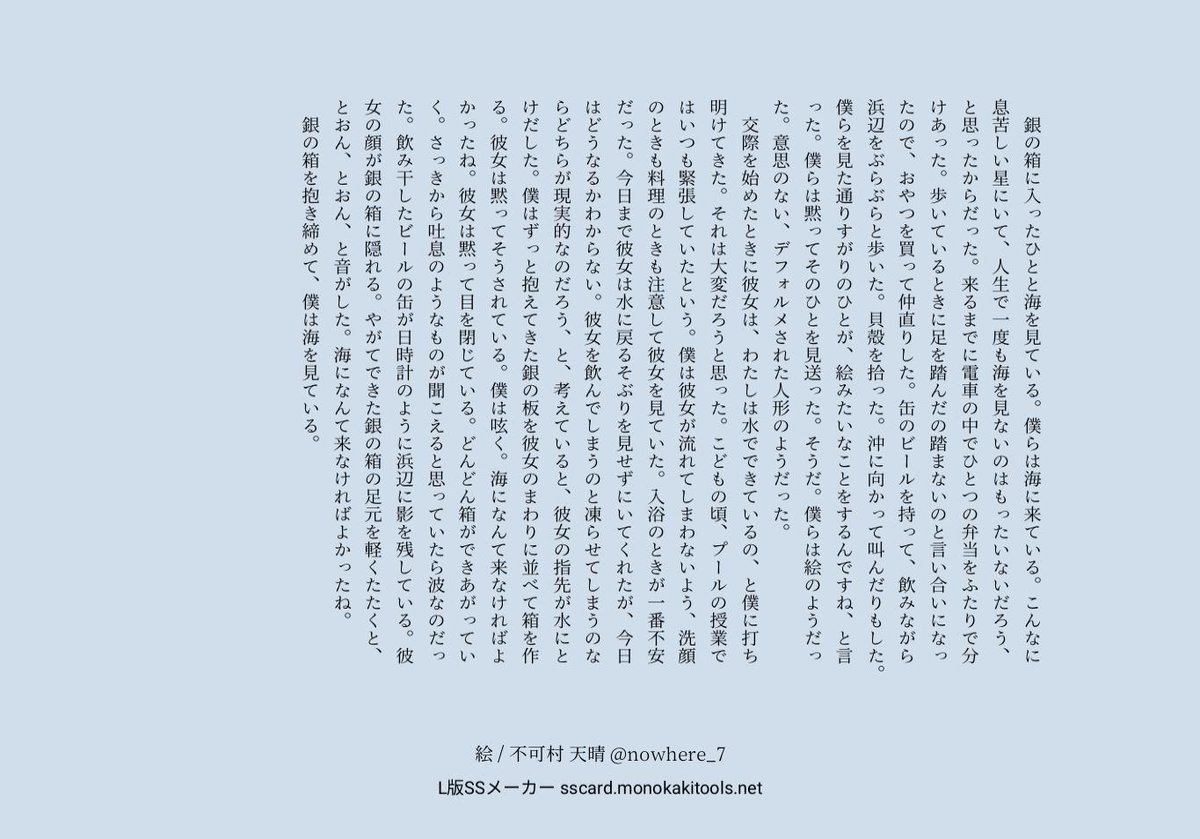
銀の器に入ったひとと海を見ている。僕らは海に来ている。こんなに息苦しい星にいて、人生で一度も海を見ないのはもったいないだろう、と思ったからだった。来るまでに電車の中でひとつの弁当をふたりで分けあった。歩いているときに足を踏んだの踏まないのと言い合いになったので、おやつを買って仲直りした。缶のビールを持って、飲みながら浜辺をぶらぶらと歩いた。貝殻を拾った。沖に向かって叫んだりもした。僕らを見た通りすがりのひとが、絵みたいなことをするんですね、と言った。僕らは黙ってそのひとを見送った。そうだ。僕らは絵のようだった。意思のない、デフォルメされた人形のようだった。
交際を始めたときに彼女は、わたしは水でできているの、と僕に打ち明けてきた。それは大変だろうと思った。こどもの頃、プールの授業ではいつも緊張していたという。僕は彼女が流れてしまわないよう、洗顔のときも料理のときも注意して彼女を見ていた。入浴のときが一番不安だった。今日まで彼女は水に戻るそぶりを見せずにいてくれたが、今日はどうなるかわからない。彼女を飲んでしまうのと凍らせてしまうのならどちらが現実的なのだろう、と、考えていると、彼女の指先が水にとけだした。僕はずっと抱えてきた銀の板を彼女のまわりに並べて箱を作る。彼女は黙ってそうされている。僕は呟く。海になんて来なければよかったね。彼女は黙って目を閉じている。どんどん箱ができあがっていく。さっきから吐息のようなものが聞こえると思っていたら波なのだった。飲み干したビールの缶が日時計のように浜辺に影を残している。彼女の顔が銀の箱に隠れる。やがてできた銀の箱の足元を軽くたたくと、とおん、とおん、と音がした。
銀の箱を抱き締めて、僕は海を見ている。
絵 190707