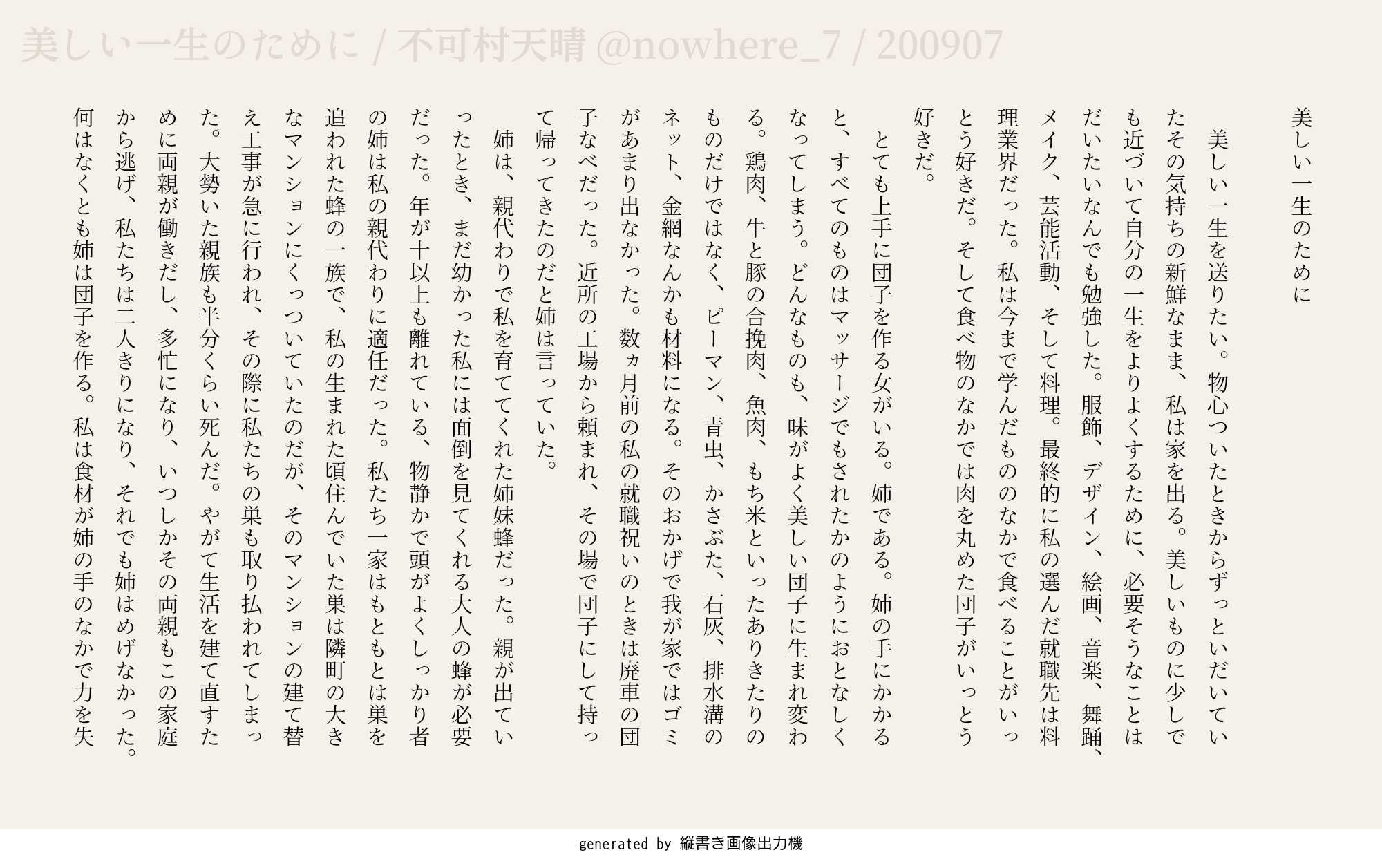
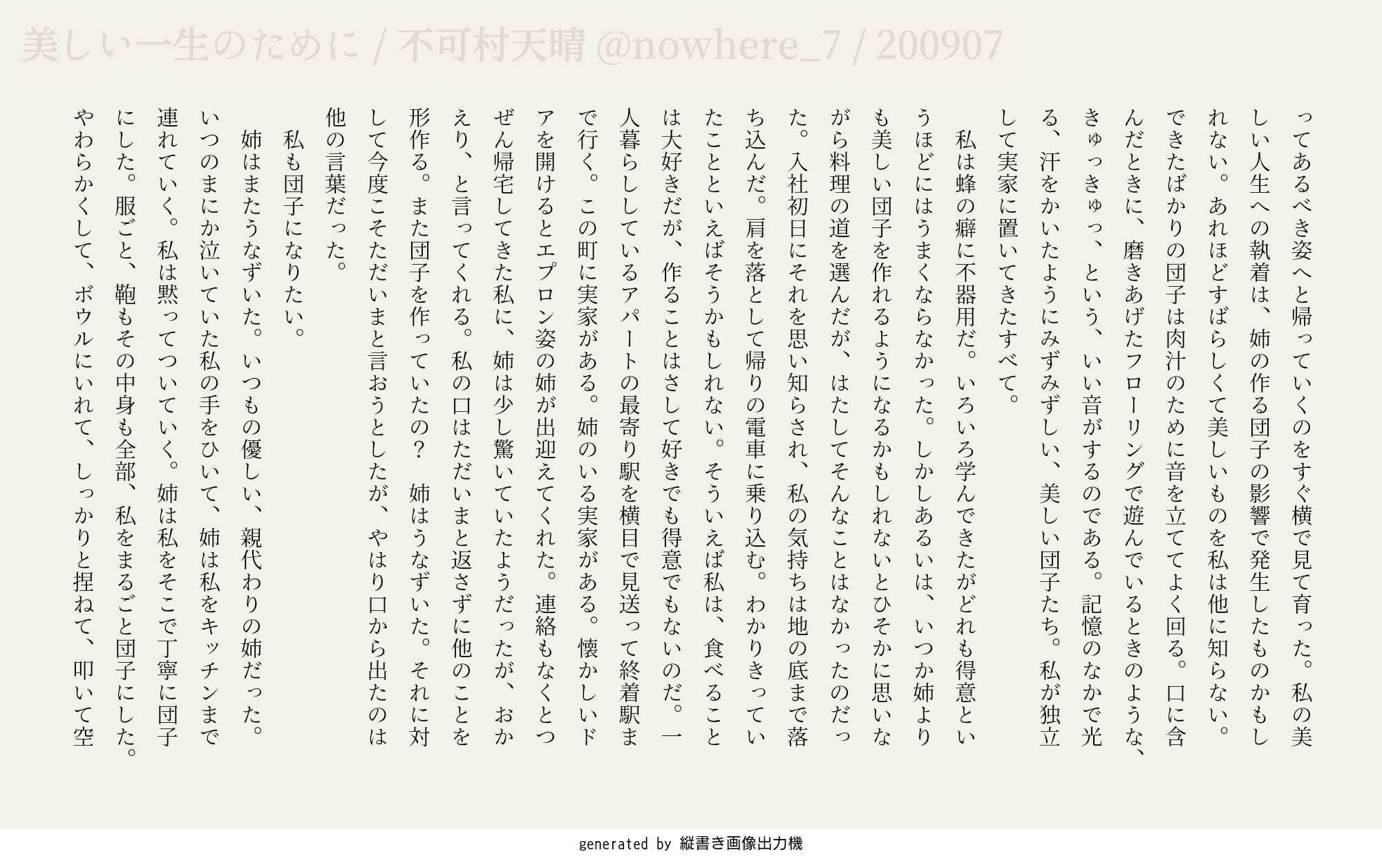

美しい一生を送りたい。物心ついたときからずっといだいていたその気持ちの新鮮なまま、私は家を出る。美しいものに少しでも近づいて自分の一生をよりよくするために、必要そうなことはだいたいなんでも勉強した。服飾、デザイン、絵画、音楽、舞踊、メイク、芸能活動、そして料理。最終的に私の選んだ就職先は料理業界だった。私は今まで学んだもののなかで食べることがいっとう好きだ。そして食べ物のなかでは肉を丸めた団子がいっとう好きだ。
とても上手に団子を作る女がいる。姉である。姉の手にかかると、すべてのものはマッサージでもされたかのようにおとなしくなってしまう。どんなものも、味がよく美しい団子に生まれ変わる。鶏肉、牛と豚の合挽肉、魚肉、もち米といったありきたりのものだけではなく、ピーマン、青虫、かさぶた、石灰、排水溝のネット、金網なんかも材料になる。そのおかげで我が家ではゴミがあまり出なかった。数ヵ月前の私の就職祝いのときは廃車の団子なべだった。近所の工場から頼まれ、その場で団子にして持って帰ってきたのだと姉は言っていた。
姉は、親代わりで私を育ててくれた姉妹蜂だった。親が出ていったとき、まだ幼かった私には面倒を見てくれる大人の蜂が必要だった。年が十以上も離れている、物静かで頭がよくしっかり者の姉は私の親代わりに適任だった。私たち一家はもともとは巣を追われた蜂の一族で、私の生まれた頃住んでいた巣は隣町の大きなマンションにくっついていたのだが、そのマンションの建て替え工事が急に行われ、その際に私たちの巣も取り払われてしまった。大勢いた親族も半分くらい死んだ。やがて生活を建て直すために両親が働きだし、多忙になり、いつしかその両親もこの家庭から逃げ、私たちは二人きりになり、それでも姉はめげなかった。何はなくとも姉は団子を作る。私は食材が姉の手のなかで力を失ってあるべき姿へと帰っていくのをすぐ横で見て育った。私の美しい人生への執着は、姉の作る団子の影響で発生したものかもしれない。あれほどすばらしくて美しいものを私は他に知らない。できたばかりの団子は肉汁のために音を立ててよく回る。口に含んだときに、磨きあげたフローリングで遊んでいるときのような、きゅっきゅっ、という、いい音がするのである。記憶のなかで光る、汗をかいたようにみずみずしい、美しい団子たち。私が独立して実家に置いてきたすべて。
私は蜂の癖に不器用だ。いろいろ学んできたがどれも得意というほどにはうまくならなかった。しかしあるいは、いつか姉よりも美しい団子を作れるようになるかもしれないとひそかに思いながら料理の道を選んだが、はたしてそんなことはなかったのだった。入社初日にそれを思い知らされ、私の気持ちは地の底まで落ち込んだ。肩を落として帰りの電車に乗り込む。わかりきっていたことといえばそうかもしれない。そういえば私は、食べることは大好きだが、作ることはさして好きでも得意でもないのだ。一人暮らししているアパートの最寄り駅を横目で見送って終着駅まで行く。この町に実家がある。姉のいる実家がある。懐かしいドアを開けるとエプロン姿の姉が出迎えてくれた。連絡もなくとつぜん帰宅してきた私に、姉は少し驚いていたようだったが、おかえり、と言ってくれる。私の口はただいまと返さずに他のことを形作る。また団子を作っていたの? 姉はうなずいた。それに対して今度こそただいまと言おうとしたが、やはり口から出たのは他の言葉だった。
私も団子になりたい。
姉はまたうなずいた。いつもの優しい、親代わりの姉だった。いつのまにか泣いていた私の手をひいて、姉は私をキッチンまで連れていく。私は黙ってついていく。姉は私をそこで丁寧に団子にした。服ごと、鞄もその中身も全部、私をまるごと団子にした。やわらかくして、ボウルにいれて、しっかりと捏ねて、叩いて空気を抜いて、なんどもなぜて、塩と胡椒をふって、そしてせっせと丸めた。私は私がまあるくまあるくなるのを感じている。とても満ち足りた気持ちだった。たぶん、就職なんか無意味だったのだ、とそう、私は思った。初めからこうなることを望んでいたのかもしれないとすら思った、少なくとも私は。では姉は? ちょうどそのとき加熱されていた私は意識をもたげて姉の気配を探る。姉は特に表情を変えることもなく淡々とテーブルを拭いていた。団子になった私を皿にのせ、皿をテーブルに置き、椅子をひいて腰かけるのが見える。よく見える。姉にもきっと私がよく見えている。きゅっきゅっ、と懐かしい音がすぐ耳元で聞こえた。
美しい一生のために 200907