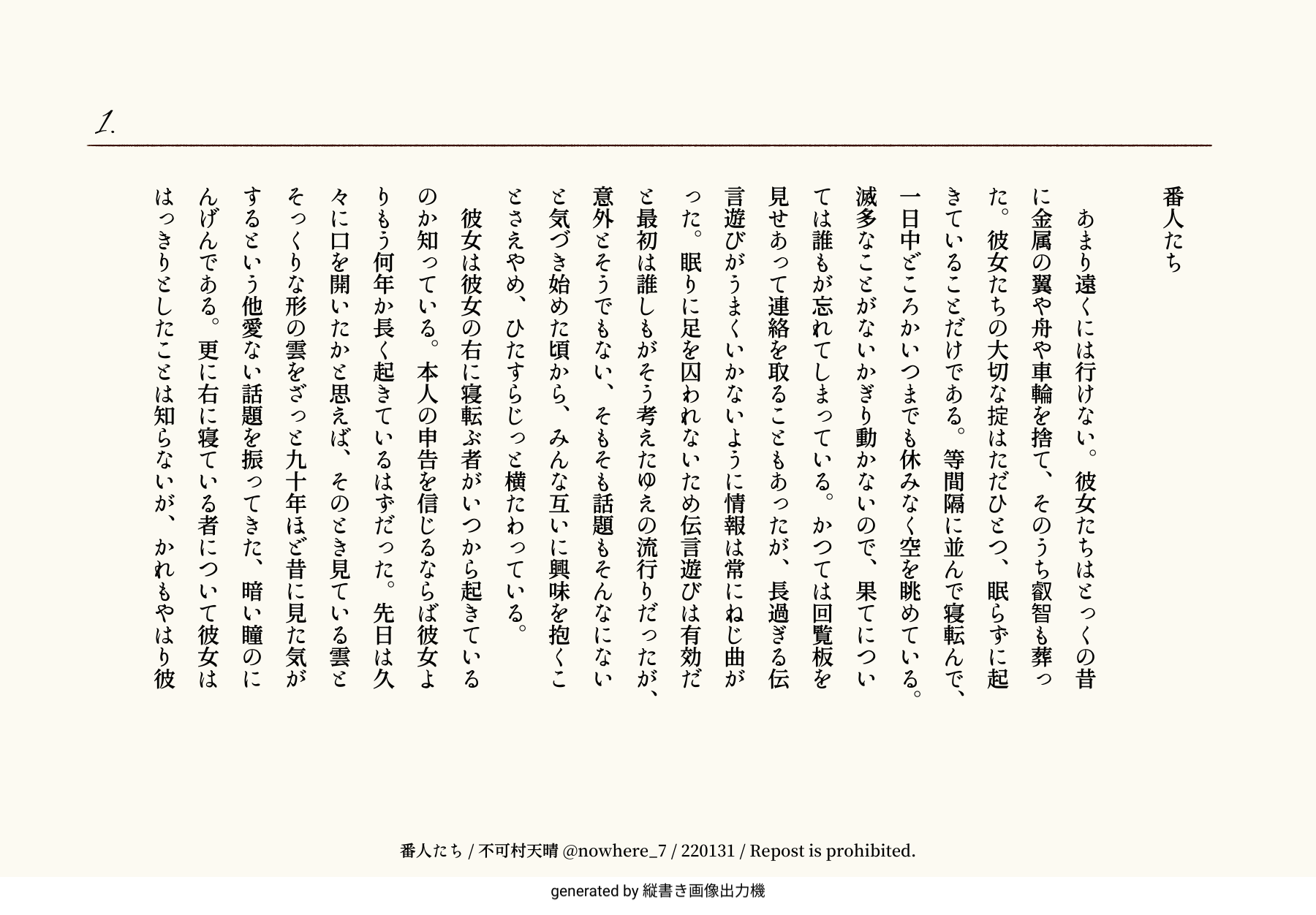
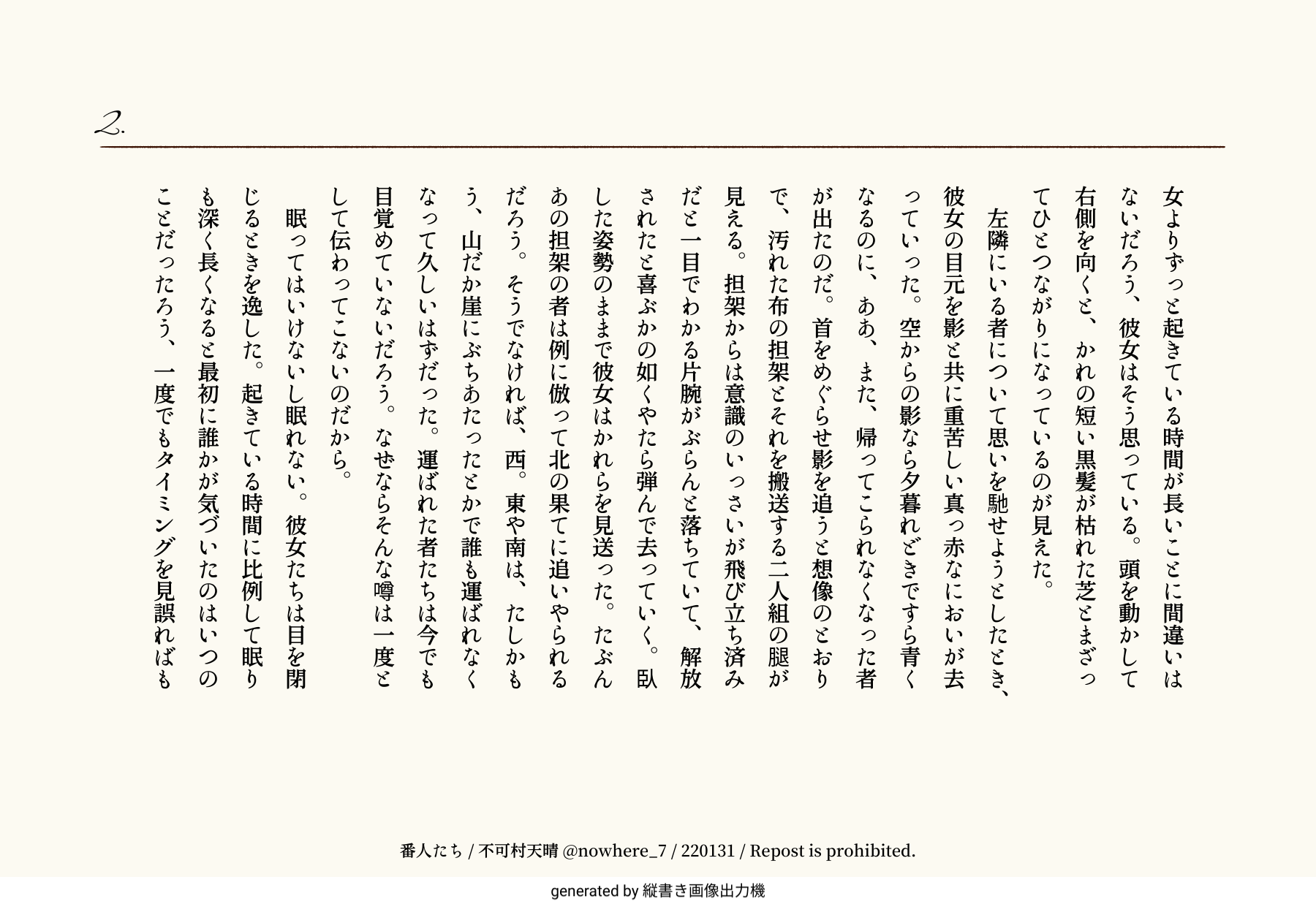
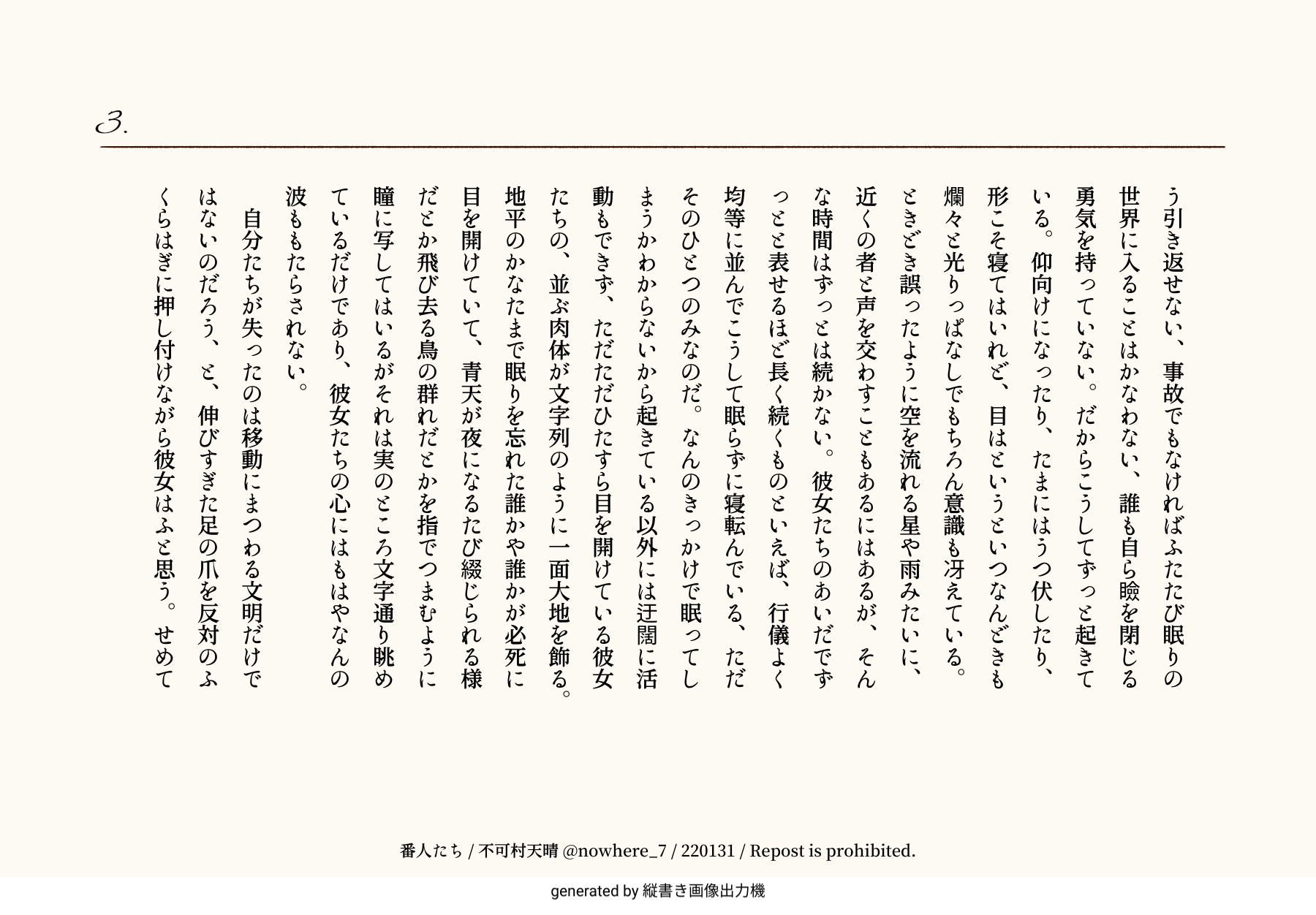

あまり遠くには行けない。彼女たちはとっくの昔に金属の翼や舟や車輪を捨て、そのうち叡智も葬った。彼女たちの大切な掟はただひとつ、眠らずに起きていることだけである。等間隔に並んで寝転んで、一日中どころかいつまでも休みなく空を眺めている。滅多なことがないかぎり動かないので、果てについては誰もが忘れてしまっている。かつては回覧板を見せあって連絡を取ることもあったが、長過ぎる伝言遊びがうまくいかないように情報は常にねじ曲がった。眠りに足を囚われないため伝言遊びは有効だと最初は誰しもがそう考えたゆえの流行りだったが、意外とそうでもない、そもそも話題もそんなにないと気づき始めた頃から、みんな互いに興味を抱くことさえやめ、ひたすらじっと横たわっている。
彼女は彼女の右に寝転ぶ者がいつから起きているのか知っている。本人の申告を信じるならば彼女よりもう何年か長く起きているはずだった。先日は久々に口を開いたかと思えば、そのとき見ている雲とそっくりな形の雲をざっと九十年ほど昔に見た気がするという他愛ない話題を振ってきた、暗い瞳のにんげんである。更に右に寝ている者について彼女ははっきりとしたことは知らないが、かれもやはり彼女よりずっと起きている時間が長いことに間違いはないだろう、彼女はそう思っている。頭を動かして右側を向くと、かれの短い黒髪が枯れた芝とまざってひとつながりになっているのが見えた。
左隣にいる者について思いを馳せようとしたとき、彼女の目元を影と共に重苦しい真っ赤なにおいが去っていった。空からの影なら夕暮れどきですら青くなるのに、ああ、また、帰ってこられなくなった者が出たのだ。首をめぐらせ影を追うと想像のとおりで、汚れた布の担架とそれを搬送する二人組の腿が見える。担架からは意識のいっさいが飛び立ち済みだと一目でわかる片腕がぶらんと落ちていて、解放されたと喜ぶかの如くやたら弾んで去っていく。臥した姿勢のままで彼女はかれらを見送った。たぶんあの担架の者は例に倣って北の果てに追いやられるだろう。そうでなければ、西。東や南は、たしかもう、山だか崖にぶちあたったとかで誰も運ばれなくなって久しいはずだった。運ばれた者たちは今でも目覚めていないだろう。なぜならそんな噂は一度として伝わってこないのだから。
眠ってはいけないし眠れない。彼女たちは目を閉じるときを逸した。起きている時間に比例して眠りも深く長くなると最初に誰かが気づいたのはいつのことだったろう、一度でもタイミングを見誤ればもう引き返せない、事故でもなければふたたび眠りの世界に入ることはかなわない、誰も自ら瞼を閉じる勇気を持っていない。だからこうしてずっと起きている。仰向けになったり、たまにはうつ伏したり、形こそ寝てはいれど、目はというといつなんどきも爛々と光りっぱなしでもちろん意識も冴えている。ときどき誤ったように空を流れる星や雨みたいに、近くの者と声を交わすこともあるにはあるが、そんな時間はずっとは続かない。彼女たちのあいだでずっとと表せるほど長く続くものといえば、行儀よく均等に並んでこうして眠らずに寝転んでいる、ただそのひとつのみなのだ。なんのきっかけで眠ってしまうかわからないから起きている以外には迂闊に活動もできず、ただただひたすら目を開けている彼女たちの、並ぶ肉体が文字列のように一面大地を飾る。地平のかなたまで眠りを忘れた誰かや誰かが必死に目を開けていて、青天が夜になるたび綴じられる様だとか飛び去る鳥の群れだとかを指でつまむように瞳に写してはいるがそれは実のところ文字通り眺めているだけであり、彼女たちの心にはもはやなんの波ももたらされない。
自分たちが失ったのは移動にまつわる文明だけではないのだろう、と、伸びすぎた足の爪を反対のふくらはぎに押し付けながら彼女はふと思う。せめて何かを待つために起きているのなら少しは心持ちが違ったかもしれない。お祭り騒ぎでどこまでも踊ってゆけただろう、が、もう眠らずにいる理由を増やすことすらもつらいのだった。やたらと高低差のある虫の声を聞き流す。右隣の者が発している呻きがそっと虫の声に重なって、景色にまぎれこんでゆく。遠くには行けないどころか、彼女たちはどこにも行けない、行けるとしてもそれは意識が途切れてからの話になるのでやはりどこにもたどりつけないだろう、たったひとつ遠ざけている何よりもすぐそばにある世界を除いては、どこにも。
番人たち / 不可村天晴 @nowhere_7 / 220131 / Repost is prohibited.