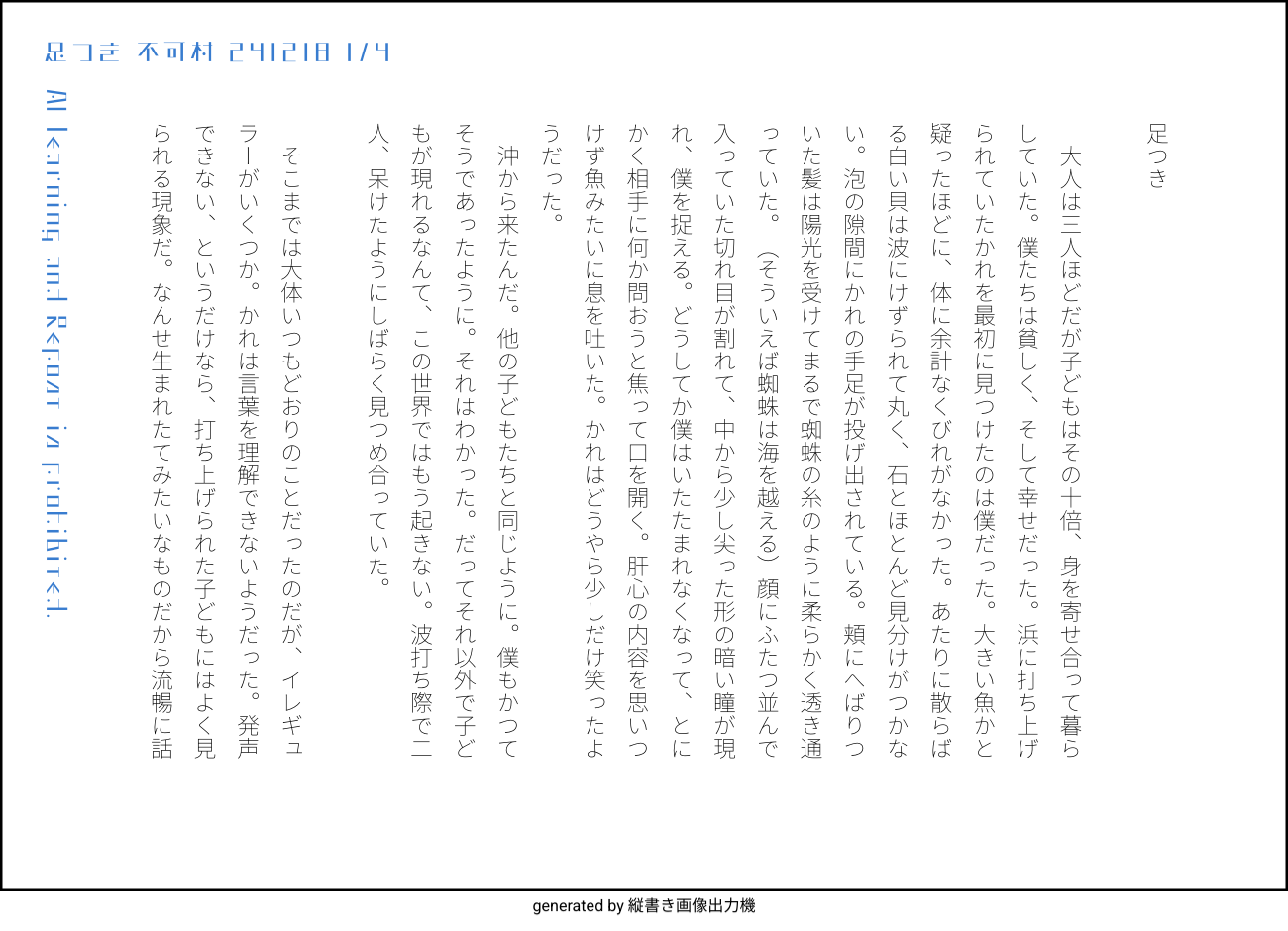
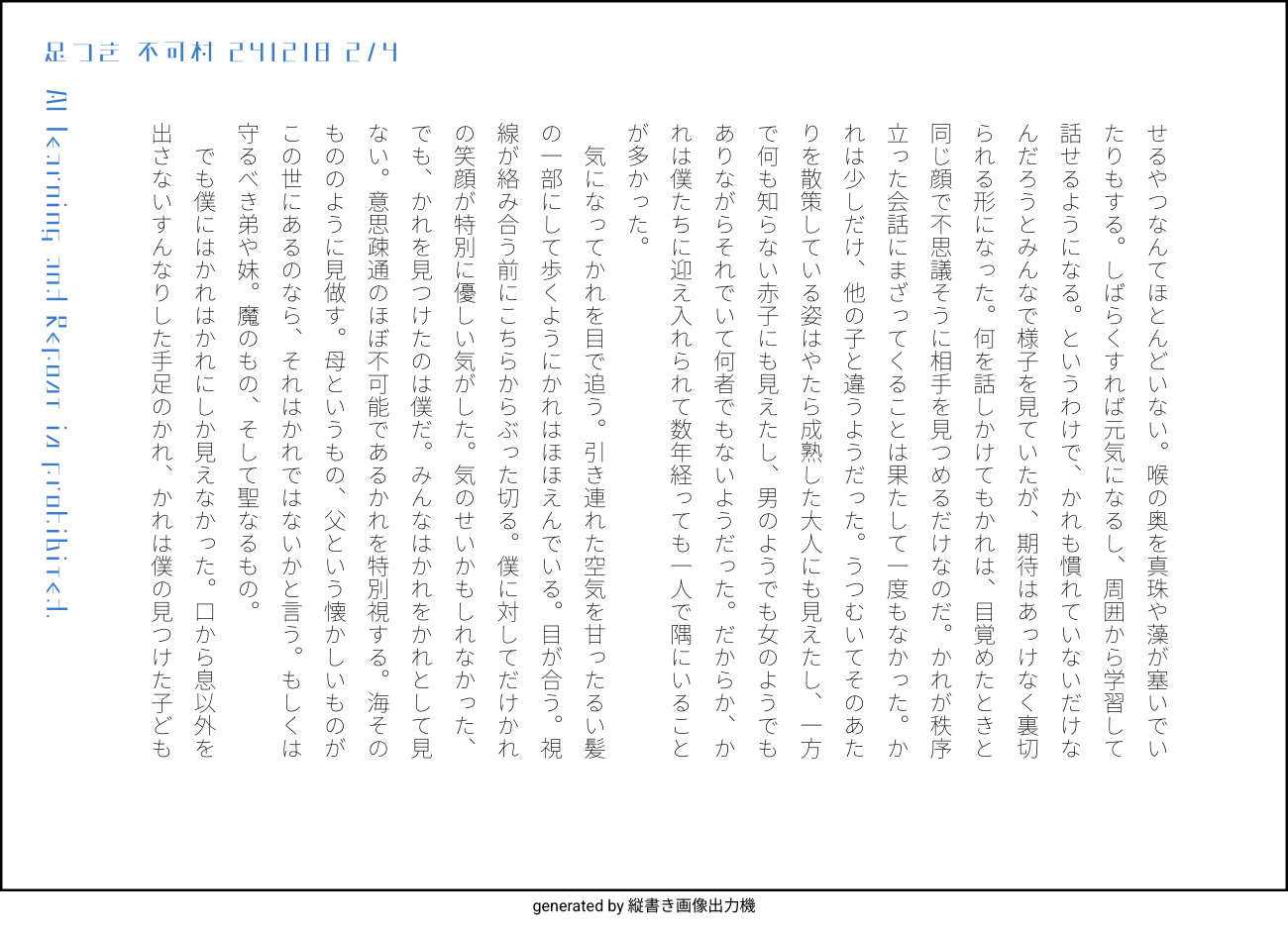
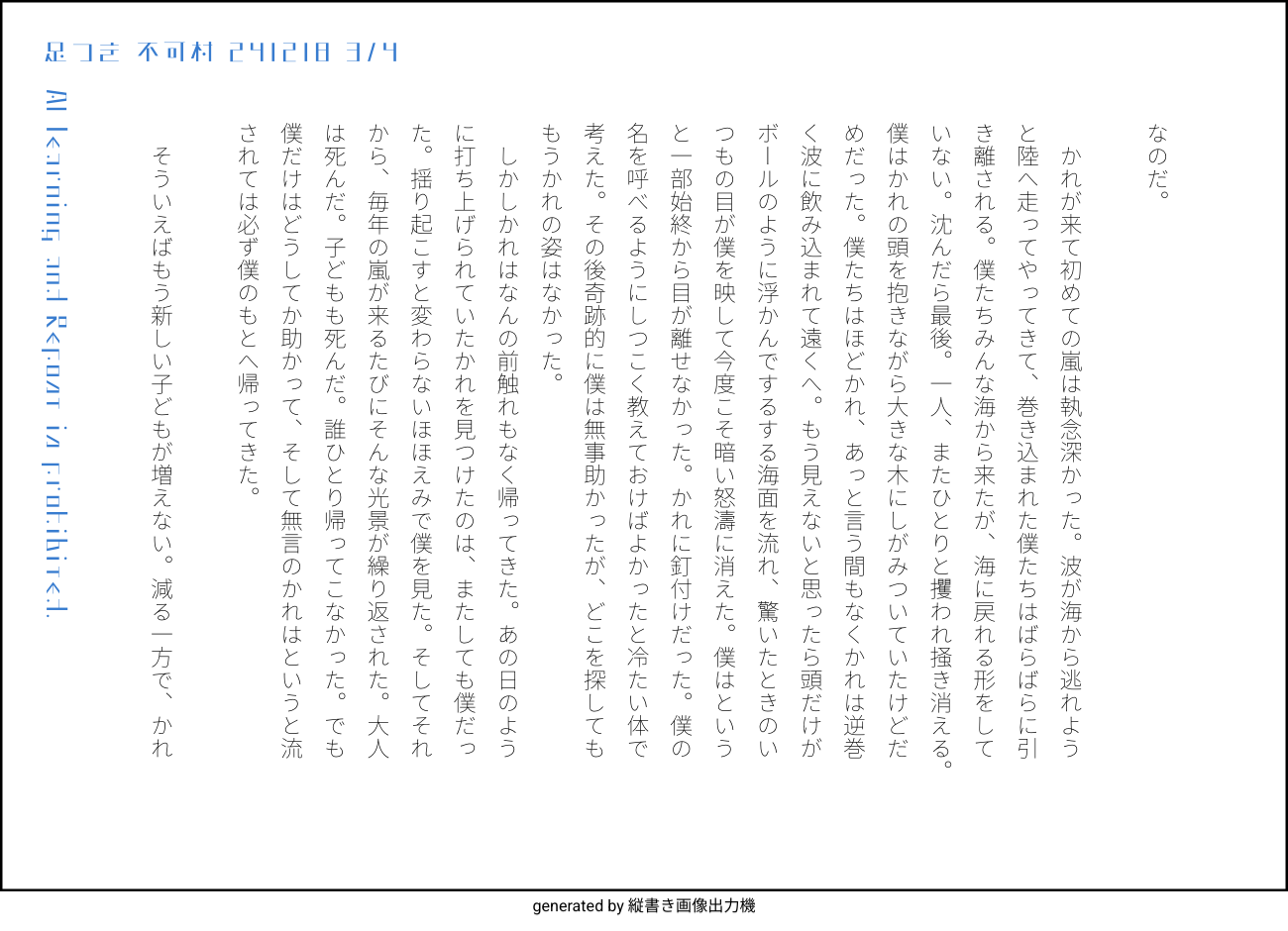

大人は三人ほどだが子どもはその十倍、身を寄せ合って暮らしていた。僕たちは貧しく、そして幸せだった。浜に打ち上げられていたかれを最初に見つけたのは僕だった。大きい魚かと疑ったほどに、体に余計なくびれがなかった。あたりに散らばる白い貝は波にけずられて丸く、石とほとんど見分けがつかない。泡の隙間にかれの手足が投げ出されている。頬にへばりついた髪は陽光を受けてまるで蜘蛛の糸のように柔らかく透き通っていた。(そういえば蜘蛛は海を越える)顔にふたつ並んで入っていた切れ目が割れて、中から少し尖った形の暗い瞳が現れ、僕を捉える。どうしてか僕はいたたまれなくなって、とにかく相手に何か問おうと焦って口を開く。肝心の内容を思いつけず魚みたいに息を吐いた。かれはどうやら少しだけ笑ったようだった。
沖から来たんだ。他の子どもたちと同じように。僕もかつてそうであったように。それはわかった。だってそれ以外で子どもが現れるなんて、この世界ではもう起きない。波打ち際で二人、呆けたようにしばらく見つめ合っていた。
そこまでは大体いつもどおりのことだったのだが、イレギュラーがいくつか。かれは言葉を理解できないようだった。発声できない、というだけなら、打ち上げられた子どもにはよく見られる現象だ。なんせ生まれたてみたいなものだから流暢に話せるやつなんてほとんどいない。喉の奥を真珠や藻が塞いでいたりもする。しばらくすれば元気になるし、周囲から学習して話せるようになる。というわけで、かれも慣れていないだけなんだろうとみんなで様子を見ていたが、期待はあっけなく裏切られる形になった。何を話しかけてもかれは、目覚めたときと同じ顔で不思議そうに相手を見つめるだけなのだ。かれが秩序立った会話にまざってくることは果たして一度もなかった。かれは少しだけ、他の子と違うようだった。うつむいてそのあたりを散策している姿はやたら成熟した大人にも見えたし、一方で何も知らない赤子にも見えたし、男のようでも女のようでもありながらそれでいて何者でもないようだった。だからか、かれは僕たちに迎え入れられて数年経っても一人で隅にいることが多かった。
気になってかれを目で追う。引き連れた空気を甘ったるい髪の一部にして歩くようにかれはほほえんでいる。目が合う。視線が絡み合う前にこちらからぶった切る。僕に対してだけかれの笑顔が特別に優しい気がした。気のせいかもしれなかった、でも、かれを見つけたのは僕だ。みんなはかれをかれとして見ない。意思疎通のほぼ不可能であるかれを特別視する。海そのもののように見做す。母というもの、父という懐かしいものがこの世にあるのなら、それはかれではないかと言う。もしくは守るべき弟や妹。魔のもの、そして聖なるもの。
でも僕にはかれはかれにしか見えなかった。口から息以外を出さないすんなりした手足のかれ、かれは僕の見つけた子どもなのだ。
かれが来て初めての嵐は執念深かった。波が海から逃れようと陸へ走ってやってきて、巻き込まれた僕たちはばらばらに引き離される。僕たちみんな海から来たが、海に戻れる形をしていない。沈んだら最後。一人、またひとりと攫われ掻き消える。僕はかれの頭を抱きながら大きな木にしがみついていたけどだめだった。僕たちはほどかれ、あっと言う間もなくかれは逆巻く波に飲み込まれて遠くへ。もう見えないと思ったら頭だけがボールのように浮かんでするする海面を流れ、驚いたときのいつもの目が僕を映して今度こそ暗い怒濤に消えた。僕はというと一部始終から目が離せなかった。かれに釘付けだった。僕の名を呼べるようにしつこく教えておけばよかったと冷たい体で考えた。その後奇跡的に僕は無事助かったが、どこを探してももうかれの姿はなかった。
しかしかれはなんの前触れもなく帰ってきた。あの日のように打ち上げられていたかれを見つけたのは、またしても僕だった。揺り起こすと変わらないほほえみで僕を見た。そしてそれから、毎年の嵐が来るたびにそんな光景が繰り返された。大人は死んだ。子どもも死んだ。誰ひとり帰ってこなかった。でも僕だけはどうしてか助かって、そして無言のかれはというと流されては必ず僕のもとへ帰ってきた。
そういえばもう新しい子どもが増えない。減る一方で、かれ以外、打ち上げられることはなくなってしまった。僕とかれ、海辺の白い白い貝殻の上でふたりきり、僕たちはこのまま歳をとるのだろうかと怖くなる。二人だけで何をしよう。何ができる。隣にいるかれの目を覗き込む。いつしか伸びたかれの長い髪の毛と僕の毛が海藻みたいに繋がって、濡れて光った。海鳴りはまるで魚の背のように輝き、僕は次の嵐がいつ来るのかを計算しようと試みる。かれが笑った。いつまでも音を覚えないかれの目がやかましく僕を呼ぶ。
足つき/不可村/241218/AI learning and Repost is prohibited.