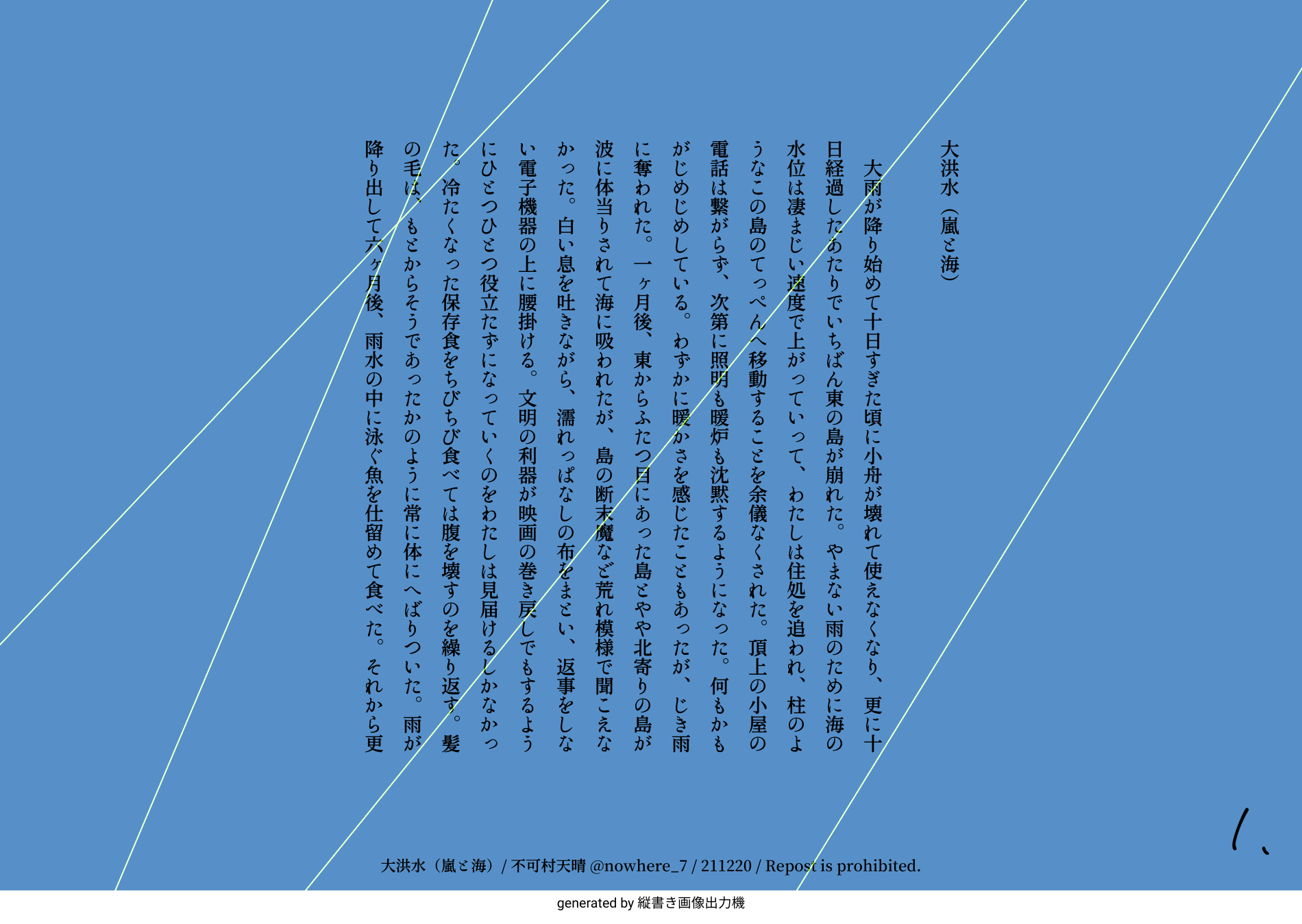
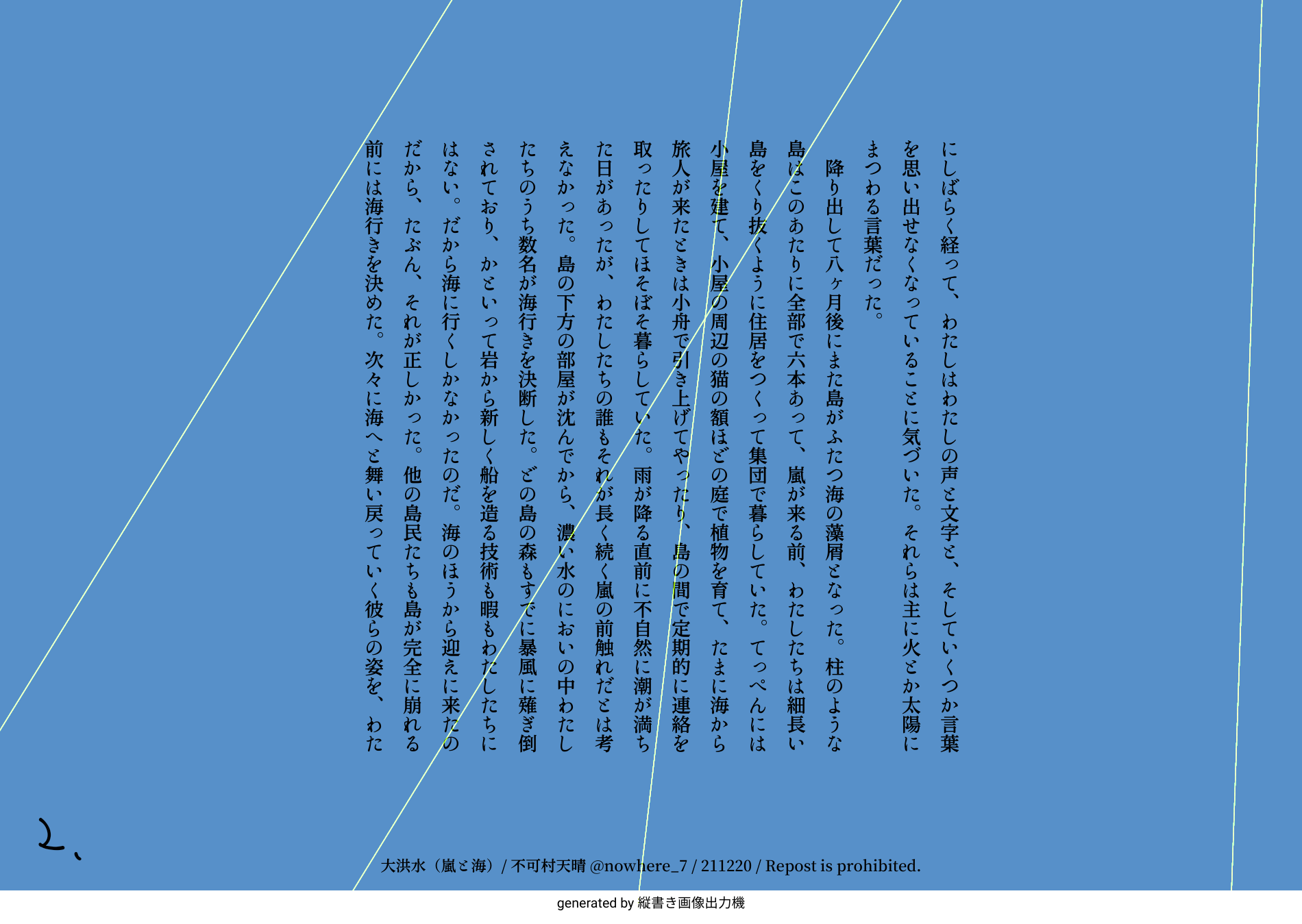
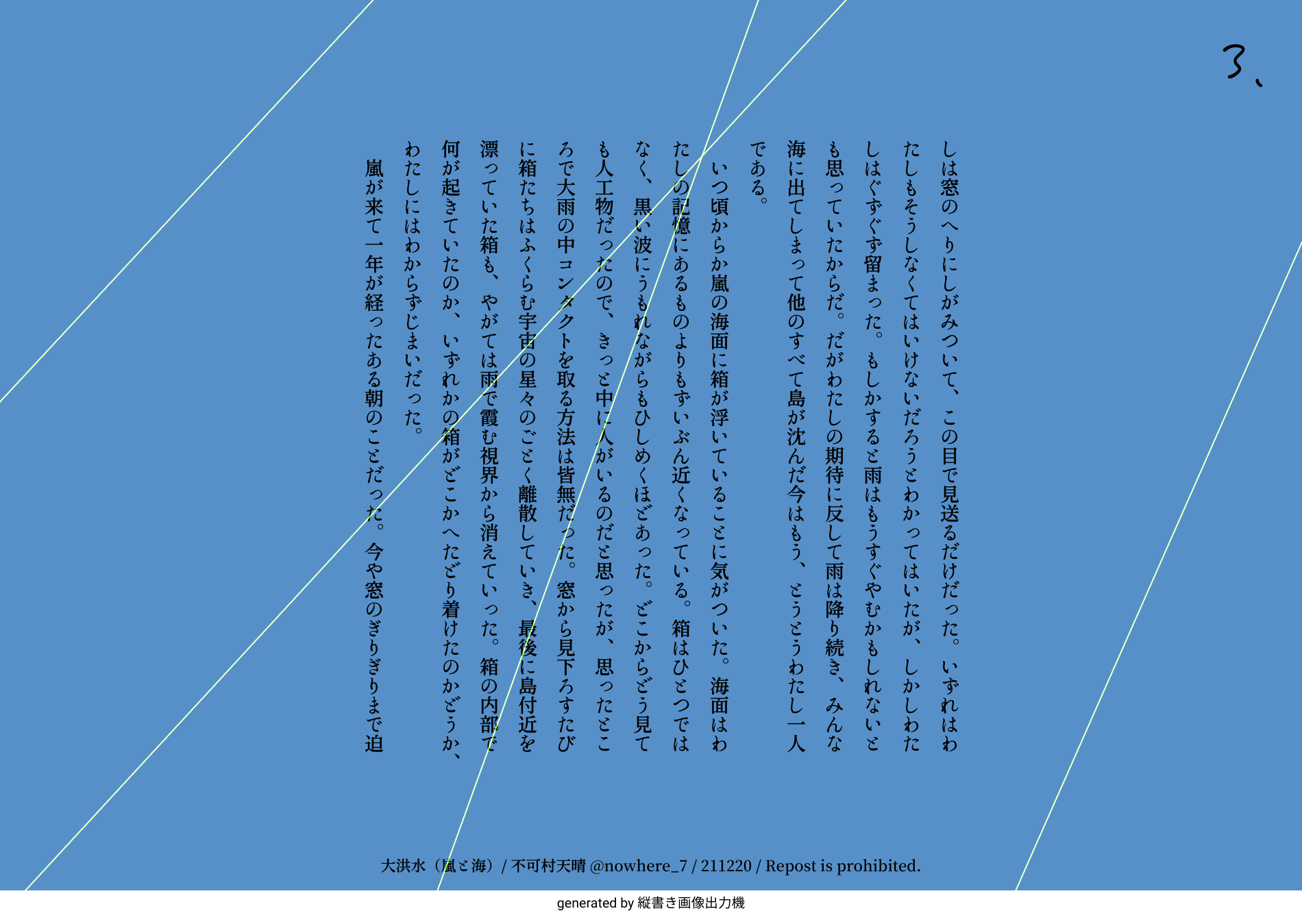

大雨が降り始めて十日すぎた頃に小舟が壊れて使えなくなり、更に十日経過したあたりでいちばん東の島が崩れた。やまない雨のために海の水位は凄まじい速度で上がっていって、わたしは住処を追われ、柱のようなこの島のてっぺんへ移動することを余儀なくされた。頂上の小屋の電話は繋がらず、次第に照明も暖炉も沈黙するようになった。何もかもがじめじめしている。わずかに暖かさを感じたこともあったが、じき雨に奪われた。一ヶ月後、東からふたつ目にあった島とやや北寄りの島が波に体当りされて海に吸われたが、島の断末魔など荒れ模様で聞こえなかった。白い息を吐きながら、濡れっぱなしの布をまとい、返事をしない電子機器の上に腰掛ける。文明の利器が映画の巻き戻しでもするようにひとつひとつ役立たずになっていくのをわたしは見届けるしかなかった。冷たくなった保存食をちびちび食べては腹を壊すのを繰り返す。髪の毛は、もとからそうであったかのように常に体にへばりついた。雨が降り出して六ヶ月後、雨水の中に泳ぐ魚を仕留めて食べた。それから更にしばらく経って、わたしはわたしの声と文字と、そしていくつか言葉を思い出せなくなっていることに気づいた。それらは主に火とか太陽にまつわる言葉だった。
降り出して八ヶ月後にまた島がふたつ海の藻屑となった。柱のような島はこのあたりに全部で六本あって、嵐が来る前、わたしたちは細長い島をくり抜くように住居をつくって集団で暮らしていた。てっぺんには小屋を建て、小屋の周辺の猫の額ほどの庭で植物を育て、たまに海から旅人が来たときは小舟で引き上げてやったり、島の間で定期的に連絡を取ったりしてほそぼそ暮らしていた。雨が降る直前に不自然に潮が満ちた日があったが、わたしたちの誰もそれが長く続く嵐の前触れだとは考えなかった。島の下方の部屋が沈んでから、濃い水のにおいの中わたしたちのうち数名が海行きを決断した。どの島の森もすでに暴風に薙ぎ倒されており、かといって岩から新しく船を造る技術も暇もわたしたちにはない。だから海に行くしかなかったのだ。海のほうから迎えに来たのだから、たぶん、それが正しかった。他の島民たちも島が完全に崩れる前には海行きを決めた。次々に海へと舞い戻っていく彼らの姿を、わたしは窓のへりにしがみついて、この目で見送るだけだった。いずれはわたしもそうしなくてはいけないだろうとわかってはいたが、しかしわたしはぐずぐず留まった。もしかすると雨はもうすぐやむかもしれないとも思っていたからだ。だがわたしの期待に反して雨は降り続き、みんな海に出てしまって他のすべて島が沈んだ今はもう、とうとうわたし一人である。
いつ頃からか嵐の海面に箱が浮いていることに気がついた。海面はわたしの記憶にあるものよりもずいぶん近くなっている。箱はひとつではなく、黒い波にうもれながらもひしめくほどあった。どこからどう見ても人工物だったので、きっと中に人がいるのだと思ったが、思ったところで大雨の中コンタクトを取る方法は皆無だった。窓から見下ろすたびに箱たちはふくらむ宇宙の星々のごとく離散していき、最後に島付近を漂っていた箱も、やがては雨で霞む視界から消えていった。箱の内部で何が起きていたのか、いずれかの箱がどこかへたどり着けたのかどうか、わたしにはわからずじまいだった。
嵐が来て一年が経ったある朝のことだった。今や窓のぎりぎりまで迫る海面を見、わたしは忽然と海に飛び込んだ。しばらく荒れ狂う波にもまれていたが、そのうち波とわたしとの境がなくなり、すぐに慣れた。見かけた箱や先に飛び込んだ他の島民の今が杳として知れぬように、激しい嵐が結局なんだったのかも知らないままでいる。やんだのかすらわからない。何も知らないがもう困ることはなく、わたしはそれからずっと海である。
大洪水(嵐と海)/ 不可村天晴 @nowhere_7 / 211220 / Repost is prohibited.