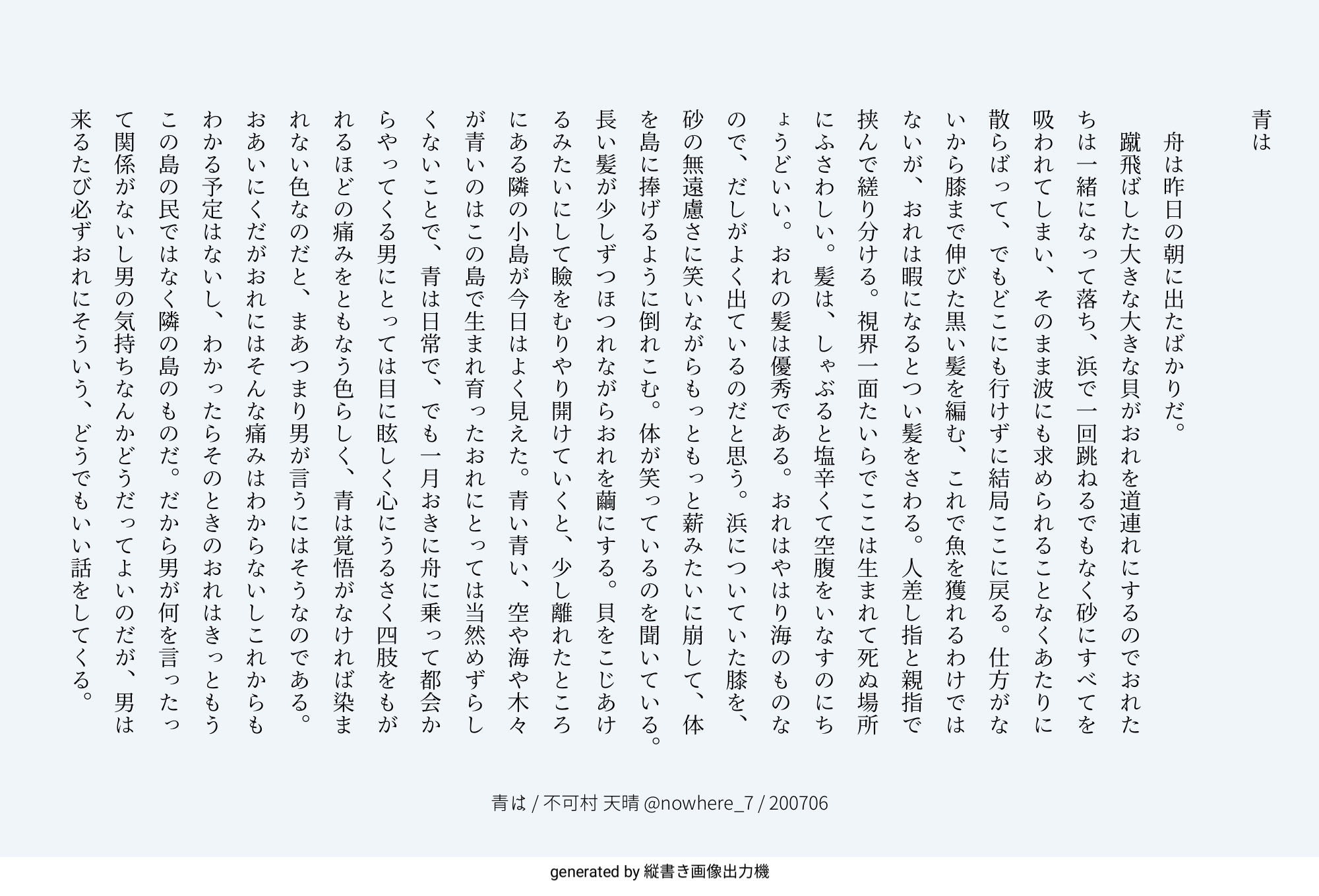
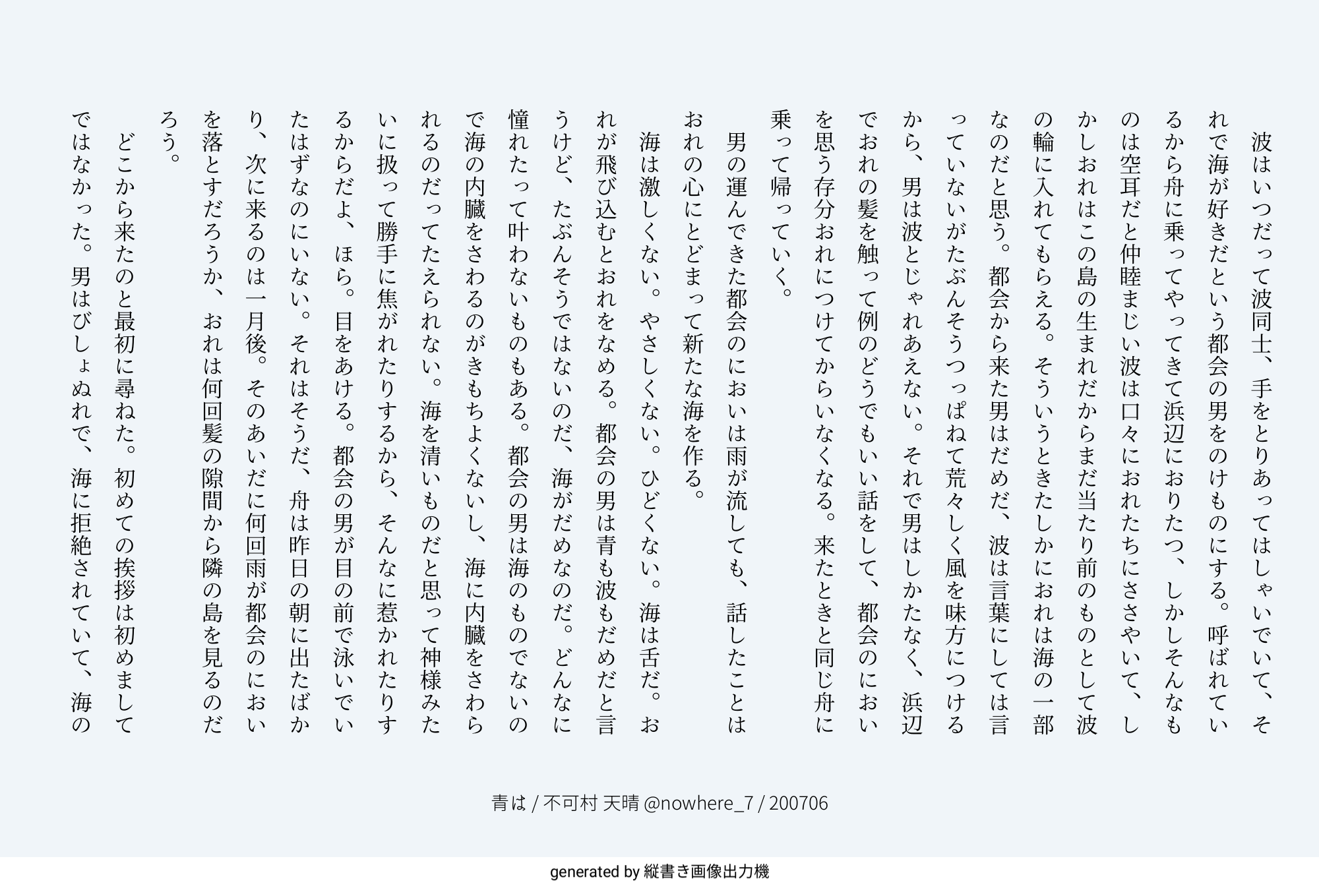
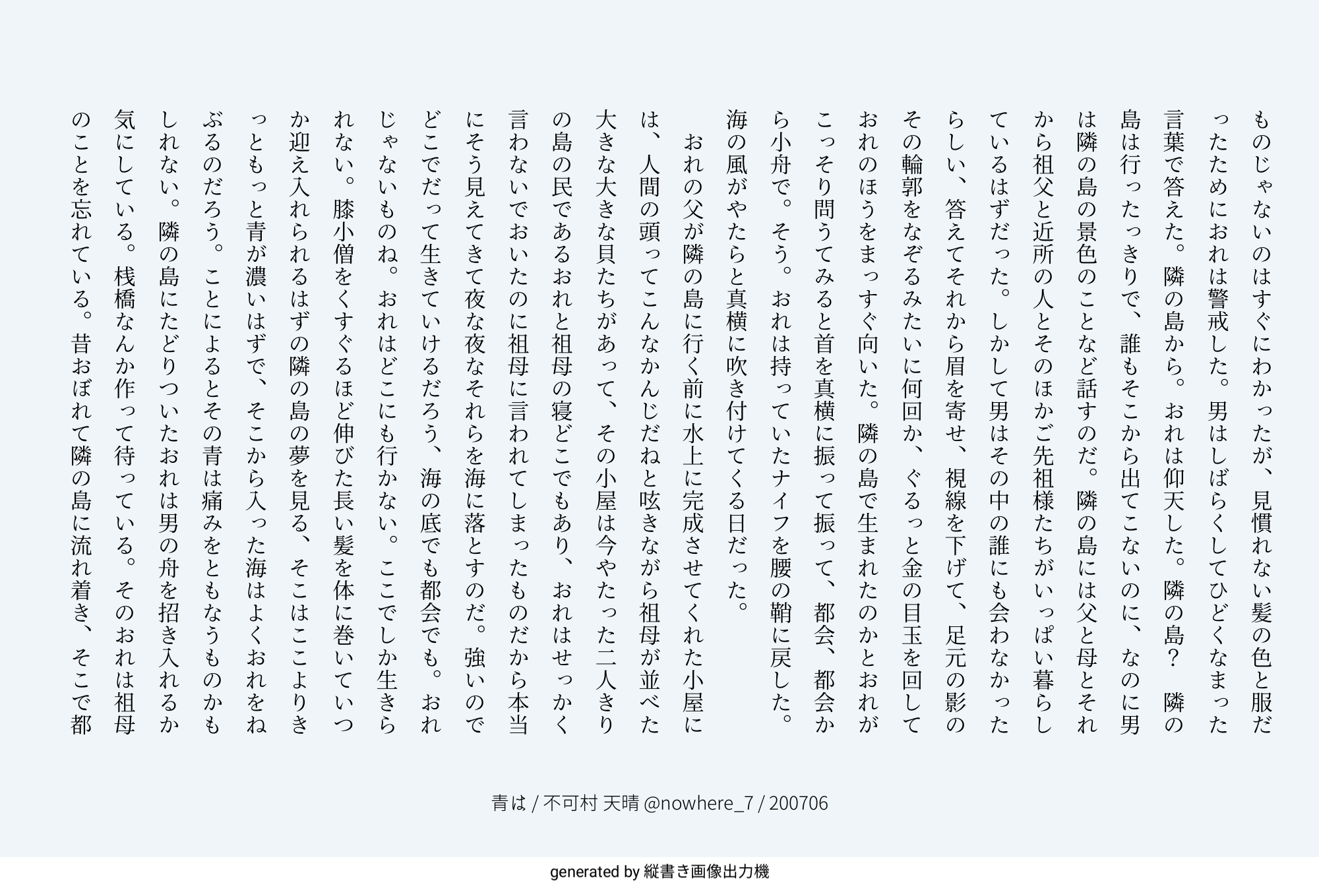

舟は昨日の朝に出たばかりだ。
蹴飛ばした大きな大きな貝がおれを道連れにするのでおれたちは一緒になって落ち、浜で一回跳ねるでもなく砂にすべてを吸われてしまい、そのまま波にも求められることなくあたりに散らばって、でもどこにも行けずに結局ここに戻る。仕方がないから膝まで伸びた黒い髪を編む、これで魚を獲れるわけではないが、おれは暇になるとつい髪をさわる。人差し指と親指で挟んで縒り分ける。視界一面たいらでここは生まれて死ぬ場所にふさわしい。髪は、しゃぶると塩辛くて空腹をいなすのにちょうどいい。おれの髪は優秀である。おれはやはり海のものなので、だしがよく出ているのだと思う。浜についていた膝を、砂の無遠慮さに笑いながらもっともっと薪みたいに崩して、体を島に捧げるように倒れこむ。体が笑っているのを聞いている。長い髪が少しずつほつれながらおれを繭にする。貝をこじあけるみたいにして瞼をむりやり開けていくと、少し離れたところにある隣の小島が今日はよく見えた。青い青い、空や海や木々が青いのはこの島で生まれ育ったおれにとっては当然めずらしくないことで、青は日常で、でも一月おきに舟に乗って都会からやってくる男にとっては目に眩しく心にうるさく四肢をもがれるほどの痛みをともなう色らしく、青は覚悟がなければ染まれない色なのだと、まあつまり男が言うにはそうなのである。おあいにくだがおれにはそんな痛みはわからないしこれからもわかる予定はないし、わかったらそのときのおれはきっともうこの島の民ではなく隣の島のものだ。だから男が何を言ったって関係がないし男の気持ちなんかどうだってよいのだが、男は来るたび必ずおれにそういう、どうでもいい話をしてくる。
波はいつだって波同士、手をとりあってはしゃいでいて、それで海が好きだという都会の男をのけものにする。呼ばれているから舟に乗ってやってきて浜辺におりたつ、しかしそんなものは空耳だと仲睦まじい波は口々におれたちにささやいて、しかしおれはこの島の生まれだからまだ当たり前のものとして波の輪に入れてもらえる。そういうときたしかにおれは海の一部なのだと思う。都会から来た男はだめだ、波は言葉にしては言っていないがたぶんそうつっぱねて荒々しく風を味方につけるから、男は波とじゃれあえない。それで男はしかたなく、浜辺でおれの髪を触って例のどうでもいい話をして、都会のにおいを思う存分おれにつけてからいなくなる。来たときと同じ舟に乗って帰っていく。
男の運んできた都会のにおいは雨が流しても、話したことはおれの心にとどまって新たな海を作る。
海は激しくない。やさしくない。ひどくない。海は舌だ。おれが飛び込むとおれをなめる。都会の男は青も波もだめだと言うけど、たぶんそうではないのだ、海がだめなのだ。どんなに憧れたって叶わないものもある。都会の男は海のものでないので海の内臓をさわるのがきもちよくないし、海に内臓をさわられるのだってたえられない。海を清いものだと思って神様みたいに扱って勝手に焦がれたりするから、そんなに惹かれたりするからだよ、ほら。目をあける。都会の男が目の前で泳いでいたはずなのにいない。それはそうだ、舟は昨日の朝に出たばかり、次に来るのは一月後。そのあいだに何回雨が都会のにおいを落とすだろうか、おれは何回髪の隙間から隣の島を見るのだろう。
どこから来たのと最初に尋ねた。初めての挨拶は初めましてではなかった。男はびしょぬれで、海に拒絶されていて、海のものじゃないのはすぐにわかったが、見慣れない髪の色と服だったためにおれは警戒した。男はしばらくしてひどくなまった言葉で答えた。隣の島から。おれは仰天した。隣の島? 隣の島は行ったっきりで、誰もそこから出てこないのに、なのに男は隣の島の景色のことなど話すのだ。隣の島には父と母とそれから祖父と近所の人とそのほかご先祖様たちがいっぱい暮らしているはずだった。しかして男はその中の誰にも会わなかったらしい、答えてそれから眉を寄せ、視線を下げて、足元の影のその輪郭をなぞるみたいに何回か、ぐるっと金の目玉を回しておれのほうをまっすぐ向いた。隣の島で生まれたのかとおれがこっそり問うてみると首を真横に振って振って、都会、都会から小舟で。そう。おれは持っていたナイフを腰の鞘に戻した。海の風がやたらと真横に吹き付けてくる日だった。
おれの父が隣の島に行く前に水上に完成させてくれた小屋には、人間の頭ってこんなかんじだねと呟きながら祖母が並べた大きな大きな貝たちがあって、その小屋は今やたった二人きりの島の民であるおれと祖母の寝どこでもあり、おれはせっかく言わないでおいたのに祖母に言われてしまったものだから本当にそう見えてきて夜な夜なそれらを海に落とすのだ。強いのでどこでだって生きていけるだろう、海の底でも都会でも。おれじゃないものね。おれはどこにも行かない。ここでしか生きられない。膝小僧をくすぐるほど伸びた長い髪を体に巻いていつか迎え入れられるはずの隣の島の夢を見る、そこはここよりきっともっと青が濃いはずで、そこから入った海はよくおれをねぶるのだろう。ことによるとその青は痛みをともなうものかもしれない。隣の島にたどりついたおれは男の舟を招き入れるか気にしている。桟橋なんか作って待っている。そのおれは祖母のことを忘れている。昔おぼれて隣の島に流れ着き、そこで都会からの調査隊に助けられて戻ってきた祖母、それ以来誰からもかえりみられず、ばたばたと旅立ったみんなを見送って一人きり長生きして、おれを育ててくれた祖母。都会の男がおれを呼ぶといつだって泣く祖母。貝はゆっくりゆっくり沈む。つれだつ雛のように沖へ消えていく貝たちがひとつずつ都会の男の頭に変わっていくようなのでおれは髪をほどいて海に飛び込んで、いつか海に拒絶される日を、青が痛みに変わる日を錯覚しながら目を開けて閉じるとやっぱりまだ同じ浜にいる。
舟は昨日の朝に出たばかりだ。
青は 2007006