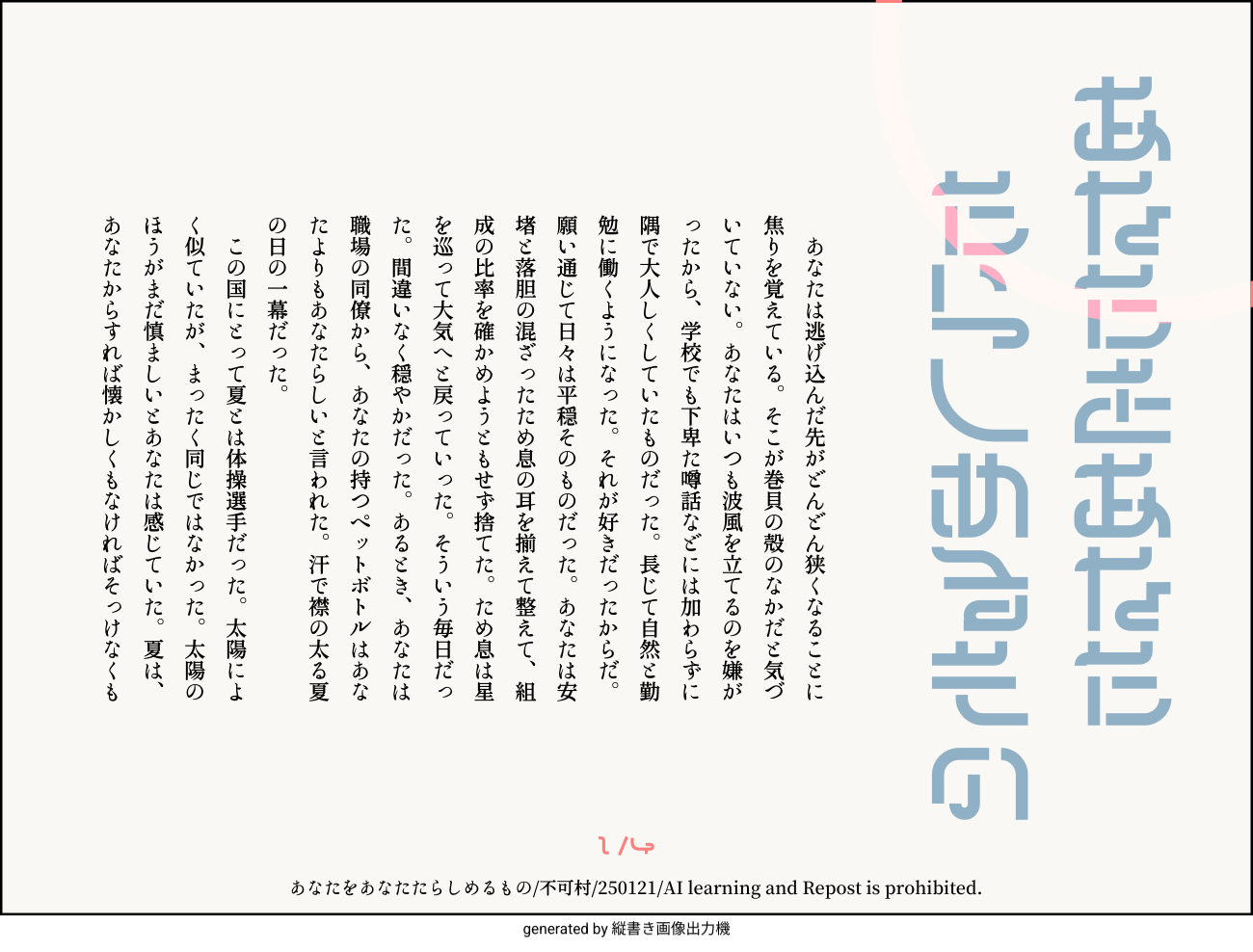
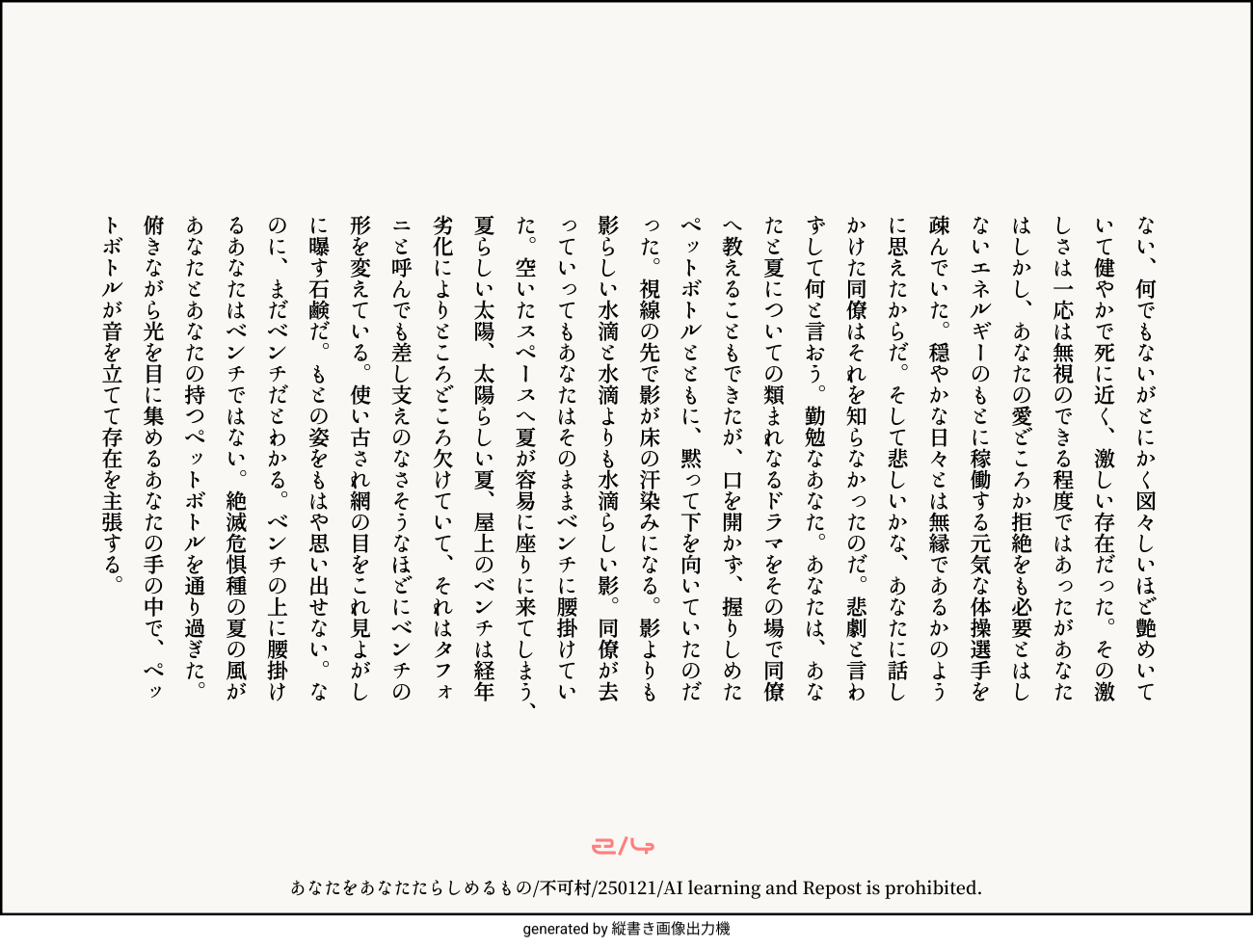
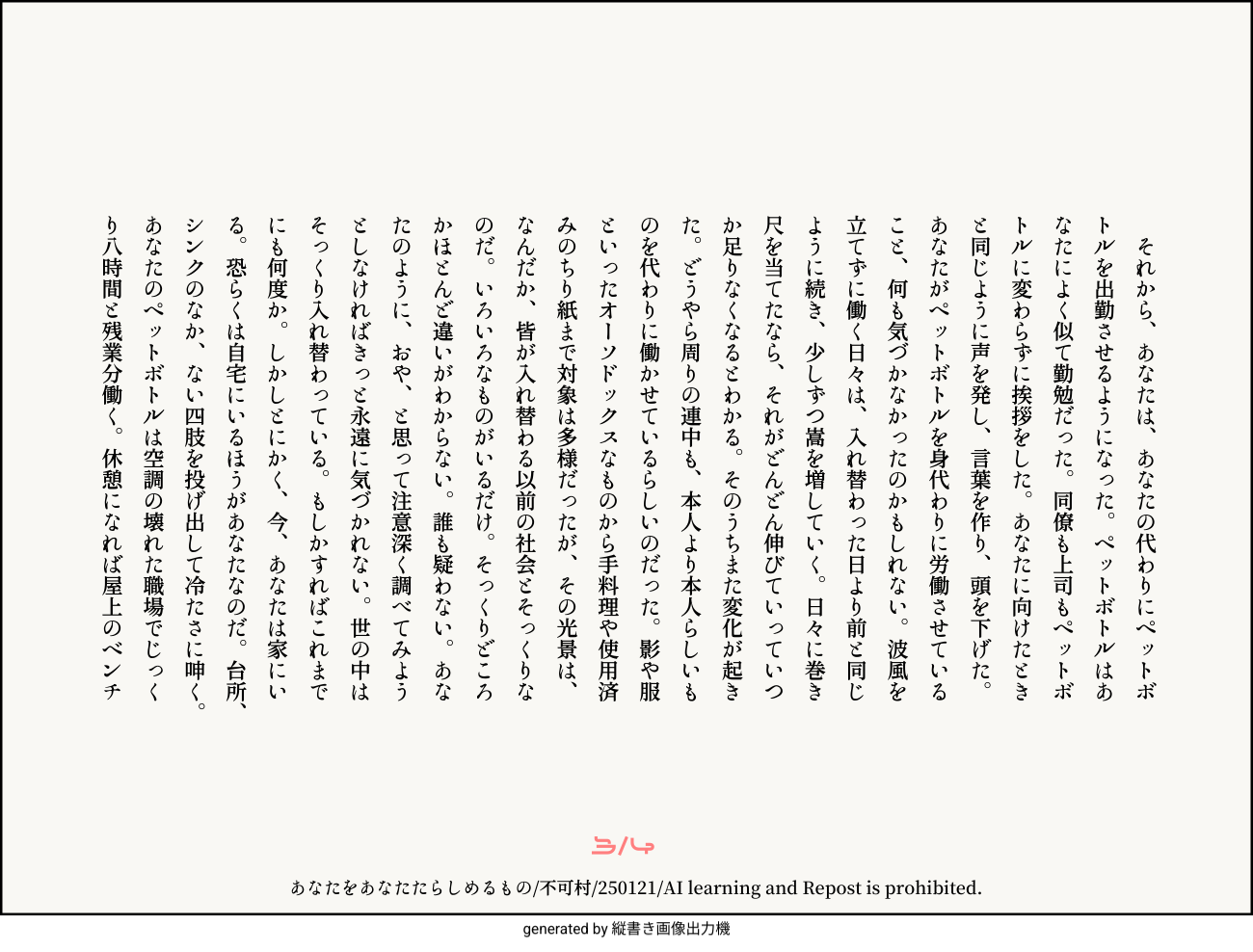
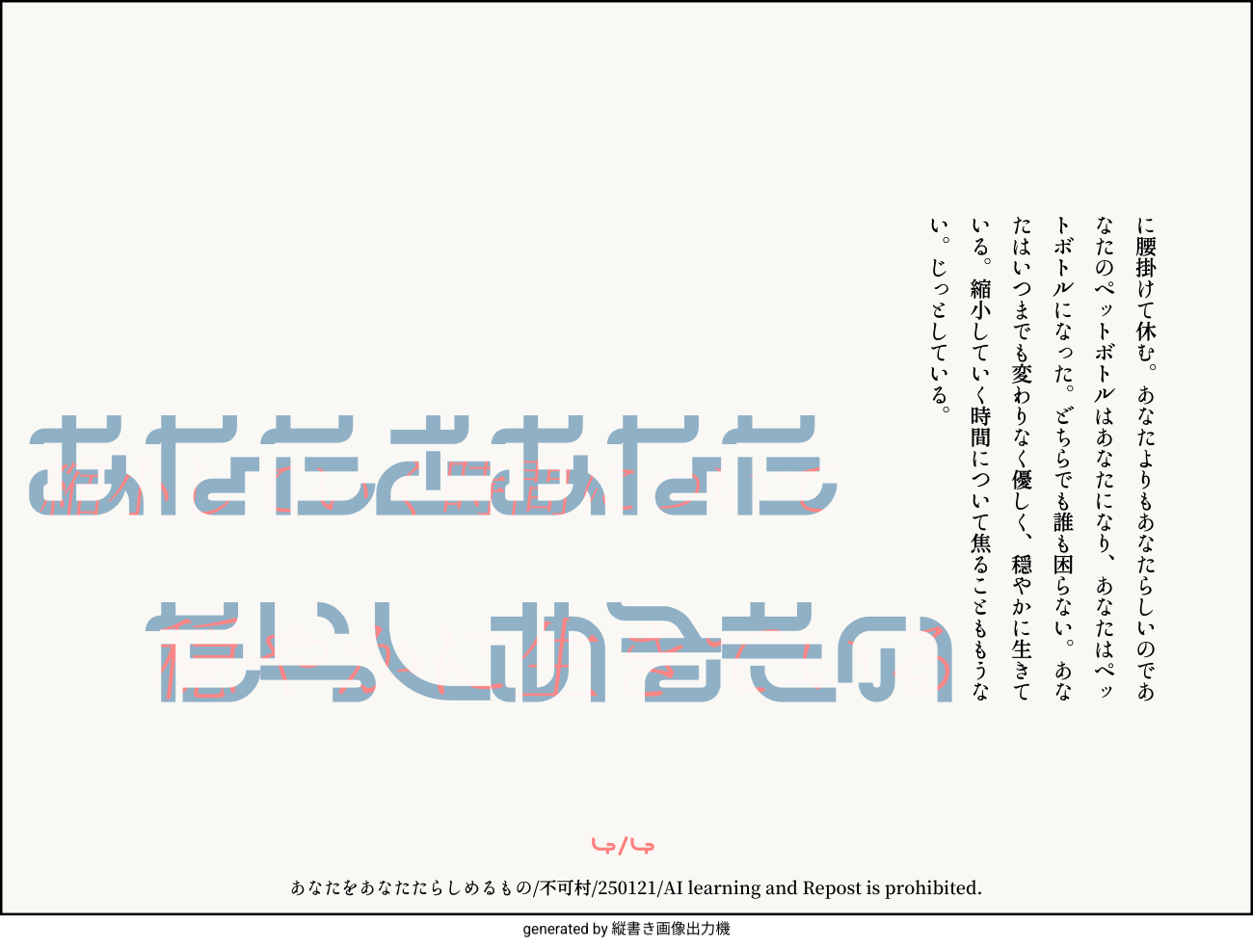
あなたは逃げ込んだ先がどんどん狭くなることに焦りを覚えている。そこが巻貝の殻のなかだと気づいていない。あなたはいつも波風を立てるのを嫌がったから、学校でも下卑た噂話などには加わらずに隅で大人しくしていたものだった。長じて自然と勤勉に働くようになった。それが好きだったからだ。願い通じて日々は平穏そのものだった。あなたは安堵と落胆の混ざったため息の耳を揃えて整えて、組成の比率を確かめようともせず捨てた。ため息は星を巡って大気へと戻っていった。そういう毎日だった。間違いなく穏やかだった。あるとき、あなたは職場の同僚から、あなたの持つペットボトルはあなたよりもあなたらしいと言われた。汗で襟の太る夏の日の一幕だった。
この国にとって夏とは体操選手だった。太陽によく似ていたが、まったく同じではなかった。太陽のほうがまだ慎ましいとあなたは感じていた。夏は、あなたからすれば懐かしくもなければそっけなくもない、何でもないがとにかく図々しいほど艶めいていて健やかで死に近く、激しい存在だった。その激しさは一応は無視のできる程度ではあったがあなたはしかし、あなたの愛どころか拒絶をも必要とはしないエネルギーのもとに稼働する元気な体操選手を疎んでいた。穏やかな日々とは無縁であるかのように思えたからだ。そして悲しいかな、あなたに話しかけた同僚はそれを知らなかったのだ。悲劇と言わずして何と言おう。勤勉なあなた。あなたは、あなたと夏についての類まれなるドラマをその場で同僚へ教えることもできたが、口を開かず、握りしめたペットボトルとともに、黙って下を向いていたのだった。視線の先で影が床の汗染みになる。影よりも影らしい水滴と水滴よりも水滴らしい影。同僚が去っていってもあなたはそのままベンチに腰掛けていた。空いたスペースへ夏が容易に座りに来てしまう、夏らしい太陽、太陽らしい夏、屋上のベンチは経年劣化によりところどころ欠けていて、それはタフォニと呼んでも差し支えのなさそうなほどにベンチの形を変えている。使い古され網の目をこれ見よがしに曝す石鹸だ。もとの姿をもはや思い出せない。なのに、まだベンチだとわかる。ベンチの上に腰掛けるあなたはベンチではない。絶滅危惧種の夏の風があなたとあなたの持つペットボトルを通り過ぎた。俯きながら光を目に集めるあなたの手の中で、ペットボトルが音を立てて存在を主張する。
それから、あなたは、あなたの代わりにペットボトルを出勤させるようになった。ペットボトルはあなたによく似て勤勉だった。同僚も上司もペットボトルに変わらずに挨拶をした。あなたに向けたときと同じように声を発し、言葉を作り、頭を下げた。あなたがペットボトルを身代わりに労働させていること、何も気づかなかったのかもしれない。波風を立てずに働く日々は、入れ替わった日より前と同じように続き、少しずつ嵩を増していく。日々に巻き尺を当てたなら、それがどんどん伸びていっていつか足りなくなるとわかる。そのうちまた変化が起きた。どうやら周りの連中も、本人より本人らしいものを代わりに働かせているらしいのだった。影や服といったオーソドックスなものから手料理や使用済みのちり紙まで対象は多様だったが、その光景は、なんだか、皆が入れ替わる以前の社会とそっくりなのだ。いろいろなものがいるだけ。そっくりどころかほとんど違いがわからない。誰も疑わない。あなたのように、おや、と思って注意深く調べてみようとしなければきっと永遠に気づかれない。世の中はそっくり入れ替わっている。もしかすればこれまでにも何度か。しかしとにかく、今、あなたは家にいる。恐らくは自宅にいるほうがあなたなのだ。台所、シンクのなか、ない四肢を投げ出して冷たさに呻く。あなたのペットボトルは空調の壊れた職場でじっくり八時間と残業分働く。休憩になれば屋上のベンチに腰掛けて休む。あなたよりもあなたらしいのであなたのペットボトルはあなたになり、あなたはペットボトルになった。どちらでも誰も困らない。あなたはいつまでも変わりなく優しく、穏やかに生きている。縮小していく時間について焦ることももうない。じっとしている。
あなたをあなたたらしめるもの/不可村/250121/AI learning and Repost is prohibited.