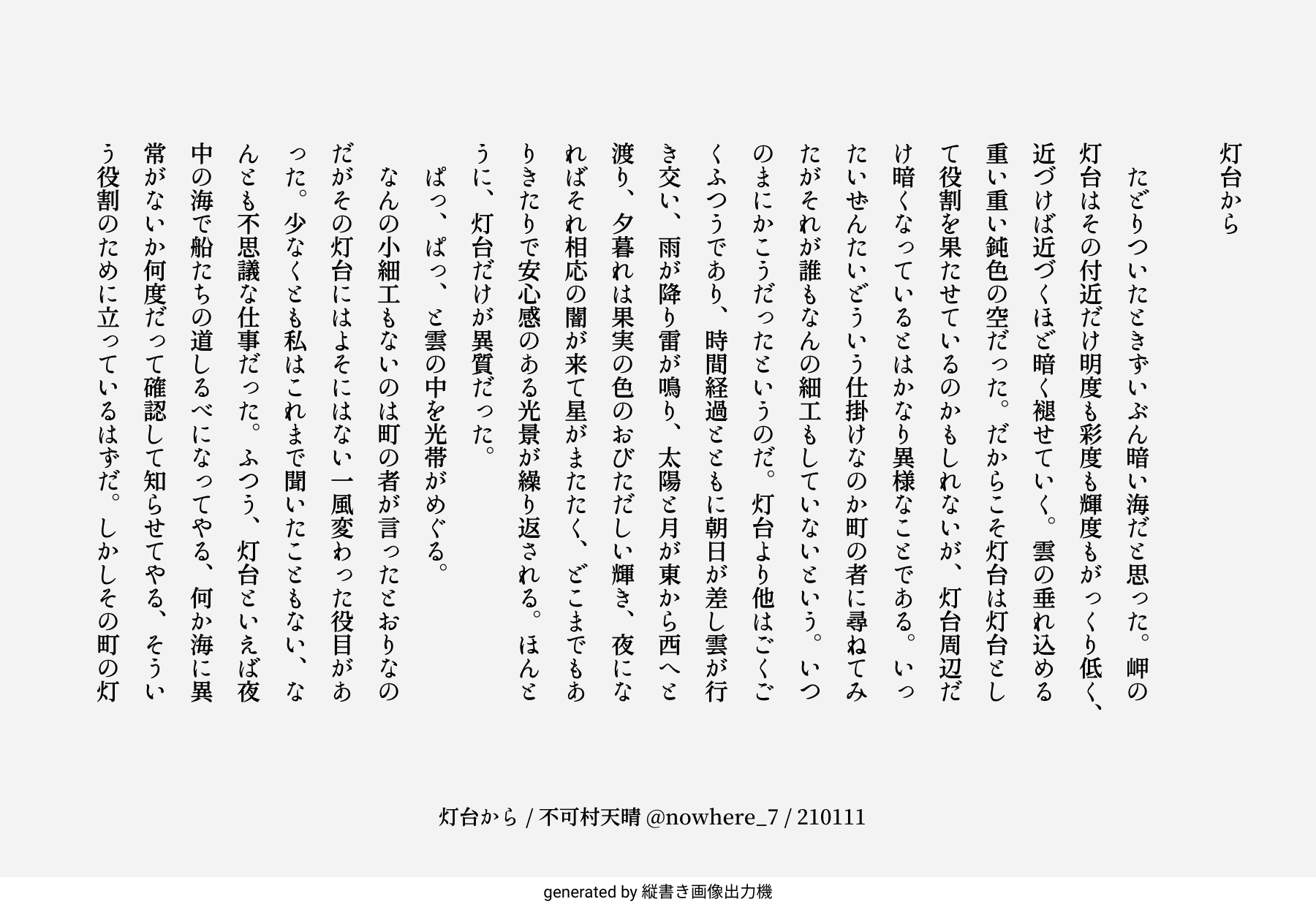
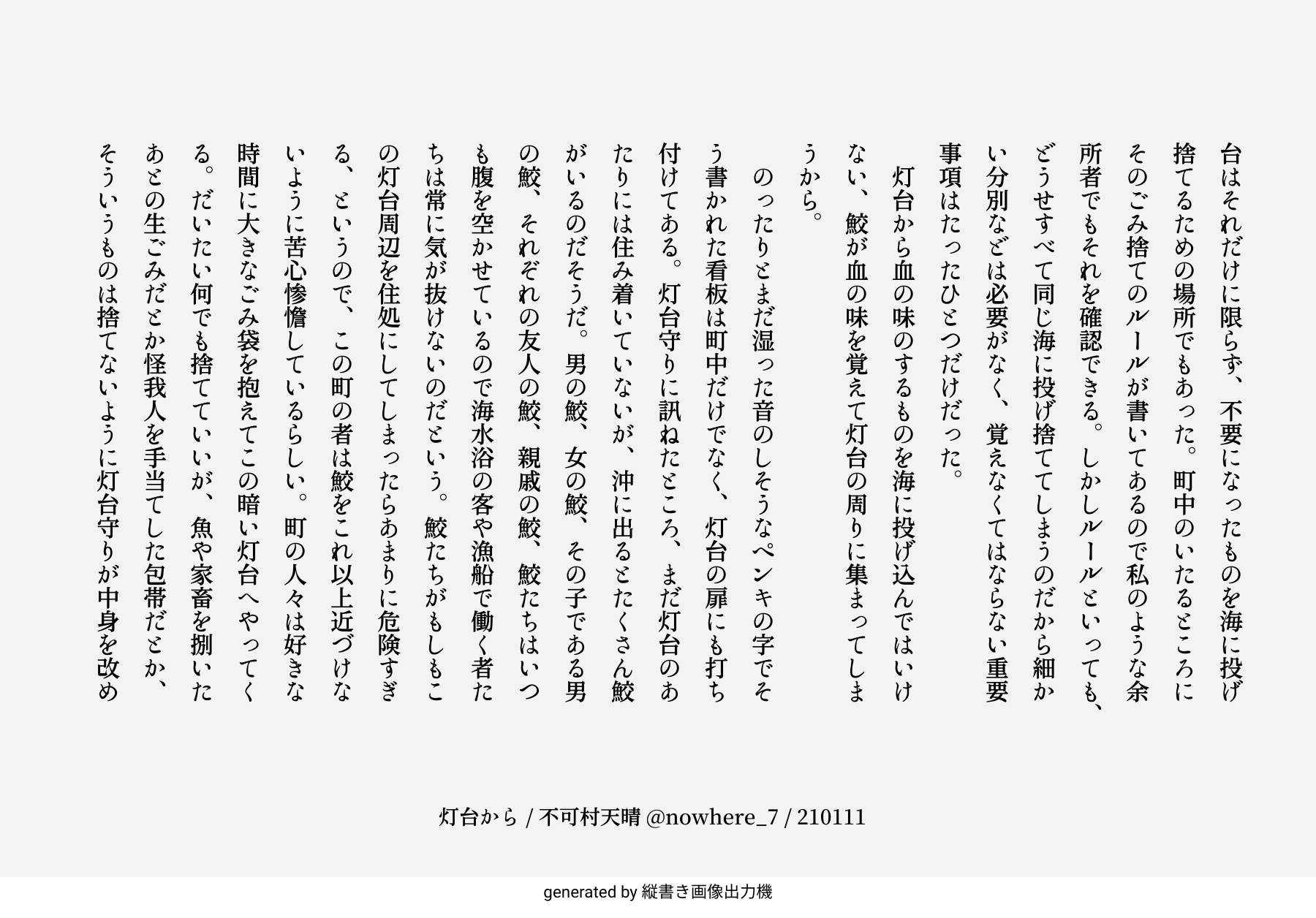
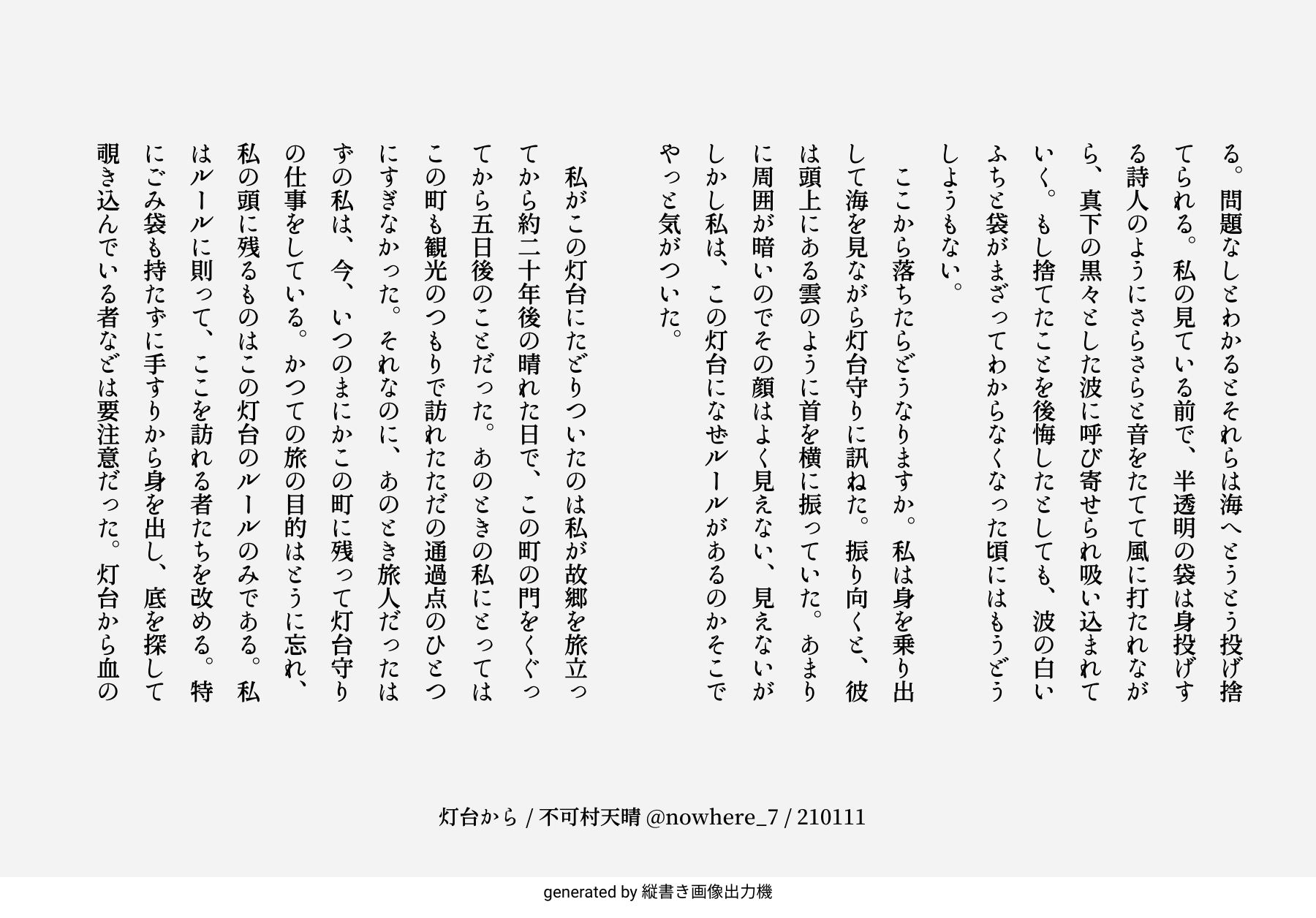
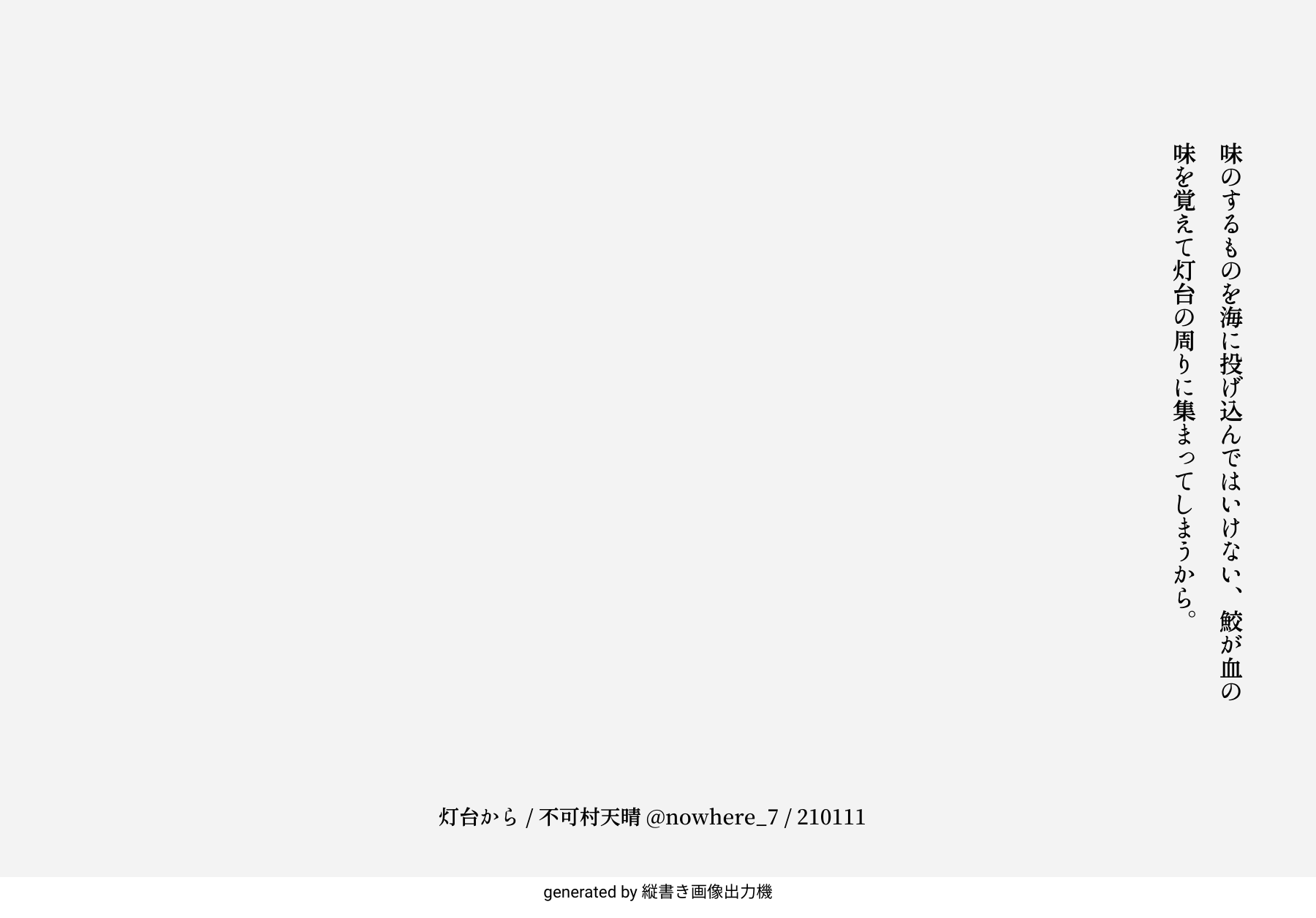
たどりついたときずいぶん暗い海だと思った。岬の灯台はその付近だけ明度も彩度も輝度もがっくり低く、近づけば近づくほど暗く褪せていく。雲の垂れ込める重い重い鈍色の空だった。だからこそ灯台は灯台として役割を果たせているのかもしれないが、灯台周辺だけ暗くなっているとはかなり異様なことである。いったいぜんたいどういう仕掛けなのか町の者に尋ねてみたがそれが誰もなんの細工もしていないという。いつのまにかこうだったというのだ。灯台より他はごくごくふつうであり、時間経過とともに朝日が差し雲が行き交い、雨が降り雷が鳴り、太陽と月が東から西へと渡り、夕暮れは果実の色のおびただしい輝き、夜になればそれ相応の闇が来て星がまたたく、どこまでもありきたりで安心感のある光景が繰り返される。ほんとうに、灯台だけが異質だった。
ぱっ、ぱっ、と雲の中を光帯がめぐる。
なんの小細工もないのは町の者が言ったとおりなのだがその灯台にはよそにはない一風変わった役目があった。少なくとも私はこれまで聞いたこともない、なんとも不思議な仕事だった。ふつう、灯台といえば夜中の海で船たちの道しるべになってやる、何か海に異常がないか何度だって確認して知らせてやる、そういう役割のために立っているはずだ。しかしその町の灯台はそれだけに限らず、不要になったものを海に投げ捨てるための場所でもあった。町中のいたるところにそのごみ捨てのルールが書いてあるので私のような余所者でもそれを確認できる。しかしルールといっても、どうせすべて同じ海に投げ捨ててしまうのだから細かい分別などは必要がなく、覚えなくてはならない重要事項はたったひとつだけだった。
灯台から血の味のするものを海に投げ込んではいけない、鮫が血の味を覚えて灯台の周りに集まってしまうから。
のったりとまだ湿った音のしそうなペンキの字でそう書かれた看板は町中だけでなく、灯台の扉にも打ち付けてある。灯台守りに訊ねたところ、まだ灯台のあたりには住み着いていないが、沖に出るとたくさん鮫がいるのだそうだ。男の鮫、女の鮫、その子である男の鮫、それぞれの友人の鮫、親戚の鮫、鮫たちはいつも腹を空かせているので海水浴の客や漁船で働く者たちは常に気が抜けないのだという。鮫たちがもしもこの灯台周辺を住処にしてしまったらあまりに危険すぎる、というので、この町の者は鮫をこれ以上近づけないように苦心惨憺しているらしい。町の人々は好きな時間に大きなごみ袋を抱えてこの暗い灯台へやってくる。だいたい何でも捨てていいが、魚や家畜を捌いたあとの生ごみだとか怪我人を手当てした包帯だとか、そういうものは捨てないように灯台守りが中身を改める。問題なしとわかるとそれらは海へとうとう投げ捨てられる。私の見ている前で、半透明の袋は身投げする詩人のようにさらさらと音をたてて風に打たれながら、真下の黒々とした波に呼び寄せられ吸い込まれていく。もし捨てたことを後悔したとしても、波の白いふちと袋がまざってわからなくなった頃にはもうどうしようもない。
ここから落ちたらどうなりますか。私は身を乗り出して海を見ながら灯台守りに訊ねた。振り向くと、彼は頭上にある雲のように首を横に振っていた。あまりに周囲が暗いのでその顔はよく見えない、見えないがしかし私は、この灯台になぜルールがあるのかそこでやっと気がついた。
私がこの灯台にたどりついたのは私が故郷を旅立ってから約二十年後の晴れた日で、この町の門をくぐってから五日後のことだった。あのときの私にとってはこの町も観光のつもりで訪れたただの通過点のひとつにすぎなかった。それなのに、あのとき旅人だったはずの私は、今、いつのまにかこの町に残って灯台守りの仕事をしている。かつての旅の目的はとうに忘れ、私の頭に残るものはこの灯台のルールのみである。私はルールに則って、ここを訪れる者たちを改める。特にごみ袋も持たずに手すりから身を出し、底を探して覗き込んでいる者などは要注意だった。灯台から血の味のするものを海に投げ込んではいけない、鮫が血の味を覚えて灯台の周りに集まってしまうから。
灯台から 210115